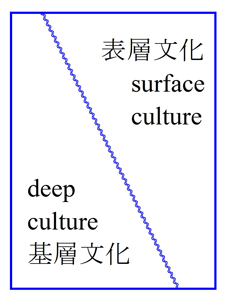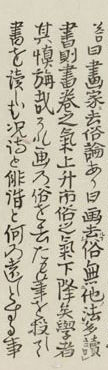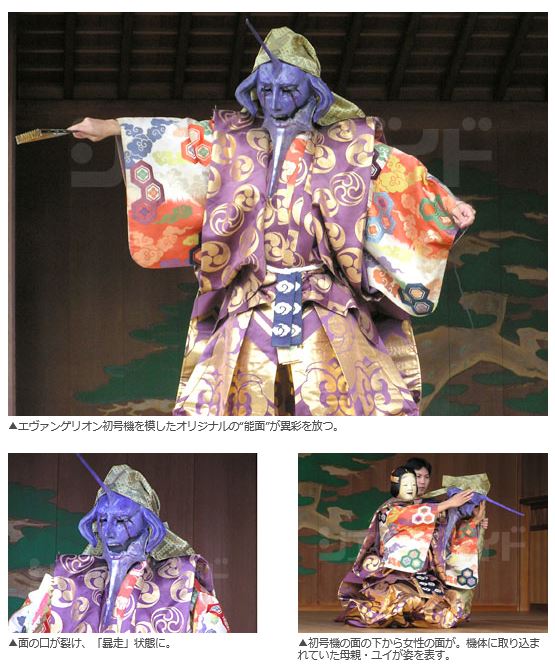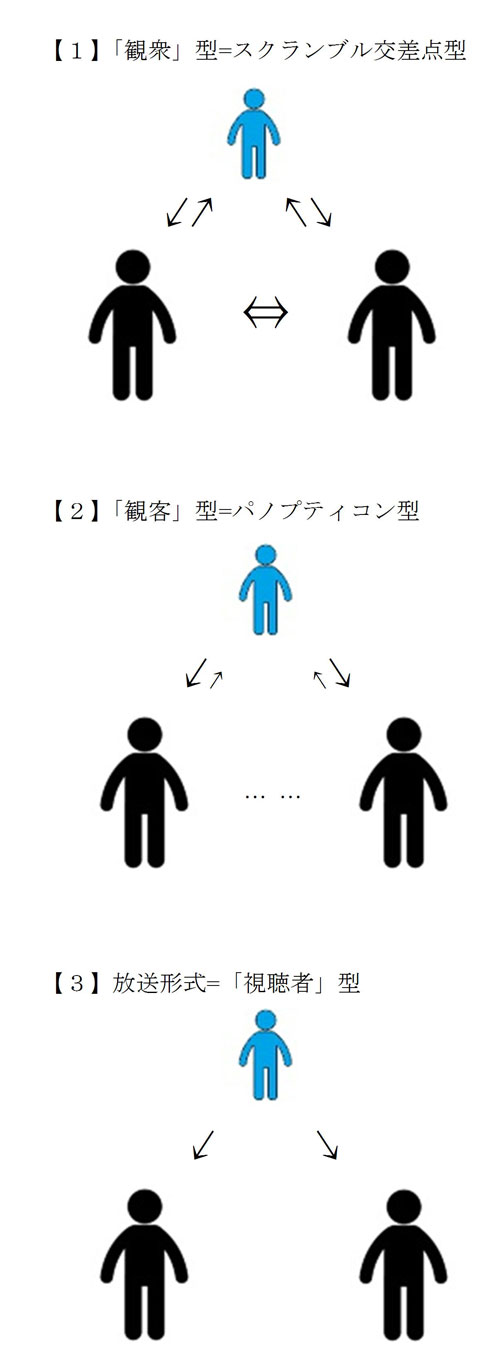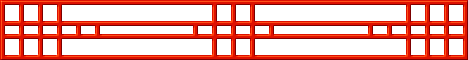東アジア芸術論 2014
この頁は、2014年度・国際日本学部・前後期兼用、授業用プラットフォーム (platform) 的な頁です。最新年度の授業用頁は[こちらの頁]を御覧ください。
This is an old webpage. Please view [the latest webpage].
この頁の短縮URLは http://p.tl/8YNe です。
| This webpage is my teaching materials for the students who take my Lectue on Art in East Asia, at The School of Global Japanese Studies,Nakano Campus, Meiji University. |
|
開講場所 明治大学 中野キャンパス 国際日本学部 金曜2限(10:40-12:10) 413教室 担当 加藤徹(法学部教授・和泉) 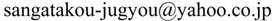 加藤の授業はペーパーレスです。随時、こちらに授業関連の内容をアップしてゆきます。 |
[シラバス] [レポートについて] [用語・術語] [教材リンク] [備忘録] [ミニリンク]
和泉キャンパスの芸術作品。「START LINE」「GOAL 40,000,000M-1M」

[こちらの頁も]
"The beginning and ending share the same moment. Good. Everything's going well." Keel Lorenz
「始まりと終わりは同じところにある。良い。全てはこれで良い」
「芸術」の本質を一言で言うと・・・
うつくしや障子の穴の天の川
この俳句についての[説明はこちら]
駿河台キャンパスの芸術作品。
|
|

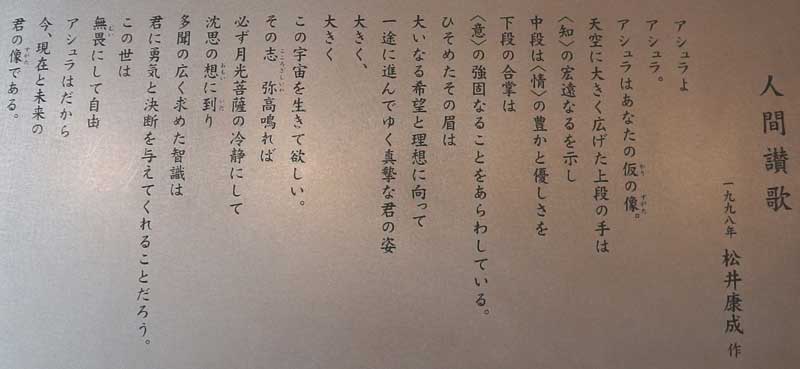

 シラバス
シラバス 参考 [Oh-o! Meiji]の授業シラバス検索機能
参考 [Oh-o! Meiji]の授業シラバス検索機能