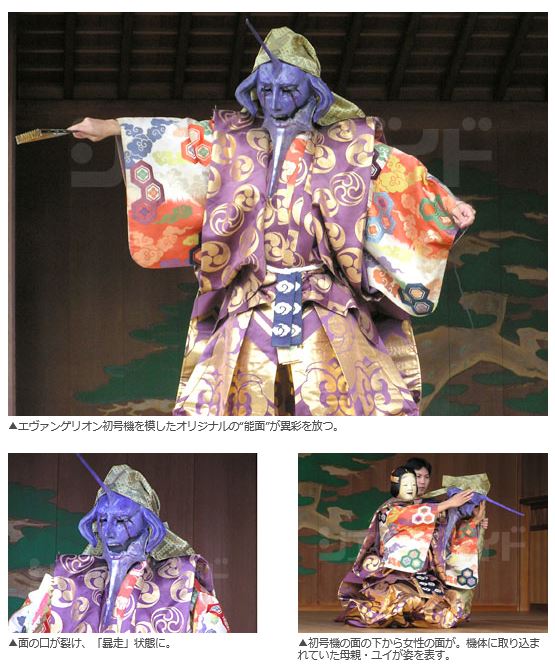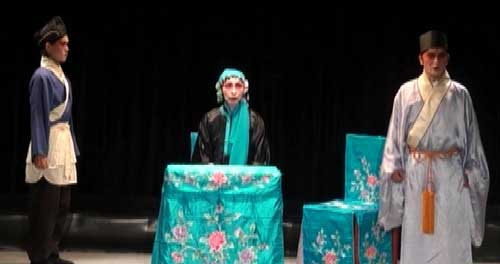| A.Waley(ウェイリー)の自由訳 | 左の大意 | 「谷行」原文の一例 |
|---|
|
1.TEACHER.
I am a teacher. I keep a school at one of the temples in the City. I have a pupil whose father is dead; he has only his mother to look after him. Now I will go and say good-bye to them, for I am soon starting on a journey to the mountains. (He knocks at the door of the house.) May I come in? |
師 私は教師です。都の寺で塾を開いています。生徒の中に、父親を亡くして女手一つで育てられた子がいる。
私はまもなく山へ旅に出るので、別れを告げに行きます。(家の戸をノックする)お邪魔します。
|
ワキ これは都東山、今熊野に住居する客僧にて候。さても某稚き弟子を一人持ちて候。名をば松若と申し候。
かの者父には後れ、母一人に候ほどに、不便に候いて常は里に置き候。また明日は、峰入を仕り候間、立ち越え松若に暇乞をせばやと存じ候。
いかに此の内へ案内申し候。 |
|
2.BOY.
Who is it? Why, it is the Master who has come out to see us! |
子 どなたです? ああ、先生がお見えになられた!
|
子方 たれにてわたり候ぞ。や、師匠のおんいでにて候。 |
|
3.TEACHER.
Why is it so long since you came to my classes at the temple? |
師 なぜこんなに長く寺の塾を休んでいるのかね?
|
ワキ 何とてこのほど寺へはおんあがりそうらわぬぞ。 |
|
4.BOY.
I have not been able to come because my mother has been ill. |
子 母が病気で行けなかったのです。
|
子方 さん候、母御の風の心地におんいり候ほどに、さて参らず候。 |
|
5.TEACHER.
I had no idea of that. Please tell her at once that I am here. |
師 それは知らなかった。私が来たと母上に伝えなさい。
|
ワキ なにと母御の風の心地におんいり候とや。それがしが参りたるよしおん申しそうらえ。 |
6.BOY. (calling into the house).
Mother, the Master is here. |
子 (奥に向かって)母さん、先生がいらした。
|
子方 かしこまって候。
いかに申し候。師匠のおんいでにて候。 |
|
7.MOTHER.
Ask him to come in. |
母 お入りいただいて。
| シテ こなたへと申せ。 |
|
8.BOY.
Please come in here. |
子 どうぞ中へ。
| 子方 かしこまって候
こなたへおんいりそうらえ。
|
|
9.TEACHER.
It is a long time since I was here. Your son says you have been ill. Are you better now? |
師 ご無沙汰いたしました。ご病気とうかがいましたが、お加減は?
| ワキ 心得申し候。
この間は久しく参らず候。風の心地におんいり候よし、松若殿仰せそうらいて承りてこそそうらえ。おん心地はなにとおんいり候ぞ。またみょうにった(明日は)峰入りをつかまつり候あいだ、おんいとまごいのために参りて候。
|
|
10.MOTHER.
Do not worry about my illness. It is of no consequence. |
母 ありがとうございます。たいしたことはございません。
|
|
11.TEACHER.
I am glad to hear it. I have come to say good-bye, for I am soon starting on a ritual mountain-climbing. |
師 それは良かった。実はお別れに来たのです。まもなく儀式の山登りに出かけます。
|
|
12.MOTHER.
A mountain-climbing? Yes, indeed; I have heard that it is a dangerous ritual. Shall you take my child with you? |
母 山登り? ああ、たしか、危険な儀式と伺っております。うちの子もお連れになるのですか?
|
シテ 風の心地は苦しからず候。また峰入りのおんことは、こと(殊)なる大事のおん行(ぎょう)とこそ承りてそうらえ。
さて松若は召し連れられ候か。
|
|
13.TEACHER.
It is not a journey that a young child could make. |
師 お子さんが来られるような旅ではないのです。
|
ワキ いやいや峰入りと申すは、難行捨身の行にて、おぼろげにてはかなわぬ事にて候。
めでとうやがて参ろうずるにて候。
|
|
14.MOTHER.
Well,--I hope you will come back safely. |
母 まあ、──ご無事でお戻りくださいますよう。
|
|
15.TEACHER.
I must go now. |
師 それでは。
|
|
16.BOY.
I have something to say. |
子 先生、ちょっと。
|
子方 いかに師匠に申し候。 |
|
17.TEACHER.
What is it? |
師 何かね?
|
ワキ 何事にて候ぞ。
|
|
18.BOY.
I will go with you to the mountains. |
子 山にお供したいのです。
|
子方 松若も峰入のおん供申し候べし。 |
|
19.TEACHER.
No, no. As I said to your mother, we are going on a difficult and dangerous excursion. You could not possibly come with us. Besides, how could you leave your mother when she is not well? Stay here. It is in every way impossible that you should go with us. |
師 いや、だめだ。母上にも申し上げたように、これは難しくて危険な旅だ。君を連れては行けない。それに、君はどうして病気の母上を残してゆけるのだ? 残りたまえ。君が一緒に来るのはとても無理だ。
|
ワキ ただいまも申し候ごとく、難行捨身の行にて、幼き者はかなわぬ事にて候。そのうえ母御の風の心地にござ候ほどに、かたがた思いもよらぬ事にて候。
|
|
20.BOY.
Because my mother is ill I will go with you to pray for her. |
子 母が病気なので、お供して、母のために祈りたいのです。
|
子方 いや母御の風の心地におんいりそうらえばこそ、おん祈りのため、かようには申しそうらえ。
|
|
21.TEACHER.
I must speak to your mother again. (He goes back into the inner room.) I have come back,--your son says he is going to come with us. I told him he could not leave you when you were ill and that it would be a difficult and dangerous road. I said it was quite impossible for him to come. But he says he must come to pray for your health. What is to be done? |
師 母上にお話ししよう。(奥の部屋に戻る)戻りました。──お子さんが、ついて来たいと申されます。
私は、さとしました、病気のあなたを残しては行けまい、それに難しく危ない旅路になる、と。ついて来るのは本当に無理だと申しました。
が、お子さんは、あなたの快復を祈るため、ぜひ来たいそうです。どうします?
|
ワキ げによく仰せ候ものかな。さらばそのよし母御に申そうずるにて候。
また参りて候。松若殿峰入りの供しょうずるよし仰せ候ほどに、母御の風の心地にござ候折節と申し、幼き者のかなわぬよし申してそうらえば、母御のおん祈りのため、峰入りしょうずるよし仰せそうらえども、まずこの度はおんとめあれかしと存じ候。
|
|
22.MOTHER.
I have listened to your words. I do not doubt what the boy says,--that he would gladly go with you to the mountains: (to the BOY) but since the day your father left us I have had none but you at my side. I have not had you out of mind or sight for as long a time as it takes a dewdrop to dry! Give back the measure of my love. Let your love keep you with me. |
母 お話しはわかりました。
息子の言葉は本心でしょう──山に喜んでお供したい、と。(子供に)でも、父上が亡くなられたその日から、私のそばにはおまえだけしかいなかった。
夜露が乾くほどの短い時間も、私はおまえを忘れたことも、目を離したこともない。
この親心に報いておくれ。後生だから、そばにいて。
|
シテ 峰入りのおんことは殊なる大事のおん行にて、幼き者のかなわぬよし仰せ候。そのうえ母が風の心地を見捨つべきか。かたがた思いとまりそうらえ。まずは松若申すごとく、師匠のおん供申し、峰入りをせん事こそ尤も望む所なれども、
おん身の父におくれし日より、ただひとりごのひたすらに、杖柱とも頼むかげの、身に添う時だに見ぬひまは、露ほどだにも忘られず、思う心を思えかし。ただただ思いとまりそうらえ。
|
|
23.BOY.
This is all as you say. Yet nothing shall move me from my purpose. I must climb this difficult path and pray for your health in this life. |
子 母さんの言うとおりです。でもぼくの心は変わりません。
この難しい道を登り、母さんの今生の健康を祈りたいのです。
|
子方 仰せはさる事にてそうらえども、心をとめておん身に添え、身は難行の道にいでて、母の現世を祈らんと、思い立ちたるばかりなりと、
|
24.CHORUS.
They saw no plea could move him.
Then master and mother with one voice:
"Alas for such deep piety,
Deep as our heavy sighs."
The mother said,
"I have no strength left;
If indeed it must be,
Go with the Master.
But swiftly, swiftly
Return from danger." |
合唱隊 どう言っても、彼は聞きいれそうになかった。
母と先生は声をそろえて言った。
「ああ、深い親孝行
われらの嘆きと同じくらい深い」
母は言った。
「もう、しかたない。
もしどうしてもと言うなら、
先生といらっしゃい。
でも早く、早く、
無事に戻っておくれ。」
|
地謡 かきくどきたるそのけしき、師匠も母ももろともに、あわれ孝行の深きや、涙なるらん。
シテ この上なれば力なし。さらば師匠のお供して、とくとく帰り給えや。
|
25.BOY.
Checking his heart which longed for swift return
At dawn towards the hills he dragged his feet.
|
子 子どもは、早く帰りたいと思う気持ちを押し殺し、
夜明けに足を引いて山に向かった。
|
ワキ・子方 帰るさの心をとめていづる日も、やがて急ぐやあしびきの大和路遠き思いかな。(以下省略) |
Footnote
Here follows a long lyric passage describing their journey and ascent. The frequent occurrence of place-names and plays of word on such names makes it impossible to translate.
|
脚注
原文ではこのあと彼らの旅と登攀を述べた長い詩が続く。地名や地名をもじった言葉遊びが頻出するため、翻訳不可能である。 |
|