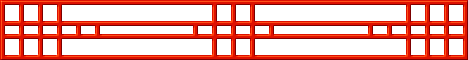引
用
文 | ――当時、「ジョーは死んだのか」という論争まで起こりました。ちばさんの中でも定まっていなかったのでしょうか。
ちば そういうことは全然考えていなかったですね。ただ自分の力を出し切って、持てるエネルギーのすべてを使い尽くして、真っ白に、抜け殻のようになっているという、そう考えながら描いたシーンですね。ある時たまたまテレビで見たのですが、上野正彦さんという監察医があの絵を見て、「生きているか死んでいるか」と訊かれて、「こういう微笑みや、肘で身体を支える姿勢は、死んでいたらできないから、この人は生きている」と断言してくれて、「ああ、そうだったのか。やっぱり生きているのか」とホッとした記憶があります。
|
出
典 | 月刊『新潮45』2013年10月号、ちばてつや「あしたのジョーは生きている」(インタビュー)、聞き手・里中高志、p.149-p.150より引用
|
加
藤
注 |
〇ちばてつや(1939-)漫画家。「あしたのジョー」の作画担当。梶原一騎の原作のラストにあきたらず、原作者や担当編集者と話した末、主人公が真っ白になってリングサイドに座っている絵、という後に伝説化したラストを創作した。
〇上野正彦(1929-)法医学者、医事評論家。著書多数。『死体の嘘 世田谷一家殺人事件から『あしたのジョー』まで』(アスキー, 2001.10)など
|


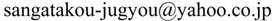
 シラバス
シラバス