白蛇伝 授業用メモ
最初の公開2015-12-4 最新の更新2021-12-10[https://www.youtube.com/playlist?list=PL6QLFvIY3e-lLDEzmdGa4oRS29EyE3GfH]
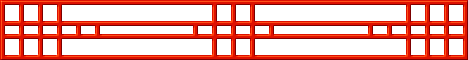
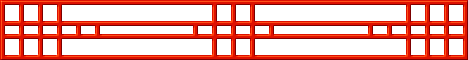
 【各国語によるタイトル】
【各国語によるタイトル】
| 日本語 | 『白蛇伝』(はくじゃでん Hakujaden) |
| 中国語 | 『白蛇傳』/《白蛇传》(bái shé zhuàn) |
| 韓国語 | 《백사전》 |
| 英語 | Legend of the White Snake (or,Madame White Snake,The Tale of the White Serpent ) |
 【白蛇伝が戦後日本のソフトパワーの出発点に】
【白蛇伝が戦後日本のソフトパワーの出発点に】
|
日本のアニメ映画は、2003年に『千と千尋の神隠し』米国のアカデミー賞を受賞するほど海外でも人気と評価を得るようになった。その出発点になったのは、1958年の東映動画『白蛇伝』だった。 以下「ほぼ日刊イトイ新聞」の記事「ジブリの仕事のやりかた。宮崎駿・高畑勲・大塚康生の好奇心。」第8回「先人からのバトンタッチ。」https://www.1101.com/ghibli/2004-07-26.html(2019/12/15閲覧)より引用。文中の太字、赤字は加藤徹。原文の改行も加藤が減らした。文中の「糸井」は糸井重里(いとい・しげさと)氏、「鈴木」は鈴木敏夫(すずき・としお)氏。引用開始。 鈴木 日本映画はある時期まで5社が支配していて、そのいちばん後発が東映ですよね。大川博という社長が作って、いちばん後発だったにも関わらず、映画会社としては大成功するわけです。(加藤徹注:大川博=おおかわ・ひろし、1896年-1971年。1951年に東映の社長に就任。海外輸出を見据えて1956年に日動映画を買収して同社を東映動画と改称。) 市川右太衛門、片岡千恵蔵が、日本国内で大ヒットしていた……だけど、大川さんという人は、野心があったんですね。 「確かに日本の国内ではうまくいっている。ところが、日本の映画というのはなかなか海外に出ていくことがない。日本人はたいがいの人が洋画をたのしんでいるじゃないか。なんとか、この日本から海外に発信できるものはないか……」 そこでこの人が目をつけたのがアニメーションなんです。 糸井 へぇー。そういうふうにはじまったんですか? 鈴木 東映のアニメーションの長編映画第1作目は『白蛇伝』っていうものだけど、この作品から、実はもくろみとしては「海外進出」が設定されていたんです。(加藤徹注:当時の日本ではまだ「アニメ」や「アニメーション」という言葉は一般的ではなく、「まんが映画や「まんが」等と呼ばれた。) 「中国ものをやりましょう。中国ものを作れば、中国に輸出ができますし、広く東南アジアはうまくいきます」 大川博という人は、こうやって大風呂敷を広げて、実際にうまくいくんですけど、そうして作った『白蛇伝』の映画の予告編のなかに、みずから登場しているんです。(加藤注:https://youtu.be/0OYPDwv1Afo) そこで演説をぶつんですね。なんだか、すごかったんですよ。 「私は……東洋のディズニーになります!」と。 糸井(笑) 鈴木「これから向こう10年、1年に1本ずつ、長編映画を作っていきます。だから、我こそはと思う人は、どんどん来ちゃって下さい」 社長みずから、予告編で求人をしちゃうんです。その呼びかけに応じたのが、まだ学習院大学に入るために受験生をしていた宮崎駿なんですよ。 高畑さんは『白蛇伝』を見たときには翌年の入社が決まっていたんですが、やはりその予告編を見ていたそうです。 宮崎駿は、高校時代に見た『白蛇伝』でガーンときて、東映動画に行っちゃうんです。他にも、とにかくいろんな人材が、翌年から東映動画にポンポンポンポン入ってくるんです。これがスタートになっちゃうんです。 (中略) 糸井 じゃあ、『千と千尋の神隠し』がアメリカでアカデミー賞を取るなんていうのは、大川博さんの野望の延長線上に起きた出来事なのかもしれない。(加藤徹注:『千と千尋の神隠し』2001年のアニメ映画。外国語でのタイトルは、Spirited Away / 센과 치히로의 행방불명 / 千与千寻 / 神隠少女、等々。2003年、第75回アカデミー賞長編アニメーション部門=Academy Award for Best Animated Feature 受賞。) 鈴木 あのアカデミー賞を、いちばんよろこんでいるのは 大川博だと思うんです。 大川博がアニメーションづくりをスタートさせたのが昭和33年、1958年ですよ。 それから10年ちょっとで作った『太陽の王子 ホルスの大冒険』という映画は、ある評論家からは「日本の長編アニメが、はじめてディズニーを超えた」と絶賛されているんです。 大川さんはうれしかったでしょうねぇ。この『ホルス』は、高畑・宮崎のコンビで作られたもので、そこに大塚さんも入っているわけで……だからこそ、糸井さんがおっしゃるように、『千と千尋』が、いろんな賞をいただけたのを、たぶんいちばん喜んでいるのは、 大川博じゃないかなぁと思うんです。 |
 【白蛇伝の登場人物】
【白蛇伝の登場人物】
 許仙をめぐり、法海と白素貞(白蛇の精)が対立。 下の三角形:許仙(夫)−白素貞(妻/女主人)−小青(下女) 小青は「わたしの大好きなおねえさまを苦しめる許仙が許せない。おねえさまはどうして目をさましてくれないの?」と、許仙を憎む。 |
 【白蛇伝のテーマ】
【白蛇伝のテーマ】
 「白蛇伝」に含まれる、主な演目
「白蛇伝」に含まれる、主な演目
|
【前日譚】(現在の京劇では廃止。地方劇では残る) 「下山」(桂枝羅漢=許仙)「収青」 【本編】 「遊湖借傘」「盗庫銀」「訂盟」「端陽驚変」 「盗仙草」「水闘(水漫金山)」「断橋」「合鉢」 【後日譚】(現在の京劇では簡素化) 「祭塔」「仏円」 / 「倒塔」 |
|
【中国国家京劇院 2016年来日公演時の「白蛇伝」の2幕10場】(京劇公演事務局・楽戯舎) 第1幕 第1場「遊湖」、第2場「結親」、第3場「説許」、第4場「酒変」、第5場「盗草」 第2幕 第6場「観潮」、第7場「索夫」、第8場「水闘」、第9場「逃山」、第10場「断橋」 |
 【現行の京劇の白蛇伝のあらすじ】
【現行の京劇の白蛇伝のあらすじ】
|
【断橋】金山寺で敗退した白蛇と青蛇は、西湖の断橋まで逃げる。そこへ、許仙が走ってきて追いつく(金山寺と西湖の距離は、東京の浅草寺と静岡県の浜名湖ほども離れているが、それは聞かないお約束)。青蛇は怒って許仙を殺そうとする。白蛇は青蛇をおしとどめ、自分の思いを切々と歌う。最後は和解する。(ここで上演を終わる場合もある) 【合鉢】白蛇は隠れ家で、許仙の子を生む。その直後、法海らに踏み込まれる。法海は、白蛇を「金鉢」の中に吸い込んで捕えた。その後、白蛇は、西湖のほとりにそびえ立つ雷峰塔の下に封じ込められた。 ★ ここから先は、結末が分岐しています。★ 古い結末。悲劇ののち「成仏」。 【祭塔】許仙と白蛇の息子は人間の子として成長し、勉学の末、難関の科挙の試験に合格した。青年となった息子は、母が封じ込められている雷峰塔を訪れ、母の霊と対面する。【仏円】この世のすべては仏陀の思し召しである。煩悩即菩提。愛欲と罪障は、悟りに至る道程であった。時が満ちて、白蛇は仏の慈悲によって塔から解放され、成仏する。 現行の白蛇伝の結末。ハッピーエンド。 【倒塔】落ち延びた青蛇は、山で修行を積んで、さらに強くなった。数年後、青蛇は雷峰塔を倒壊させ白蛇を救出する。白蛇は許仙と、幼い息子、青蛇と再会する。(終わり) ★参考:民間説話の後日譚「蟹和尚」 法海が白蛇を調伏したあと、民衆は「白蛇があまりにもかわいそうだ。法海は坊主のくせに慈悲の心がない」と憤った。民衆の怒りは天に通じた。天兵天将がくだり、法海を攻めた。法海は逃げ場所がなかったので、苦しまぎれに大閘蟹(日本で「上海がに」と呼ばれる蟹)の甲羅の中に逃げ込んだ。今でも上海がにを食べると、甲羅の中に「蟹和尚」と呼ばれる部位を見つけることができる。蟹和尚は、色も形も、袈裟を着てすわる法海の姿そっくりである。 |
 【「白蛇伝」の物語の舞台】
【「白蛇伝」の物語の舞台】
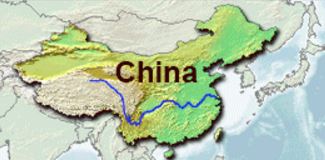
 【「白蛇伝」関連の過去の主な作品】
【「白蛇伝」関連の過去の主な作品】
| 北宋 | 『太平広記』「李黄」 | 唐の時代の怪談。白蛇伝の起源とみなす説もある |
|---|---|---|
| 南宋 | 『孔淑芳双魚扇墜伝』 | 白蛇伝の原型ないし同系と思われる物語 |
| 明 | 『西湖三塔記』 清平山堂話本 | 白蛇伝の原型の物語 |
| 明 | 馮夢竜(1574-1646)『警世通言』「白娘子永鎮雷峰塔」 | 小説。「古い白蛇伝」の決定版 |
| 清 | 【戯曲】方成培(1713−1808)『雷峰塔伝奇』 | 京劇以前の、長編の「白蛇伝」の芝居。過渡期の作品 |
| 清 | 【謡い物】『義妖伝』弾詞 | 白蛇を正義の味方として描く新しい白蛇伝。語り物 |
| 中華人民共和国 | 【戯曲】京劇「白蛇伝」田漢(1898-1968)本 | 下記を参照。 |
|
|
 【日本との縁】
【日本との縁】
| 1776年 | 上田秋成(1734-1809)『雨月物語』刊行。 『警世通言』の白蛇伝を翻案した怪奇小説「蛇性の婬」を含む。 |
| 1956年 | 梅蘭芳(メイランファン)を団長とする京劇団が来日。 白蛇伝の演目「盗仙草」「水漫金山」も上演。 |
| 1956年 | 東宝映画『白夫人の妖恋』公開。 出演は山口淑子(白素貞)、八千草薫(小青)、池部良(許仙)、徳川夢声(法海)、他。 |
| 1958年 | 東映動画『白蛇伝』(アニメ)公開。 声の出演は、森繁久彌と宮城まり子。 cf.NHKの朝ドラ「なつぞら」 |
 その他、メモ書き
その他、メモ書き
