 |
|
 |
|
 |
| 『自然体のつくり方−レスポンスする身体へ』 齋藤 孝著 |
| (太郎次郎社,2001,\2,000) |
|
 |
それは誰でも獲得できる<技>である
〜内なる「中心感覚」と、
他者との「距離感覚」を習得する〜
|
|
|
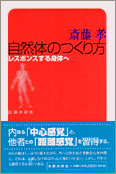 |
| 書評1 評者:関川夏央(作家) |
| 書評2 評者:栗原彬(政治社会学) |
 |
プロローグ 「自然体」から「レスポンスする身体」へ
なぜ<身体文化カリキュラム>が必要なのか/身体という大きなテーマを絞り込む/内なる中心感覚と、他者との距離感覚と/失われた自然体を「技化」でとり戻す/無反応な冷えたからだが増えている/レスポンスする身体とはどういうものか/応答サインのやりとりを習慣化する/自然体の構えからレスポンスする身体へ/公共的な場でのコミュニケーション力を高める/「息を合わせる」感覚を技として身につける/シンプルで、だれでもできるメニューとして
第1部 自然体のつくり方
1.自然体とはどういうものか
上半身は柔らかく、下半身は力強く/電車のなかでも鍛えられる中心感覚/不測の事態にパニックしない柔軟な構え/宇宙とのつながり感を生む自然体/リラックスしながらも集中した身心の状態
2.足腰のつくり方
へっぴり腰か、「腰が決まっている」か/四股立ち−ねばり腰の土台づくり/一流のサッカー選手はなぜ転ばないか/六方−歌舞伎の型を踏む/背負う−重さが目覚めさせる身体の感覚/カベ押し−「つっかい棒」型と「腰の入った」型/ストップ・アンド・チェックの相撲/すり足−静寂と無心の境地を味わう
3.足裏感覚
土踏まず−「踏んばれる」足裏のキーポイント/「湧泉」のツボ−心地よく全身に伝わる芯の感覚/鼻緒−足指で大地をつかむ感覚/手足と腰肚をつなぐ回路をつくる/「労宮」のツボ−外界の気を感じとるてのひら感覚/竹刀やラケットは小指から握る/指先にまで神経を通わせる/緊張と弛緩をコントロールする/腰をおとして踏んばる姿のソーラン節
4.上半身のつくり方
力まず方の力を抜く「上虚」づくり/腕はどこからはじまるのか/二人で行う肩胛骨マッサージ/野口三千三の「上体ぶら下げ」体操/みずおちをおとす−緊張をゆるめる技/みずおちをゆるめて動きを引きだす活元運動/スワイショウ−でんでん太鼓のような回転運動
5.肚の感覚
懐を深くする−「受ける」ゆとりを生む技/肚を据える−動揺しない重心感覚/二分間丹田呼吸法−息を吐いて集中する技/名詞で割りばしを折る
6.方向性をもった感覚
石になる、水になる/サンス−方向性をもった身体の感覚/いくつものサンスを共存させる/動きのなかでいかされる自然体/中心軸がブレない歩き方/反復運動で不必要な力を抜く/自分のからだの緊張に気づく技
第2部 レスポンスする身体
1.コミュニケーションできる身体とは
人に、場に、応答できる身体/他者との関係をつくる距離感覚/コミュニケーションが自然体をつくる/公共的な場での身体技法を位置づけなおす/ディスカッションにはどんな距離感覚が必要か/演劇メソッドを日常の振る舞いにいかす/ふりかけ事件−「NO」を表現できるからだ/レスポンス・アビリティ/応答責任能力
2.息を合わせる
相手の呼吸をはかって息を合わせる/指圧・マッサージは息の合わせ方が決めて/のしいかマッサージ−「積極的受動性」の構え/能動・受動を自在に反転させる/相手に「沿いつつずらす」動きの技化/投げられて、転がる/息を合わせて上手な抵抗をかける
3.中心軸をやりとりする
たがいの中心軸(正中線)をとりあう/流す感覚、ねばる感覚/まかせる感覚、背負う感覚/上手におんぶする・される/目をつぶってまかせる−ブラインド・タクシー/大人と子どもで楽しむ−おんぶタクシー
4.欧米流のパブリックな身体技法
アイコンタクトを技化する/目と目で意思疎通する−囚人ゲーム/目・声・アクションで−ジップ・ザップ・ボイン/間合いと息づかいを聴く−カウントゲーム/場の雰囲気を感じとって動く/うなずくというレスポンス/相づちで会話のリズムを調える/レスポンスのキメ言葉をつくる/自分のレスポンスの癖を技化する |
|
 |
 |
|