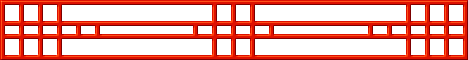
曜日 火曜日 時間 10:40~12:10 日程 全5回 ・10月24日 ~ 11月21日自己引用終了。
(日程詳細) 2023/10/24, 10/31, 11/07, 11/14, 11/21
目標
・私たちが生きている今の時代がこのようになった理由を考える。
・日本史と中国史という枠組みを取り払い、世界的な視野から東アジアを見直す。
・歴史の予備知識がない人にも、身近なことから考える楽しさを体験してもらう。
講義概要
中国史で首都となったことがある古都――長安、洛陽、開封、南京、北京は、それぞれ長い歴史をもつ個性的な都市です。この5つの古都の地理的条件はバラバラです。なぜ中国の首都はダイナミックに移動してきたのか。紀元前11世紀から21世紀まで、中国文明の変遷の歴史と、それぞれの古都の魅力を、豊富な映像資料を使い、予備知識のないかたにもわかりやすく解説します。
 第1回 長安 ――前漢と唐の世界帝国の首都
第1回 長安 ――前漢と唐の世界帝国の首都
長安は、紀元前3世紀に前漢の初代皇帝・劉邦が築かせた首都でした。以来、歴代の王朝や政権の首都として栄えました。唐の時代の長安は人口100万の国際都市であり、日本の平城京や平安京をはじめ東アジアの都市設計に大きな影響を与えました。しかし11世紀以降は地方都市に戻り2度と首都になることはありませんでした。玄宗皇帝や楊貴妃、李白、杜甫、空海らも暮らした世界都市・長安の歴史と魅力を、豊富な映像資料を使い、予備知識のないかたにもわかりやすく解説します。
長安 ちょうあん
中国中東部,黄河支流の渭水 (いすい) 下流域にあった古都。現在は陝西 (せんせい) 省の省都西安 (せいあん) (シーアン)
渭水盆地の中心都市で,早くから要害の地として知られ,前漢の首都となってのち,五胡十六国時代の前趙 (ぜんちよう) ・前秦 (ぜんしん) ・後秦 (こうしん) ,南北朝時代の西魏 (せいぎ) ・北周・隋・唐がここに都を置いた。特に栄えたのは前漢・唐の時代で,前漢時代は周囲が約28㎞,城の内外に9つの市があった。唐の長安は,隋の文帝楊堅が造った大興城に手を加えた東西約10㎞,南北約8㎞の大規模なもので,宮城・皇城(官庁所在地)・市・住宅地をもつ計画都市であった。最盛期は玄宗 (げんそう) のころ(8世紀前半)で,人口は100万に達し,渤海 (ぼつかい) ・新羅 (しんら) ・日本・ペルシア・アラビア・インド・トルキスタンから人が集まる国際的な文化都市であった。日本の平城京・平安京,渤海の上京はこれをまねて造られた。
| 長安一片月 | 長安 一片の月 | ちょうあん いっぺんのつき |
|---|---|---|
| 萬戸擣衣声 | 萬戸 衣を擣つの声 | ばんこ ころもをうつのこえ |
| 秋風吹不尽 | 秋風 吹きて尽きず | しゅうふう ふきてつきず |
| 総是玉関情 | 総て是れ玉関の情 | すべてこれ ぎょっかんのじょう |
| 何日平胡虜 | 何れの日か 胡虜を平らげて | いずれのひか こりょをたいらげて |
| 良人罷遠征 | 良人 遠征を罷めん | りょうじん えんせいをやめん |
 第2回 洛陽 ――歴史と文化の落ち着いた古都
第2回 洛陽 ――歴史と文化の落ち着いた古都
洛陽は、紀元前8世紀の東周から10世紀の唐末まで、2千年間にわたりたびたび中国の首都となった古都です。西の長安が栄華を誇る政治都市だったのに対して、東の洛陽は落ち着いた感じの文化都市でした。長安を首都とした唐の時代も、武則天(則天武后)の時代は洛陽が首都でした。芥川龍之介の『杜子春』や司馬遼太郎の「洛陽の穴」など日本人の洛陽観にも触れつつ、洛陽の歴史と魅力を、豊富な映像資料を使い、予備知識のないかたにもわかりやすく解説します。
らくよう〔ラクヤウ〕【洛陽】
(1)中国河南省北西部の都市。洛河北岸にある。西周時代に都として建設され洛邑(らくゆう)とよばれ、漢代に改称、北魏・晋・隋・後梁・後唐などの首都。唐代には長安に対して東都とよばれ、経済・文化の中心として繁栄した。現在は機械製造が盛ん。白馬寺・竜門石窟など古跡が多い。人口、行政区149万(2000)。ルオヤン。
(2)京都の異称。
(3)平安京の左京の異称。右京を「長安」というのに対する。
洛陽市〔中華人民共和国〕
位置 中華人民共和国の内陸に位置する河南省第2の都市で、北京の西南約850キロメートルにある。
人口 約714万人 【加藤注:655万人 (2019年)】
面積 約15,230平方キロメートル(市街地面積は803平方キロメートル) 【加藤注:東京都区部の面積は619平方キロメートル】
河南省の西部、黄河の中流に位置する洛陽市は、内陸の割には比較的温暖で、四季がはっきり分かれている。周囲を山脈に囲まれ、黄河の支流、洛河の河谷盆地にある。市街行政区は老城区、西工区などの6区に分かれ、ほかに1市、8県を管轄下に置く。
洛陽は歴史上、十三の王朝が1529年もの間、都を置いた古都であり、北京、西安、開封などと並び、「中国七大古都」のひとつに数えられており、世界遺産の龍門石窟や中国最古の仏教寺院と伝えられる白馬寺、三国時代の武将・関羽の墓のある関林廟など、数多く名所旧跡が残っている。洛陽を中心とする河洛地域は中華文明発祥の地であり、また、シルクロードの中国側の起点とされている。
市花である牡丹は特に有名で、毎年4月に行われる「洛陽牡丹文化節」には、国内外から観光客が訪れる。中国歴史文化の都と称される有名な観光都市である。
日本との時差は-1時間。
|
洛陽というのは、宋において衰微するまでは、大した町であった。唐代では首都が長安であったとはいえ、なお副首都の位置を保っていたとされる。 唐の長安は世界都市として当時、遠く西方にまで光芒を放っていたが、その背後地である「関中」は秦漢時代ほどの農業生産力をもたなくなり(長安の消費人口が大きすぎたために)、食糧その他の物資は洛陽にあおがざるをえなかった。このため洛陽が副首都とされ、長安なみとまではゆかなくても相当な規模の宮殿や官衙が備えられていた。 日本史でできた先入主では信じがたいことだが、皇帝でさえ長安で食糧不足になると、めしを食うために(ごく具体的な意味で)洛陽まで出てきて長期滞在した。百官を連れてきた。当然後宮の女どももきた。みな洛陽で、数万人の支配階級とその寄生者たちが、箸をうごかしてめしを食った。 星斌夫(ほしあやお)氏の『大運河』(近藤出版社)によれば、玄宗皇帝などは洛陽にやってきてめしを食うことがしばしばで、それより前、盛唐のころの高宗などは、在位三十三年のうち十一年もこの洛陽で暮らしたという。江南の穀倉地帯から大運河などの水路をへて食糧が洛陽まではこばれてくる。洛陽から長安への輸送は険阻な陸路が多く、難渋をきわめた。その輸送を待つより、いっそ口を洛陽に持って行って食物を食うほうが手っとりばやく、そういう発想で洛陽への行幸が営まれた。その移動は百官や後宮の女たち、宦官たちをふくめると、一万数千人になったであろう。かれらが洛陽に移って最初の食卓で箸をとりあげることを想像するとき、一万数千人のはげしい咀嚼音がきこえそうである。江南から洛陽への食糧輸送は、経費も労働も、すべて農民たちの負担によった。その輸送は、挙げて政治都市長安の政治組織にめしを食わせるためだったことを思うと、支配と被支配の関係がひどく簡単なような気がする。 (中略)中国においては日本の奈良朝以前から洛陽(あるいは塩の揚州もふくめて)という大きな商業機能が存在し、これによって中国人が洛陽の機能を通じ、物価、交通、輸送、需給の相関といういきいきした商業的思考法を身につけたということである。この刺激は経済を知るだけでなく、モラルの点でも多くのものを中国思想に加えたかと思える。 (中略) 「この含嘉倉の穴の中に、二十五万キログラムから三十万キログラムまでの穀物を入れることができます。保存の能力は、粟なら九年、米なら五年です」 と、説明者がいった。 ともかくも、洛陽には現在発見されているだけで二百六十一個というおびただしい穀物収蔵用の窖(あなぐら)の跡があるということから想像すると、隋唐時代におけるこの副首都がどんな機能をもっていたかが、具体的にわかってくるような気がする。 |
|
洛陽は、東周、後漢、曹魏、晋、北魏、隋、唐、後梁、後唐の九つの王朝の首都であったので、「九朝王都」と呼ばれている。 最も栄えたのは、隋、唐の時代であったが、それぞれの王都の時代は、華々しく栄えていた。 後漢時代、明帝がある明け方夢を見た。金色に光り輝く人が項(うなじ)から白光を出し、空から宮廷に飛び降りてきた。 (中略) 中国に仏教が伝来した最初の伝説である。 明帝は、洛陽の郊外に寺を建て、二人のインド僧はそこで終生暮した。寺は、経典を運んだ馬にちなんで白馬寺と名づけられた。 仏教が最初に根を下したのが洛陽であるということは見のがすことが出来ない。 (中略) 洛陽の街はどこへ行っても静かだった。 (中略) 殷賑を極めた古都の大建築も、胡人の朝貢の列の鳴らす異域の音楽の旋律も、凱旋を告げる軍鼓のひびきも、夢のまた夢の中に幻の影をたゆたわせているだけで、現実の洛陽の木もれ陽は、絹糸のようにやさしく、靴の下の土には、匂いとやわらかさを千古のままに伝えて、生きていた。 |
|
十 洛陽 モハメット教の客桟の窓は古い卍字の窓格子の向うにレモン色の空を覗かせている。夥しい麦ほこりに暮れかかった空を。 麦ほこりかかる童子の眠りかな |
|
或春の日暮です。 唐の都洛陽の西の門の下に、ぼんやり空を仰いでゐる、一人の若者がありました。 若者は名は杜子春とししゆんといつて、元は金持の息子でしたが、今は財産を費ひ尽くして、その日の暮しにも困る位、憐れな身分になつてゐるのです。 何しろその頃洛陽といへば、天下に並ぶもののない、繁昌を極めた都ですから、往来にはまだしつきりなく、人や車が通つてゐました。門一ぱいに当つてゐる、油のやうな夕日の光の中に、老人のかぶつた紗の帽子や、土耳古の女の金の耳環や、白馬に飾つた色糸の手綱が、絶えず流れて行く容子は、まるで画のやうな美しさです。 しかし杜子春は相変らず、門の壁に身を凭(もた)せて、ぼんやり空ばかり眺めてゐました。空には、もう細い月が、うらうらと靡いた霞の中に、まるで爪の痕かと思ふ程、かすかに白く浮んでゐるのです。 「日は暮れるし、腹は減るし、その上もうどこへ行つても、泊めてくれる所はなささうだし――こんな思ひをして生きてゐる位なら、一そ川へでも身を投げて、死んでしまつた方がましかも知れない。」 杜子春はひとりさつきから、こんな取りとめもないことを思ひめぐらしてゐたのです。 |
|
洛陽攻略戦は機動砲兵隊が部隊の掩護をしつつ、敵軍に包囲された洛陽を見下ろす三山村の台上に陣地を構築しました。昼間、洛陽より撃ち出す砲弾が陣地周辺に落下し気味が悪かったものですが、夕方、軍砲兵隊が敵の発射光を目標にして三発目で制圧したのには、その精度の良さに感服しました。 洛陽の十キロほど手前の竜門峡の隘路の戦闘や白沙鎮の戦闘では戦死者が出ました。この竜門峡は山全体に何万と知れない多くの石仏の彫刻があり、それを見ることが出来ましたが、戦争中であり平和になったらぜひ今一度と思っておりました。戦後に二度ほど行きましたがここは中国の観光地として有名です。 河南作戦である中国の古都洛陽に対する総攻撃は、四月二十日、火蓋が切って降ろされ、五月二十五日に陥落しました。 |
 第3回 開封 ――中国人がもっともなつかしさを感じる古都
第3回 開封 ――中国人がもっともなつかしさを感じる古都
中国の中央部に位置する開封は、紀元前4世紀、戦国時代の魏が首都・大梁をこの地に置いて以来、五代十国の諸王朝や北宋の首都が置かれました。特に北宋時代の開封は、活気に満ちた商業都市としても繁栄し、庶民文化が花開きました。開封の繁栄ぶりは、『東京夢華録』や『清明上河図』などの歴史資料でも描かれています。また、古典小説『水滸伝』や井上靖の歴史小説『敦煌』、日本でも放送された中国の歴史ドラマでも開封は物語の舞台として登場します。開封の歴史と魅力を、豊富な映像資料を使い、予備知識のないかたにもわかりやすく解説します。
開封 かいほう Kāifēng
中国河南省北東部,黄河流域にある都市。汴州 (べんしゆう) ・汴京ともいう。
戦国時代の魏 (ぎ) の都大梁 (たいりよう) として繁栄し,のち梁州・汴州などが置かれ,中原 (ちゆうげん) の一大中心地であった。隋代に大運河通済渠が開かれると,南北運輸交通の要衝を占め,経済の中心地として一段と発展。また,五代(後唐を除く),さらに北宋の首都として繁栄した。その繁栄の様子は張択端 (ちようたくたん) の「清明上河図」や,孟元老の『東京夢華録 (とうけいむかろく) 』に詳しい。
ほく‐そう【北宋】
中国の王朝(九六〇‐一一二七)。宋朝が靖康の変で金の圧迫により江南に移るまでをいう。趙匡胤(太祖)が五代のあとをうけて建国。首都は汴(べん)(=開封)。第二代太宗が中国を統一。集権的官僚制を樹立したが、遼・西夏・金の台頭により対外的にはふるわず、内政でも新旧両法党の党争により疲弊。士大夫・庶民の新文化が誕生した時代として重要。宋。
水滸伝 すいこでん
中国の代表的な長編口語小説。四大奇書の1つ
北宋末期に山東の湖,梁山泊 (りようざんぱく) に集まった宋江 (そうこう) 以下108人の豪傑が,貪官汚吏 (どんかんおり) に抗して山東・河北の地を荒らしまわる武勇伝。元の施耐庵 (したいあん) の原作,明の羅貫中 (らかんちゆう) の編纂 (へんさん) といわれるが,すでに南宋時代に読本 (よみほん) として民間に普及し,元代に戯曲化され,明初期に完成したと推定される。
「清明上河図」は、北宋の都・開封(かいほう)(現在の河南省開封市)の光景を描いたものと言われています。作者である張択端(ちょうたくたん)は、北宋の宮廷画家であったということ以外、詳しいことがほとんど分かっていない謎の画家です。全長約5メートル、縦24センチの画面のなかに登場する人物は773人!(異説あり) 。まさに神技です。
汴河(べんが)の流れに沿って、市民の生活が衣食住にいたるまで細かに描かれ、宋代の風俗を知るためにも一級の資料です。北宋文化の絶頂期・徽宗(きそう)皇帝のために描かれたとされ、庶民の幸せな日常生活が画面に満ち溢れています。後世にもたくさんの模本が作られました。
ここまで精密に描かれた都市風景は、もちろん同時代の西洋にもほとんどありません。北京故宮でも公開される機会はごくまれで、上海博物館で公開された時は夜中まで行列が続いたほどの熱狂的大ブームを巻き起こしました。まさに中国が誇る至宝であるとともに、世界でも屈指の幻の名画なのです。
(中略)
清明上河図のクライマックス、虹橋の場面です。虹橋(にじばし)とは橋脚を使わず、木組みだけで支えられたアーチ型の橋。虹の形に見えることから虹橋と呼ばれ、橋の下を船が通り抜けられるように開発されたものです。かつて開封に実在し、高い建築技術がうかがえる名橋でした。右からくる船がマストをおろし、虹橋にさしかかります。船首で大声を出して叫んでいる水夫、橋桁から身を乗り出すヤジ馬たち…。宋代の都市の喧騒が聞こえてくるような名場面です。
画面左に見られるひときわ高い建物が見えます。この建物はお店で、酒楼です。河べりのお座敷で一杯、といったところ。今も昔も、同じく楽しい時間ですね。旗には「新酒」の文字が描かれています。木組みの克明な描写も必見です。清明上河図には都市に生きるさまざまな職業の人たちが描かれています。
北宋の首都の開封は、大運河と黄河をつなぐ地点にある商業都市であり、長安が遊牧地帯には近いが中国のなかでは西北の隅にあったのと比較すると、中国内部の東西南北の交通の要に位置していた。城壁の中の道路は整然たる碁盤の目状ではなく、入り組んだ道が主流であり、また城内には運河が掘られていた。長安では、道路で区切られた一つ一つの区画が壁で囲まれていたが、開封ではそのような壁はなく、商店は直接道路に面していた。
はじめて見る開封の景色はなにもかも珍しかっただろう。運河、とりわけ?河を通行する沢山の船は、人々を驚かせたはずである。その混雑ぶりに驚きつつ、入城すると、そこはもう世界有数の大都会で、宏壮な建物が並んでいる。荷物を宿においた人々は、なにをおいても城内のそこかしこに出かけたことだろう。例えば宮城。日本からの旅人である成尋もただちに宮城のまわりを歩いている。「我が国の御所のごとし」。これが彼の感想である。実際、宋の宮殿は小さい。『水滸伝』を読むと、密かに忍び込んだ宋江の手のものの柴進がまるで天国かなにかのように感嘆しているが、じじつはそれほどでもない。(中略)
経済的に繁栄し、人々が密集すれば、盛り場ができる。これも定石どおりのことである。(中略)開封が真に開封らしい姿を見せるのも歓楽街であった。これは瓦子(がし)とよばれる。ほかにも瓦、瓦市、瓦舎などとよぶ。人が集まるときには瓦のようにひしめき、散るときは瓦のように砕けるからというのが語源という。
 第4回 南京 ――ここに首都を置く王朝は短命というジンクス
第4回 南京 ――ここに首都を置く王朝は短命というジンクス
南京は、中国四大古都(西安・北京・南京・洛陽)の1つです。西暦229年「三国志」の孫権が呉の都「建業」を現在の南京に置いて以来、六朝時代(呉・東晋・宋・斉・梁・陳)や、明王朝の初期、清末の太平天国、20世紀の中華民国は、南京を首都としました。日本との距離も比較的近く、5世紀の「倭の五王」の遣使や、近現代の日本語「南京錠」「南京玉すだれ」「南京そば(ラーメンの原型)」の語源にもなるなど、距離感の近さが伺えます。古都・南京の歴史と魅力を、豊富な映像資料を使い、予備知識のないかたにもわかりやすく解説します。
なんきん【南京】(「きん」は「京」の唐宋音) [1][一] 中国、江蘇省の省都。揚子江下流の曲流点の江浙デルタの頂点に位置する。水陸交通の中心地で、名産の南京繻子などのほか重化学工業も発達している。 戦国時代の楚の金陵にあたり、三国の呉および南朝諸王朝では都の建康の地にあたる。明の永楽帝の時北京に対して称した。近世、このあたりの地一帯、ひいては中国のことをもいった。引用終了。中国の都市名のうち、長安や洛陽はふつうの音読みなのに、北京・上海・南京・香港・青島など一部の都市名は唐宋音で読むことに注意。
※浮世草子・日本永代蔵(1688)五「こまかに心を付てみしに、是も南京(ナンキン)より渡せし菓子」
|
吉川英治の小説『三国志』「出師の巻」より引用。https://www.aozora.gr.jp/cards/001562/files/52418_51069.html 魏の急使は、呉の主都、建業に着いて、いまや呉の向背(こうはい)こそ、天下の将来を左右するものと、あらゆる外交手段や裏面工作に訴えて、その吉左右(きっそう)を待っていた。 建業城中の評議はなかなか一決しない。呉にとっても重大な岐路である。 |
|
唐の時代の凋落した南京を詠んだ漢詩
烏衣巷 劉禹錫(772―842) 朱雀橋辺野草花。烏衣巷口夕陽斜。旧時王謝堂前燕、飛入尋常百姓家。 朱雀橋辺、野草の花。烏衣巷口、夕陽斜めなり。旧時の王謝、堂前の燕、飛びて入る、尋常百姓の家に。 朱雀橋のあたりの野草の花。 南京の烏衣巷の出入口に、傾く夕日がさしている。 その昔、六朝時代の名門貴族である王氏や謝氏の豪邸の前に巣をかけていたツバメが、 今は、ふつうの庶民の家の軒先に飛びこんでゆく。 金陵図 韋荘(836-910) 江雨霏霏江草斉。六朝如夢鳥空啼。無情最是台城柳、依旧煙籠十里堤。 江雨(こうう)霏霏(ひひ)として江草(こうそう)斉(ひと)し。六朝(りくちょう)夢の如く、鳥空しく啼(な)く。無情は最も是れ台城(だいじょう)の柳、 旧に依りて煙は籠(こ)む、十里の堤(つつみ)。 南京のあたり、長江では細かい雨がしずかに降り 川岸の草がびっしりと続く。 六朝時代の栄耀栄華は夢のように去った。今は鳥がむなしくさえずるばかり。 最も無情を感じさせるのは、いにしえの建康宮の跡地のヤナギだ。昔のまま、十里にわたる堤防が煙雨のなかにかすんでいる。 |
 第5回 北京 ――中国を越えた東ユーラシアの首都
第5回 北京 ――中国を越えた東ユーラシアの首都
北京は今から三千年前、春秋戦国時代の燕の首都となって以来、漢民族の農耕圏と北族の遊牧圏を結ぶ東ユーラシアの主要都市として、独特な歴史を歩んできました。13世紀、元の時代の北京の繁栄はマルコ・ポーロを驚嘆させました。 以来、一部の例外的時期を除き、明王朝や清王朝、そして現代の中国でも、北京は中国の首都であり続けています。 欧州の都市を見慣れた洋画家の梅原龍三郎も、北京の美しさに魅了され、作品を残しました。 北京の歴史と魅力を、豊富な映像資料を使い、予備知識のないかたにもわかりやすく解説します。梅原龍三郎(1888-1986)は洋画家。 若き日にパリで洋画を学び、1939年に満洲からの帰途はじめて北京を訪れて感動。 「雲中天壇」(1939年、京都国立近代美術館蔵)、「紫禁城」(1940年、大原美術館蔵)、「北京秋天」(1942年、東京国立近代美術館蔵) を描く。 パリと北京の対比は横光利一と共通(後述)。
本棚の整理がなかなか進まない。昔、学生時代に愛読した本を、ついつい読んでしまう。鐘ケ江信光(1912年- 2012年)著『中国語のすすめ』講談社現代新書もその一つ。ことばの勉強は「暗記、根気、年期」の3つの「き」が大事、というくだりには、いまも納得。 pic.twitter.com/mW9WL0toko
— 加藤徹(KATO Toru) (@katotoru1963) March 23, 2021
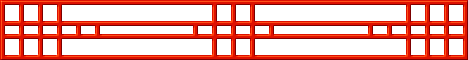
北京と東京、同一縮尺による比較
|
世界の大都市圏人口ランキング、2020。世界第1位は日本の首都圏の約3800万。・・・こんなに集中して、大丈夫かな??? ちなみに中国の首都圏は世界第12位。韓国の首都圏は世界第8位。欧米のいわゆる先進国の首都圏の人口はどこも意外と少ないのは、示唆的。https://t.co/6Re4UyvYfg pic.twitter.com/ep6JRtSNtY
— 加藤徹(KATO Toru) (@katotoru1963) March 19, 2021
|
登幽州臺歌 陳子昂 前不見古人 後不見來者 念天地之悠悠 獨愴然而涕下 幽州の台に登れる歌 陳子昂 前に古人を見ず / 後に来者を見ず / 天地の悠悠たるを念ひ / 独り愴然として涕下る ユウシュウのダイにノボれるウタ チンスゴウ マエにコジンをミず / シリエにライシャをミず / テンチのユウユウたるをオモい / ヒトりソウゼンとしてナミダ、クダる |
|
芥川龍之介(1892-1927)「北京日記抄」より。「青空文庫」より引用。 今日も亦中野江漢君につれられ、午頃より雍和宮(ようわきゅう) 一見に出かける。喇嘛寺(らまでら)などに興味も何もなけれど、否、寧ろ喇嘛寺などは大嫌いなれど、 北京名物の一つと言えば、紀行を書かされる必要上、義理にも一見せざる可らず。(このあと、詐欺めいた挿話がある。中略) 天壇。地壇。先農壇。皆大いなる大理石の壇に雑草の萋々(せいせい)と茂れるのみ。 天壇の外の広場に出ずるに、忽(たちま)ち一発の銃声あり。何ぞと問えば、死刑なりと言う。 紫禁城。こは夢魔のみ。夜天よりも厖大なる夢魔のみ。 |
|
横光利一(1898-1947)「北京と巴里(覚書)」より。「青空文庫」引用 (前略)北京は消費の街だという。なるほどこの街では生産というものをかつてしたことのない人物が、 代々かかってどれほど人間が消費を出来るものかと、あらゆる智慧を絞って工夫に工夫をこらせた有様が歴然と現れている。 (中略)北京へ行くものは悪徳と戦うつもりで行かない限り、身につけた現世の健康なものはすべて無くなってしまうかもしれぬ。 ここには精神のある美よりも詐術の美を美とする精神がある。 もし疲労と孤独のために難なくこれに襲われたら、恐らく北京ほど美しく見える都会はないだろう。 死体に色づけ客間に置き放したまま嫣然と笑わせたようなこの都会の女性的な壮麗さは、 たしかにどこの国にも類例はあるまい。 (中略)数世代も続いた都を他民族に征服され、またそれが崩れると次の民族が交代するという肉体の死滅して来た累積層 の中には、残るものはこのように頓狂なものばかりかと思って私は茫然とした。かつて有ったに相違ない良いものは、 殆ど演劇だけを残して死んでしまっていて、尨大な駄作ばかりが本尊となりすまし、樹の海がひとり祭壇をめぐっている。 ここで一番人心に感動を与えているものは、今は小唄のような哀れな歌調をもった節廻しだけである。しかし、大衆というものは駄作ほど喜ぶ。駄作が傑作となって永久に残るというこの地の特種な機構は、何かこの北京に限り他国とは比較にならぬ犯罪の深さを物語ってやまぬものがある。 北京に遊ぶ知識人はよく前から、ここは全くパリに似ているというのを私は聞いた。あるフランス人は北京はパリ以上だとも言ったという。(以下略) |