HOME > 授業教材集 > このページ科挙と儒教
最新の更新2025年10月3日 最初の公開2025年10月3日
https://www.asahiculture.com/asahiculture/asp-webapp/web/WWebKozaShosaiNyuryoku.do?kozaId=8399831 より自己引用。
YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PL6QLFvIY3e-lWgIKS7RlOvCYpMQnPKGXq VIDEO
国家 こっかstate ”、
中国語訳は“朕即国家 ”(Zhèn jí guójiā)、
韓国語訳は“짐은 국가 (國家)이다”である。
修身斉家治国平天下 しゅうしん せいか ちこく へいてんか 中華帝国 ちゅうかていこく 散逸構造 さんいつこうぞう 古人主義 こじんしゅぎ 儒教 じゅきょう confucianism 焚書坑儒 ふんしょこうじゅ 士大夫 したいふ 科挙 かきょasahi20230713.html#04 、蘇軾 asahi20240411.html#05 、朱子 asahi20250109.html#04 、
文天祥 asahi20250410.html#04 、林則徐 asahi20240111.html#06 、李鴻章 20210708.html#05 、等々。asahi20250109.html#03 、黄巣 asahi20250710.html#04 、洪秀全 asahi20231012.html#05 、等々。 高考 ガオカオ
日本では神道・儒教・仏教の3つの思想・宗教をまとめて「神儒仏(しんじゅぶつ)」と呼ぶ。この3つはどれも水と油のような思想であり、「習合」はしても「融合」はしなかった。 日本は遣唐使の時代から中国の文物制度を熱心に学んだが、中国の科挙・宦官・城郭都市・纏足(てんそく)などは取り入れなかった。https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/6366c5ceb782cb1a81f426f704448c2765f7b495 より引用。閲覧日2025年10月3日。引用開始
今から1153年前の貞観12年(870年)3月23日、後に学問の神様となる菅原道真(当時26歳)が、方略試(ほうりゃくためし)という、最高位の官吏試験を受けています。
合格の最低点である「中の上」で合格 しています。
地震について論ぜよ
菅原道真が方略試を受けた貞観12年(870年)の試験問題は、「氏族を明らかにせよ」と「地震について論ぜよ」の2つで、ともに1000字程度の漢文で解答するものでした。
朝鮮王朝(李氏朝鮮)は中国より早く1894年に科挙を実質的に廃止し、ベトナムは中国よりも遅く1919年に科挙を廃止した。
中国の歴代王朝は、外廷と内廷(後宮)から成り立っており、両者の組織は儒教的なヒエラルキー(階層性)を採用していた。book.html#koukyuu )を参照。
[一番上 ]
HOME > 授業教材集 > このページ
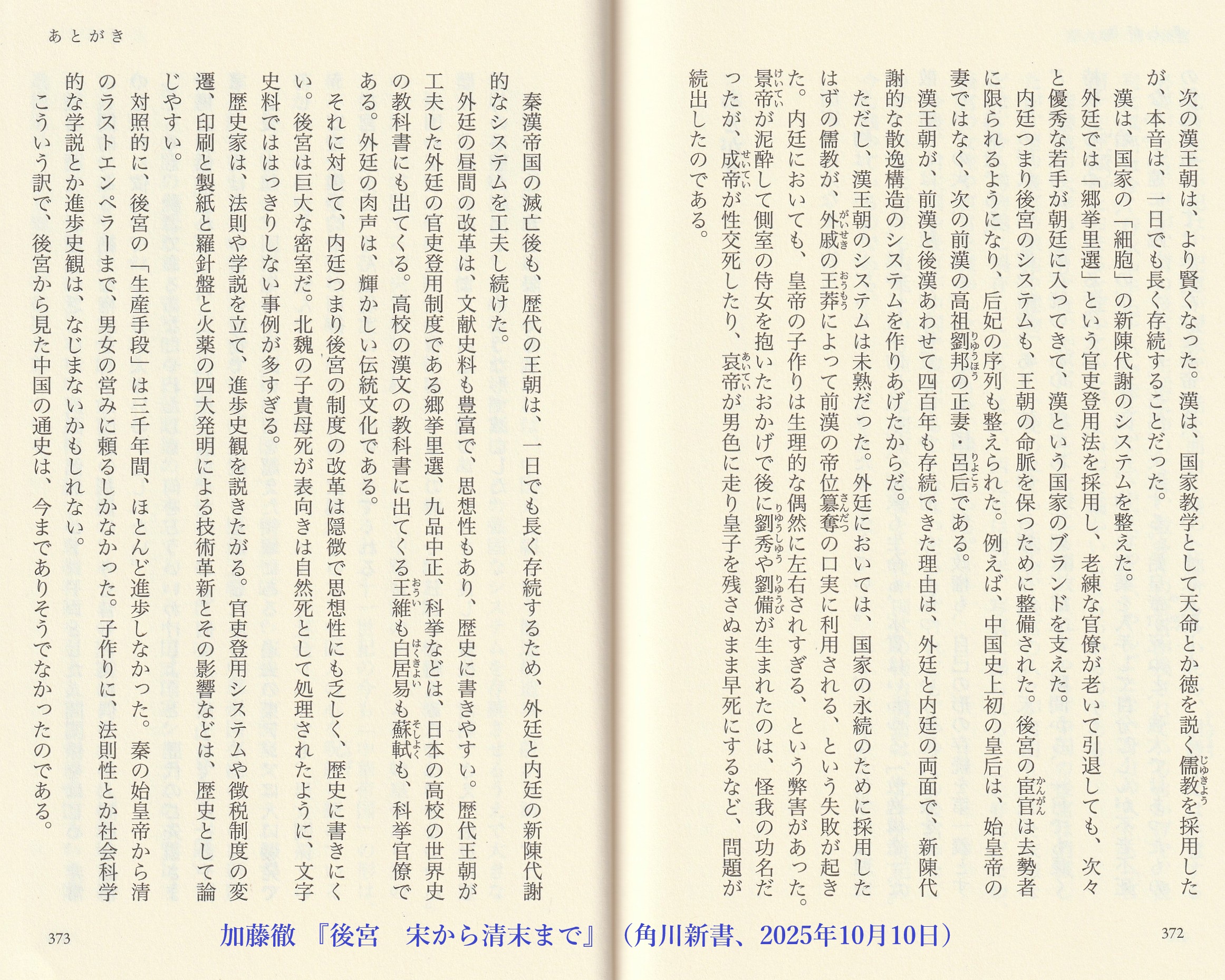
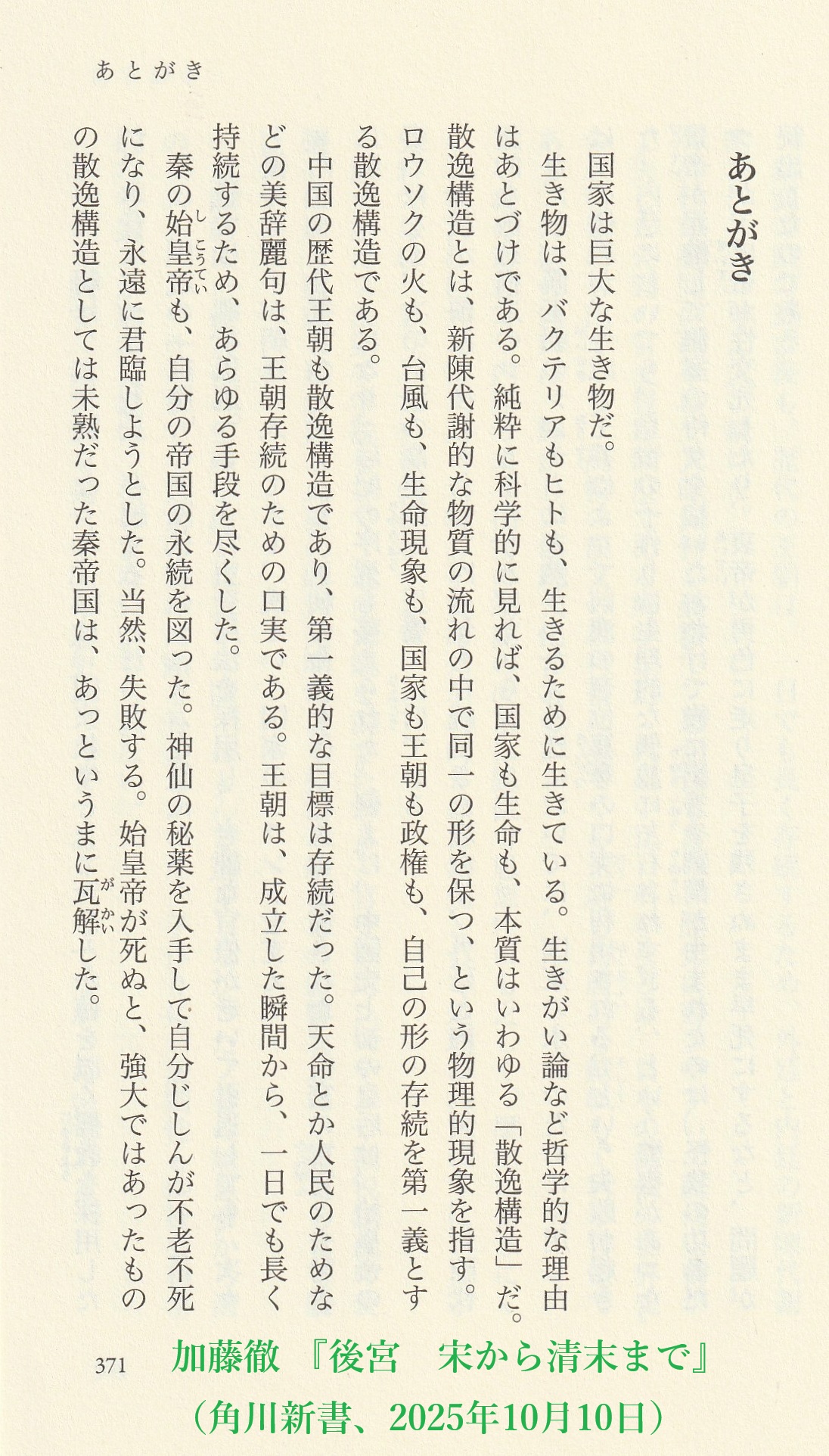
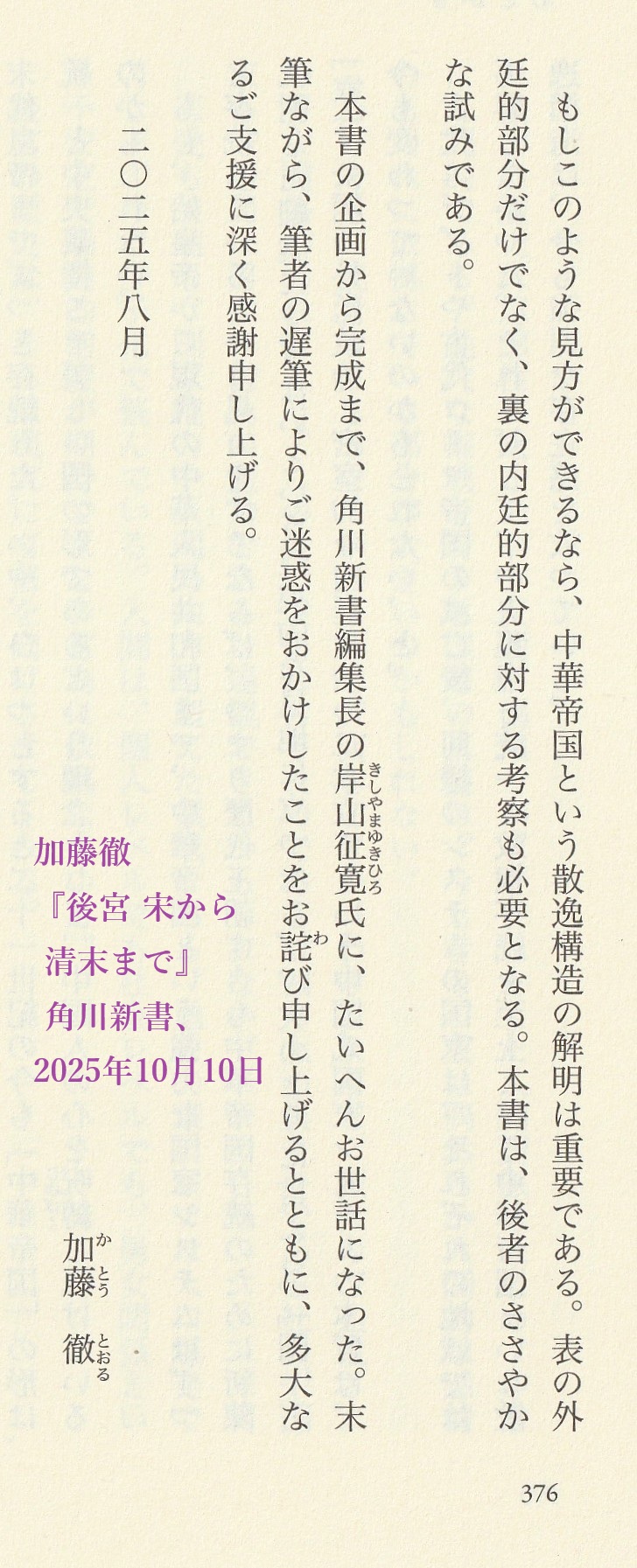
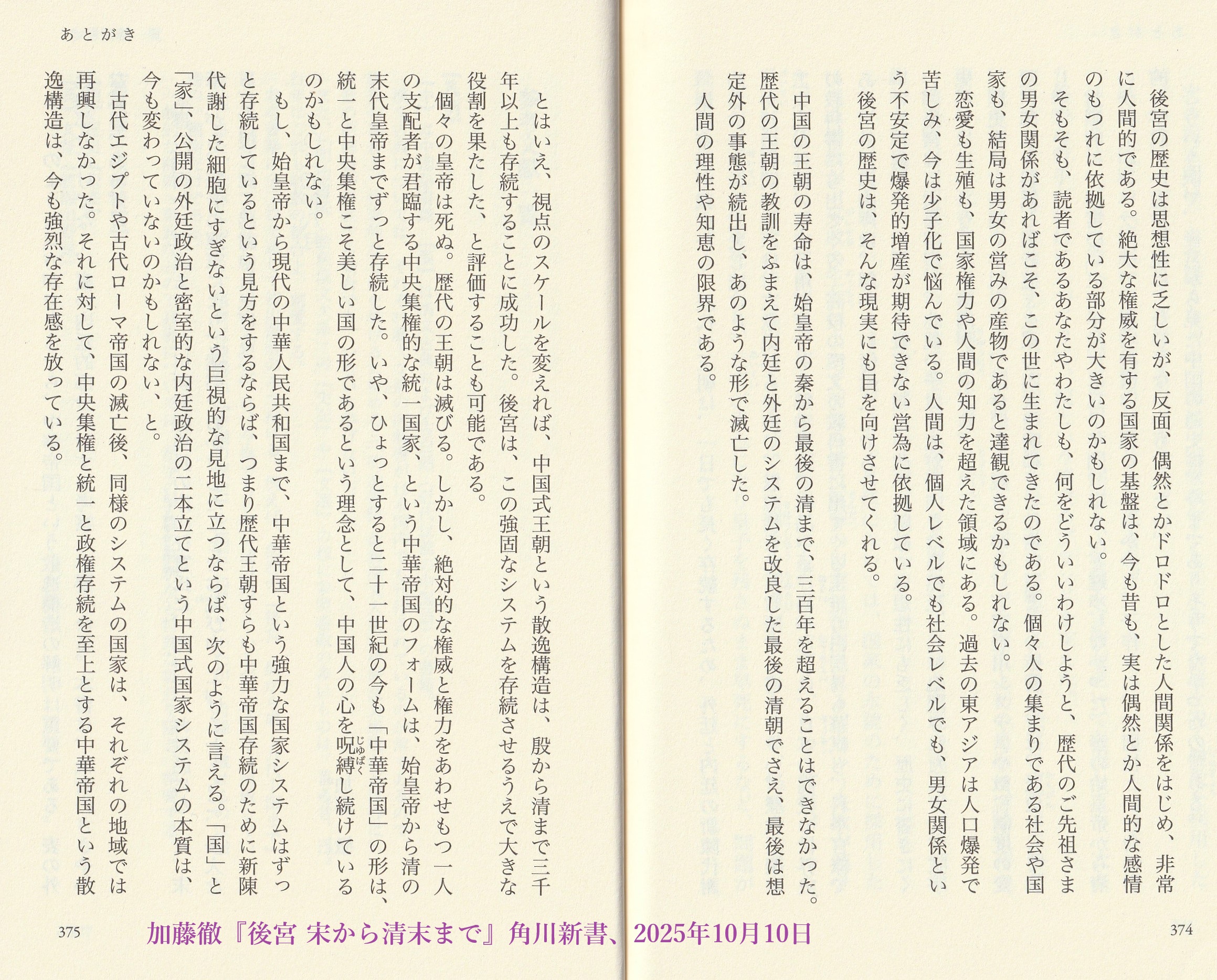

 朝日カルチャーセンター新宿教室 公式サイトより
朝日カルチャーセンター新宿教室 公式サイトより