�����傤�]���k�S�M���E�]�l�y�܍s���z
�@�����Ñ�̊w���ŁA���R���l�ԁE�Љ���A�E�E�y�E���E���̌܂̌��f�̈��̏z�@���ɏ]���ĕω������Ƃ������B �E�E�y�E���E���̊e���f�����X�Ɏ��̌��f�ݏo���Ă䂭�Ƃ���܍s����(��������)���ƁA�E�y�E���E�E���̊e���f�����ꂼ�ꎟ�̌��f�ɂ��������Ă䂭�Ƃ���܍s����(��������)���Ƃ�����B���܍s
�܍s���@�����傤����
�@�����Ñ�l�̐��E�ς̈�B�܍s�͂܂��܍ނƂ����A�w�t�H�����`(����イ�����ł�)�x�i���`�j�Ɂu�V�܍ނ��A�����тɂ����p���v�Ƃ���悤�ɁA�����ɕK�v�Ȑ��A�A���A�A�y�̌܂̑f�ށi���p�܍ށj�ł���B ���̌܍s�̎����́A�w���o�x�́u�^��(�����͂�)�v�ɂ���A�u�����̌܍s�v�Ƃ����B���̌܍s�̎������A���R�̑�������W�ɔz���āA�A�A�y�A���A���Ƃ��A�l�G�̏z�Ɏ����ꂽ���̂��܍s����(��������)���Ƃ����B �w�C���t�H(��債����イ)�x�̏\��I��(�ւ�)�ɂ݂���z���Ȃǂ͂���ŁA�܍s�z�̎��R�ς��_��I�Ȍ܍s���ɓ]���������̂ł���B ����ɑ��āA�퍑����A��(����)��羟�(��������)���A���A�A���A�A�y�Ǝ������āA������ւ̊v�����Ƃ����B������܍s����(��������)���Ƃ����B�܍s�̑����z�ɂ̂��Ƃ������͊v�����ł���B ����ł́A��(������)�����܍s�������ɂ���Ċv�������m�����A�Ȍ�̉����́A��������ɂ���Ă��̉����̓����咣�����B�ܓ��I�n(���イ��)���Ƃ������̂ł���B �Ȃ��A����ł͌܍s���͉A�z(����悤)���ƌ������ĉA�z�܍s���ƂȂ�A�Ȍ�̒����l�̂��̂̌����A�l�����̊�ƂȂ����B
�m�������R�n
�����N�\
- �I���O21���I����@�`����̌܍s�̏��o�B
�@�w�����x(�w���o�x)�Ð��тƍ^�͕тɌ܍s���o�Ă���B
�@�^�͕тł́A�Ă��Z�����V������������u�^�͋��e�v(�����͂イ���イ�B�������Ȃ�̂�A��9�̃W�������B�܍s�E���E�����E�܋I�E�c�ɁE�O���E�m�^�E�����E�ܕ��Z��)�̕M�����܍s�ł���A���ꂼ��A���͏����i����j�A�͉���A�͋Ȓ��A���͏]�v(�ϊv�ɏ]��)�A�y�͉��p(�d��Ǝ��n)�Ƃ����B
�Ă��Z���͋I���O21���I����̓`���̓V�q(����݂̉\��������)�B
�@�w�����x�́A�����I�ɂ͖�3��N�O�̕������܂܂�Ă���\�������邪�A���݂̂悤�Ȍ`�ɂȂ����̂͐퍑����̖�(�I���O3���I)�̉\���������B - �O3���I�O���@羟�(��������@�I���O305�N�� - �O240�N)���܍s�������āu�ܓ��I�n���v��B
�@羟��́A�퍑����̐�(����)���l��(���傭��)�̊w�m�̈�l�ŁA���q�S�Ƃ̈�u�A�z�Ɓv�B ��Ƃ̂�����u�����v(��B�̈��)�́A�S���E��81����1�ɂ����Ȃ��Ƃ����u���B���v���B �J�𐁂��ĕs�т̓y�n��L���Ȕ_�Y�n�ɕς����Ƃ����u�����v�̘b��A�l�߂ō����ɂ������Ƃ��ĂȂ̂ɑ������肽�Ƃ����u�~���v�̘b�ȂǁA �A�z�܍s�̃p���[���g�����Ƃ����_��I�Ȉ�b���`���B - �O3���I�㔼�@�`�̍ɑ��������C�s��(���ӂ� �H�`�O235�N)���w�҂����ĕҎ[�������S�ȑS���w�C���t�H�x(��債����イ)�ɁA�܍s�z�����������B �̌o�T�w��L�x����(�炢���E����傤)�Ɠ��l�̓��e�B
- 7���I���߂���A�@���J�g(���傤���@�H-614�N)���w�܍s��`�x�i�����傤�������j���q�B���{�ɂ̂ݎc��Ñ����i������j�B
cf.�������@�@https://www.meijishoin.co.jp/book/b97689.html
���܍s�z���\�̈��
| �܍s | �� | �� | �y | �� | �� |
|---|---|---|---|---|---|
| �ܐF | �� | �� | �� | �� | �� |
| �ܕ� | �� | �� | ���� | �� | �k |
| �� | �t | �� | �y�p | �H | �~ |
| �ܖ� | �_ | �� | �� | �h | �c |
| �� | �m | �� | �M | �` | �q |
| �� | �e | �� | �v | �� | �� |
| �ܐ_ | �� | �_ | �� | � | �u |
| �� | �� | �y | �� | �{ | �� |
| �u | �{ | ��E�� | �v�E�� | �߁E�J | ���E�� |
| �ܑ� | �� | �S | �B | �x | �t |
| �Z�D | �_ | �����E�O�� | �� | �咰 | �N�� |
| �ܐ� | �ΐ� | 熒�f | ���� | ���� | �C�� |
| �ܒ� | �� | �H | �� | �� | �� |
| �b | �� | �鐝 | �����E�i�� | ���� | ���� |
| �܊� | �� | �� | �� | �@ | �� |
| �܉� | �剹 | �㉹ | �O�� | ���� | �A�� |
| �ܐ� | �p | �� | �{ | �� | �H |
| �w | ��w | ���w | �H�w | �e�w | ���w |
| �܉t | �� | �� | �� | �� | �� |
| �� | �E�� | ���� | �����E�O | ��� | �����E�� |
| �܉� | �� | �� | �� | �� | �I |
| �܍� | ���E�Ӗ� | �� | �� | �o | �哤 |
| �܍� | �� | �E | �R�� | �K | 藿 |
| �ܒ{ | �{ | �r | �� | �n | �� |
| �܌o | �y | �� | �� | �� | �� |
| �ܕ� | �� | �J | 噦 | 欬 | �� |
| �\�� | �b�E�� | ���E�� | ��E�� | �M�E�h | �p�E� |
| �\��x | �ЁE�K�E�C | ���E�߁E�� | �C�E���E���E�N | �\�E�сE�� | ��E�q�E�N |
| ���T | ���E�� | �� | �R�E�n | �V�E�� | �� |
| �܋C | �z | �z | �y�p | �A | �A |
| �㐯 | �O�ɁE�l�� | �㎇ | �E�܉��E���� | �Z���E���� | �ꔒ |
| �܍s | �� | �� | �y | �� | �� |
�����̑�
- �u�t�v��u���H�v�́A�܍s�v�z�R���̊���ł���B
- �����ł́A��w�◿���A�|�p�A�������܍s�v�z�ŗ��_�Â����Ă����B
- ���{�̖��M�u����(�Ђ̂�����)�v�́A�����߂��܍s�́u�v�ł��邱�ƂɗR���B
 �@����@�ܖ��@
�@����@�ܖ��@
�@���������̌ܖ��́u�_�E��E�ÁE�h�E�c(���h��)�v�ł��B���{�����̌ܖ��u�Ö��E�����E�_���E�ꖡ�E���ܖ��v�Ə��������Ⴂ�܂��B �������|�p�ɍ��߂������l�́A�����ɋZ�p�����łȂ��N�w�����߂܂����B �̌ÓT�w��L�x���ߕтł́A�܍s�v�z�ɂ̂��Ƃ�G�߂��Ƃ̌ܖ����K�肳��Ă��܂��B �{�엿�������łȂ��A�����̉ƒ뗿���⋽�y�����̖������A�ܖ��̉e���������B ���㒆���̖��Ԃ̂��Ƃ킴�Łu���͎_���ς��A��͊Â��A���͐h���A�k�͂�����ς��v�ƌ����܂��B �������ؗ����ł�������k�ł͊�{�I�Ȗ����Ⴄ�B���̎R�������͂����ς����A��̍L�������͊Â��A���̎l�엿���͐h���A�k�̖k�������͂�����ς��B �܍s�v�z�́u�؉Γy�����v�u���쒆���k�v�u�_��Ðh�c�v�̔z���ƁA21���I���݂̒��ؗ����̖����̌��������ׂ�ƁA���Ɛ��Ɩk�͍����܍s�v�z�̂܂܂ł��B ���������̖��Ƃ����ڋ߂ŋ�̓I�Ȏ��Ⴉ��܍s�I�Ȏ��_�œǂ݉����ƁA�����l�̒n�捷���A��Ɏ��悤�ɂ킩��܂��B
���|�C���g�A�L�[���[�h
- ���o
���⎞��ɂ���Ď�ނ��Ⴄ�B
�@�����F�ܖ�=�_�i����j�E��i���j�E�Ái����j�E�h�i����j�E�c�i����j
�@���m�F4��{����=�Ö��A�_���A�����A�ꖡ(1916�N�Ƀh�C�c�̐S���w�҃n���X�E�w�j���O����)
�@���{�F���{���̌ܖ�=�Ö��A�_���A�����A�ꖡ�A���ܖ�(1908�N�ɉ��w�҂̒r�c�e�c���O���^�~���_�����ܖ��̌��ł��邱�Ƃ�)
���������{�ł��A�����̉e�������������T�m�́A�������̌ܖ����P�����B �h���́w�i���{���L�x�ŁA�_���͊��q�E�k�E�M�ȂǁA�h�����G(�L���E/�͂�����/�V���E�K)�E�Ӟ��E�����G�ȂǁA�Ö��������ȂǁA�ꖡ�͒��E�؍��ȂǁA�c���͉��ȂǁA�]�X�Ə������B - ��H�����@�₭���傭�ǂ�����
��H�����A�Ƃ��B������w��A���{�̊�����w�ł́A�܍s���ɉ����Č��N�Ɩ��t�����֘A�t����B
�ȉ��A�u�H�ו��̐�����m��u�ܖ��v�Ƃ́y���N���߂����ƒ�̖�V�z�v�����p�B �{����2025�N7��6���@�����ł́A�H�ו��̐�����m����@�Ƃ��āu�ܖ��v�Ƃ����l����������܂��B�܋C�Ɠ��l�Ɍ܍s�̖@���ɂ̂��Ƃ�A�H�ו������̖��̈Ⴂ�ɂ����5�̐����ɕ��ނ������̂ł��B�܂��A�ܖ��ƌܑ��͐[���W���Ă��āA����̖���̂��~���Ă���Ƃ��͑̂̂��镔�������Ă�����A����Ă����肷�邱�Ƃ�����܂��B (����)�����̌Â������ɂ́A�_�͊́E�_�A��͐S�E�����A�Â��B(��)�E�݁A�h�͔x�E�咰�A�c�͐t(����)�E�N���ɓ���Ƃ���A������������H�ו��͖��̈Ⴂ�ɂ���Ă��ꂼ��Ⴄ����ɓ���������Ə�����Ă��܂��B (����)�̂́A�����ɂ����Ă͊̑������łȂ����_���R���g���[�������p������ƍl�����Ă��܂��B���̂��߁A�C���C���������Ȃǂɂ͎_���̋������̂����ɓ���邱�ƂŃX�g���X�U�����邱�Ƃ��ł��܂��B (�ȉ���)
�@���̑��ɂ��A�����l�͏������x���Łu��H�����v�̊��o�������Ă���B
��@�S�Ă̈��H�����u�����v�u�����v�u�����v�u�����v�u�M���v�̌ܐ��ɕ��ނ���B�ێ�I�Ȓ����l�͗₽�����H���͔�����X��������B
��@�u���H�ցv�u�H���킹�v�̋֊��̃��[�c�͒����ŁA���㒆����ł́u���H�֊��v�ȂǂƌĂԁB - ���_�A��煁A��[�A�k�c�@�Ƃ�����@������A�Ȃ�Ă�A�ق�����
���㒆����̌������B���͎_���ς��A���͐h���A��͊Â��A�k�͂�������A�Ƃ����Ӗ��B�n�����Ƃ̗����̖��킢�̈Ⴂ�������B
�܍s���Ɣ�ׂ�ƁA�u��=��v���u��=�Ö��v�ƂȂ��Ă��鑼�́A�قړ����ł���B
�Q�l�@NHK�w������!�i�r�x2025�N6�����@https://drive.google.com/file/d/1oDbt811pogNmmUfLeHMraK-ZzCX_KL1H/view?usp=drive_link �@https://drive.google.com/file/d/19bL5l0qWnv-NaLYPGpN6jVj1KCDkJ2WA/view?usp=drive_link - �����́u����،n�v(�u�v�͒�����ŗ����̈�)
�R�������A�]�h�����A���]�����A���J�����A���������A�L�������A�Γ엿���A�l�엿���B�ڂ����͉��L���Q��
���ܖ��ƌ܍s��
| �܍s | �� | �� | �y | �� | �� |
|---|---|---|---|---|---|
| �� | �t | �� | �y�p | �H | �~ |
| �ܖ� | �_ | �� | �� | �h | �c |
| �� | �e | �� | �v | �� | �� |
| �u | �{ | ��E�� | �v�E�� | �߁E�J | ���E�� |
| �ܑ� | �� | �S | �B | �x | �t |
| �Z�D | �_ | �����E�O�� | �� | �咰 | �N�� |
| �܉� | �� | �� | �� | �� | �I |
| �܍� | ���E�Ӗ� | �� | �� | �o | �哤 |
| �܍� | �� | �E | �R�� | �K | 藿 |
| �ܒ{ | �{ | �r | �� | �n | �� |
���̌o�T�w��L�x����(����傤)�̖`����
|
�@�Џt�V���C���ݚz���C���Ғ��C�U�����B�����b���B������r�C���_��䊁B��峗B�����p�B���������B���ɔ��B�����_�C���L㽁B���J�ˁC�Ր��B�B �@�����𓀁C�峎n�U�C����u�C�ڍՋ��C����ҁB �@�V�q���z�����B���a�H�C��q���C�ڐ�旂�C�ߐ߁C���q�ʁB�H�m�o�r�C����`�ȒB�B |
�@�Џt�i�܂������j�̌��i���j�A���i�Ёj�͚z���i�������j�ɍ݁i���j��A���i��ӂׁj�əҁi����j���i�����j���A�U�i�������j�ɔ��i�сj���i�����j���B ���i���j�̓��i�Ёj�͍b���i���ӂ��j�A���i���j�̒�i�Ă��j�͑��r�i���������j�A���i���j�̐_�i����j�͋�䊁i�������j�A���i���j��峁i�����j�͗i���j�A���i���j�̉��i����j�͊p�i�����j�A ���i��j�͑����i���������j�ɒ��i�����j��A���i���j�̝Ɂi�����j�͔��i��j�A���i���j�̖��i�����j�͎_�i����j�A���i���j�̏L�i�����j��㽁i�Ȃ܂����j���A���i���j���J�i�܂j��͌ˁi���j�A�Ձi�܂j����B�i�Ёj�Ɛ�i�����j�ɂ��B
�@�����i�Ƃ��ӂ��j���i���فj������i�Ɓj���A�峁i�������j�n�i�͂��j�߂ĐU�i�����j���A���i�����j�͙u�i�Ёj�ɏ�i�̂ځj��A�ځi���j�A���i�����j���Ձi�܂j��A����i��������j�ҁi�����j��B
�@�V�q�i�Ăj�A�z�i�����₤�j�̍����i�����j�ɋ��i���j��A�a�H�i����j�ɘ��i�́j��A�q���i������悤�j�ɉ�i���j���A ��旂�i�������j���ځi���j�āA�߁i�������j���߁i���j���A�q�ʁi�������悭�j�i�ӂ��j���A �m�i�ނ��j�Ɨr�i�Ђ��j�Ƃ�H�i����j���B���i���j�̊�i���j�͑`�i���j�ɂ��Ĉȁi�����j�ĒB�i�Ƃفj��Ȃ�B
��ӁF�Џt�i��������t�̂͂��߁j�̌��i������j�̂���A���z�́u�z���i�������j�v�Ƃ��������̈ʒu�ɂ���A�[���ɂ́u�ҏh�i���キ���I���I����������j�v�̒����ɒ��݁A���ɂ́u���h�i�т��キ����������̔�������j�v�̒������珸��B ���̎����̓��̊��x�́u�b���i���������̌Z�E�̒�j�v�A���̋G�߂��i��V��́u���r�i���������j�v�A�x�z����_�́u��䊁i�����ڂ����t�̐_�j�v�ł���B �����ł́u�i����ȂǗ����������j�v������ɂȂ�A���K�ł́u�p�i�����j�v�̉�����ł���A�����ł́u�����i���������j�v�ɓ�����B �����ł́u���v���ے�����A���o�́u�_���ς��v�A�����́u㽁i�Ȃ܂������j�v�ɑ�����B ���̎����̍Ղ�́u�ˁi�Ƃ̌ˌ��̐_�j�v���J��A��ł́u�B�i�Ё��B���j�v������邱�Ƃ��ł��悢�Ƃ����B
�@���R�E�ł́A�����i�t�̕��j��������a�炰�A�����Ă������̂��������A�n���ɂ������Ă����������������n�߁A���͕X�̉����琅�ʂɌ���A�ځi���키���j�͋����Ƃ炦�ĕ��ׁA�܂�ōՂ邩�̂悤�Ɍ�����B�܂��A�����i�������n�蒹�j���k�������B
�@�V�q�i�c��j�͂��̋G�߁A�u�z�i�����悤���t�j�v�́u�����i�����������̋�ԁj�v�ɋ����A�u�a�H�i���끁����ԁj�v�ɏ��A �u�q���i������イ�������j�v����ԂɌq���A�u�����v�𗧂āA�u���߁v���܂Ƃ��A�u�q�ʁi����ʁj�v��g�ɒ�����B �H�ו��͔���r��H�ׂ邱�Ƃ��悵�Ƃ����A��͑f�p�Ȃ��̂�p���āA�C�̗��ꂪ��ʂ悤�ɂ���B
���܍��@������
�����n�悲�ƂɁu�܍��v�̓��e�ɂ́A�o���肪����B
- �̌o�T�w��L�x�i�炢���j�ł́A���i�����j�A�o�i�L�r�j�A�l�i�q�G�������̓A���j�A���i�唞�Ȃ��������j�A���i���j
- �Ñ�̎����w���������x�ł́A���i�C�l�j�A�o�A�l�A���A��
- ���{�̕�������́w���쎮�x�i�������j�ł́A��E���E���i����j�E�o�i���сj�E��
�R���Ȃ�������S���������莜��(���E�~�F��/�䂤�߂�)�̓G���o�N(����)�B
�Ñ㒆���̉��͕����͎G���ƃ��M�A���]�����͈�삪���S�������B
����������،n
- �R�������i�D�E���[�T�C�j
�ꏊ�F �R���ȁi���A�ϓ�Ȃǁj
���̓����F�Z���߂̉�������{�B�X�[�v���u�ߕ��̋Z�@�����B�B�C�Y�����L�x�ŁA�������͋�����
��\�����F���ʌ�i�Ð|�̌�j�A�K�ĊC�Q�i�i�}�R�ƃl�M�̎ύ��݁j - �]�h�����i�h�E�X�[�T�C�j
�ꏊ�F �]�h�ȁi�싞�A�h�B�A�g�B�Ȃǁj
���̓����F�Â߂ő@�ׁA�܂�₩�Ȗ��t���B����t�����������A��i�B�ς�E�����̋Z�p������
��\�����F�g�Ď��q���i�ύ��ݓ��c�q�j�A����鰣���i�������j - ���]�����i���E�W�F�[�T�C�j
�ꏊ�F ���]�ȁi�Y�B�A�J�g�A�Ћ��Ȃǁj
���̓����F �����ς肵�Ă��đf�ނ̕������������B ���y�H�i�i���E�ݖ��E�|�Ȃǁj�����p�B �D��Ő������ꂽ���B
��\�����F �����ʋ��i�Ð|�̋��j�A ����ڐm�i�G�r�Ɨ��䒃�u�߁j - ���J�����i�J�E�z�C�T�C�j
�ꏊ�F ���J�ȁi���R���Ӂj
���̓����F�R�̍K�i���̂��E�쑐�E���b�j�𑽗p�B
��������ύ��ޗ����������B
���{�E��V�I�v�f�������B
��\�����F �ѓ����i���y�����̏Ă����j�A �����W�Č{�i�Ă��{�j�B - ���������i?�E�~���c�@�C�j
�ꏊ�F �����ȁi���B�A��B�A�͖�Ȃǁj
���̓����F �X�[�v���L�x�ŁA���荂���B �o�`�i�C�N�E�����j���d���B �Â߂ŗD�������킢�B
��\�����F ����ୁi�����X�[�v�����j�A �����ˁi�s�[�i�b�c�����̖ˁj
- �L�������i��E���G�c�@�C�j
�ꏊ�F �L���ȁi�L�B�A���`�A�}�J�I�Ȃǁj
���̓����F �������蔖���A�f�ނ̗ǂ������B ���l�Ȓ����@�i�u�߁A�����A�ύ��݁j�B �_�S���������B�B
��\�����F �_�S�i����~�����`���j�A ���āi�Ă��j�A �����Δ����i���̏������j - �Γ엿���i�ÍE�V�����c�@�C�j
�ꏊ�F �Γ�ȁi�����Ȃǁj
���̓����F ���h�q�̐h���������i�����Ȑh���j�B �_����Е����悭�g���B �l�엿����肵�т�͏��Ȃ��B
��\�����F 剁�������i���h�q�y�[�X�g�Ƌ��j�A 煎q�{�i�{�̓��h�q�u�߁j - �l�엿���i��E�`�������c�@�C�j
�ꏊ�F �l��ȁA�d�c�Ȃ�
���̓����F ���i���т�j�{煁i�h���j�����(�}�[���[)�B �Ԟ��i�z�A�W���I�j�Ⓜ�h�q���L�x�B ���̕ω��ɕx�݁A�u�S�ؕS���v�ƌ�����B
��\�����F ���k�����A �Γ�A �{�ی{���i�s�[�i�b�c�ƌ{�u�߁j
 �@��O��@�ܗρ@
�@��O��@�ܗρ@
�@�䏊�̃K�X�R�����œ���������������u�ܓ��v�ƌ����܂��B �ܓ��͖{���A�́u���E�ǁE���E���E���v�̌܂̓����w���܂��B �ł́A�l�Ԃ���ɔ�����ׂ��܂̐������u�m�E�`�E��E�q�E�M�v�́u��v�ɂ܂Ƃ߂܂����B �܂��܂̎Љ�I�Ȑl�ԊW���u���q�E�N�b�E�v�w�E���F�E���c�v�́u�ܗρv�Ƃ��܂����B �ܓ��A��A�ܗςȂǐl�ԊW�̃G�b�Z���X���A�܍s�v�z�Ɏ��ʂ���A�܂̗v�f�Ƃ��Ĕz������܂����B ��������́u���璺��v�́u��J�b�����N���j���N�F�j�v�u���b������j�F�j�Z��j�F�j�v�w���a�V���F���M�V�v�Ƃ������t���ܗς��ӂ܂��Ă��܂��B ���m��nation�̖�ꂪ�u���Ɓv�ł��邱�Ƃ�����킩��悤�ɁA�����̐�����Љ�́u�Ƒ��v���o���_�Ƃ���l�ԊW����������Ƃ������z�ʼn^�c����Ă��܂����B �̂̒����ł�����u���敧���v���蒅���Ȃ��������R�A�ߌ���̒������u�Љ��`�v�����ꂽ���R���A�����ɂ���܂��B �ƒ������Y�}�͐^�t�ł���ƌ��������{�l�͑����ł����A���������j�Ƃ��������I�Ȋϓ_���猩��A�����͍����̂��l��`���W�c��`�̍��ł���A�l�ԊW�����ő�̎��{�ł���Ƃ��鉿�l�ς������ł��B�u���q�E�N�b�E�v�w�E���F�E���c�v�Ɓu�؉Γy�����v�̔z��������ׂ�ƁA����(�y)�́u�v�w�v�ł��B������{��́u�s�ρv���A�ܗς̂����v�w�W�̕s�ς������w�����R���A���͂����ɂ���܂��B
���|�C���g�A�L�[���[�h
- ���Ɓ@������
������{��́u���Ɓv�͋ߑ㐼�m�� nation �Ȃ��� state �̖��(�V����)�B
�{���̊���u���Ɓv�͎I�ȍ��ƉƁB
�w�势�a���T�x�́u���Ɓv�̉���ł́A1.���ɁB�����ƍ��y�B
�Ƃ���5�̈Ӗ���������B cf.�����w�F���N�x(�����イ�ق�)�F�q���C���́A���̍c��ƁA�ƕ����ł��镃�e�Ɛ키�B
2�D�V�q�B���B
3�D����̍��Ƌ���v�̉ƁB
4�D���݂̒���B
5�D���̒n��ɋ��Z���鑽���l���琬��A�������ɂ���đg�D�����Ă���c�́B�̓y�E�l���E���������A���̊T�O�̎O�v�f�Ƃ���Ă���B
- �ܗρ@�����
�l�Ɛl�Ƃ̊Ԃ̌܂̓��B�܋��Ƃ������B�o�T�͎̎l���̂ЂƂw�Ўq�x(��q)�B
���q�A�N�b�A�v�w�A���c�A���F�B
���q�̐e�C�N�b�̋`�C�v�w�̕ʁC���c�̏��C���F�̐M�B - �u�ρv�̎���
�R�A�C���[�W�F���ʂ�悤�ɏ����悭���ׂ�B
���`�F����ɕ��Ԓ���
�����F�Ӂi���ʂ�悤�ɏ����悭���ׂ�)�{�l(����L��)�@�`������
������F�ρA�ցA�_�A�d�A��
�P��Ƒ��F�ρA�ہA�ށA�� - �O�j��@���������傤
�O�j�F�N�b�E���q�E�v�w
��i�܂��͌ܓ��j�F�m�E�`�E��E�q�E�M
- �����@�͂��Ƃ�
�m�E�`�E��E�q�E�M�E���E�F�E��
cf.���n�Ձw�쑍���������`�x�̔����m�́A���ꂼ��m�E�`�E��E�q�E���E�M�E�F�E��̕����̂��鐔��̋ʂ����B - �C�g�ĉƎ������V���@���イ����@�������@�������@�ւ��Ă�
�̎l���̂ЂƂw��w�x���o�T�Ƃ��錾�t�B
�܂������̍s�Ȃ��𐳂������A�ƒ���ƂƂ̂��A���Ƃ����߁A�V���a�ɂ���A�Ƃ����Ӗ��B - �x�z�̎O�ތ^
�@�}�b�N�X�E�E�F�[�o�[�ɂ��A���͂𗠕t���鐳�����iLegitimacy�j�̊�b�Ɋւ���O�̗��O�^�B
�u�J���X�}�I�x�z�E�`���I�x�z�E���@�I�x�z�v��3�B
�@�ܗς́u�`���I�x�z�v�̍����Ƃ��č���A���E�I�Ɍ���Ήƕ�����(patriarchy)�I�Ȕ��z�̎Y���ł���B
���ܗςƌ�̌܍s�z��(��������܂��j
| �ܗ� | �� | �܍s | ���� |
|---|---|---|---|
| ���q�̐e | �m | �� | �͐����E�琬���ے����A�e���q�������݁A�q���e���h���u�m�v�ɑΉ�����B |
| �N�b�̋` | �` | �� | ���͋`���E�����E���`���ے����A�N�b�W�̌����ȏ㉺�W�ɒʂ���B |
| �v�w�̕� | �� | �� | �͖��E��E��ʂ��ے����A�v�w�̖����̕������u�j���L�ʁv�ɑΉ�����B |
| ���c�̏� | �q | �� | ���͒q�E�_�����ے����A�N���҂ƔN���҂̏���Ɠ����ɑΉ�����B |
| ���F�̐M | �M | �y | �y�͖������e����肳���鐫��������A�M���Ɋ�Â����F�W�ɒʂ���B |
�N�b�A�ɉ����B�N������Ė�����ށA�̏𗝂ɏہi�����ǁj��B
���q�A�ɉ����B�͉��������āA������{���B
�v�w�A�y�ɉ����B�y�͖������A�v�w�̘a�A�Ƃ̂��Ƃ��ƂȂ�B
���F�A���ɉ����B���͋`���M�сA�����ɐM�𗧂Ă�B
���c�A���ɉ����B���͉��ɗ���ď��Ȃ�B�N���͓����A�N���͏]���B
�������I�Ȑ���
- �w�����V�Ł@���E��S�Ȏ��T �x�����p
�ܗ� (�����) Wǔ lún
�����ɂ����āC�l�̏d�ׂ��܂̐l�ԊW�������B���q�̐e�C�N�b�̋`�C�v�w�̕ʁC���c�̏��C���F�̐M�������B �ܗςƂ�����́C�����ɐl�̎��ׂ�����������C���̒��Ղ́s�ܗώ��t�C�܂��N���C�b���C�����C�q���C�v�w�̓��C�Z��̓��C���F�̓��ɂ��ďq�ׂ��C���̐�@�̌��s�ܗϏ��t�ɏ��߂Č����B �������C���̓��e�Ƃ��Ă̌܂̐l�ςƂ��ꂼ��̓��ڂ́s�Ўq�t�ɗR������B �@�l�i�������悭�j��p���Ė��������肳�����w���C���Ɍ_�i���j���N�p���āC�q���q�ɐe����C�N�b�ɋ`����C�v�w�ɕʂ���C���c�ɏ�����C���F�ɐM����r�Ɛl�ϓ����������������B ���ꂪ�s��L�i�炢���j�t�ł́C�������N�b�C���q�C�v�w�C����C���F�ɕς���āq�V���̒B���܁r�ɂ��������C�����́s�̓�q�i���Ȃj�t�ł́q�N�b�̋`�C���q�̐e�C�v�w�̕فC���c�̏��C���F�̍ہr�ƕ\������Ă���B �ܗς̋����͎��H�����Ƃ��đ��d�����C�����i�q�j�͋���̍j�̂Ƃ��Čf���C���㕣�i�ێR�j�͓��ʉ����ĐS�w���������B ���{�ł��F��R�́s�ܗϏ��t�C�������́s�ܗϖ��`�t�Ȃǂ��q�삳��C�����̋��璺���ɂƂ�����ꂽ�B
���M�ҁF���� ���� - �w�f�W�^���厫��x�����p
�ނ���]���Ⴉ���k�]�V���N���C�l�y�����Љ�z
�Љ�̒��ŌǗ����Đ�����l���������Ă��錻�ۂ�\�����t�B����22�N�i2010�j��NHK�̕ԑg�̒��ŗp����ꂽ����B�����E���̏㏸�A�Ƒ��E�e����n��Љ�ɂ�����l�ԊW�̊��A�l���ی�̍s���߂��A�I�g�ٗp���̕���A�����ɂ킽��s���Ȃǂ������Ƃ���A�ǓƎ��̑����Ƃ�������肪�����Ă���B
���̎l���̂ЂƂw�_��x�畣��\�� ��11��
������
�@�Či������E�q�B�E�q�ΞH�A�N�N�A�b�b�A�����A�q�q�B���H�A�P�ƁA�M�@�N�s�N�A�b�s�b�A���s���A�q�s�q�A嫗L���A�ᓾ���H���B
����������
�@�āi�����j�̌i���i���������j�A���i�܂育�Ɓj���E�q�i�������j�ɖ�i�Ɓj���B �E�q�i�������j�i�����j���ĞH�i���j�킭�u�N�i���݁j�N�i���݁j����A�b�i����j�b�i����j����A ���i�����j���i�����j����A�q�i���j�q�i���j����v�ƁB ���i�����j�H�i���j�킭�u�P�i��j�����ȁA�M�i�܂��Ɓj�ɔ@�i���j�� �N�i���݁j�N�i�����j���炸�A�b�i����j�b�i����j���炸�A���i�����j���i�����j���炸�A�q�i���j�q�i���j���炸��A ���i�����j�L�i���j���嫁i�����ǁj���A��i���j���i���j�ď��i����j��H�i����j����v�ƁB
���
�@�Ă̌i���������ɂ��čE�q�ɐq�˂��B �E�q�͓����Č������B
�u�N�͌N�Ƃ��Ă̖������A�b�͐b�Ƃ��Ă̖������A���͕��Ƃ��Ă̖������A�q�͎q�Ƃ��Ă̖��������ꂼ��ʂ������Ƃł��B�v
�@�i���͌������B
�u�悢���Ƃ��B�����{���ɂ����łȂ���A���Ƃ������������Ă��A���̌��ɂ܂łǂ����ē͂����낤���B����A�͂��Ȃ��v
���̎l���̂ЂƂw�Ўq�x�앶���͋��
�������F
�@�l�V�L����C�O�H���߁C�틏�����́C���߉����ׁB ���l�L�J�V�C�g�_i�k�C�͈Ȑl�ρF ���q�L�e�C�N�b�L�`�C�v�w�L�ʁC���c�L���C���F�L�M�B
�ǂ݉������F
�@�l�i�ЂƁj�̓��i�݂��j�����A�O�H�i�ق����傭�j�g�߁i���j�A�틏�i������j���ċ��i�����j���Ȃ���A���Ȃ킿�b�i���イ�j�ɋ߁i�����j���B���l�i��������j�����J�i����j���邠��B�_�i���j�����Ďi�k�i���Ɓj���炵�߁A���i�����j����ɐl�ρi������j�������Ă��B���q�i�ӂ��j�e�i�����j���݂���A�N�b�i����j�`�i���j����A�v�w�i�ӂ��Ӂj�ʁi�ׂj����A���c�i���傤�悤�j���i����j����A���F�i�ق��䂤�j�M�i����j����B ��ӁF
�@�l�Ƃ��ĕ��ނׂ����Ƃ������̂�����B�����A�l���������A�g�������𒅂āA���������̂�т��炵�Ă��Ă��A������Ȃ���A�قƂ�Ǐb�ƕς��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B����l�i�����ꂽ�l���j�͐S�z�����B�����Ō_�i���j�Ƃ����҂Ɂu�i�k�i����������ǂ銯�j�v��C���A�l�X�ɐl�ԂƂ��Ă̓��i�l�ρj�������������B���Ƃ��A���Ǝq�̂������ɂ͐e���݂�����A�N��ƉƗ��̂������ɂ͋`�i���������j������A�v�w�̂������ɂ͈Ⴂ�i��ʁj������A�N���҂ƔN���҂̂������ɂ͏���������A�F�l�ǂ����ɂ͐M��������A�Ƃ��������Ƃł���B
�����璺��
�쐬���@1890�N�i����23�N�j10��30���@�@�N���ҁ@���B(���̂��� ���킵)�A���c�i�t(���Ƃ� �Ȃ�����)
�����͋������J�i�B�V���V�����A���������������蕶�ɕϊ����A�U�艼���Ƌ�Ǔ_���{�����B
�@���i����j�ҁi�����j���ɁA ��i��j���c�c�c�@�i���������������j���i���Ɂj�i�͂��j�ނ邱�ƍG���i��������j�ɁA���i�Ƃ��j�����i���j�邱�Ɛ[���i�����j�Ȃ�B ��i��j���b���i����݂�j���i��j�����i���イ�j�ɍ��i��j���F�i�����j�ɁA �����i�������傤�j�S�i������j����i���j�ɂ��Đ��X�i���j�i���j�̔��i�сj���ρi�ȁj����́A ���i���j���i��j�����́i���������j�̐��i�������j�ɂ��āA����i���傤�����j�̕����i����j���i�܂��j���i���j�ɍ��i�����j�ɑ��i����j���B ���i�Ȃj�b���i����݂�j����i�ӂځj�ɍF�i�����j�ɁA�Z��i�����Ă��j�ɗF�i�䂤�j�ɁA�v�w�i�ӂ��Ӂj���i�����j�a�i��j���A���F�i�ق��䂤�j���i�����j�M�i����j���A�����i���傤����j�ȁi���́j������i���j���A�����i�͂������j�O�i���イ�j�ɋy�i����j�ڂ��A�w�i�����j���C�i�����j�߁A�Ɓi���傤�j���K�i�Ȃ�j���A�ȁi�����j�Ēq�\�i���̂��j���[���i�����͂j���A����i�Ƃ����j�𐬏A�i���傤����j���A�i�i�����j��Ō��v�i���������j���L�i�Ђ�j�߁A�����i�����ށj���J�i�Ђ�j���A��i�ˁj�ɍ����i��������j���d�i�����j�A���@�i�����ق��j�ɏ��i�������j���A��U�i��������j�ɋ}�i���イ�j����`�E�i���䂤�j���i�����j�ɕ�i�ق��j���A�ȁi�����j�ēV�떳���i�Ă傤�ނ��イ�j�̍c�^�i��������j��}���i�ӂ悭�j���ׂ��B ���i���j���̔@�i���Ɓj���͓Ɓi�ЂƁj�蒽�i����j�����ǁi���イ��傤�j�̐b���i����݂�j����݂̂Ȃ炸�A���i�܂��j�ȁi�����j�Ď��i�Ȃj�c��i������j�̈╗�i���ӂ��j�������i���傤�j����ɑ��i���j���B
�@�z�i���j�̓��i�݂��j�͎��i���j�ɉ�i��j���c�c�c�@�i���������������j�̈�P�i������j�ɂ��āA�q���i������j�b���i����݂�j�̋�i�Ƃ��j�ɏ���i�����j���ׂ����i�Ƃ���j�A�V�i����j���Í��i������j�ɒʁi���j���ĕT�i����܁j�炸�A�V�i����j�𒆊O�i���イ�����j�Ɏ{�i�قǂ��j���Ĝ��i���Ɓj�炸�A���i����j���i�Ȃj�b���i����݂�j�Ƌ�i�Ƃ��j�Ɍ��X���^�i����ӂ��悤�j���āA���i�݂ȁj���i���j�̓��i�Ƃ��j����i���j�ɂ��Ƃ�����i�����˂��j���B
��Ӂ\��(�����V�c)�͎v���܂��B �䂪���́A�c�c�c�@�i���Ȃ킿���̓V�c�j�̂��n���ɂ���āA�����̂Ɍ��Ă��܂����B �����Ă��̂������́A�[���������ɂ���Ďx�����Ă��܂����B ���̍����́A���`��s�����A�e�ɍF�s���A �����Ƃ��������S���ЂƂɂ��āA��X���̔��������`���Ă��܂����B ����͂܂������A�䂪���̂̐��ł���A ����̍��{���܂��A�����ɂ�������̂ł��B �����ŁA�����ł��邠�Ȃ������́A ����ɍF�s���A�Z��͒��r�܂����A �v�w�͘a�₩�ɕ�炵�A�F�l�Ƃ͐M�������A ���ݐ[���g�𐳂��A�L���l�X���v�����A �w��������߁A�d���̋Z�p��g�ɂ��āA �m�b���J���A�������߁A ���v�̂��߂ɐs�����A�Љ�W�����A ��ɍ��Ƃ̌��@�сA�@���ɂ��������A �������ƂɊ�@������A���`�̐S�������āA�E�C�������āA �V�c�̂��߂ɐs�����˂Ȃ�܂���B �������āA�V�n�ƂƂ��ɐs���邱�Ƃ̂Ȃ��A�c���̉^���������x����ׂ��ł��B ���̂悤�ɐ����邱�Ƃ́A�P�Ɏ��ɒ��`��s�����悫�b���ł���Ƃ��������łȂ��A ���Ȃ������̑c�悪����Ă����`���Ɛ��_���A���̎���ɋP�����邱�Ƃɂ��Ȃ�̂ł��B
�@���̓������A�c�c�c�@���c���Ă������������������ł���A ���ׂĂ̎q���E�b�����A�Ƃ��Ɏ��]���ׂ����̂ł��B ����͐̂��獡�Ɏ���܂Ő��������ł���A �܂����������łȂ��A�O���ɂ��ʗp���镁�Ղ̓��ł��B ���́A���Ȃ����������ƐS�����킹�āA ���̋�����[�����ɍ��݁A �݂Ȃ����̓������L���Ă���邱�Ƃ��A�S�������Ă��܂��B
�����̑�
- �ܗς̂��ꂼ��̂��Ƃ킴�̗�
���q�F�g�̔����A�����ɎB�����Ěʏ�������͍F�̎n�߂Ȃ�i�w�F�o�x�j
�N�b�F�ڂ݂đ��������i�J�G���݂ă^���C��)�i�w�Ўq�x���b�����j
�v�w�F���쑊�a���i�L���V�c�A�A�������j
���c�F�E�Z�����i�R�E���E�A�i�V�����Y��)�@cf.
���F�F��鸂̌����i�J���|�E�̃}�W���j�u��ގ҂͕���A���m��҂�鸎q�Ȃ�v - �u���Ȃ��Ɨ~����F�Ȃ炸�A�F�Ȃ��Ɨ~����Β��Ȃ炸�v
�w���ƕ���x�̕��d���̌��t(�t�B�N�V�����ł���A�j���ł͂Ȃ�) - �u���@�o�e�T���F�S�t�v�~���|�E�A�C�łă`���E�R�E�A�z����
1889�N�|1892�N�̓��{�̖��@�T�_���̂Ƃ��A�����h�̕�ϔ����i�قÂ� ����j�����\�����_���̃^�C�g���B
 �@��l��@�܉��@
�@��l��@�܉��@
�@ �ߑ㐼�m�̉��C�w���`���ȑO�A���A�W�A�̊����������ł́A�q���̔�������́u�܉��v�ɑ�ʂ��Ă��܂����B�܉��́u�O�E��E���E��E�A�v��5�ł��B�̕���́w�O�Y���x(�����낤����)�̌���u����Ⴛ��Ⴛ�炻���A����ė�����A����ė����B�A�����A�A�T�^���i��ɃJ��T�����A�n�}�̓�͐O�̌y�d�B�J���u�₩�ɁA�A�J�T�^�i�n�}�������A�I�R�\�g�m�z���������v���A�܍s�v�z�̌܉����ӂ܂����Z���t�ł��B�܂����y�̌܉�(�ܐ�)�́u�{�E���E�p�E���E�H�v�ŁA���ꂼ�ꐼ�m���K�̃h�E���E�~�E�\�E���ɂ�����܂��B�{�u���̍u�t(�����O)��NHK�e���r�̔ԑg�w������!�i�r�x�̒S���u�t�ł�����A�܂������̐��͋����▾���y(�݂�)�Ȃǂ̉��y�����ł��B���{��ƒ�����́A�������A�W�A�̍��ǂ����Ȃ̂ɁA�ǂ����Ă���Ȃɔ����̂��������Ⴄ�̂��B�����Ɠ��{�̉̋Ȃ́A�ǂ����Ă���Ȃɕ��i���Ⴄ�̂��B�����l�̉����́A���퐶���̉�b���A�̐����A�u�����n�����͂�����A��������Ƌ�ʂ���v�Ƃ����܍s�v�z�̔��z������ɗ���Ă��܂��B���y�⌾��ɋ����̂Ȃ������ɂ��킩��₷���A�u���ŕ����킩�钆���l�̐S�̂����v�������������܂��B
���|�C���g�A�L�[���[�h
- �����u���v�̎���
�@��������B
�@���u��(����)�͈�(����)�Ȃ�v�B���̃R�A�C���[�W�́u���ɓ���Ăӂ����v�ŁA��������ÁA�ŁA喑�A�}�A����ȂǁB�Q�l�F�y�������z�������ہE���{���E�|�c�W�E���[���(��)�w�������i������Z�Łj�x(Gakken�A2018�N) p.2054�ȉ�
�@������Áw��p�����x�̐�
�u��ӁB���ƈ�Ƃ�g�ݍ��킹���`�B ���́A�_�ɐ����F��j������ꂽ��ł���ᄇ�̏�ɁA�����U��\�����Ƃ�����Γ���n�̌Y������Ƃ����Ӗ��ŁA ����n�p�̐j�i�h�j�𗧂ĂĂ���`�ŁA�_�ɐ����ċF�邱�Ƃ������B ���̋F��ɐ_����������Ƃ��́A�钆�̐Â��ȂƂ���ᄇ�̒��ɂ������ȉ��𗧂Ă�B ���̉��̂Ђт��́Aᄇ�̒��ɉ����̈�������Ď�����A���̎��ƂȂ�B ����ʼn��́g���Ɓh�̈Ӗ��ƂȂ�B���Ƃ͐_�́g���Ȃ��i�K��j�h�ł���A���ɂ���Ď������_�ӁA�_�̂������ł���v - �܉�/�ܐ��@������/������
�@�{�i���イ�A�h�j�E���i���傤�A���j�E�p�i�����A�~�j�E徴�i���A�\�j�E�H�i���A���j�́u�܉��K�v�̂��ƁB
�@�t�@�ƃV�ɂ����鉹���������u�����K�v�͑��y�̉��K�ŁA���y�ł͎g��Ȃ������B
�@���{�̍��Ɓu�N����v�̃����f�B�[���u�h���~�\���v�̌܉��K�ł���B�t�@��1����g�킸�A�V�͂Ȃ���1���g���B �@�Ȃ��A���㉹�y�̃t�@�̓~�̉d��(�~��B�~�̃V���[�v�B�~��蔼��������)�ł��������A�Ñ㒆���̃t�@�̓\�̕ω��ł���u��徴(�ւ�)�v(�\��B�\�̃t���b�g�B�\��蔼���Ⴂ���ŁA���ϗ��ł̓t�@�̃V���[�v�Ɠ�����)�ł������B
���܍s�z���ƌ܉�/�ܐ�
�܍s �� �� �y �� �� �ܐ� �p �� �{ �� �H �܉� �剹 �㉹ �O�� ���� �A�� �܊� �� �� �� �@ �� �ܐF �� �� �� �� �� �ܕ� �� �� ���� �� �k �� �t �� �y�p �H �~
- ���y�@��������
�@���y(���Ԃ̒ʑ��I�ȉ��y)�̑ΊT�O�ŁA�I�ȉ됳�ȉ��y�̈ӁB
�@�Ñ㒆���ł́A��s�̒���̉��y(�{�쉹�y��_�����y)���u���y�v�A�n���̑�O�̉��y���u���y�v�ƌĂB
�@���{�ɓ`�������������y�̂����A�Պw(����)�▾�y(�݂�)�Ȃǂ�����ɂ�����B
�@���{�̂�����u��y�vhigashiajia-gagaku.html�̂����A�����`���̓��y�͒����ł͋{��̉���y�u���y�v(����)�ł���A�Ñ㒆���ł͉�y��������Ȃ��������y�ł���B - �����@�����@temperament
�@�ߌ���̉��y�p��B�u�h���~����v�Ȃǂ̉��̍������A���w�I�Ɍv�Z���Đ��m�Ɍ��肵�����́B
�@�Ñ㒆���̐��y�ł́u�O�����v�@�v�ɂ���āA�Ñ�M���V�A�ɂ����Ắu�s�^�S���X�����v�ɂ���āA�U����2����3�̏���5�x���d�˂Ă䂭���ƂŁu�h���~����v�����肵���B �Ñ㒆���̉��y�ς́A�s�^�S���X�́u�V���̉��y�v��(Musica universalis)�Ɠ��l�A���y�̒��a�͉F���̐_��I�Ȓ����̒��a�ƘA�����Ă���A�Ƃ������̂������B
�@�����ł́A���y�͎v�z��܍s�v�z�Ɗ֘A�Â���ꂽ�B���y�́A���R�z���ł������B - �Ձ@����
�@���㒆����ł́u�ËՁv(�O�[�`��)�ƌĂԁB�ōł��d�����鐳�y�̊y��́u�Ձv�ł������B �s�^�S���X�����m�R�[�h(�ꌷ��)�ʼn��������������悤�ɁA�Ñ㒆���l�ɂƂ��āu�����Ձv�́u�V�n�l�v���Ȃ��y��ȏ�̑��݂ł������B
�@�Ȃ��A���{��ł́u�Ձv�Ɓu�(����)�v(�uⵂ̋Ձv=�\�E�̃R�g)���������ė��҂��u���Ɓv�ƌĂ�ł��܂����A���҂͊y��̍\�����i�i���S���قȂ�y��ł���B
�@�����́u�ËՁv�̌�(��)�̐���7�{�ɌŒ艻�����̂͊��ォ��ŁA�Ñ�̋Ղ͌܌�����\���܂ł��܂��܂������Bcf.https://www.tenri-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/GT290-3.pdf
�@�u����v(����)�Ƃ������t������悤�ɁA�ł�����d���B
���w�_��x�̉��y�W�̋L��
�@�E�q�̎́u��y(�ꂢ����)�v�܂�u��V�v�Ɓu���y�v���̍����Ƃ��ďd���B
- ��佾
�q�H�u��豁A�y���s���A�����s���B�v
�y�P�ǁz�q�H���u��豂́A�y����ň������A������ŏ��܂��B�v
�y������z�搶�͌���ꂽ�B�u�w��豁x�̎��́A��т������Ă��x�����A�����݂������Ă��S�����߂����Ȃ��B�v
cf.���y�u��豁v(�݂��E����)msg-kns-sfj.html#kansho�́u�����v�̋ȁB - ��佾
�q��D��t�y�B�H�u�y���m��F�n��A�Ô@��A�]�V�A���@��A�t�@��A㈔@��A�Ȑ��B�v
�y�P�ǁz�q�A�D�̑�t�Ɋy�����B�H���u�y�̂��̒m��ׂ����Ƃ́A�n�߂č�i�ȁj�����Ái���イ�j�@����A����ɏ]���Ώ��@����A�t�@����A㈔@����A�����Đ���Ȃ�B�v
�y������z�E�q�͘D���̊y���ɉ��y�ɂ��Č�����B�u���y�̗��͗����ł���B���t���n�܂�Ƒ����҂���ƍ����A�i�ނɂ�ď����ɁA���邭�A�����悤�ɂȂ��āA���������̂��B�v - �q��
�q�ݐĕ���A�O���s�m�����B�H�u�s�}�y�V�����z��I�v
�y�P�ǁz�q�A�Ăɍ݂������A�O�����̖���m�炸�B�H���u�}�炴�肫�A�y���ׂ����Ƃ̂����Ɏ����Ƃ́I�v
�y������z�E�q���Ăɂ����Ƃ��Ɂu��i���傤�j�v�Ƃ������y���A�O�������̊ԁA���̖�����킩��Ȃ��قNJ������Ă����B�u���y������قǂ܂łɐl������������Ƃ͎v��Ȃ������v�ƌ������B
cf.�����{�쉹�y�̒��a��y�@singaku-31.html - �ה�
�q�H�u�������A������B�����y�B�v
�y�P�ǁz�q�H���u���ɋ���A��ɗ����A�y�ɐ���B�v
�y������z�搶�͌���ꂽ�B�u�l�͎��ɂ���Ċ������āA��ɂ���ė������U�镑���𐮂��A���y�ɂ���Ċ��������̂��B�v - ��i
�q�H�u�R�V������u�V��H�v��l�s�h�q�H�B�q�H�u�R�珡����A����������B�v
�y�P�ǁz�q�H���u�R����i���j�A���i�Ȃ�j���ꂼ�u�̖�ɉ����Ă����H�v ��l�A�q�H���h�킸�B �q�H���u�R�⓰�ɏ��i�̂ځj���B�������ɓ��炴��Ȃ�B�v
�y������z�搶�͌���ꂽ�B�u�q�H����̉��t�́A���̖剺�Ƃ��Ăӂ��킵�����Ƃ��낤���H�v �i���̔����̂��Ɓj��q�����͎q�H�����܂�h��Ȃ��Ȃ����B �搶�͌���ꂽ�B�u�R�i�q�H�j�́A���łɓ��ɂ͓o���Ă���B�܂����̕����ɓ����Ă��Ȃ��������B�v - �G��
�E�q�H�u�V���L���A����y�������V�q�o�G�V�������A����y����������o�B�v
�y�P�ǁz�E�q�H���u�V���ɓ�����A��y�����͓V�q���o���B�V���ɓ�������A��y�����͏�����o�ÁB�v
�y������z�搶�͌���ꂽ�B�u���̒��ɓ����s���Ă���A��E���y�E�푈�͂��ׂēV�q���哱����B���������������Ă���A������ɗ�≹�y�����n�߂�悤�ɂȂ�B�v - �z��
�q�H�u��]��]�A�ʛ�]���ƁH�y�]�y�]�A���ۉ]���ƁH�v
�y�P�ǁz�q�H���u��Ƃ�����Ƃ������A�ʛ�̂��ƂȂ���B�y�Ƃ����y�Ƃ������A���ۂ̂��ƂȂ���B�v
�y������z�搶�͌���ꂽ�B�u��Ƃ����Ă��A�����V�q�⏔��̑����p�̌��̂��Ƃł͂Ȃ��B���y�Ƃ����Ă��A���⑾�ۂ�炷���Ƃł͂Ȃ��B�v - �z��
�q�V����A�����̔V���B�v�q�Ύ����A�H�u���{���p�����H�v �q���ΞH�u�̎Ҙ�畷���v�q�H�w�N�q�w�������l�A���l�w�����Վg��B�x�v�q�H�u��O�q�I��V������B�O���Y�V���B�v
�y�P�ǁz�q�A����ɔV���A���̂̐����B�v�q�Ύ��Ƃ��ď��A�H���u�{����������������p������B�v �q���A���ĞH���u�́A��₱���v�q�ɕ�����B�w�N�q�����w�ׂΑ����l�������A���l�����w�ׂΑ����g���₷���x�ƁB�v �q�H���u��O�q��A��̌��␥�Ȃ�B�O�̌��͋Y��ɔV��������̂݁B�v
�y������z�E�q������ɍs�����Ƃ��A���y�̐����Ăɂ�������A�u�{�������̂ɋ������g���悤�Ȃ��̂��v�ƌ������B �q�����u�ȑO�A�搶���w�N�q�������w�ׂΐl�������A���l���w�ׂΏ]���ɂȂ�x�Ƃ���������Ă��܂����v�Ɠ�����ƁA �E�q�́u���N�A��i�q���j�̌������Ƃ͐������B��قǂ̎��̌��t�͏�k����v�ƌ������B - ���q
�Đl�A���y�A�G���q��V�B�O���s���A�E�q�s�B
�y�P�ǁz�Đl�A���y���A���B�G���q������B�O���������A�E�q������s�i���j��B
�y������z�Ă̐l�X�������̊y�����Ă����B�G���q�͂�������ꂽ�B�O����������ӂ����B�E�q�͋������B
�����y�̌܋{��
�{���@�h���~�\���h�@���{�̋Ȃł����u�j�͂炢��v(�ߑ�̓��{���K)
�����@���~�\���h���@���{�I�ȋȂɂ͂Ȃ��B���y�u�Ï��v�ȂǁB
�p���@�~�\���h���~�@���{�I�ȋȂɂ͂Ȃ��B
徴���@�\���h���~�\�@���{�́u�����K�v�ɑ����B
�H���@���h���~�\���@���{�́u���̉��K�v�ɑ����B
�@���t�ɁA���{�́u�s���K�v��u���ꉹ�K�v�ɑ������鉹�K�́A�Ñ㒆���̐��y�ɂ͑��݂��Ȃ��B
cf.ongakutokagaku.html#scale
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | |||||||
| ���{�ݗ����K | ���ꉹ�K | �h | �~ | �t�@ | �\ | �V | �h | ||||||||
| ���̉��K | �h | b�~ | �t�@ | �\ | b�V | �h | |||||||||
| �����K | �h | �� | �t�@ | �\ | �� | �h | |||||||||
| �s���K | �h | b�� | �t�@ | �\ | b�� | �h |
���܉���2�̈Ӗ�
���y�I�ȁu�h���~����v�ƁA�����́u�O���A�㉹�A�����A�剹�A�A���v��\���ꍇ������B
cf.chinvu3.html#09
�y�Q�l�z�̕���w�O�Y���x(�����낤����)�̌�����B
�u����Ⴛ��Ⴛ�炻���A����ė�����A����ė����B
�A�����A(�̂��)�A�T�^���i��(����)�ɃJ��(��)�T����(������)�A�n�}�̓�͐O�̌y�d�B
�J���u�₩�ɁA�A�J�T�^�i�n�}�������A�I�R�\�g�m�z���������B�v
�Q�l YouTube https://youtu.be/xgJNhAKI3Pk?si=vMwk0EFErZMhttPF&t=347
| ���� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �܉� | |||||||
| �܉��̖��� | �O�� | �㉹ | ���� | �剹 | �A�� | ���㉹ | ������ |
| ���㒆����̐��� | �O��(bpmf) | ��뉹(dtnl) ���㉹(zh,ch,sh,r) |
��ʉ�(jqx) �㎕��(zcs) |
�㍪��(gk) | �㍪��(h) | (l) | (r) |
| �]�ˎ���̓��{�� | �n�} | �^���i | �T | �J | �A���� | ||
��������y�̌܉�(�����A�ܐ�)�u�{���p徴�H�v(���イ���傤��������)�Ɓu���ԍH�ځv�̊W�B
singaku-20.html
| ���m�K�� | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | |||||
| �u�ȕ��v | 1 | #1 | 2 | #2 | 3 | 4 | #4 ��5 | 5 | #5 | 6 | #6 ��7 | 7 | 1 |
| �ܐ��� | �{ | �� | �p | 徴 | �H | �{ | |||||||
| ����(1) ���K��� |
�{ | �� | �p | �� 徴 | 徴 | �H | �� �{ | �{ | |||||
| ����(2) �V���K��� |
�{ | �� | �p | �� �p | 徴 | �H | �� �{ | �{ | |||||
| ����(3) �������K��� |
�{ | �� | �p | �� �p | �� | �H | �[ | �{ | |||||
| ���{��y | �{ | �� �� | �� | �d �� | �C �p | �� �p | �� 徴 | �� | �� �H | �H | �d �H | �� �{ | �{ |
| ���ԍH��(��) | �� | �� | �H | �} | �Z | �� | �� | 仩 | |||||
| ���ԍH��(�V) | �� | �� | �H | �} | �Z | �� | �� | 仩 |
���m���y�̌ܓx���i�T�[�N���E�I�u�E�t�B�t�X�j�Ɠ��l�̌����ł���Ȃ���A�Ⴄ�R���Z�v�g�ŕ��ׂ����m���y�́u��ɐ}�v�B
singaku-20.html
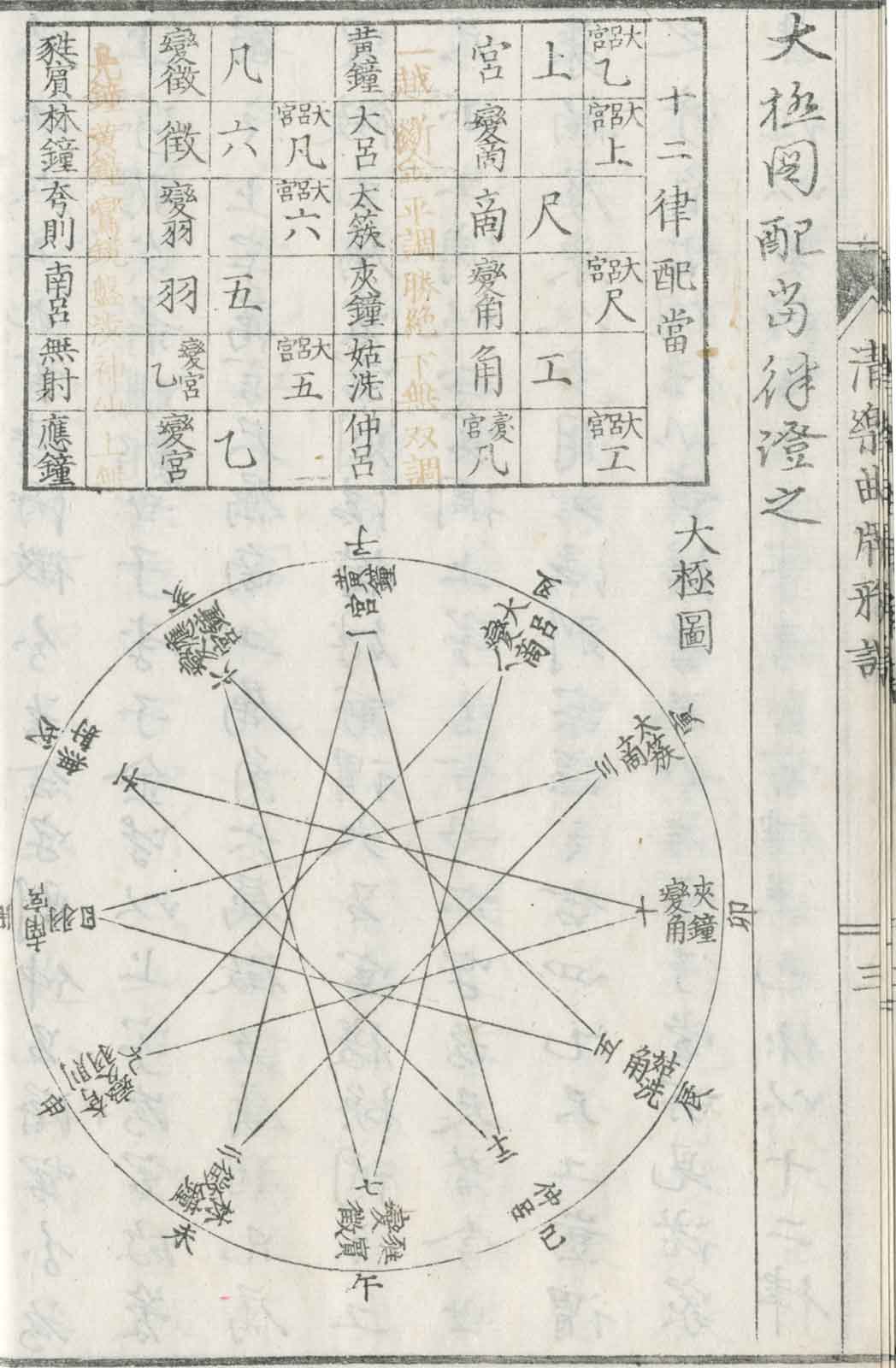
���u�K���`��v��������ڂ����傤
�@����łڂ��悤�Ȉ��r(�����)�ȉ��y�A�̈ӁB
�@�o�T�́A�����ÓT�w�ؔ�q�x�\�߂ɍڂ��鉹�y�̉��k�B
�@�I���O11���I�A�u���������̖\�N�E�@��(���イ����)�́A�t���Ƃ����y�l�ɂ݂���ȉ��y����点���B �u�����ɖłڂ����ƁA�t�����`���Ƃ�����ɔ�э���Ŏ��E�����B 500�N��̑O6���I�A�`���̂قƂ�ŕ��������s�v�c�ȋȂ��A�y�l�̎t��(������)���ʂ����A�W�̕����̂��߂ɉ��t�����B �y�l�̎t�D(������)�͖S���̉��y�ł���Ƃ��āA���t���~�߂悤�Ƃ�����������
�@cf.�����O�w���̊����́x�������Ɂ@����с@https://ctext.org/hanfeizi/shi-guo/zh
�@��ȓo��l���F�q�̗��(�݈ʁA�I���O534�N - �O493�N)�A�W�̕���(�݈ʁA�I���O557�N - �I���O532�N)�A�t���A�t�D�B
�@����F�I���O534�N����O532�N�ɂ����ẮA����N�B
�@�ꏊ�F�`���i�ڂ������j=���ĉ��͂ƍϐ��̕��������킳���Č`�����ꂽ��B�������Ȃ��B�W=���݂̎R���Ȃɂ������卑�B
�y������zAI�����p
�@���y���D��(���Ƃ͌N��̏\�̂���܂��̈�ł���)�Ƃ́A�ǂ��������Ƃ��B
�@�́A�q�̗���Ƃ����N�傪�W�Ɍ������r���A�`���i�ڂ������j�Ƃ�����̂قƂ�ɓ��������B �ނ͔n�Ԃ��~�߂Ĕn������A���̏h��݂��Ĉ����߂������Ƃɂ����B �邪�����߂�������A�s�v�c�ȉ��y���ǂ�����Ƃ��Ȃ��������Ă����B����͂��̉��y�ɐS��D���A�Ɛb�����Ɂu�ǂ����畷������̂����ׂ�v�Ɩ������B �������N��l�Ƃ��āA���̉��̏o�ǂ�����m�F���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B �����ŗ���͉��y�ɒʂ����Ɛb�E�t���i������j���ĂсA �u���̉��͂܂�Ől�̉��t�ł͂Ȃ��A�S�_�̂��킴�̂悤�ł���B���O����������Ċy���ɋL���Ă���v�Ɩ������B �t���́u�������܂�܂����v�Ɠ����A�Â��ɍ����ċ�(����)��t�łȂ���A���̉����Č����A�������߂��B
�@�����A�t���͗���Ɂu���y�͔c���ł��܂������A�܂��K�����Ă���܂���B������ӁA���K���鎞�Ԃ����������v�Ɗ肢�o���B����͂���������A�t���͂���Ɉ�ӂƂǂ܂��ė��K���A���̉��y��g�ɂ��Ă���W�ւƏo�������B
�@�W�ɓ�������ƁA�W�̕����͗�����{�̑�ʼn��ł��ĂȂ����B�����i�݁A������Ȃ𗧂����Ƃ���ŁA�������������B
�u�V�����Ȃ��A����ꂽ�����ł��ˁB���Ђ����������������B�v
�@����́u�킩��܂����v�Ɠ����A�t���ɉ��t�������B�t���́A�W�̖����y�ƁE�t�D�i�������j�̂��ɍ����ċՂ�t�Ŏn�߂��B �Ȃ̓r���ŁA�t�D�����t�𐧂��Č������B
�u����͖S���̉��y�ł������܂��B�Ō�܂ʼn��t���Ă͂Ȃ�܂��ʁv
�@�������u���̋Ȃ̏o���́H�v�Ɛq�˂�ƁA�t�D�͓������B �u����͟u�����̖����A�\�N�E�@���i���イ�����j�̂��ƂŎt���Ƃ������y�Ƃ�������ޔp�I�ȉ��y�ł��B ���̕������@�ƁA�t���͓��֓���A�`���ɂ��ǂ蒅���Ď��疽��₿�܂����B �ȗ��A���̉��y�́A�`���̂قƂ�ł������ɂ��邱�Ƃ�����܂���B ���̉��y�����ꂽ���́A�K�����^�������܂��B���t���ׂ��ł͂���܂���v
�@����ł������́u�킵�͉��y���D���Ȃ̂���B���t�𑱂���v�Ɩ������B�t���͖��ɏ]���A�Ȃ��Ō�܂ʼn��t�����B
�@���t���I���ƁA�����͎t�D�ɖ₤���B
�u���̉��y�͉��Ƃ����̂��H�v
�@�t�D�́u����͐����i�������傤�j�ƌĂ����̂ł��v�Ɠ������B
�u�����́A�����Ƃ��߂������y�Ȃ̂��H�v
�u�����B������߂����̂͐�徵�i�������j�ł������܂��v
�u���̐�徵�͕������Ƃ��ł���̂��H�v
�u����͓�イ�������܂��B�Ñ�ɐ�徵�����̂́A�݂ȓ��Ƌ`�����˔��������h�ȌN�����ł����B ������Ȃ���A�킪�a�͓����A�������Ƃ͂ł��܂��ʁv
�u�킵�͉��y���D���Ȃ̂���B�����ɒ������Ă���v
�@�t�D�͂�ނȂ��Ղ����o���A��徵�����t�����B
�@1��ڂ̉��t�ŁA������16�H���삩����ł��āA�{�a�̖�ɕ����~�肽�B2��ڂ̉��t�Œ߂����͐��A3��ڂ̉��t�Ŏ��L���Ė��A�����L���ĕ������B���͌܉��́u�{�v�u���i���傤�j�v�ɂ҂���ƍ����A���F�͓V�܂ŋ������B
�@�����͂����ւ��сA���Ȃ̐l�X���݂Ȋ��삵���B�����͔t����ɂ��ė����A�t�D�Ɏ��i���Ƃفj���̌��t�����̂��A�Ăі₢�������B
�u��徵�����߂������y�͂Ȃ��̂��H�v
�u��������߂����̂͐��p�i���������j�ł������܂��v
�u���p�͕������Ƃ��ł���̂��H�v
�@�t�D�͐��������B
�u�́A���邪�R�ŋS�_���W�߂đ�Ղ��s�����Ƃ��ɐ��p�Ƃ������y�����܂�܂����B �ۂɈ��������Ԃɏ��A�Z����倗�������������A�L��(�Ђ��ۂ�)�Ƃ����_�b���������A�o��(���䂤)���擱���A���̐_������|���A�J�̐_�������܂��A�Ղ�T���O���s���A�S�_�����̌�ɏ]���A���ւ͒n�ɕ����A�P���͋畢�����Ԃ���܂����B ���̂悤�ȑ����Ȑ_�X�̍s��̂Ȃ��őt���ꂽ�̂����p�Ȃ̂ł������܂��B ���̉��y���ɂӂ��킵���̂́A��z��������������N�傾���ł��B�������A�킪�a�͓��������A�����ׂ��ł͂���܂���B �������t����A�Ж�N����ł��傤�v
�@�����͌������B
�u�킵�͘V����Z���B���y�������y���݂Ȃ̂��B���В������Ă���v
�@�t�D�͂��ɐ܂�āA���p�����t�����B 1��ڂ̉��t�ŁA���k�̋獕�_���N���オ�����B 2��ڂŗ������r��A�������J���~��A ���͗A�Ջ�͉��A������������A�Q��҂͊F�����o�����B �����͋���āA�L���̋��ɐg�����B
�@���̌�A�W�̍��͑励�Ɍ�����ꂽ�B��n��3�N�Ԃ��Ԃ��A�Ђъ��ꂽ�܂܂ƂȂ����B �������g���d�������g�s���̕a�ɂ����邱�ƂƂȂ����B
�@�����炱���A�Ðl�͌������̂ł���B
�u�������ڂ݂��A���y�̉��y�ɂӂ��葱����A������g��łڂ����ƂɂȂ�v�ƁB
�y�����P�ǂɂ��ǂ݉������z
�@���i�ȂɁj���������D�ނƈ��i���j����H
�@�́A�q�̗���A���i�܂��j�ɐW�ɔV����Ƃ��A�`���̏�Ɏ���A�Ԃ�Łi�Ɓj�߂Ĕn������A�ɂ�݂��ĈȂďh���B�镪�ɂ��āA�V���������ۂ���҂��āA������x�сA�l�����č��E�ɖ�킵�ނ��A���Ƃ��Ƃ��ĕ������B�T���t���i������j�������Ă���ɍ����ĞH���A�u�V���������ۂ���҂���A�l�����č��E�ɖ�킵�ނ��A���Ƃ��Ƃ��ĕ������B���̏�A�S�_�Ɏ�����B�q�A�䂪���߂ɂ�����Ă�����ʂ��v�ƁB�t���H���u���v�ƁB����ĐÂ��ɍ����Ղ��Ă�����ʂ��B
�@�t���A�����A�ĞH���u�b�A�������B���܂��K�킸�B�����A������h���Ă�����K���v�ƁB����H���u���v�ƁB����ĕ������h���B�����A������K���āA���ɐW�ɔV���B
�@�W�̕����A������{�̑�ɂċ����B���łȂ�B����N�B���H���u�V����������B��킭�͐����Ă���������v�ƁB�����H���u�P���v�ƁB�T���t���������A�t�D�i�������j�̝Ӂi������j��ɍ������߁A�Ղ����i�Ɓj��Ă�����ۂ��B�����I��炴��ɁA�t�D�A������Ď~�߂ĞH���u����͖S���̐��Ȃ�B�����ׂ��炸�v�ƁB
�@�����H���u���̓��A���i�����j���ɏo�����H�v�t�D�H���u����͎t���i������j�̍�鏊�ɂ��āA�@�i���イ�j���r�r�i�тсj�̊y���ׂ��Ȃ�B�����A�@�ɋy�сA�t���A���ɑ���A�`���Ɏ���Ď��瓊���B�̂ɂ��̐����҂́A�K���`���̏�Ȃ�B��ɂ��̐����ҁA���̍��K���킪��B�����ׂ��炸�v�ƁB
�@�����H���u�ǐl�̍D�ޏ��͉��Ȃ�B�q�A��������Đ������߂�v�ƁB�t���A������ۂ��I���B
�@�����A�t�D�ɖ₢�ĞH���u����A�������̉��̐�����H�v�t�D�H���u����A�������̐����Ȃ�v�ƁB���H���u�����͂��ƍł��߂������H�v�t�D�H���u��徵�ɔ@�����v�ƁB���H���u��徵�͓��ĕ����ׂ����H�v�t�D�H���u�s�Ȃ�B�Â̐�徵���҂́A�݂ȓ��`����N�Ȃ�B���A�Ⴊ�N�A���������āA�ȂĒ����ɑ��炸�v�ƁB
�@�����H���u�ǐl�̍D�ޏ��͉��Ȃ�B��킭�͎��݂ɂ������v�ƁB�t�D�A�߂ނ����āA�Ղ�����Ă�����ۂ��B
�@�ꂽ�ёt����A���ߓA��������藈����āA�Y���垝�i���j�ɏW�܂�B�Ăёt����A������ʁB�O���ёt����A��������Ė��A���𘮁i�́j�ׂĕ����B���͋{���̐��ɒ��i�����j��A���͓V�ɕ�����B
�@�����A�傢�ɉx�сA������ҊF��ԁB�����A�[�i���������j��ċN���A�t�D�̎��i���Ƃفj�����ׂ��A����č����Ė₢�ĞH���u���ɐ�徵�����߂����͔��i�ȁj�����H�v�t�D�H���u���p�ɔ@�����v�ƁB
�@�����H���u���p�͓��ĕ����ׂ����H�v�t�D�H���u�s�Ȃ�B�́A����A�S�_��R�̏�ɍ��킷�B�ێԂ��킵�A�Z倗��������Ă��B�L���i�Ђ��ۂ��j����ɕ��тĊ����A�o�ށi���䂤�j�O�ɋ���A�����i�݂đ|���A�J�t�����r�i�����j���A�T�O�ɂ���A�S�_��ɂ���A���֒n�ɕ����A�P������B�傢�ɋS�_�������A���p����ׂ��B���A��N�A���������āA������ɑ��炸�B������A���ɋ��炭�͔s���v�ƁB
�@�����H���u�ǐl�V���ʁB�D�ޏ��͉��Ȃ�B��킭�͐����Ă������v�ƁB�t�D�A�߂ނ����Ă�����ۂ��B
�@�ꂽ�ёt����A���_�A���k�̕����N����B�Ăёt����A�啗����A��J����ɐ����A�疋��A�ד��i���Ƃ��j��j��A�L����隳�i�����j���A������ҎU������B�����A���A�L���̊Ԃɕ����B
�@�W���A�傢�ɝہi�Ђł�j���A�Ԓn�O�N�B�����̐g�A����癃�a�i�낤�т傤�j���B
�@�̂ɞH���u�����߂����āA�܉����D��ś߂܂���A����g�����߂�̎��Ȃ�v�ƁB
�����k�u���i�S�v�т킫
�o�T�w�{�_�L�x�@�Q�l�Fwaseda20250107.html#01
�ȉ��A���{�Y���w����������W�x�����p�Bhttps://www.aozora.gr.jp/cards/000082/files/1298_11892.html
�@���i���j�̐ԉG�i�������j�O�N�A��́i�������傤�j�̔_�v�k�x�i�悤�����j�Ƃ����҂��]�L�i���悤�j�Ƃ����Ƃ���܂ŏo�Ă䂭�ƁA�r���œ�����ꂽ�B�����_�̉��k�u��(�ނ���)�v�̌��l�^�Ǝv����B
�@�ЂƂ�̏��N�����i�i�т�j���������ė��āA�k�̎ԂɈꏏ�ɍڂ��Ă���Ƃ����̂ŁA���m���ē��悳����ƁA���N�͎Ԓ��Ŕ��i���\�Ȃ��Ђ��ĕ��������B �k�͂����S���Œ����Ă���ƁA�ȏI���A���̏��N�͍��i�����܁j���S�̂悤�Ȋ�F�ɕς��āA����сi�����j�点�A���f���āA�k�����ǂ��ė����������B
�@���ꂩ��X�ɓ�\���i�Z���i���傤�j�ꗢ�B���{�͎O�\�Z���ňꗢ�j�j�قǍs���ƁA���x�͂ЂƂ�̘V�l��������āA�k�̎Ԃɍڂ��Ă���ƌ������B �O�ɏ��������i���j��Ă͂��邪�A���̘V���������i����j���ŁA�k�͍Ăэڂ��Ă��ƁA�V�l�͉����i���������j�Ƃ����҂ł���Ƃ݂����疼������B �k�͓r���Řb�����B
�u��������ڂɈ����܂����v
�u�ǂ����܂����v
�u�S���킽���̎Ԃɏ�荞��Ŕ��i��e���܂����B�S�̔��i�Ƃ������̂����߂Ē����܂������A�Ђǂ����i���ȁj�������̂ł���v
�u�킽�������i���悭�e���܂��v
�@�������Ǝv���ƁA���̘V�l�͑O�̏��N�Ƃ��Ȃ��悤�Ȋ�����Č������̂ŁA�k�͂����Ƌ���ŋC�������Ȃ����B
���t�^�@��O�����ɂ�����u�{���p���H�v
�ȉ��A������R(1885-1944)�w���F���x�����H�̊������p�Bhttps://www.aozora.gr.jp/cards/000283/files/4504_7079.html
(���p�J�n)
�킽���������ӁA���𗬂��ĎQ��܂��ƁA�ӂƎڔ��̉��������܂����B �킽�����͊Ⴊ�����܂���A�������Ƃ��D���ł������܂��B���ɂ͌䏳�m�̒ʂ�A�{���p���H(���イ���傤��������)�Ȃǂ̊��ʂ���������܂��A �܂��o��(�������傤)�A�Տ�(�����傤)�A������(�����������傤)�Ƃ������悤�Ȓ��q�����낢�낲�����܂��A ������킽�����͕����킯��̂��D���ł������܂��B���̂ق��ɉ��Ƃ������̂́A�l�̐S���ɂ���ĕω����N����̂Ȃ�ł������܂��B�S�ɔ߂��݂����������́A ��т̒��ׂ𐁂��܂��Ă���тɂ͋����܂���A�S�Ɋy���݂��������Ƃ��́A�悵�A�߂������𐁂��܂��Ă��A���̔߂��݂̒��Ɋ�т�����̂ł������܂��A �g�̂̑s�������₩�Ȏ��ɐ������ƁA�a�C�̑O�ɐ������Ƃ͈���Ă���܂��B����Ȃ���A���Ȃ������������ɂȂ��Ă͏��������Ȃ��Ƃ�������鉹���A �킽�����������Έ�����Ɛ\�����Ƃ��������܂��B�l�ɍЂ킴�킢�̋N��O�ɂ͂��̉����Ă���ƁA�ЂƂ�łɂ킩�邱�Ƃ������̂ł������܂��c�c����ł������܂�����A�킽�����́A�C�ɂ����镨�̉��F�́A�����߂����ɒv�����Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł������܂��B�����ŁA���ӁA�����܂����ڔ��̉��F�́A�߂��뒿�������̂ł������܂����B�킽�����͂��̉��F���Ȃ���A���낢��Ƒz����v���܂��āA�����A����ȂƂ���܂ŁA�����Ƃ����ė����悤�Ȃ킯�Ȃ�ł������܂��B�@ (���p�I��)
 �@��܉�@�ܑ��@
�@��܉�@�ܑ��@
�@�u�ܑ��v�͊����ÓT�ł͌܂̎����E�e�����w�����t�ł����B���オ������ƁA�܂́u�����v���w���悤�ɂȂ�܂��B�u�܌ӏ\�Z����v�́u�܌Ӂv�́A�܂̔����u���z�E�N�ځE㹁E氐�E㳁v�ł��B20���I���߂ɐ����������ؖ����̃X���[�K���u�ܑ����a�v�ł́u���E���E�ցE��E���v(���̓`�x�b�g�l)��5�̖����Ƃ���܂����B���F���́u�ܑ����a�v�ł́u���E���E�ցE���E�N�v(���̏��Ԃ́w�势�a�x�ܑ̌��̍�)�ŁA���F���̍����̌ܐF�Ɗe���������т����܂����B1949�N�ɐ����������ؐl�����a���̍����u�ܐ��g���v�̌܂̐��͖����ł͂Ȃ��A�܂̎Љ�K���ł��B�u�ܑ��v���L�[���[�h�ɁA�����̗��z�Ɠ��`�̌����̗��j�������������܂��B
���|�C���g�A�L�[���[�h
- ���؎v�z�@���イ��������
�������̓`���I�Ȏ��������S��`���w���A���{�̊w�E�̏q��B���ؐl�����a���̊w�E�ł͎g�����Ƃ�����Ă���B
�����̊w�E�ł͏��������̖���������h�����Ȃ��悤�z�����A�u�؈Β����v(Hua-Yi distinction)��u�������S��`�v(sinocentrism)�Ƃ����p����g���B - �l�@����
���̎l���ٖ̈����B���i�Ƃ����j�A���^�i�������イ�j�A��i�Ȃ��j�A�kཁi�ق��Ă��j���w���B
���킹�āu��ཁv�i���Ă��j�Ƃ������B - �����@���イ����
�����ÓT�ɂ����Ắu�V���̒��S�v�Łu�����v�̗ދ`��B�`���C�i�̈Ӗ��ɂȂ�̂͋ߑ�ȍ~�B
�����ÓT�ł́A���͒�������u�����v�u�����v�u�㍑�v�ƌĂсA�������̑c����u�؉āv�u���āv�ƌĂB - �������@����̂����傤��
���{�j�ł͖����̕W��B�o�T�͌Ñ㒆���̊����ÓT�w�t�H���r�`�x�B �Ă̊���(�O685�N-�O643�N)�́u�������v���Ȃ킿���̉����������Ĉٖ�������u�����v����邱�Ƃ�W�Ԃ��A�V���̔e�҂ƂȂ����B20180710waseda.html
���t�H�퍑����́u�l�v�Ǝ���
| �܍s | �� | �� | �y | �� | �� |
|---|---|---|---|---|---|
| �ܐF | �� | �� | �� | �� | �� |
| �ܕ� | �� | �� | ���� | �� | �k |
| �ܕ� | �� | �� | �؉� | �^ | � |
| �� | �t | �� | �y�p | �H | �~ |
�@�C�A���т��@�w�������xp.423
�@�R�A�C���[�W�F�Ⴂ
�@���`�F�����ٖ̈���
�@�����F��(�l�̌`)�{�|�B��ӕ����B�����ł͋|�́u��݁v�ł͂Ȃ��A�܂������Ȃ��̂�܂肽����ŒႭ�Z������C���[�W�B
�^�@�����W���E�@�����j���E�@�w�������xp.699
�@�����F�u��(�ق�)�{�b(��낢�v��ӕ����B���܂��܂ȕ���B�܂��u�S�苭���āA�����Ȃ��v�C���[�W�B
�@�����o���@���������@�w�������xp.1641
�@�R�A�C���[�W�F�����
�@���`�F��������ٖ̈���
�@�����F�����́u�Łv�̏㔼��(���{���{��)�́u�����v(�����A���邸�鑱��)�{��(�ނ��B���蕄)�B�`�������B
�@���ꂽ�悤�ɂ��邸��ƁA�킯�̂킩��Ȃ����t�関�J�l�̈ӁB
ཁ@�����e�L�@�����W���N�A�`���N�@�w�������xp.1185
�@�����F�{���B��ӕ����B��R�₵�Č������ɒǂ������C���[�W�B
�Q�l�@�ȉ��͎i�n�ɑ��Y�w�X�����s��5�x�����p�Basahi20240411.html
�(�Ă�)�ȂǂƂ��������̌`�̂悳�Ƃ����A���̋����I�ȉ����͂ǂ��ł��낤�Bག͔��R�Ɩk���̔������������t�����A�����Ɂg���̂悤�Ȃ��h�Ƃ����C��������B���̂悤�ɑf�����A���̂悤�ɌQ����Ȃ��A���̂悤�ə����ŁA���̂悤�ɒ��������ɖ��m�ł���Ƃ���ɁA�������삯��ག̏W�c�̑��u����̂�ʂ��悤�Ȃ��������Ƃ����u�������������Ȃ����B
���܌Ӂ@����
�u�Ӂv�͒����̖k���E�����ٖ̈����B�Ӟ��A�Ӗ��A�ӉZ(���イ��)�A�Ӌ|�́u�Ӂv�B
�����j�̌܌ӏ\�Z������(304�|439)�ɂ́A���z�E�N�ځE㹁E氐�E㳂̌܂̖������A�������܂ޖk�����ɉ��������Ō��Ă��Basahi20220714.html#02
���z(���傤��)�F���[�c�͖k���V�q�����A�����n���͕s���B�I���O3���I������5���I����܂ŁBwaseda20230110.html#02
�N��(�����)�F���[�c�͖k���V�q�����A�����n���͕s���B�I���O3���I������o�ꂵ�A�����܂ދ��͂ȁu���덑�Ɓv��������B
�(����)�F���[�c�͖k���V�q�����A�����n���͕s���B4���I����5���I�ɂ����Ċ���B���{�̉�y�̑Ŋy��u㹌ہi������)�v��㹁B
氐�i�Ă�)�F���_���q�̃`�x�b�g�n�����ŁA�̒n�͐C�B�O2���I���납��6���I����܂ő��݁B�O�`��䘌��͂��̖����B�O�`�́A�Z���ɏI��������̂́A�`�x�b�g�n���������Ă������Ƃ��Ă͍ő�̔Ő}���ւ����B氐�́A580�N�A�Ō��氐�l���Ɓu�w�r�v���@�ɖłڂ��ꂽ���ƂŁA�j������ޏꂵ���B
㳁i���傤)�F�u����(�O17���I����|�O11���I)�́u�b�������v�ɂ��u㳁v�Ƃ�����������������قnjÂ����j�����A���_���q�̃`�x�b�g�n�����ŁA�̒n�͐C�B21���I�̌��݂����\���l�قǂ̐l�������݂��A���ؐl�����a���̐��{�����F����56�̖@�薯����1�u�`�������v�Ƃ��āA�����I�Ȃ܂Ƃ܂��ۂ��Ă���B2008�N5��12���ɋN�����u�l���n�k�v�̐k���n�́A�l��ȃA�o�E�`�x�b�g���`�����������B汶�쌧�ł������B
㳑�(���㒆���́u�`�������v)�ȊO�́A�q���͑��̖����ɓ����z������āA�����̂܂Ƃ܂�Ƃ��Ă͎c���Ă��Ȃ��B
���ܑ����a�@���������傤��
1912�N�ɐ����������ؖ����̃X���[�K���B
1912�N����1928�N�܂ł̒��ؖ����̍����́A�ܑ����ے�����ܐF����Ȃ�u�ܐF���v(������1906�N����P�����f�U�C��)�ł������B
�ܐF���́A�ԁE���E�E���E����5�F�̉����̑т��ォ�珇�ɔz���ꂽ���̂ŁA���E���E�ցE��E���̊e�������u�c�����đ勤�a����z���v���Ƃ��ے�����B�܂��܍s�v�z�̓�����k�{�����̌ܕ���\���Ƃ��錩��������Bcf.https://web.archive.org/web/20200617173132/http://www.chinanews.com/cul/2012/12-11/4398878.shtml(������) 1928�N����́u�V�������n�g���i�����Ă�͂����܂������j�v�ɕύX�ɂȂ����B
��(����)�F�������B����(asahi20211014.html#05)�ȂǁB
��(�܂�)�F���F�����B��V(asahi20211014.html#06)�ȂǁB
��(����)�F�Ö����B�{�O�h�E�n�[���ȂǁB
��(����)�F�ƃE�C�O�����R�Ƃ܂��ČĂԁB��҂̗�̓A�u�h�D���J�f�B���E�_���b���ȂǁB
��(����)�F�`�x�b�g�l�B�_���C�E���}13���ȂǁB
�@���F(�܂イ�B�}���W��)�����́A�������k�������˂̒n�ŁA�c��́A���������ł�����������������^�B17���I�ɓ���A���/�����������B ���̎x�z�K�w�ł������u���l�v�́A���F�����A�Ô����A���R�����ł���u���֊��v�̘A�������ł������B
�@�����S������(��)��7���I������j�ɓo�ꂵ���B�����j�㏉�̐��������ł����(�_�O)�����������_�O�l�������S�������Ƌ߉��ł������炵���B 13���I�̃`���M�X�E�J���̎���Ƀ����S���鍑�����������B14���I�́u���̖k���v����傫�ȑ��݊��������������B
�@�u��v�́A��������̍s���敪�u�v(���݂̐V�d�E�C�O��������ɑ���)�̏������A�Ƃ����Ӗ��ƁA�����̑S���ɂ���C�X�����n�́u�v���w���B ���҂͖����I�ɂ����j�I�ɂ��ʌ̐l�ԏW�c�ł��邪�A�̂̒����ł́u���v�Ƃ�����╎�̓I�Ȍď̂ł������傭���ɂ���Ă����B
�@�u���v�́A�`�x�b�g�l���w���B
�@���ؐl�����a���̍s���敪�ɂ́A�����������������߂�u�ȁv�ƁA���������́u������v������B �������S��������A�V�d�E�C�O��������A�`�x�b�g������́A���ꂼ��u�ցv�u��v�u���v�̎�����ł���B���F�����͗�O�ŁA���˂̒n�ł��铌�k���́u�ȁv����������Ă��邪�A����ɂ͕��G�ȗ��j�I�o�܂�����B
���ܑ����a�@���������傤��
���ؖ����ܑ̌��u���v�a�Ƃ̈Ⴂ�ɒ��ӁB
���F��(1932�N�|1945�N�B������ł́u�U���v�ƌĂ�)�̖�������̕W��Łu���E���E���E�ցE���v�ܑ̌����w���B
���F���̍������ܐF���ł���A1933�N�i�哯2�N�j2��24���̍����@�z����3���u�����m�Ӌ`���߃j�փX�����v�̌��������ł́A�܍s�v�z��\���B
�E���W���E�K���}�[�G���B�`�E�K���}�[�G�t�F�u�����[�g�l(�����S�������Ƌ߉�)�B���F�����R�㏫�B
��V�F���̐铝��B���F�l�Basahi20211014.html#06
�쓇�F�q�F���V�o����㺭�B���F�l�Basahi20250410.html#06
�������F���f�̃X�^�[�B�R���i�q�B���{�l�Basahi20211014.html#06
�p�����F���{���͍��ؐ��Y�B1944�N9���ɖ��F���R���тɔC���B��Ɋ؍��哝�́B
��u�����q�F1940�N7��2���A�V�����܂�B���e�͖��F���o�ϕ���b�鏑���B���D�B
�����̑�
- ���ؐl�����a���̌ܐ��g���̌܂̐��́A�����ł͂Ȃ��B �傫�Ȑ��͒������Y�}���A4�̏����Ȑ��͂��ꂼ��J���ҁA�_���A�����Y�K���E�����I���{�ƁA�m���l��4�̊K����\���B
- ������v���̎��́u�g�ܗށA���ܗށv���A�����ł͂Ȃ��A�K���ɂ�镪�ނł������B
�g�ܗށF�J���ҁA�n�_�A�v�������A�v���R�l�A�v����m
���ܗށF�n��A�x�_�A���v�����q�A�j�q�A�E�h
