 三蔵法師と孫悟空
三蔵法師と孫悟空
第652回 武蔵野大学 日曜講演会 2024年9月22日(日)10:00〜11:30最新の更新2025年5月26日 最初の公開2024年8月7日
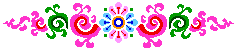
|
この講演の内容を文字化した文章は (武蔵野大学、2025年4月1日刊行)pp.62-85 合掌
|
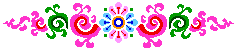
|
この講演の内容を文字化した文章は (武蔵野大学、2025年4月1日刊行)pp.62-85 合掌
|
 ☸☸☸☸
本日、お話しさせていただく内容の3つのキーワード
☸☸☸☸
☸☸☸☸
本日、お話しさせていただく内容の3つのキーワード
☸☸☸☸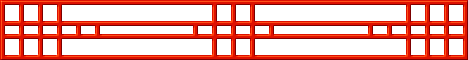
明日 2024年9月22日 の武蔵野大学 日曜講演会
— 加藤徹(KATO Toru) (@katotoru1963) September 21, 2024
「三蔵法師と孫悟空」(加藤徹)の要旨です。
日本版の三蔵法師が「おかま言葉」(野沢那智)、俗物(吾妻ひでお)、女優(夏目雅子)、二重人格(珍遊記)など「いじくられキャラ」になった理由は・・・
YouTube 無料配信のURLなど詳細はhttps://t.co/qrmjmaYVIp https://t.co/TyYR7NS5hn pic.twitter.com/USqKZl37Nt
|
以下、武蔵野大学のサイトの https://www.musashino-u.ac.jp/event/detail/20240922-3554.html より引用。閲覧日2024年9月21日。引用開始 第652回 武蔵野大学 日曜講演会引用終了 |
2024年9月22日、武蔵野大学で日曜講演会「三蔵法師と孫悟空」https://t.co/LgjeDRs2K9 を担当します。自分の本をスキャンして画像資料を作成。好花堂野亭『浄土宗回向文和訓図会』巻之中(1846年)の、松川半山による挿絵「孫悟空が神通、釈迦の六神通に及ばず」。 pic.twitter.com/PxqV93Tp6f
— 加藤徹(KATO Toru) (@katotoru1963) September 16, 2024
|
中谷宇吉郎「『西遊記』の夢」 「文藝春秋」1943(昭和18)年1月1日 子供の頃読んだ本の中で、一番印象に残っているのは、『西遊記』である。 もう三十年も前の話であり、特に私たちの育った北陸の片田舎には、その頃は子供のための本などというものはなかった。(中略) 漸く振仮名を頼りに読めるようになった時に、最初にとっついたのが『西遊記』であった。この頃になって、久しぶりで手にしてみると、劈頭から、南贍部洲(なんせんぶしゅう)とか、傲来(ごうらい)国とかいうようなむつかしい字が一杯出て来る。こういう画(かく)の多い字が一杯並んで、字づらが薄黒く見えるような頁が、何か変化(へんげ)と神秘の国の扉のように、幼い心をそそった。 面白さは無類であった。学校から帰ると、鞄(かばん)を放り出して、古雑誌だの反故だののうず高くつまれた小さい机の上で『西遊記』に魂をうばわれて、夕暮の時をすごした。昼でも少し薄暗い四畳半の片隅には、夕闇がすぐ訪れた。その訪れにつれて、本を片手にだんだん窓際に移って行った。ふと顔をあげると、疲れた眼に、すぐ前の孟宗籔の緑が鮮やかにうつった。 仏教の寓意譚であるという『西遊記』が、これほど魅魔的に感ぜられたのは、雰囲気のせいもあった。その頃の加賀の旧い家には、まだ一向一揆時代の仏教の匂いが幾分残っていた。 一番奥の六畳間(ま)が、仏壇の間になっていた。仏壇の間は昼でも薄暗かった。家に不相応な大きい仏壇は旧くすすけていて、燈明の灯がゆるくゆれると、いぶし金の内陣が、ゆらゆらと光って見えた。(中略) 時々燈明がぼうっと明るくなると、仏壇の中の仏像だの、色々な金色(こんじき)の仏様の掛軸だのが、浮いて見えた。そして孫悟空のいた時代がそう遠い昔とは感ぜられなかった。 |
|
中国史のスケール感は、ムック本と相性がよい。
大判なので、広大な風景の写真は迫力がある。
地図も大きくて見やすい。
図版を軸として、渾沌(こんとん)とした膨大な事象が、すっきりまとめられている。
『時空旅人別冊 大人が読みたい西遊記』(三栄、1300円)は、ムック本の特長を満喫できる歴史書だ。 7世紀、唐の玄奘(げんじょう)は命がけでインドに渡り仏法を学んだ。 彼は帰国後、旅で得た濃密な知見を弟子に口述筆記させた。 これが『大唐西域記』である。 後世、この史実をもとに、玄奘(三蔵法師)が孫悟空(そんごくう)や猪八戒(ちょはっかい)、沙悟浄(さごじょう)と天竺(てんじく)を目指す『西遊記』の物語が創られた。 上原究一・東大准教授は『西遊記』の受容史をわかりやすい筆致で解説する。 玄奘の没後まもなく伝説化がはじまり、13世紀から物語や芝居が続々と仕組まれた。 16世紀末、明の時代に「百回本」(全100回で構成される版本)の古典小説『西遊記』が成立した。 これに関して日本の存在感は印象的だ。 現存する明代の『西遊記』刊本は10種18点。中国には1点しか残っていないが、日本には8種15点も現存する。 徳川家康に仕えた僧侶・天海も『西遊記』の原書のコレクターだった。 日本での変容も興味深い。 日本では沙悟浄はカッパとなり、三蔵法師は1978年のドラマで夏目雅子が演じてから女優の役柄になった。 鳥山明氏が漫画『ドラゴンボール』でアレンジした独自の要素は、中国人にも影響を与えた。 歴史ライターの上永哲也氏らによる記事やインタビューも面白い。 子どものころ京劇(ペキンオペラ)の孫悟空を見て感動し、中国に渡り京劇俳優になった石山雄太氏。 史実の玄奘の足跡をたどり仏教聖地訪問の旅をした岡田真幸・大信寺住職。 第二次大戦中に日本にもたらされた玄奘の遺骨を今も埼玉県でまつる大嶋法道・華林山慈恩寺住職。 豊富な写真つきのインタビュー記事を読むと、玄奘と『西遊記』の数奇な歴史の旅は、今も終わっていないことに気づく。 私たちがどんな本を読み、どんな作品を楽しむか。それもまた『西遊記』の歴史の一部になるのだ。 |
西遊記の物語で、孫悟空のお師匠さんである「三蔵法師」(中国語では「唐僧」)のモデルは、歴史に実在した玄奘である。
2011年9月25日、俳優座劇場にて。京劇の孫悟空役の石山雄太さんと。こちらも参照
史実の現状については、加藤徹「玄奘 孫悟空の三蔵法師のモデルはタフガイ」asahi20230413.html#03も参照。
玄奘は隋の時代に生まれ、少年時代から出家し天才の誉が高かった。唐の初め、国禁を犯して密出国し、陸路でインドに渡ってインド仏教を学び、16年後に中国に戻った。 玄奘は長安で訳場(やくじょう。訳経道場)を開いて仏典(お経)の翻訳事業を行った。現代の日本人が読誦する「般若心経」は、鳩摩羅什訳(旧訳)ではなく玄奘訳(新訳)である。また口述により弟子に旅行見聞録『大唐西域記』を作らせた。
653年に日本から遣唐使の一員として渡った道昭(629−700)は、玄奘と同室で暮らしながら指導を受けた。
664年、玄奘は遷化(せんげ)。日本では、経蔵・律蔵・論蔵の三蔵に精通した高僧を指す「三蔵法師」と呼ばれることが多い。
玄奘の旅行記『大唐西域記』については、加藤徹「三蔵法師とインドの杜子春」waseda20240702.html#01も参照。
『大唐西域記』で玄奘が中国に紹介したインドの説話は、日蓮の手紙(兄弟抄 建治2年(1276)4月 55歳 池上宗仲・池上宗長あて)や、芥川龍之介の童話『杜子春』の元ネタになった。
また玄奘の死後、民衆のあいだで「唐三蔵西天取経伝説」が生まれ、世代累積型集団創作により、数百年をかけて古典小説『西遊記』が誕生した。
加藤徹「『西遊記』は子ども向け? もとはアダルトな成人向けエンターテインメントです」waseda20220517.html#05を参照。
敦煌莫高窟(とんこうばっこうくつ)からは、経巻を背負い虎を伴う行脚僧の絵(9世紀ごろ?)が発見されており、これを玄奘三蔵と見なす説もある。
cf.WikiMedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xuan_Zang.jpg PD
| 知 | 情 | 意 | |
|---|---|---|---|
| 雅 | 三蔵法師 | ||
| 雅俗共賞 | 孫悟空 | 白龍 | |
| 俗 | 猪八戒 | 沙悟浄 |
| 知 | 情 | 意 | |
|---|---|---|---|
| 雅 | 諸葛孔明 | 関羽 | |
| 雅俗共賞 | 劉備 | ||
| 俗 | 張飛 |
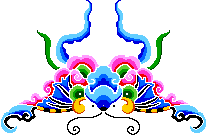
| 古典小説『西遊記』原文 | 日本語訳(加藤徹) わざと直訳的にしてます。 |
|---|---|
| 次早、那合家老小都起來、就整素齋、管待長老、請開啓念経。 這長老浄了手、同太保家堂前拈了香、拝了家堂。 三蔵方敲響木魚、先念了浄口業的真言、又念了浄身心的神呪、然後開『度亡経』一巻。 誦畢、伯欽又請写薦亡疏一道、再開念『金剛経』『観音経』。 一一朗音高誦。誦畢、吃了午齋、又念『法華経』『弥陀経』、各誦幾巻、又念一巻『孔雀経』、及談苾蒭洗業的故事、早又天晩。 献過了種種香火、化了衆神紙馬、燒了薦亡文疏。仏事已畢、又各安寝。 | 次の朝。家じゅうの老いも若きもみな起きるや、御斎(おとき)を整え御坊(ごぼう。ここでは三蔵法師を指す)をもてなし、開経(かいきょう)、読誦(どくじゅ)をお願いした。 かくて御坊は手を清め、太保(親分さん。ここでは劉伯欽を指す)とともに家堂の前で香をたき、家堂を拝した。 三蔵は木魚をポクポク叩き、まずは口業(くごう)を清める真言(しんごん)をとなえ、次に身心を清める神呪をとなえ、そのあと『度亡経』(どもうきょう)一巻を読んだ。 誦(ず)し終わると、劉伯欽からまた薦亡疏(せんもうそ)一通を書くことを請われ、そのあと『金剛経』と『観音経』を開き、それぞれを高らかに朗誦。 誦し終わり、午(ひる)の御斎を食べ、また『法華経』と『弥陀経』をそれぞれなん巻か読誦。『孔雀経』(くじゃくきょう)一巻を読み、苾蒭洗業(ひっしゅせんごう)の故事を談ずれば、早くも日は暮れた。 種々の香火を献じ、神々の紙馬を焼き、薦亡文疏を炊き上げ、仏事が終わると、おのおの安らかに就寝した。 |
|
却説那伯欽的父親之霊、超薦得脱沈淪、鬼魂児早来到自家宅内、託一夢与合宅長幼道。 「我在陰司裏苦難難脱、日久不得超生。今幸得聖僧念了経巻、消了我的罪業、閻王差人送我上中華富地、長者人家託生去了。 你們可好生謝送長老、不要怠慢、不要怠慢。我去也。」 |
さて、かの劉伯欽の父親の霊は、供養のおかげで浮かばれて、霊魂は早くも自宅に帰り、夢に託して家中(いえじゅう)の老若に言った。 「わしは、あの世で苦難から脱しがく、久しく生まれ変われずにおった。今、幸いに聖僧が経巻(きょうがん)をお読みくださり、わが罪業(ざいごう)を消してくださった。 閻魔大王の差配人により、わしは中華の富裕な地の長者の家へと送られ、生まれ変われることにあいなった。 おまえたち、よくよく御坊に感謝し、お送りせよ。ぬかるな、ぬかるな。では、さらば」 |
| (中略。劉伯欽の一家は三蔵法師に感謝する。劉伯欽は、三蔵法師を国境の山まで見送る。) | |
|
行経半日、隻見対面処有一座大山、真個是高接青霄、崔巍険峻。
三蔵不一時到了辺前。 那太保登此山如行平地、正走到半山之中、伯欽回身、立於路下道、 「長老、請自前進、我却告回。」 三蔵聞言、滾鞍下馬道、 「千万敢労太保再送一程。」 伯欽道、 「長老不知。此山喚做両界山、東半辺属我大唐所管、西半辺乃是韃靼的地界。 那廂狼虎不伏我降、我却也不能過界、你自去罷。」 三蔵心驚、掄開手、牽衣執袂、滴涙難分。 正在那叮嚀拝別之際、隻聴得山脚下叫喊如雷道、 「我師父来也! 我師父来也!」 諕得個三蔵痴呆、伯欽打掙。 畢竟不知是甚人叫喊、且聴下回分解。 |
道を行くこと半日で、正面に大きな山があらわれた。まことに青空に接するほどの高さ。巍巍(ぎぎ)として崔嵬(さいかい)たる険峻な山だった。
三蔵は、ほどなくふもとに着いた。かの太保といえば、この山を登ること平地を行くがごとく、山の半ばまで来ると、伯欽はくるりと身を回し、道ばたに立って言う。 「御坊、これよりは、おひとりでお進みくだされ。わたしは戻らせていただきます」 三蔵は、馬の鞍からころげ落ちるようにおりて言う。 「なにとぞ、太保どの、どうかこの先も、お送りくだされ」 劉伯欽は言う。 「御坊はご存知ないでしょうが、この山は両界山と申しまして、東の半分はわが大唐の所管なれど、西半分は韃靼(だったん)の領域です。 かの地の虎狼(ころう)はわが手に負えず、われも国境を越えられず、おひとりでお行きくださいまし」 三蔵は仰天し、腕をふりまわし、劉伯欽の服やたもとを引っ張り、涙を流して別れがたく、ねんごろに拝別の言葉をかわすそのうちに、山のふもとより雷のような叫びが聞こえてきた。 「わがお師匠が来たれり! わがお師匠が来たれり!」 たまげた三蔵は呆然。劉伯欽はかろうじてふんばる。 さて、この叫び声の主は何人(なんぴと)ぞ。続きは次回のお楽しみ。 |
|
2016年6月5日、池袋の京劇「白蛇伝」楽屋にて。 法海(に分した俳優さん)とともに合掌。  法海禅師は歴史に実在した唐末の高僧だが、後世の物語「白蛇伝」では悪役にされてしまった。 |
|
新潮劇院 京劇公演 「孫悟空 vs 孫悟空(中国語原題「真仮孫悟空」)」 2010年5月・6月 cf.KGevent2010.html 写真つき 新潮劇院のサイト https://www.shincyo.com/zhenjia/index.htm 孫悟空(本物):石山雄太 孫悟空(偽物):馬征宏 三蔵法師:中川晃教(横浜公演)/張冠玉(中野公演) 観音菩薩:盧思 釈迦如来:殷秋瑞、他 |
【拡散希望】10月25日水曜のフライヤーを作りました。#明治大学 映像資料プログラム
— 加藤徹(KATO Toru) (@katotoru1963) September 23, 2023
「坊主バンド」@vowzband
浄土真宗の僧侶でミュージシャンでもある藤岡善信先生をお招きし、先生の動画を鑑賞し、お話と弾き語りもうかがいます。入場無料、予約不要。詳細は、https://t.co/XwAshqboqS pic.twitter.com/NuqhfhZIIZ
|
毛沢東(1893-1976)が詠んだ漢詩「和郭沫若同志」一九六一年十一月十日
※毛沢東が、「孫悟空、天宮で大暴れ」と「孫悟空、三たび白骨の精を打つ」の話をふまえ、みずからを孫悟空にたとえ、後の「文化大革命」の発動をほのめかした漢詩。 一従大地起風雷、 一たび大地に風雷の起こりてより 便有精生白骨堆。 便ち精の白骨の堆きより生ずる有り 僧是愚氓猶可訓、 僧は是れ愚氓なるも猶ほ訓ふべし 妖為鬼蜮必成災。 妖は鬼蜮と為りて必ずや災を成さん 金猴奮起千鈞棒、 金猴 奮起す 千鈞の棒 玉宇澄清万里埃。 玉宇 澄清す 万里の埃 今日歓呼孫大聖、 今日 孫大聖を歓呼するは 只縁妖霧又重来。 只に妖霧の又重ねて来るに縁る ヒトたびダイチにフウライのオコりてより、スナワちセイのハッコツのウズタカきよりショウずるアり。ソウはコれグボウなるもナおオシうべし。ヨウはキイキとナりてカナラずやワザワイをナさん。キンコウ、フンキす、センキンのボウ。ギョクウ、チョウセイす、バンリのホコリ。コンニチ、ソンタイセイをカンコするは、ヒトエにヨウムのマタカサねてキタるにヨる。 大地に嵐と雷が起きてから、白骨の山からとんでもない妖怪が生まれた。三蔵法師は愚かだがまだ再教育できる。妖怪は陰険な化け物なのできっと災厄をもたらすだろう。金色のサルが、千鈞の重さの如意棒を勢いよく振り回す。天上界の神々の宮殿の万里のほこりは、綺麗にはらわれる。今こそ、斉天大聖・孫悟空を歓呼の声で迎えるべきだ。その理由は、妖しい霧がまたぞろただよっているからに他ならない。 |
|
吉川英治(1892ー1962)『小説のタネ』「西遊記の面白さ」 雑誌「文藝春秋」1957(昭和32)年11月号 僕の読書ですか、読書といっても、くつろぎの気持で手を伸ばす本は、きまって美術書だとか、平易な科学書とか旅行記みたいな物ですね。この頃は怠けぐせになったんでしょうか、勉強のためになんて、読みませんな、ひとの小説もよほどでないとめったに読まない。以前は、暇さえあると、神田、本郷の古本屋街を日課のように歩いては買い集めましたがね、またその当時は片っ端から買って来るとすぐ読んだものですが、近年は買ってもすぐには読まんですな。読まないくせに、古書目録を見るとつい買いこんで、それがだんだん溜っちゃうんで、いまでは書庫に困ってますよ。けれど唯、カードだけは頭にあるんで、必要にせまると、もちろん役に立つわけです。ともかく、雑書雑然というやつです。 最近、ちょっと思い寄りがあって、「西遊記」に関する本を大分集めましたよ。あの中の、孫悟空ってものは実におもしろい。少年時代から「西遊記」は三、四回ぐらい読んでいますね。今年は軽井沢で暇があったので、孫悟空研究ってほどじゃないけど、ひとつ、おさらいをしてみようと思って、もう一回全編を読んでみました。そして「西遊記」の作者の空想力にあらためて驚嘆したですよ。いかに僕が空想家だと云っても、あれにはとてもかなわない。日本の古典とおなじように、「西遊記」の作者も誰なのか、よく分ってませんが、魯迅の説だと、明代の呉承恩だといってますね、ま、それはとにかく、あの雄大な空想力というものは、島国に生れた作家の小ッさい空想などとはてんでケタが違うんだな。まったく天衣無縫ですよ。 けれど、あの「西遊記」も、今日読んでみると、おもしろいのは、全編の五分の一ぐらいのところ迄でしょうか。あとはどうも面白くない。然し、その空想力の逞しさは、たとえば今日の科学者が電子、量子へ向って、挑みかけている夢とも匹敵するほどなもんですよ。東洋の四大奇書の一つといわれるわけですね。惜しむらくは、前半以後になると、悪魔外道の出没とおなじ手法のくり返しになっちゃって、退屈を感じ出させますが、少年時分によくも克明にあんな大部な物を読んだもんだと、幼い頃の読書慾にも、われながら、つくづく感心しちゃったな。 ところで、その「西遊記」は、今日までに幾たびも翻訳翻案されてますが、これを現代にとって書いたらどうなるかなんて、ついまた空想をほしいままにしてみたんです。 悟空というあの半人半猿の性格は、現代人のたれの中にもいる一種の怪物ですからね。三蔵法師が天竺に経を求めにゆく願望を、今にすれば、さしずめ、人類の浮沈にかかわる原水爆のことになるでしょうな。人類が原水爆を使うか使わないかというのがラストでいいでしょう。悟空がよく駈けつける観世音菩薩は、真理の象徴とか、愛の具現とかになりますね。猪八戒と沙悟浄とは、われわれ仲間の現代人です。そういった仮設で、あの悟空を現代に用いて、二十世紀の三千世界を舞台にする。地球はもちろん、地軸から地上、天上から九天までを大舞台として現代を書けば今のあらゆる世態が書けると思う。思想、政治諷刺、小さくは銀座から汚職までね、飯茶碗の中まで書けるんじゃないですか。僕の空想癖でやれば……いや今は書きはしませんよ、もし書くとすればですね、悟空が自分の毛を抜いて、ふッと吹きさえすれば、変身の術を行うから、彼を用いて、一度は女体の子宮にも入れてみたいなんて思いますね、悟空という半人間の生命を一ぺん精子に戻して、そこから再出発させてみたい。まだ世に出ない子宮の中で、篤と、人間っていうものの出発を考え直さしてみたいような気がしますね。そして現行の政治方式というものやら何々主義などと絶対的に思われているものが、果してほんとに人間の社会の暮し方に好適なものか、どうかなんてことを、悟空に考えさせてみるわけです。 いや、そんなことを云っても、やっぱり書くのはむずかしいな。一朝一夕にはやれないな。空想ってやつは、孫悟空が何万里を一瞬に駈けるようなもんで、とめどもないが、われに返ッてみたら、如来の手のヒラを駈けていたに過ぎなかったっていうようなもんですな。……しかしこの夏は「西遊記」を手に悟空と共に宏大無辺を遊びましたよ。 「西遊記」には、後代に書かれた「後西遊記」もあるけれど、「後西遊記」はつまらない。「続金色夜叉」の類で、いけないですね。また、小説の「西遊記」には、史実の種本があるんですよ。千三百年の昔、大唐の長安から、その頃の中央亜細亜を通って、十八年がかりで印度へ行った玄奘三蔵法師の旅行記がそれなんです。その「大唐西域記」は三蔵自身の記録といわれてるから、ほとんど史実ですからね、そんな厳然たる史実をとって、あんな奔放きわまる空想を書いたんですから、じつに自由無礙な想像力です、いわゆる大陸文学というもんでしょう、とても小国作家の頭脳ではありませんね、敬服しますな。 |