���@�g(������)�Ə��l�C�e�B�u
�Ñ���{�ɂ����ẮA�l�C�e�B�u�Ȃ������l�C�e�B�u�u�n���n�����v�̒�����͂�����ɂ��ꂽ�B
���얅�q�̒�����ʖ�(�u�����v)���Ƃ߂��ƍ앟��(������� �� �ӂ���)�͒����n�n���l�̎q���B
���ÓV�c16�N�i608�N�j��O�����@�g�̂Ƃ��A���얅�q�ɂ����������@�ɂ킽�������w���̖ʁX�́A�n���n�����������B
�E��������(�����ނ� �� ����܂�) �\ 鰂̕��邱�Ƒ���(���� ��)�̎q���B �u����܂낭��v(���{�E�͓�����s���U�w�K���i�}�X�R�b�g)�̃��f���@https://www.yurugp.jp/jp/vote/detail.php?id=00000911
�E�앣����(�݂ȂԂ� �� ���傤����) �\ ����Z�c�q�ƒ��b�����̐搶
�E��(�݂�) �\ �w�m
�E�b�B(������) �\ �w�m�B�����͎u�ꊿ�l(�����̂���Ђ�) �E�`������(��܂Ƃ̂��� �� �ӂ�����)
�E��t�b��(������ �� ���ɂ�) �\ �����n�n���l�B���N�����n�B
�Q�l�@���얅�q�̎q����X(���c�C�b�^�[)�A�J�E���g�@https://twitter.com/onoonomakoto (���얅�q���琔����44���)
�ȉ��A�������g�u���{�̌������w���Ɠn���l�v(�w��C��w���A�W�A���E�j�����Z���^�[�N��@��1���x2008�N3��, p.51 / https://core.ac.uk/download/pdf/71785708.pdf�@�{����2024�N1��31��)�����p�B���p�J�n
����16�N9�������̌��@�g�ɂ�8�l�̗��w����w��m�����s������� �w���{���I�x�ɂ��Ƥ���̊�Ԃ�͘`����������ޗǖ��b����������l������V���l�卑(�w��)��V���l������앣���l������u�ꊿ�l�b�B��V���l�L��(�w��m)��萬�顔ނ�̑����͏抿���₻�̌n�̊��l�̏o�g�Ť�������l�����ͤ�����𢍂���j��Ƃ��L���悤�ɤ������(�������̎}��)�̉��ŕ��M��L�^�̔C�ɂ��������t�~�q�g(���}�g�m�t�~�q�g)�̈���ł����顎c��ޗǖ��b���͌Ȓq���̓�����u�ꊿ�l�b�B�͐������n�̊��l�Ƃ݂��邪�A����2�l���܂��S�����n���l�ł������p�I��
���ߍ��Ǝ���̓��{�ł́A�������l��n���m�ނ��̒�����w�K���s���Ă����B�����̒�����w�K�ɂ��Ă͋L�^���c���Ă��Ȃ��B
- ��w����������B�����ÓT�𒆍���ʼn��ǂ���B�u�lj��v���S�B
��w��(���o��)���400���A���w��(�Z��)���30���B���w���i�͌܈ʈȏ�̋M���̎q�킩�A�j��(�ӂЂƂׁB�����쐬����)�̎q�ǂ��B�݊w�N����9�N�B
��@���쎭��(������ �� ���Ƃ� 774-843)�͋M���B�u�����Ԃ�j���ɏ�A���˂Ċ�����m��v
��w�Ȃł͔����w���̋����u�����m�v�ɂ��A�����ÓT�𒆍��ꉹ�œǂތP�����s��ꂽ�B
817�N�ɂ́A������ʖ�{���̂��߁A�u�X�����A�N�O�\�ȉ��̑��߂̓k�A���F(�ɂイ����)�l�l�A�����Z�l��I�сA��w���ɂ����āA������w���ނׂ��v(�w���{�I���x)�Ƃ������߂��o�����A���F���������ʼn��w�̊��l�ŁA�ʖ̒n�ʂ͒Ⴉ�����B
�����g����ʖ�̍ō��ʂ́A�݊C�g�̒ʖ�߂��t���(������ �� �₩�Ȃ�)�̐�6�ʏ�ŁA�ނ��ŏ��ɔC�p���ꂽ859�N�̎��_�̊��ʂ͑叉�ʉ��i28�ʁj�ɂ����Ȃ������B�����g�̒ʖ�̍ō��ʂ́A�D���Ɠ����ł������B - ���w����L�͋M����9���I�ȍ~�A��w�����w�O�̎q��ɗ\��������{�����߂ɗ��Ă������w�Z�B��������821�N�ɍ�������w�@���L���B
- �����E����L�͎��@�̒���A�l���ƂȂǂŒ�����̊w�K���s���Ă����B
��@����(629-700)�E�E�E�D�b��(�ӂ� �� ������)�̎q�Ŗ@���@�̑m�B653�N�ɓn�����A�����O��(602-664)�̕����œ������Ȃ���w�������B
��@�I�t��(���� �͂�ʂ�)�́A���ۂɓ������������g�Ƃ��Ă͍Ō�ƂȂ��19��̏��a5�N(838�N)�̌����g�̒ʖ�B���Ƒ�����̑m�őm�ʂ͓`����@�t�ʂ��������A���a3�N(836�N)�Ɋґ��������A���Z�ʏ�E�������i�ʖ�j���A�n�����ɏ��C���ꂽ�B�~�m�́w�������@����s�L�x�ɂ��u�I�ʎ��v�Ƃ��ďo�Ă���Bcf.���K�u���A�㐢�I���A�W�A�ɂ�����O��p����v(1997) NII�_��ID 110000330741
�@�ȉ��A��f�u�������g 2008�vp.53�����p�B���p�J�n
���Ďg�̎��قǂł͂Ȃ��ɂ��Ăऌ����g�̏ꍇ�ओn���n�̗��w����w��m�������䗦���߂Ă����Ƃ݂���̂ł������p�I��
�@����ɑ��Ĥ��n���n�̗��w����w��m�ͤ�������~��ɂ�Ď���ɑ����̌X�������ǂ���̤̂�{�V���N�����̉���(�g��)���b�^�����`��������l(��a���̒���)��V������4�N�̑V�b��u����N����(?)�̑P�c(�����b��A)���T8�N�̉i��(�����H���b)�����23�N����C(����������) ��`�^(�����ێq�A�܂��͊ۓs�A)����a5�N�̉���(�����}��) ��t���h�I�ʐ�(�O�f�\1�̒�4�Q��)����a9�N�̈��^(�������h�I)�̂悤�ɤ��ʂ���������̊��l�w��n�������w(�����^��-�������C�����-�]��`�^-���ͤ�t���h�I�ʐ�-����)�̎q�킪�����B
���l�C�e�B�u�̒����ꋳ���̃��[�c
���猾(���傭 ���グ��)�E�F�O�����7���I�A����̒����n�n���l�ŁA�����m(����̂͂���)�B
�͐W���E�����E�c�ᓌ�����8���I�A�ޗǎ���́u�j���[�J�}�[�v�ŁA���{�ɋA�����������l�œ��y�̉��t�ɂ������Ă����B
�����g�ƂƂ��ɒ����ɓn�������{�l���w���̒�����\�͂́A�܂��܂��������B
�O�@��t���Ƌ�C�͒�����E�����E�T���X�N���b�g(����)�ɐ��ʂ�����w�̓V�˂ł����������A�k�퐨�͒�����̔����ō��܂����B
�Q�l�L���@�����O�@�w������̊x(https://www.chuken.gr.jp/study/wa.html)��126�� �f�ڋL����莩�Ȉ��p�B���p�J�n
�������g����J����������̐�̓������������p�I��
�@���{�l�̒����ꔭ���w�K�̃L���͐�ł���B
�@������̐���(�q��)�̈ꗗ�\������Ɓu�O���A��뉹�A�㍪���A��ʉ��A���㉹�A�㎕���v�]�X�Ƃ���Bb p m f �́u�O���v�������݂ȁu��v���܂ށB
�@������̉C��(�ꉹ)�̂����A���{�l�����Ƃ��� e�A ü �Aer��3�P�ꉹ���A�R�c�͐ゾ�B���S�҂́u�O���猩������̌`�v����C�ɂ���B�{���́u�O����͌����Ȃ��A���̂Ȃ��̐�̈ʒu�Ɠ����������v���錍���B����e�́A���ȏ��ɂ́u�P�ꉹ�v�ȂǂƏ����Ă��邹���ŁA���S�҂͂Ă�����ue�̔����̍Œ��͐�����Ȃ��v�Ǝv�����ށB�{���́Ae�́u�P�ꉹ�̊������������̕����ꉹ�v���Be�́A�������Ȃ�����̒��Ő�����̉��ɃX���C�h�����A�E�͂���B���́A���̒��̐�̓����́A���k�������̌�����������W�[�b�ƌ��Ă��A�킩��Ȃ��B
�@�u�@�ꉹ�v�܂�n��ng�̋�ʂ��A�L���́u�@�̌��v�ł͂Ȃ��B��͂�A���̂Ȃ��̐�̓������Ble�̔����̃R�c���Azhi chi shi ri �̃R�c���A���������߂邪�A�Ƃɂ����A���{�l�̒�����w�K�҂ɂƂ��Ă̋S��́A��ł���B
�@������1200�N�O�̌����g�̎�����A���{�l�͐�ŋ�J�����B
�@���{�̏����j��A��C(��������)�E����V�c(�����Ă�̂�)�E�k�퐨(�����Ȃ̂͂�Ȃ�)��3�l���u�O�M�v�ƌ����B��C�Ƌk�퐨�͌����g�̓����̗��w���������B2�l�Ƃ�804�N�ɓ��ɓn�����B�{���͏\�N�ȏ㗯�w����\�肾�����B���A2�l�Ƃ�2�N�ŗ��w���グ�A806�N�ɋA�������B��C�͒�����̒B�l�ŁA�w�Ԃׂ����̂��w�ѐs�������B�k�퐨�͒�����̔����ō��܂��A�����Ɍ���������B
�@��C�̎����W�w����W�x��5�̊����u�k�w���^�{���g�[���v�́A�k�퐨�������A����\�������{��(���{)���Ă̕��͂ł���B��|�́u�������b�ō��܂��܂����B���̂܂ܗ��w�𑱂��Ă����ʂł��B��w�͂��n��ł��}�X�^�[�ł����(����)�Ə����́A���Ȃ��玩�M������܂��B�A�������F�߂��������v�B�����ŁA
���R��u�����V��A��硗V�ŗсB �@�܂�u���{�ƒ����͒n���I�ɉ����A�����̕��͐�̓������������S�R�������̂ł��B�������b���ł����A�����̍�����������܂���v�ƕى������B
(���܁A�R��͗����̐���u�āA���܂��ŗтɗV�Ԃɂ��Ƃ܂��炸�B)
�@������ƁA�k����B��C����́A���{�ɂ����Ƃ�����w�͂��Ē�������}�X�^�[���܂�����B���̐\�������A�����ŏ������ɐe�F�̋�C�ɑ�M���Ă�������Ƃ́I�@���Ԃ��Â��݂Ă܂��H�@�ł��A������̐�ŋ�J�����̂́A�킽�������㐢�̒�����w�K�҂��悭�킩��܂��B������͂��n��ł��A�Ղ⏑���ȂNJw�ׂ钆�������͂���B����Ȏ������j�Ɏc���Ă������������Ƃɂ́A���ӂ��܂��B
�Q�l�@��C�w����W�x��5��8�t�̎ʐ^�@https://lab.ndl.go.jp/dl/book/819438?page=9 (������f�W�^�����C�u�����[)
�k�퐨���A��C�ɑ�M���Ă�����������A���肢�B��|�́u������̔�����������āA���x�ȓ��e���w�ׂ܂���B�Ղ̉��y�Ə����̓}�X�^�[���܂����̂ŁA����ł��������������B�������A�ƂĂ�����܂���B20�N�����w����Ȃ�Ė����ł��B�O�|���ŋA�����邱�Ƃ����������������v�Ƃ����������ɋ߂�����B
�y�������z�k�w���^�{���g�[
���Z�w���퐨�[�퐨��野q�V���a�ܔV�㗝�{�V���n���}����������ʐU�t���f�R���R��u�����V�㖢硗V�ŗъ������K���w�Տ������`䒎����s�s���������ߗƋ͈ȑ����s�������Ǐ��V�p��g�������V�M毑ғ��N�V������]屖����ِ������ƔV����獡�����w�V��嫕s�哹���L���V���_�V�\��w�镏�Ȉ��l�C��������ꍑ���ވ╗�^�����L���Y�����ԓ�ʎv�~�����Ŕ��t�V���V���s�C�����[��s��ތ[
�y�����������z�k�w���̖{���̎g�ɗ^�ӂ邪�ׂ̌[
���Z�̊w���A�퐨�A�[���B�퐨��野q�̖��͖������Đ܂̌�ɗa���B���Ƃ��Đ{�炭�V���n���͐�̌����}�A�����ʐU���ĉ��f���t�ɂ��ׂ��B�R��ǂ����A�R��͗����̐���u��A�����ŗтɗV�Ԃ�硂��炸�B�����͏K�ӏ������ˁA���˂ċՂƏ��Ƃ��w�ԁB�����͉`䒂Ƃ��Ď����͓s�Đs������B���̍��̋��ӏ��̈ߗƂ́A�͂��ɈȂĖ��𑱂��A�����ƓǏ��̗p�ɂ͑��炴��Ȃ�B��g�A�������̐M�����Ƃ��A毁A���N�̊���҂����B���A屖���قɓ]����݂̂ɔA���ɑ������Ƃ̈����Ȃ�B���A�w�ԏ��̎҂�����ɁA�哹�Ȃ炸��嫂��A����V�����_���������ނ�̔\�A�L��B�w��͕��łĈȂĎl�C�����A����͔����Ĉꍑ�����ށB�ނ̈╗�����тāA�^�����Č��͕L��B���Y�͐��ꗧ�Ă���A�Ԃ͒ʂ���B���̏Ŕ�������ĔV��V�ɑt����Ɨ~���邱�Ƃ��v�ӁB���A����ɔC�ւ��B��[���Ē�B�s��A�ތ[�B
�y��Ӂz�k���{���̎g�҂ɓn�����߂̎莆
���w���ł��鎄���Ƌk�퐨���\���グ�܂��B���͏x�˂̗_����Ȃ��g�ł���Ȃ���A�����g�̃G���[�g���w���̖��[�ɉ����Ă��������܂����B�{���Ȃ�V���n���̊w����u��̌��̋Εׂ��ŕ����ׂ��ł���A���h�Ȋ����̕��͂������������K�����ׂ��ł���܂��B�������Ȃ���A�����Ɠ��{�͍��y���݂��ɗ���A�����̔����̐�̓������������Ⴄ���߁A���͒������b�ł܂Â��Ă��܂��A�܂��A������̊w�Z�ɒʂ����Ƃ��ł��܂���B�����ŁA���K���Ȃ���A�����̋Ղ̒e�������⏑���ȂǁA��w�̃n���f���y�����������܂����B�����������邤���ɁA�w�����g���ʂ����܂����B�������{�������ߕ���H���́A���肬�萶���ł���Ă��ǂł��B�w��⏑�Б�ɂ͑S�R����܂���B�������ɁA���������̐M������ē����̗\��ǂ���20�N�̗��w�������撣�낤�Ƃ��Ă��A�ƂĂ������ł��B���́A������̂悤�ɉ��l�̂Ȃ��l�Ԃ�������܂���B���A����Ȏ��ł��A���{�l���w���������ł܂�Ȃ����ɕ���������A���ЂƂ肪�����̂ɂȂ邾���Ȃ�Ƃ������A���{���̒p�ɂ��Ȃ肩�˂܂���B���āA������������Ŋw�Ղ̉��y�̋Z�ʂ����ȕ]�����܂��ƁA���y�͎̑哹�ł͂Ȃ����̗̂̎�y�ł͂���܂��B���Ȃ���A�S�_�����������邭�炢���ɋՂ����t�ł���\�͂�g�ɂ��܂����B�̌ÓT�ɂ��A���ɂ����̏w��͋Ղ�e���Đ��E�̕��a�������炵�A�u�{����������������p����v�̌̎��ŗL���Ȍ���Ǝq��(�E�q�̒�q)���Ղ̉��y�ňꍑ�������ɓ������܂����B�����A�Ðl�̈╗�������ƂтA�Ղ̉��y��[���������A����߂܂����B��|������߂��҂͂���Őg�𗧂Ă邱�Ƃ��ł���ƌ��������ŁA�Ԍܑ�Ԃ�̑�ʂ̏��Ђ�ǔj���Ă��w�₪�听���Ȃ��l�����܂��B���̈�|�́A�Ղ̉��t�ł��B���̊�]�́A�����̏Ŕ��Ղ������ē��{�ɋA��A�݂��ǂ̂��������ɉ��t���邱�Ƃ�������������������A�Ǝv���܂��B����Ȃ��肢�ł܂��Ƃɋ��k�ł͂������܂����A�����A���̒��\���o�鎟��ł��B�ȏ�A�ނ�Ő\���グ�܂��B
�Q�l�@������́u�q���v�c�u�O�v�Ƃ��������������Ƃɒ��ӁB

�ޗǎ���̌����g�̓n�C�͖������ŁA�Ӑ^(688-763)�������ɋ�J�����B
���オ������ƁA�q�C�Z�p���i�����A���S�ɓn�C�ł���悤�ɂȂ����B
���q����ȍ~�́A�T�m�̉������������B���������̎嗬���u��y�T�v�u�O���T�v�ɂȂ������߁B
cf.�����O�u�T��R���̒�����v�A�w������̊x��121��(2022.9)p.17�yPDF�z
���a�̃e���r�A�j���u��x����v�̃Z���t�u���������v�u�������v�́A�v�̎���̑T�ⓚ�Ŏg��ꂽ�Â�������u������v�Ɓu���j�v�B
�T�@�́u�s�������v�ł���A�̂̒�����̌���̂ɂ��T�ⓚ�̉�b�𗝉�����K�v���������B
���{�̒����̊|�����Ȃǂł��悭��������T��́A�̂̒�����̌���̂������B��u�i�����v(��������)�B
- ���R(938-1016) �@���{↔�k�v�@cf.�����O�u���R(���傤�˂�)�̖}�l�����炱���o���邱���v
- �h��(1141-1215)�@���{↔��v(2��)
- �Y�����J(1197-1276)�@��v↔���{�@cf.�u���������v�̌ꌹ�́u�Y���v�Ƃ�����
- ����(1200-1253)�@���{↔��v
- ���k����(1213-1278)�@��v�����{
- ���w�c��(1226-1286)�@��v�����{�@cf.�u�}�����v(�܂������� mòzhíqù)
- ��C����(1334-1405)�@���{↔���@���̏���c��E�^����Ɗ����̉��V�������B
- ��M(1420-1506)�@���{↔��
- �B�����g(1592-1673)�@�������{�@cf.�C���Q����
- ���H�S�z(1639-1696)�@�������{
�Q�l�@���H�S�z�T�̋Օ��@singaku-fusizen.html#kimpu
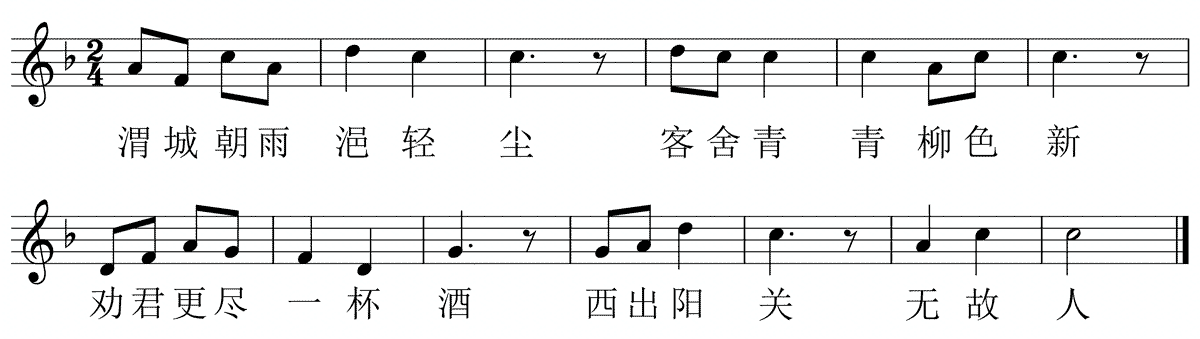
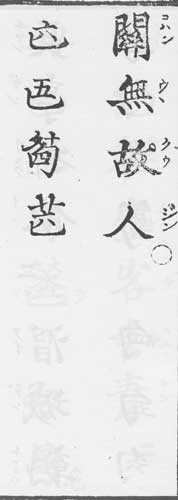 |
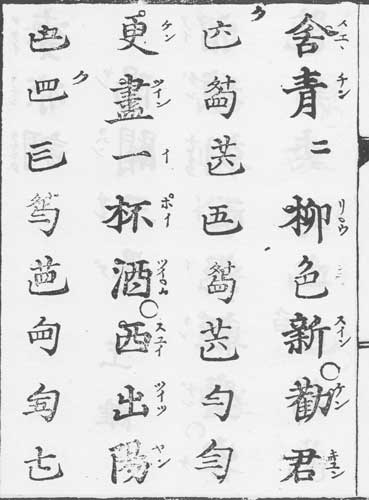 |
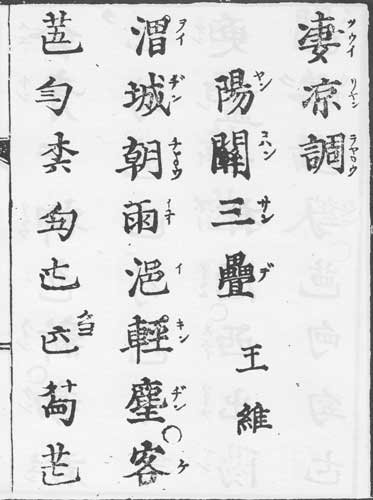 |
���y���R����A�L�b�G�g�����p������̗��ɂ́A�Ђ炪�ȂŁA�ȒP�Ȓ����ꂪ�J���j���O�y�[�p�[�I�ɏ����Ă������B
cf.�Օ��M�u��ʂɕ`���ꂽ��S�Ɗ��ҁv https://www.teikokushoin.co.jp/files/common/�L��/bookmarker/2022-2/11_msggbl_2022_10_p28-29.pdf
���{���璆��(���A��)�ւ̏�[�g�́u�����h�E�M�k�h�v�Ɓu���b�h�E��b�h�v��2���������B���q���G�Ƃ������{�l�́A�ߐ��̒����̗��j���ł́u���q�v�Ɓu����x(�A�P�`)�v��2�l�̐l���Ƃ��Č�F���ꂢ��B
cf.�����O�u���q���G�Ɍ��錴����`�Ƒ��Ύ�`�v�A�w������̊x��113��(2020.1)p.05�yPDF�z
�����鍽���̎���̒���ɂ����āA�I�����_��̐��Ƃł���u�I�����_�ʎ��v�ɑ��āA���b(������)�̐��Ƃ́u���ʎ��v�ƌĂꂽ�B�u�ʎ��^�ʎ��^�ʎ��v�͂ǂ���u�����v�����A���������ɂ��j���A���X�̈Ⴂ�ɒ��ӁB
�Q�l�r�f�I�@YouTube�u������w�T�� ��5��@������̕\���@ - ���c�c�s�@����w�O����w�������v
14��14�b�ڂ��]�ˊ��̒����ꋳ��ɂ��ĉ��
https://youtu.be/MjsNhvbETdQ?si=sqLtWfguOoH7O39l&t=854
�]�ˎ���ɂ́u�����v�u���b�v�u�[�����������B��⋳�{�Ƃ��āA������̔����u�����v�Ŋ����E���������ǂ�����A�̂����肷�邱�Ƃ��A�ꕔ�̓��{�l�̂������ŗ��s�����B
.cf.�����O�u�]�ˎ���̓�����U��Ԃ�v�A�w������̊x��111��(2019.4)p.05�yPDF�z
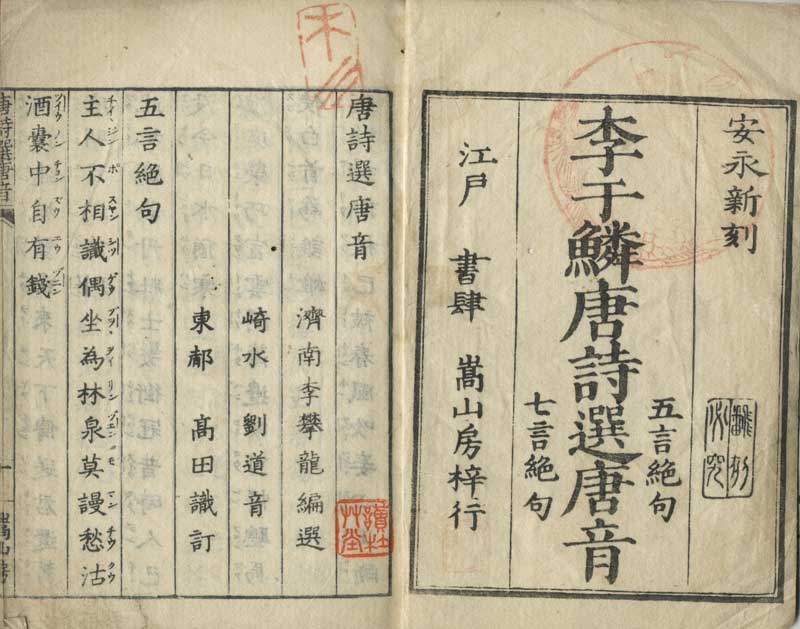 cf.�w�����I�����x(1777�N���A�]��)
cf.�w�����I�����x(1777�N���A�]��)�]�ˎ���ɂ́A�����P�ǂɂ�鎍��(�P�Nj�r)�����łȂ��A������r�E���������̓`��������A���ꂪ�]�ˌ���̖����y�u�[���̌Ăѐ��̈�ƂȂ����B
�]�˂��疾������͂��߂܂ŁA���������̏Љ�Ⓜ�b�w�K�ł́A�Ñ�́u�n���l�v��u�n���n�����v�Ə��������Ƃ��낪����l�C�e�B�u�⏀�l�C�e�B�u���A�]�ˎ���̓��ʎ��A��������ȍ~�̒ʖ�Ƃ��Ċ����B
��@��(������ 1728-1774 ���{�����莭=������)�͒���̉ؐl4�����������A�����̉Ƃő�X�`������Ă����u���y�v(�݂�)�𐢂ɍL�߂邽�ߋ��ɂ̂ڂ��Ċ����B
msg-kns-sfj.html#cjgj
��@����̒����l�ʖ�ł��������Ǒ��́A���{�ɋA�����ĉ͕���\�Y�𖼏��A�w���y�Ȕv�땈�x(1877)�����B
singaku-14-70s.html#1877gafu
�ȉ��Ahttps://www.chuken.gr.jp/association/organization.html�����p�B�{����2024�N2��21���B���p�J�n
���āC���{�ɂ����钆���ꋳ��̗��j�͌Â��C�Ⴆ�C�]�ˎ���ɂ͒����Ƃ̌��Ղ̂��߂ɒ���ɐ݂���ꂽ�u���ʎ��v�ɂ���Ē����ꂪ�w��C�܂�5�㏫�R�j�g�̎���ɂ͉�檗�@�Ƃ̊W�ō]�ˏ���ł�������w�K��Â��ꂽ���Ƃ�����܂����B���̌�C�����ȍ~�͓��ɖ��ԍu�K��𒆐S�ɒ����ꋳ�炪�W�J����C���C���ɓ���������͒�����u�[���������N������������܂����B���݂́C��w���ł����C�Ґ��͉p��Ɏ����ŁC���̌���y���ɗ��킵�Ă���܂��B���p�I���B �Q�l����@https://youtu.be/MjsNhvbETdQ?si=V79loKNsvhJmCWot&t=830�@�u������w�T�� ��5��@������̕\���@ - ���c�c�s�@����w�O����w�������v830�b�ڂ���ɑ�C��ƍ]�ˎ���̓��b�w�K
�������珺�a�O���܂ł́A�����l�Ɖ�b�����邽�߂ɁA���{�l�����p�I�Ȓ�������w�Ԃ��Ƃ��������B
�푈�̉e�����܂Ƃ����B�����̓����푈�⏺�a�̓����푈���A���{�l�̒�����w�K�ɉe����^�����B
���a�����܂ł̒����ꋳ�ނ͔������J�i�ŕ\�L�������̂����������B
cf.�X��P���u���a�����̎q�������̒����ꋳ�ނ̈�[ : �߂E���邽�E�V���v2020�@https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/records/16406
�J�i�ȊO�ɂ��A�����ꋳ�ނ̔����̏������́A�E�F�[�h�����[�}���A���ꎮ���[�}���A���������ȂǁA���܂��܂ł������B
1958�N(���a33�N)�@�����Łu����拼�����āv�������B�s���C��(拼���i�s���C���Apīnyīn)�̋��ނ����܂��B
1967�N(���a42�N)�@���{��NHK���e���r�Łw�������b�x�����J�n�B
1972�N(���a47�N)�@�������𐳏퉻�B
1981�N(���a56�N) �@���Łu������w�͔F�苦��v(�����̑O�g)���ݗ��B
1985�N(���a60�N) �@������̎������𓌋��Ɉړ]���u���{�����ꌟ�苦��v(����)���ݗ��B���⏇�ꎁ���������ɏA�C�B 2000�N(����12�N)�@��율�i���������̗������ɏA�C�B
2020�N(�ߘa02�N)�@���c�c�s���i���j�������̗������ɏA�C�B