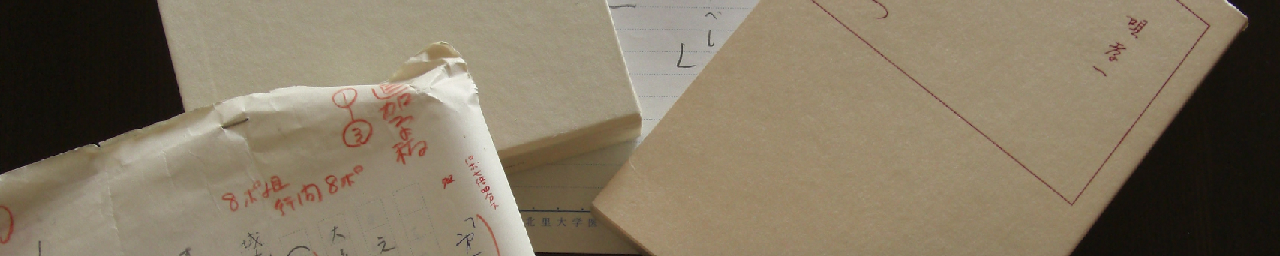~1960年>> 1970年>> 1980年>> 1990年>> 2000年以降>>
西先生文献リスト 1980年
1980年(昭和55年)
| 書名/表題 | 掲載誌/巻号 掲載紙/年月日 発行所等 |
発行年月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 『からだの科学 (なぜなぜ理科学習まんが)』 | 阿木二郎(著),集英社 | 1980 | 【監修】 |
| 保健・医療と福祉の供給体制 | 保健・医療社会学研究会(編)『保健・医療と福祉の統合をめざして』,p123-141,垣内出版 | 1980 | |
| 地域保健 | 西川滇八、小泉明(編)『公衆衛生学』,p213-232,朝倉書店 | 1980 | |
| 地域社会における保健と医療 | 社会保障講座編集委員会(編),『社会保障講座6 地域社会と福祉の展開』,p91-119,総合労働研究所 | 1980 | |
| シンポジウムを始めるにあたって(シンポジウム:先天異常への対応と問題点) | 第21回社会医学研究会総会演題抄録集,p2,社会医学研究会 | 〔1980〕 | 【司会】西三郎・木下安子 |
| 第一小分科会(分科会報告 第一分科会) | みんなのねがい,(126),p242~247,全国障害者問題研究会出版部 | 1980/1 | |
| <私の提言> 保健所のより積極的な取り組みを | 看護学雑誌,44(1), p55-56,医学書院 | 1980/01 | |
| 保健婦活動は衛生行政である | 月刊地域保健,11(2) ,p 78-81,東京法規出版 | 1980/02 | |
| 疫学における利用 | 医療情報システム開発センター(編)『日本の医療情報システム』,p95-97,社会保険出版社 | 1980/03 | |
| 報告のねらい-総合司会 (特集 医師-患者関係の新視点-イギリスにおける展開) | 法律時報,52(3)(630),p11-12,日本評論社 | 1980/03 | |
| 国と自治体の保健・医療政策と地域の保健医療の動向 | 医学評論,(64),(特集 80年代並びに保健医療状況とわれわれの対応),p29-38,新日本医師協会 | 1980/04 | |
| 今後の医師会に期待するもの | 社会保険旬報,(1320),p24-27,社会保険研究所 | 1980/04 | |
| 保険制度内の長期透析-社会的問題点 | 日本臨床,38(6)(457),(特集 長期透析とその問題点),p174(2460)-182(2468),日本臨床社 | 1980/06 | |
| “市民のための”から“市民とともに”の医療への創造-世界の先端を行くプライマリ・ケアの実践 | 『Primary Care Today-日本における課題と展望』,'80年保存版,p18-20,第3回日本プライマリ・ケア学会 | 1980/06 | |
| 医療経済実態調査(III)マクロ調査 | 社会保険旬報,(1325),p39-37,社会保険研究所 | 1980/06 | 【共同執筆者】日下公人、篠原三代平、市川洋、佐貫利雄 |
| 医療経済に関する理論的実証的研究(3) / 中央社会保険医療協議会 | 週刊社会保障,34(1077),p42-47,法研 | 1980/06 | 【共同執筆者】江見康一 |
| 医療経済に関する理論的実証的研究(4) / 中央社会保健医療協議会 | 週刊社会保障,34(1078),p42-47,法研 | 1980/06 | |
| 医療経済に関する理論的実証的研究(5) / 中央社会保健医療協議会 | 週刊社会保障,34(1079),p42-47,法研 | 1980/06 | 【共同執筆者】篠原三代平、市川洋 |
| 保険制度内の長期透析 | 日本臨床,38(6)(457),p174-182,日本臨床社 | 1980/06 | |
| 日野市の新しい地域医療運動によせて | 池上洋通(著)『燃えさかれ、いのちの火: 「未来型地域医療」をめざす日野市の難病運動 』,p3-9,自治体研究社 | 1980/07 | |
| 先天異常への対応と問題点 | 『第21回社会医学研究会総会演題抄録集』,p2-14,社会医学研究会 | 1980/07 | 西三郎、木下安子(司会) |
| ヘルスマンパワーについて | 高安久雄、他(編)『未来の医学』,p225-240,講談社 | 1980/8 | |
| 地域社会における保健と医療 | 社会保障講座編集委員会(編)『地域社会と福祉の展開』,総合労働研究所 | 1980/09 | |
| 老人保健厚生省案を診断する | 総合社会保障,18(10),p25-36,社会保険新報社 | 1980/10 | 【共同執筆者】松崎芳伸、野海勝視、首尾木一、小寺勇、 岡村文雄 |
| 老人保健制度の別建てに望む | 社会保険旬報,(1340),p4-8,社会保険研究所 | 1980/11 | |
| 難治である疾患をもつ人々の諸問題と看護の役割(成人看護分科会(秋田)シンポジウム) | 看護 : 日本看護協会機関誌,32(12),p49-79,日本看護協会出版会 | 1980/11 | 【共同執筆者】木下安子、新関敏子、藤原良子、足利量子、佐藤和子 |
1981年(昭和56年)
| 書名/表題 | 掲載誌/巻号 掲載紙/年月日 発行所等 |
発行年月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 国民の疾患構造と最近の変化 | 菅谷章(編)『現代の医療問題』,p85-98,有斐閣 | 1981 | |
| 保健活動と保健所 | 上掲書所収,p187-195 | 1981 | |
| <インタビュー> 医療におけるマンパワー政策について | 医療労働 : 医療・介護・福祉労働者のための月刊誌,(232),p17-25,日本ホームヘルパー協会 | 1981/01 | |
| シンポジウムのねらいとまとめ (第21回社会医学研究会総会<特集>)-(先天異常への対応と問題点(シンポジウム)) | 公衆衛生,45(2),p116-117,医学書院 | 1981/02 | 【共同執筆者】木下 安子 |
| <資料> 特定疾病患者に対する保健指導の手引き | 月刊地域保健,12(2),p60-80,東京法規出版 | 1981/02 | 【共同執筆者】松野かほる、島内節、木下安子、川村佐和子 |
| 国民医療費 | 健康保険組合連合会(編),『社会保障年鑑1981年版』,p47-51,東洋経済新報社 | 1981/03 | |
| 保健・医療チームの連携による効果的な活動 | 月刊地域保健,12(3),p29-70,東京法規出版 | 1981/03 | 【共同執筆者】吉田すず子、沢田俊一郎、 小川清、池上洋通、和地よし子 |
| 衛生行政研究の視点から | 上掲誌所収,p57-70 | 1981/3 | |
| 医療制度 | 金森久雄、他(編),『日本経済事典』,p1034-1039,日本経済新聞社 | 1981/4 | |
| 保健所における地域保健医療政策の展開 | 益子義教、野村拓、野村拓(編),『地域医療Ⅲ』,p88-95,新日本医学出版社 | 1981/05 | |
| 10年後のわが国の医療と保険-各界の第一線代表にきく | 社会保険旬報,(1360),p6-21,社会保険研究所 | 1981/05 | |
| 計量分析に耐える乳幼児健診 (乳幼児健診--その現代的課題を探る<特集>) | 公衆衛生,45(6),p436-440,医学書院 | 1981/06 | |
| 保険制度内の維持透析 | 日本臨床,39(474)(特別号),p531-548,日本臨床社 | 1981/08 | |
| プライマリ・ヘルスケアに関する看護教育方法論-難病を中心とする授業の展開(東京都神経科学総合研究所セミナー) | 看護教育,22(8)(251),p473~489,医学書院 | 1981/08 | 【共同執筆者】 渋谷優子、石川左門、川村佐和子、木下安子 |
| 社会保険医学会研修会で病院のあり方を中心に論議 | 社会保険旬報,(1369),p32-37,社会保険研究所 | 1981/09 | 【共同執筆者】大谷藤郎、伊賀六一、西本昭二、浜名正太郎、佐分利輝彦、太田裕祥、田中明夫、諸橋芳夫、紀伊国献三、倉田正一、石本忠義、牧野永城、 仲村英一、長谷川恒雄、古市圭治 |
| ひとりごと | レクリエーション,(251),p6-7,日本レクリエーション協会 | 1981/09 | 【共同執筆者】大嶋仁 |
| 高齢者の健康と医療制度-治療から予防とケアへ | 松原治郎(編)『日本型高齢化社会 : ソフト・ランディングへの提言 (有斐閣選書)』,有斐閣 | 1981/10 | |
| <シンポジウム> 人間ドック・自動化健診と集団検診 | 日本病院会雑誌,28(10),p27-35,日本病院会 | 1981/10 | 【共同執筆者】樫田良精、北川定謙、川村昇、藤間弘行、岩塚徹 |
| 新しいまちづくりのエネルギーが | 新しい地域医療をもとめて 日野市難病レポート'81(4),p66,日野市医師会 | 1981/11 | |
| 医療施設と医療従事者の現状に関する社会経済的考察 | 総合研究開発機構医療経済懇談会 | 1981/12 | 【研究委員会委員】常松己一(主査)、青柳精一、加藤善弘、黒木延、盛宮喜 |
1982年(昭和57年)
| 書名/表題 | 掲載誌/巻号 掲載紙/年月日 発行所等 |
発行年月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 公衆衛生と社会福祉 | 社会保障運動史編集委員会(編)『社会保障運動全史』,p350-354,労働旬報社 | td>1982||
| 三鷹市における神経難病検診と地域ケア | 日本プライマリ・ケア学会誌,4(4),p351-353,日本プライマリ・ケア学会 | 1982 | |
| プライマリ・ケアに関する医学教育改革の鍵穴 | 医療研究レポート,(2),p1-13,日本プライマリ・ケア学会 | 1982 | |
| 専門医、開業医はきずなを強め患者、市民との対話を深めよ | 日経メディカル,(134),p146-151,日経メディカル | 1982 | |
| 医師とともにまちづくりの運動を | 三多摩の保健と医療,(5),p3-21,三多摩保健医療問題研究会 | 1982 | |
| 筋ジストロフィー症児の援助の緊急性について | 第4回難病看護研究会総会報告,p43-47,難病看護研究会 | 〔1982〕 | 【共同執筆者】島内節、川村佐和子、木下安子、野村陽子、牛込三和子、石川左門、関谷栄子 |
| 二つの顔をもつ知事-結核行政における行政権と裁量 | 三柏園事件記録編纂委員会(編)『碧海のサナトリウムでなにが 三柏園事件物語』,p220-231,労働旬報社 | 1982/01 | |
| 都市における地域医療の展開 | 社会保険旬報,(1382),p4-9,社会保険研究所 | 1982/01 | |
| <座談会> 「人工腎臓」医療と技術と社会と・・・ | 日経メディカル,11(1),p122-135,日経マグロウヒル社 | 1982/01 | 【出席者】阿岸鉄三、渥美和彦、岩喬、平沢由平 |
| 国民医療費 | 健康保険組合連合会(編)『社会保障年鑑1982年版』,p50-58,東洋経済新報社 | 1982/03 | |
| National Health Development Plan in Japan and its Problems | 公衆衛生院研究報告,31(1),p45-52,国立公衆衛生院 | 1982/03 | |
| 『三鷹市における心身障害児の早期発見早期療育に関する研究委員会報告』 | 三鷹市 | 1982/03 | 委員長:西三郎 委員:木村和郎、関谷行子、伊藤史子、保科弘毅、伊藤久夫 |
| 武見日医会長の退陣と今後の医療・保険-各界の第一線代表33氏にきく | 社会保険旬報,(1394),p6-22,社会保険研究所 | 1982/05 | |
| 『衛生法規・社会福祉(現代看護学基礎講座 9)』 | 真興交易医書出版部 | 1982/06 | 本田良行, 石川稔生(編) |
| 患者と医師に発送のズレ-プライマリケアの条件3“癒し”への参与 | Modern medicine of Japan,11(6),p63-65,朝日新聞社 | 1982/06 | |
| まだ十分でない連携プレー-プライマリケアの条件4“癒し”への参与 | 上掲誌所収,p66-68 | 1982/06 | |
| 地域ケアの体制づくりと患者団体の担った役割 | 日本プライマリ・ケア学会誌,4(臨時増刊号)(第5回日本プライマリ・ケア学会抄録集),p68,日本プライマリ・ケア学会 | 1982/06 | 【共同研究者】石川左門、木下安子、川村佐和子、小松真 |
| <講演> 医療行政の現状と問題点 | 医療と行政,(1),p7-23,医療行政研究会 | 1982/06 | 第2回医療システム勉強会にて第1回講演 |
| <講演> 医師患者関係の新しい視点 | 医療と行政,(1),p24-31,医療行政研究会 | 1982/7 | 第3回医療システム勉強会にて第2回講演 |
| 実践をふまえた地域医療の将来 | 高崎医学,(32),p9-14,高崎市医師会 | 1982/07 | |
| 筋ジストロフィー症児の援助の緊急性について | 第4回難病看護研究会総会報告,p43-47,難病看護研究会 | 1982/08 | 【共同研究者】島内節、川村佐和子、木下安子、野村陽子、牛込三和子、石川左門、関谷栄子 東京都障害者福祉会館 昭和57年8月21日 演題 |
| 「医療サ-ビスの効率化」についての考察-昭和57年度年次経済報告を読んで | 季刊社会保障研究,18(3),p380-384,国立社会保障・人口問題研究所 | 1982/12 |
1983年(昭和58年)
| 書名/表題 | 掲載誌/巻号 掲載紙/年月日 発行所等 |
発行年月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| <座談会> 一般教育の問題点とその解決策を探る | 医学教育,14(4),p261-270,日本医学教育学会 | 1983 | 【出席者】田中勧、中野康平、真島英信、高久史麿、田口茂敏、 |
| 『からだのしくみ からだと健康(こども学習まんが)』 | 北本善一(著),集英社 | 1983 | 西三郎(監修) |
| 保健所における電子計算機の導入 | 医療情報学,13(2),p36-37,日本医療情報学会 | 1983 | |
| 衛生行政の転機としての老人保健法 | 日本公衆衛生雑誌,30(11),p81,日本公衆衛生学会 | 1983 | |
| 高齢化社会における医療需要の増大と供給の対応 | 薬局と調剤,(21),p7-10,薬局新聞社 | 1983 | |
| 筋ジストロフィー症児の援助の緊急性について-難病看護研究会の意義と第4回活動報告(第2群チームケアの展開) | 健康会議,35(3)(408),p43-47,医療図書出版社 | 1983/03 | 【共同執筆者】島内節、川村佐和子、木下安子、野村陽子、牛込三和子、石川左門、関谷栄子 |
| 地域医療と供給システム 医療供給システムのあり方について(3) | 健康保険,37(3),p18-27,健康保険組合連合会 | 1983/03 | |
| 健康教室のすすめ方 | 健康・体力づくり事業財団(編)『健康教育の展開: 老人保健を中心に』,p57-123,財団法人健康・体力づくり事業財団 | 1983/03 | |
| 医療経済の立場から 柱ⅢS-3 現行医療制度諸問題と将来 | 第21回日本医学会総会会誌,(3),p2753-2755,日本医学会 | 1983/04 | |
| 地域で医療文化を明らかに | 大阪保険医雑誌,11(4),p6,大阪府保険医協会 | 1983/04 | |
| 第21回日本医学会シンポジウムの要旨-現行医療制度の諸問題と将来 | 週刊国保実務,(1317),p767-773,社会保険実務研究所 | 1983/05 | 【共同執筆者】小池昇、三浦大典、内藤景岳、朝倉新太郎 |
| 医療保険 | ファルマシア,19(7),p679-686,公益社団法人日本薬学会 | 1983/07 | |
| 老人保健法と地域保健 | 全国社会福祉協議会(編),『老人福祉年報1983』,p84-90,全国社会福祉協議会 | 1983/08 | |
| 福祉政策のゆくえと厚生省 (官庁と官僚)-(官庁の政策と活動--官庁のかかえる重要課題) | 法学セミナ-増刊 総合特集シリーズ,(23),p64-72,日本評論社 | 1983/08 | |
| 医療の発展と変貌 | 唄孝一(編著)『医療と法と倫理』,p2-56,岩波書店 | 1983/09 | |
| <コメント>生と死 | 上掲書所収,p511-519 | 1983/09 | |
| 看護婦の継続教育への公衆衛生からの期待 | 看護教育,24(9)(278),p520-521,医学書院 | 1983/09 | |
| 老人医療の包括システム化 (包括的老人医療<特集>)-(老人の社会保障) | 日本臨床,41(10),p2341-2345,日本臨床社 | 1983/10 | |
| 在宅ケアにおける法的諸問題 | 月刊地域保健,14(10),p57-65 ,東京法規出版 | 1983/11 | |
| 国民の望む検診と予防活動 | 月刊保団連,(190),p30-40,全国保険医団体連合会 | 1983/11 | |
| 地域保健におけるコンピュータ利用の現状と期待 | 公衆衛生,47(12), p819-833、医学書院 | 1983/12 |
1984年(昭和59年)
| 書名/表題 | 掲載誌/巻号 掲載紙/年月日 発行所等 |
発行年月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| わが国における医師対策の問題点と解決の方向 | 全国自治体病院協議会(編)『へき地医療の現状と対策(第四編)』,p23-25,社団法人全国自治体病院協議会 | 1984 | |
| 脳死の議論に「ヒト」と「人」との区分を | 人間の医学,20(3),p13-15,実地医家のための会 | 1984 | |
| <めだかの目> 2000年までにすべての人々に健康を-世界保健機関(WHO) | めだか通信,(1),p2-3,めだか社 | 1984/01 | |
| 厚生省の「医療保険改革案」をどうみるか-各界のオピニオン・リーダーにきく | 社会保険旬報,(1453), p6-29,社会保険研究所 | 1984/01 | |
| 公衆衛生の研究・教育・実践 | 公衆衛生,48(1),(特集 公衆衛生の研究・教育・実践),p4-8,医学書院 | 1984/01 | |
| 施設医療と在宅医療 | からだの科学,(115),p9-14,日本評論社 | 1984/01 | |
| <時評> 老人保健法による地域の老人保健の現状と問題点 | 月刊ゆたかなくらし,(25),p86-89,本の泉社 | 1984/03 | |
| 入浴福祉の研究 | 那須宗一先生古希祝賀記念出版委員会(編)『赤門 白門 不老門』,p251-254,非売品 | 1984/03 | |
| 医療関係制度をめぐる現状と諸問題 (医療・福祉の現状と論点<特集>) -- (第三回日本社会保障法学会報告) | 賃金と社会保障,(887),(特集 医療・福祉の現状と論点),p17-21,労働旬報社 | 1984/04 | 第三回日本社会保障法学会報告 |
| 今後の日医に注文する | 社会保険旬報,(1464),p14-19,社会保険研究所 | 1984/04 | |
| 良いホームドクターを地域で育てるために | 医療経営情報,1(1),p16-23,ミクス | 1984/04 | |
| <めだかの目> 今の国民生活をみて「消費ルネサンス」といえるのか | めだか通信,(3),P2-3,めだか社 | 1984/05 | |
| <シンポジウム> 看護婦の継続教育への公衆衛生よりの期待 | 日本看護研究学会雑誌,7(1/2),p55,日本看護研究学会 | 1984/05 | |
| 都市近郊型のプライマリ・ケア | クリニカ,11(5),p24(332)-27(335),トプコ・出版部 | 1984/05 | |
| 医療の危機からの開放を | 新しい地域医療をもとめて 日野市難病レポート'84,(6),p16-20,日野市医師会 | 1984/06 | |
| 医療と保健の将来-老人健診とフォローについてのあり方 | 週刊社会保障,38(1284),p14-17,社会保険法規研究会 | 1984/06 | |
| <めだかの目> 人間が主体的に動き働ける社会を | めだか通信,(4),P2-3,めだか社 | 1984/07 | |
| <書評> 『朝倉新太郎著作集』 | 新しい医師,(1020),p3,新日本医師協会 | 1984/8 | |
| 高齢化社会における地域住民に対する健康教育のすすめ方について | ほすぴたる,(319),p1-9,福岡県病院協会 | 1984/08 | |
| Phase3 : 最新医療経営,8月(1),p11,日本医療企画 | 1984/08 | ||
| 予防接種判決と衛生行政 (予防接種判決<特集>) | ジュリスト,(820), p40-44,有斐閣 | 1984/09 | |
| 公衆衛生学初代教授予定であられた曽田長宗先生のご逝去を悼む | 千葉大学医学部公衆衛生学教室同門会報,(3),p2-3, | 1984/09 | |
| 日本の医療制度 | 加藤一郎、森島昭夫(編)『医療と人権 : 医師と患者のよりよい関係を求めて』,p15-39,有斐閣 | 1984/09 | |
| <めだかの目> 高齢化社会の裏路地を覗いてみませんか | めだか通信,(5),P2-3,めだか社 | 1984/09 | |
| 医療施設の経営を論ずる前に | Phase3 : 最新医療経営,9月(2),p7,日本医療企画 | 1984/09 | |
| 健保改悪案の問題点と今後の運動の進め方 | 三多摩の保健と医療,(9),p4-13,三多摩保健医療問題研究会 | 1984/9 | |
| 地域保健医療活動の計画立案(策定)とその展開 | 青山英康(編)『明日の医療②地域医療』,p131-152,中央法規出版 | 1984/10 | |
| 医療サービス供給体制の整備 | 自治研修,(294),p11-19,第一法規出版 | 1984/10 | |
| <潮流> 医療施設の特長とその経営 | Phase3 : 最新医療経営,10月(3),p7,日本医療企画 | 1984/10 | |
| 医療費予測モデル-国民医療費研究グループ | 厚生の指標,32(12),p9-24,厚生労働統計協会 | 1984/10 | |
| <めだかの目> 医療についての的確な情報提供を | めだか通信,(6),P2-3,めだか社 | 1984/11 | |
| 医療保障改革の方向 | 大熊一郎、地主重美(編)『福祉社会への選択 : 江見康一教授退官記念論文集』,p66-89,勁草書房 | 1984/11 | |
| <潮流> 病院の目的の再確認を | Phase3 : 最新医療経営,11月(4),p5,日本医療企画 | 1984/11 | |
| 三鷹市医師会の発展の基本は | カレントテラピー,2(12),p20,カレントテラピー | 1984/11 | |
| 医療制度の欠陥 | 江見康一(編)『明日の医療④医療経済』,p87-110,中央法規出版 | 1984/12 | |
| 医療供給の周辺体制の整備 | 上掲書所収,p220-244 | 1984/12 | |
| これからの老人処遇をめぐって | 大森医師会(編)『続・健やかに老いる』,p174-194,人間と歴史社 | 1984/12 | |
| <潮流> 在宅患者にも目を向けて | Phase3 : 最新医療経営,12月(5),p5,日本医療企画 | 1984/12 |
1985年(昭和60年)
| 書名/表題 | 掲載誌/巻号 掲載紙/年月日 発行所等 |
発行年月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 病歴データの標準化とプライバシー保護 | 医療情報学,5(1),p75-80,日本医療情報学会 | 1985 | |
| 大都市の医療体制 | ジュリスト増刊総合特集,(40),p165-169,有斐閣 | 1985 | |
| 地域保健計画と活動手順 | 湯沢布矢子(編)『保健婦のための保健活動の進め方』,p162-172,新企画出版社 | 1985/01 | |
| マンパワー | 上掲書所収,p123-133 | 1985/01 | |
| 保険制度内の維持透析 | 日本臨床,43(特別)(522),p781-801,日本臨床社 | 1985/01 | |
| 医療情報のシステム化とその展開 | 月刊薬事,27(1),p57-62,じほう | 1985/01 | |
| 阿部正和(編)『明日の医療⑥医学教育』,p349-376,中央法規出版社 | 1985/02 | 【出席者】藤咲進、大谷藤郎、佐野正人、西三郎(司会) | |
| ニューメディア時代の公衆衛生 | 第12回山形県公衆衛生学会特別講演 山形,山形県公衆衛生学会 | 1985/02 | |
| 衛生の行政の管理と運営 | 橋本正己、他(編)『衛生行政大要改訂第12版』,p45-61,日本公衆衛生協会 | 1985/03 | |
| INSとこれからの医療 | 社会保険旬報,(1496), p6-11,社会保険研究所 | 1985/03 | |
| 本田良行, 石川稔生(編) 『衛生法規・社会福祉(現代看護学基礎講座 9)』 | 真興交易医書出版部 | 1985/03 | |
| 診察室の内と外 | 医療経営情報,2(2)(7),p5-8,ミクス | 1985/04 | |
| 保健所の現状と課題 (市民の健康と保健<特集>) | 都市問題研究,37(4)(412),p59-72,都市問題研究会 | 1985/04 | |
| <めだかの目> 診療費は誰が払うのか | めだか通信,(8),P2-3,めだか社 | 1985/04 | |
| <めだかの目> 障害者は生きることに感謝しなければならないのか | めだか通信,(9),P2-3,めだか社 | 1985/07 | |
| 開業医制度…この独自なるもの | 医療,1(4)(4),p6-9,メヂカルフレンド社 | 1985/07 | |
| 日米産業比較 非製造業-医療 大幅な設備投資必要とするわが国の医療 | 日本経済研究センター会報,7月15日(492),p45-51,日本経済研究センター | 1985/07 | |
| 在宅難病患者の保健指導と保健婦への期待 | 乾死乃生、木下安子(編)『難病と保健活動』,p135-145,医学書院 | 1985/08 | |
| 病院経営危機の事例に思う | 病院,44(8),p658-664,医学書院 | 1985/08 | 【共同執筆者】 黒岩卓夫、石原信吾 |
| 老後の医療保障と老人保健活動 | 『第14回日本老年学会特別講演 東京』,日本老年学会 | 1985/09 | |
| 医学校における日米の比較 | 『第44回日本公衆衛生学会 富山』,日本公衆衛生学会 | 1985/10 | |
| <めだかの目> 治療を受けているのになぜ子どもの命を絶ったのか | めだか通信,(10),P2-3,めだか社 | 1985/10 | |
| 社会指標における健康指標とその内容 | 『日本健康科学学会第1回学術大会 東京』,日本健康科学学会 | 1985/11 | |
| 「健康権」の提唱とその意義 | 『日本健康科学学会第1回学術大会 東京』,日本健康科学学会 | 1985/11 | |
| 高齢化社会における新しい医療福祉の課題 | 『第8回日本計画行政学会 仙台』,日本計画行政学会 | 1985/11 | |
| 医療と福祉の政策の合理化と体系化 | 社会保障研究所(編)『医療システム論 (社会保障研究所研究叢書 ; 16) 』,p293-305,東京大学出版会 | 1985/11 | |
| 「腎炎・ネフロ-ゼ症候群およびネフロ-ゼ」死亡ならびに人工透析患者の都道府県較差に関する検討 | 日本公衆衛生雑誌,32(11),p703-705,日本公衆衛生学会 | 1985/11 | 【共同執筆者】本橋 豊、前田 博 |
| 医療社会のコンピュータ化とプライバシー侵害の可能性 | 看護展望,10(12)(111),p13-19,メヂカルフレンド社 | 1985/11 | |
| 「東京宣言」と医療制度の基盤としての地域社会-特集 「東京宣言」をふり返るPART1 | 保健の科学,27(11),p732-735,杏林書院 | 1985/11 |
1986年(昭和61年)
| 書名/表題 | 掲載誌/巻号 掲載紙/年月日 発行所等 |
発行年月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日本医師会のあり方を考える"材料"として | ばんぶう,(55),p48-52,日本医療企画 | 1986/01 | |
| 健康概念に係わる理論的研究 昭和60年度科学研究費補助金 総合研究(A)研究成果報告書 | 東京大学 | 1986/03 | 昭和60年度科学研究費補助金総合研究(A)研究成果報告書 研究分担者西三郎 |
| 在宅ケアにおける行政及び専門職団体の役割についての考察 | 厚生省特定疾患 難病の治療・看護調査研究班 昭和60年度研究報告,p141-157,厚生省特定疾患「難病の治療・看護」調査研究班 | 1986/03 | |
| これからの日医に期待するもの | 社会保険旬報,(1537),p13-16,社会保険研究所 | 1986/04 | |
| <座談会> 地域が動くような活動を | 保健婦雑誌,42(4),p16-32,医学書院 | 1986/04 | 【出席者】 柴沼和加子、長弘千恵、星野ゆう子、伊藤悦子、中村裕美子 |
| <めだかの目> まじめな保健婦が何故こわい | めだか通信,(11),P2-3,めだか社 | 1986/04 | |
| (医療と医療産業のゆくえ<特集>)公衆衛生からみた日本の未来医療 | 未来医学,(2),p36-41,ミクス | 1986/06 | |
| 法令解説[昭和60年1月~12月] | 『年報医事法学(1)』,p233(35)-235(33),日本評論社 | 1986/06 | |
| <書評> 古瀬徹(著)『創造的な長寿社会への道』 | 月刊地域保健,17(6),p102-103,東京法規出版 | 1986/6 | |
| 医師・患者関係の残された課題 | 日本医事法学会(編)『医事法学叢書1』,p305-315,日本評論社 | 1986/07 | |
| <めだかの目> プライバシー保護を理由に障害者の療育の発展を阻害させないで | めだか通信,(12),P2-3,めだか社 | 1986/07 | |
| <書評> 中村安秀(著)『ハンディキャップをもつ赤ちゃん』 | 月刊地域保健,17(8),p108,東京法規出版 | 1986/8 | |
| 誰のための「家庭医」論議か | 社会保険旬報,(1549),p6-12,社会保険旬報 | 1986/8 | |
| 医療の制度と保障 | 日本医事法学会(編)『医事法学叢書4』,p3-8,日本評論社 | 1986/9 | |
| 「健康権」を提唱する | 上掲誌所収,p9-17 | 1986/09 | |
| 在宅ケアにおける専門職の責任-施設での医療と在宅ケアの違い | 島内節、川村佐和子(編)『在宅ケア その基盤づくりと発展への方法論』,p233-241,文光堂 | 1986/09 | 【共同執筆者】星旦二 |
| 国と自治体の責任-医療をめぐる行政と財政 | ジュリスト増刊総合特集,(44),,(特集 日本の医療-これから),p84-91,有斐閣 | 1986/09 | |
| 与える福祉のまちづくりから,つくり出す福祉のまちづくりを-「東京都における総合的な福祉のまちづくりの推進」についての意見(提言) | 月刊福祉,69(14),p48-56,全国社会福祉協議会 | 1986/09 | |
| 開業医制度・・・この独自なるもの | メヂカルフレンド社編集部(編)『日本の医療の行く手を読む』,p84-89,メヂカルフレンド社 | 1986/10 | 【共同執筆者】 編集部、饗庭忠男、井上幸子、岡本祐三、加藤万利子、川上武、川島みどり、木下安子、草刈淳子、穀山聡子、小島ユキエ、佐藤智、島内節、須川豊、砂原茂一、瀬尾攝、二木立、宝珠山ウメ、前沢政次、水野肇、村上国男、村松静子、山田里津 |
| 高度化する医療技術のコスト・ベネフィット | 技術と経済,(10)(236),p24-29,科学技術と経済の会 | 1986/10 | |
| <アンケート> 看護婦の業務範囲について | 看護展望,11(12)(124),p4-11,メヂカルフレンド社 | 1986/11 | |
| 三鷹市保健審議会 | 川久保亮、他(編)『社団法人三鷹市医師会二十年誌』,p154-155,三鷹市医師会 | 1986/12 |
1987年(昭和62年)
| 書名/表題 | 掲載誌/巻号 掲載紙/年月日 発行所等 |
発行年月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 長寿社会に向けて厚生省の責任が見えない厚生白書 | 新医協,1,新日本医学出版社 | 1987 | |
| 六二年度の老人の保健・福祉をめぐる行政の動向 | ホームヘルパー,(180),p3-9,日本ホームヘルパー協会 | 1987/01 | |
| <めだかの目> 患者運動の転換-「みんなでつくろう地域の医療」へ | めだか通信,(13),P2-3,めだか社 | 1987/02 | 1986年10月+1987年2月合併号 |
| 地方自治体における保健計画策定とその体系についての一考察 | 人文学報 社会福祉学,3(194),p41-56,東京都立大学人文学部 | 1987/03 | |
| 衛生行政の管理と運営 | 橋本正己、他(編)『衛生行政大要改訂第13版』,p44-61,日本公衆衛生協会 | 1987/03 | |
| 在宅における診療、看護、介護に関する医事法学的考察 | 厚生省特定疾患 難病の治療・看護調査研究班 昭和61年度研究報告,p91-95,厚生省特定疾患「難病のケア・システム」調査研究班 | 1987/03 | 【共同研究者】川村佐和子、宇津木伸、平林勝政、藤巻和弘 |
| 三鷹市医師会の在宅ケアの確立に果たした役割 | 三鷹市医師会(編)『難病検診の意義とその役割: みんなが幸せで健康なまちをめざして』,p32-39,有斐閣 | 1987/04 | |
| 難病の地域ケアシステムの確立とその事例 | 上掲書所収,p207-219 | 1987/04 | |
| 医薬品の基礎研究にもっと国が関与すべき | カプセル,(21),p12,日本製薬工業協会 | 1987/04 | |
| 社会の営みとしての医療資源の確保 | 上掲誌所収,,p14-19 | 1987/04 | |
| 潮流——合理的な病院経営にも“ゆとりと遊び”を | Phase3 : 最新医療経営,5月,p5,日本医療企画 | 1987/05 | |
| 潮流——看護を家族にまかせるのは看護の専門性の放棄では | Phase3 : 最新医療経営,6月,p5,日本医療企画 | 1987/06 | |
| 法令解説[昭和61年1月~12月] | 『年報医事法学(2)』,p183(49)-182(50),日本評論社 | 1987/06 | |
| 地域保健計画と活動手順 | 湯沢布矢子(編)『保健婦のための保健活動の進め方 改訂版』,p153-190,新企画出版社 | 1987/07 | |
| マンパワー | 上掲書所収,p142-152 | 1987/07 | |
| 血液透析実態調査とその意義 | 社会医学研究,1987特別号,p50,医療図書出版社 | 1987/07 | |
| 三鷹市難病検診の意義と役割 | 上掲誌所収,p58 | 1987/07 | |
| 国民健康づくり計画モデル事業とその評価 | 上掲誌所収,p62, | 1987/07 | |
| 看護の専門性確立を期待する | 社会保険旬報,(1586),p15-17,社会保険研究所 | 1987/8 | |
| 潮流——医療計画策定に求められる政治感覚 | Phase3 : 最新医療経営,8月,p5,日本医療企画 | 1987/08 | |
| 長寿社会に向けて医療と福祉の供給とその予測 | 日本計画行政学会第10回記念全国大会研究報告要旨—国際社会に於ける国家と企業,p27-28,日本計画行政学会 | 1987/9 | |
| 公衆衛生と住宅 (昭和61年度プロジェクト報告研究課題4「社会保障と住宅政策との関連に関する理論的・実証的研究」) | 季刊社会保障研究,23(2),p220-226,国立社会保障・人口問題研究所 | 1987/9 | |
| コメント(第21回社会保障研究所シンポジウム : テーマ「転換期の社会保障」) | 上掲書所収,p171-172 | 1987/9 | |
| わが国における在宅ケア制度-その現状と将来展望 | 日本プライマリ・ケア学会誌,10(3),p173-182,日本プライマリ・ケア学会 | 1987/09 | 【共同執筆者】大貫稔、鈴木荘一、丸地信弘、竹内雅夫、前澤政次、木下安子、小松真、川村佐和子 |
| 潮流——国民医療の“主役”は誰か | Phase3 : 最新医療経営,9月,p5,日本医療企画 | 1987/9 | |
| 有識者として看護職への期待と批判-社会へ“看護”を示すには | 看護 : 日本看護協会機関誌,39(12),p43-49,日本看護協会出版会 | 1987/11 | |
| 在宅人工呼吸療法の現況と問題点(第62回日本医科器械学会シンポジウムⅢ) | 医科器械学,57(12),p549-560,日本医療機器学会 | 1987/12 | 【共同執筆者】渡辺敏、川村佐和子、宍戸輝男、季羽倭文子、斉藤豊和 |
1988年(昭和63年)
| 書名/表題 | 掲載誌/巻号 掲載紙/年月日 発行所等 |
発行年月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| <寄稿> 保健計画策定に向けて-保健活動の基本から発想の転換を | 月刊地域保健,19(1),p47-52,東京法規出版 | 1988/01 | |
| 看護料の基本的考え方とその問題-看護の量と質の評価 | 看護展望,13(1)(139),p17-22,メヂカルフレンド社 | 1988/01 | |
| <めだかの目> いま何故「ボランティア」が論じられるのでしょう | めだか通信,(14),P2-3,めだか社 | 1988/01 | |
| 保健医療体制の推移と歯科医療の未来 | 歯界展望,臨時増刊71(3),p704-707,医歯薬出版 | 1988/02 | |
| 保健と医療と福祉の連携に向けて医療における固有の課題とその展望 | 人文学報. 社会福祉学,4(202),p47-65,首都大学東京 | 1988/03 | |
| 保健医療関連職種とその資格条件 | 田中恒男、他(編)『公衆衛生看護ノートⅡ改訂第3版』,p395-407,日本看護協会出版 | 1988/03 | |
| 衛生行政の財政 | 上掲書所収,p447-479 | 1988/03 | |
| 衛生統計と健康指標 | 上掲書所収,p519-545 | 1988/03 | |
| 保健・医療・福祉におけるソーシャル・サポート・ネットワーク-その前提と課題 | 社会福祉研究 (42),p25-30,鉄道弘済会社会福祉部 | 1988/04 | |
| 継続医療を必要とする患者の退院の基準に関する医事法学的考察 | 日本プライマリ・ケア学会誌,臨時増刊(11),第11回日本プライマリ・ケア学会抄録集,p80,日本プライマリ・ケア学会 | 1988/05 | 【共同執筆者】川村佐和子 |
| 三鷹市における在宅ケア環境に関する課題 | 上掲誌所収,p92 | 1988/05 | 【共同執筆者】川村佐和子、中村努、村田欣造、佐藤政之助、浅野英一郎、高木克芳、熊本亮、植木美正 |
| 三鷹市における在宅ケアの現状と今後の課題 | 上掲誌所収,p92 | 1988/05 | 【共同執筆者】高木克芳、中村努、村田欣造、佐藤政之助、川村佐和子 |
| 地域医療問題検討会第9回「今後の地域医療のなかでの開業医の役割」 | 那覇市医師會報,16(1),('88初夏号) | 1988/05 | |
| はじめに-問題の所在(シンポジウム「継続医療を必要とする老人をめぐる諸問題」) | 『年報医事法学(3)』,p50,日本評論社 | 1988/06 | 【共同執筆者】宇都木伸 |
| <討論> シンポジウム「継続医療を必要とする老人をめぐる諸問題」 | 上掲書所収,p94-109 | 1988/06 | (司会) |
| 法令解説[昭和62年1月~12月] | 上掲書所収,p178(46)-177(47) | 1988/06 | |
| 保健・医療・福祉体系 | 勝沼英宇,長谷川恒雄(編),『老人の診療 その特性と周辺』,p426-433,南山堂 | 1988/07 | |
| <めだかの目> 庶民の日々の暮らしを大切にすることこそ政治では | めだか通信,(15),p2-3,めだか社 | 1988/07 | |
| 『エイズの社会的衝撃 The social dimensions of AIDS』,ダグラス・A・フェルドマン、トーマス・M・ジョンソン(編) | 日本評論社 | 1988/07 | 【共同監訳者】姉崎正平 |
| 今、地域保健・医療は・・・-憲法にある「公衆衛生」を守るには | 社会医学研究,特別号,(第29回社会医学研究会総会講演集),p24-25,社会医学研究会 | 1988/07 | 第29回社会医学研究会総会,1988.7.23-24 |
| はじめに-情報機器の利用とその発展(総合シンポジウム「公衆衛生における情報の役割」Ⅰ) | 日本公衆衛生雑誌,35(8),日本公衆衛生学会 | 1988/08 | |
| 保健所におけるコンピューターを用いた保健活動支援システム | 上掲誌所収,p32- | 1988/08 | |
| 衛生行政法の基本とその考察 | 公衆衛生,52(8),p551-554,医学書院 | 1988/08 | |
| <開会あいさつ> -憲法・反核・平和について語り合う草の根運動交流会’87 | 『草の根人間の暮らせる街へ』めだか通信,(16・18),p7-8,めだか社 | 1988/10 | |
| まとめ・雑感・状況 | 草の根 人間の暮らせる街へ めだか通信16・17号,p49-52,めだか社 | 1988/10 | 【共同執筆者】福井田鶴子、東倉俊一 |
| 開業医への期待とそれに応えるために | 社会保険旬報,(1633),p11-15,社会保険研究所 | 1988/11 |
1989年(昭和64年・平成元年)
| 書名/表題 | 掲載誌/巻号 掲載紙/年月日 発行所等 |
発行年月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| MISO SOUP Red Bean Paste Soup | INTERNATIONAL Cook-ing,p56 | 1989 | |
| 保健・医療・福祉におけるソ-シャル・サポ-ト・ネットワ-ク--その連携と課題 | 健康保険 43(1),p26-34,健康保険組合連合会 | 1989/1 | |
| 年3万人の准看を養成しながら制度一本化は実現できるか | Nurse eye = ナースアイ,(3),p91-96,桐書房 | 1989/01 | |
| 潮流 医学の限界と医師個人の限界とを区別して説明を | Phase3,(53),p9,日本医療企画 | 1989/01 | |
| 医療(保健)福祉と法 | 佐藤進(編)『現代社会福祉法入門』,p316-339,法律と文化社 | 1989/02 | |
| 地域組織活動 | 新井宏朋、他(編)『脳卒中・寝たきり・痴ほうの地域ケア』,p69-87,日本公衆衛生協会 | 1989/02 | 【共同執筆者】新井宏明、岩崎清 |
| 衛生行政の管理と運営 | 橋本正己、他(編),『衛生行政大要 改訂第14版』,p41-58,日本公衆衛生協会 | 1989/2 | |
| 地域における難病対策のすすめ方-地域の難病対策機構 | 松野かほる、他(編)『難病への取り組みと展望』,,p2-21,日本公衆衛生協会 | 1989/2 | |
| 地域における難病対策のすすめ方-難病対策機構の研究成果とその発展 | 上掲書所収,p58-66 | 1989/2 | |
| 難病患者に対する保健指導-難病患者に共通する保健指導 | 上掲書所収,p67-85 | 1989/02 | 【共同執筆者】松野かほる、島内節、木下安子、川村佐和子 |
| 高齢者に先が見え、安心して夢がもてる施策を | Phase3,(54),p9,日本医療企画 | 1989/02 | |
| 長期療養分科会報告 | 厚生省特定疾患 難病の治療・看護調査研究班 昭和63年度研究報告,p18-21,厚生省特定疾患「難病のケア・システム」調査研究班 | 1989/03 | |
| 神経筋疾患対策についての衛生行政試案に関する行政研究 | 厚生省特定疾患 難病の治療・看護調査研究班 昭和63年度研究報告,p72-79,厚生省特定疾患「難病のケア・システム」調査研究班 | 1989/03 | 【共同研究者】広瀬和彦、久保伴江、堀川楊、水谷智彦、川村佐和子 |
| 三鷹市における在宅重症患者のケアの実際とその組織的対応に関する報告 | 人文学報 社会福祉学,5(211),p51-65,首都大学東京 | 1989/03 | |
| 医療の世界的潮流と日本の実情 | 民間病院問題研究所(編)『民病研フォーラム’88報告書 超高齢化時代の病院経営 これからどうなる、どうする-私的病院医院の活動と拡大戦略』,p1-33,民間病院問題研究所 | 1989/03 | |
| 今、地域保健・医療は・・・-憲法にある「公衆衛生」を守るには | 社会医学研究:日本社会医学会機関誌,(8),p121-127,日本社会医学会事務局 | 1989/03 | |
| 全国いきいき公衆衛生の会ニュース-5月19・20日大阪集会・予告 | 月刊地域保健,20(3),p106,東京法規出版 | 1989/03 | |
| <座談会> 地域医療を語る | ばんぶう,(93),p33-43,日本医療企画 | 1989/03 | 【出席者】村田欣造、浅野英一郎、高木克芳、高瀬雄一、中島正治 |
| 長期療養分科会報告 | 厚生省特定疾患 難病の治療・看護調査研究班 昭和63年度研究報告,p18-21,厚生省特定疾患「難病のケア・システム」調査研究班 | 1989/03 | |
| 神経筋疾患対策についての衛生行政試案に関する行政研究 | 厚生省特定疾患 難病の治療・看護調査研究班 昭和63年度研究報告,p72-79,厚生省特定疾患「難病のケア・システム」調査研究班 | 1989/03 | 【共同研究者】広瀬和彦、久保伴江、堀川楊、水谷智彦、川村佐和子 |
| <潮流> 医療施設に寄付する習慣を社会に広めよう | Phase3,(55),p9,日本医療企画 | 1989/3 | |
| <潮流> 市民不在の大病院移転計画と反対運動 | Phase3,(56),p9,日本医療企画 | 1989/4 | |
| <講演> 「在宅ケア」その問題点をさぐる | 日本プライマリ・ケア学会誌,臨時増刊(12),第12回日本プライマリ・ケア学会抄録集,p57,日本プライマリ・ケア学会 | 1989/5 | 座長:村瀬敏郎、演者:西三郎 |
| 在宅入浴サービスの現状と基準づくり | 上掲誌所収,p184 | 1989/05 | 【共同執筆者】立井宗興 |
| 入浴介護の課題と効用 | 上掲誌所収,p187 | 1989/05 | 【共同執筆者】立井宗興 |
| 筋萎縮性側索硬化症患者の人工呼吸器装着後の予後 | 上掲誌所収,p204 | 1989/05 | 【共同執筆者】広瀬和彦 |
| 筋萎縮性側索硬化症患者数と必要医療関係者数の推計 | 上掲誌所収,p204 | 1989/05 | |
| 時代の流れを汲んだ人の限界とを区別して説明を | Phase3,(57),p9,日本医療企画 | 1989/05 | |
| 医療改革論議を前に、いま患者は・・・ | 社会保険旬報,(1652),p6-10,社会保険研究所 | 1989/05 | |
| 新宿区難病検診のこれからの課題-保健と医療と福祉の連携なくして難病患者の在宅ケアはできない | 『検診から在宅ケア 難病医療 -新宿区神経難病10年のあゆみ-』,p102-111,新宿区医師会 | 1989/06 | |
| インフルエンザ予防接種禍事件 | 別冊ジュリスト,医療過誤判例百選(102),p20,有斐閣 | 1989/06 | |
| 病診連携と称する誤った病院開放 | Phase3,(58),p9,日本医療企画 | 1989/06 | |
| 在宅ケアの充実よりは長期療養施設の整備を 誰が在宅ケア・地域ケアを支えるのか | 月刊民病研,(19),p1,民間病院問題研究所 | 1989/06 | |
| 継続医療の討議の残された課題 | 『年報医事法学(4)』,p71~79,日本評論社 | 1989/7 | |
| 法令解説[昭和63年1月~12月] | 上掲書所収,p178(46)-177(47) | 1989/07 | |
| 貧しく幸せな生活の北欧 | Eco-forum,8(2),p26,統計研究会 | 1989/07 | |
| 結論先行、論理性に欠ける報告書 | 生活教育,臨時増刊33(8),p42-43,生活教育の会 | 1989/07 | |
| <潮流> 個々の医療を公開し検討できる体制を | Phase3,(59),p9,日本医療企画 | 1989/07 | |
| <潮流> 患者サービスの改善よりも不当表示の医療の排除を | Phase3,(60),p9,日本医療企画 | 1989/8 | |
| エイズで考えるもの 人権・法制の面から | からだの科学,臨時増刊エイズ戦略,p169-172,日本評論社 | 1989/08 | |
| 先端医学の開発とともに、適正な医療技術の普及向上のためへの努力を | Phase3,(61),p9,日本医療企画 | 1989/09 | |
| 「在宅ケア」その問題点をさぐる | 日本プライマリ・ケア学会誌,12(3),p214-220,日本プライマリ・ケア学会 | 1989/09 | |
| 「高齢化社会と老人医療」-在宅ケアを本気ですすめるために | 日本医事新報,(3412),p106-108,日本医事新報社 | 1989/09 | |
| 行政のなかの保健婦 | 保健婦雑誌,45(9),p7~12,医学書院 | 1989/09 | |
| 住民に依拠した保健所への脱皮を | 新医協,号外1989年8月31日号,p10-14,新日本医学出版社 | 1989/09 | |
| 社会福祉のデータベース化で満足するのは誰だろう | 福祉展望,(8),p88,東京都社会福祉協議会 | 1989/09 | |
| 健康の維持・増進ヘルス・ケア・サービス | 西武百貨店池袋コミュニティ・カレッジ、流通産業研究所(編)『ウェルネス・ビジネスの発想』,p217-228,ダイヤモンド社 | 1989/10 | |
| <潮流> 医学の限界と医師個人の限界とを区別して説明を | Phase3,(62),p9,日本医療企画 | 1989/10 | |
| システムダイナミクスモデルを用いた人工透析患者数の将来予測 | 日本公衆衛生雑誌,36(10),p6,日本公衆衛生学会 | 1989/10 | 【共同執筆者】本橋豊 |
| 県の基本構想・基本計画における保健所の位置づけ | 上掲誌所収,p152 | 1989/10 | |
| 保健所運営費の一般交付税化と地方自治体衛生行政の主体性 | 上掲誌所収,p206 | 1989/10 | 【共同執筆者】前田博明、星旦二 |
| ニューライフ健康づくり-やまびこ運動事業 | 全国いきいき公衆衛生の会(編著)『いきいき公衆衛生シリーズ第1巻 今、いきいきとした公衆衛生活動のために』,p128,社会保険出版社 | 1989/10 | |
| 住民とともに地域福祉をめざして | 自治労福生市職員組合(編)『そして、青い空 いのちとくらしを大事にするまちに 第2集』,p7-32,自治労福生市職員組合 | 1989/10 | |
| システムダイナミクス(SDS)を用いた人工透析患者の将来予測 | 日本透析医会雑誌,5(2),p51-70,日本透析医会 | 1989/10 | 【共同執筆者】本橋豊 |
| 新日本医師協会東京支部'89年度のまとめと'90年度の活動-医学教育 | 新医協,号外,p15,新日本医学出版社 | 1989/10 | |
| 医療制度 | 事典刊行委員会(編)『社会保障・社会福祉事典』,労働旬報社 | 1989/11 | |
| 不可解な医療のシステム化-自分の病院が担当できる診療機能を明確に | 月刊民病研,(24),p1,民間病院問題研究所 | 1989/11 | |
| 高齢者に先が見え、安心して夢が持てる施策を | Phase3,(63),p9,日本医療企画 | 1989/11 | |
| 災害対策のために救急隊員の権限拡大と必要な養成訓練を | Phase3,(64),p9,日本医療企画 | 1989/12 | |
| 地域医療と福祉計画 (福祉とコミュニティ<特集>) | 季刊社会保障研究,25(3),p225-235,国立社会保障・人口問題研究所 | 1989/12 | |
| 一人ひとりの療養生活を保障する自治体に | Nurse eye = ナースアイ,(14),p10-15,桐書房 | 1989/12 |