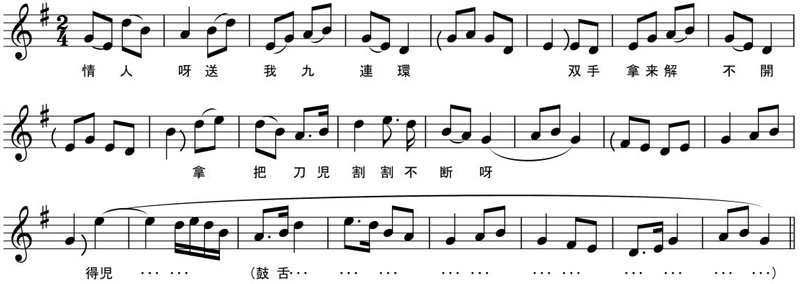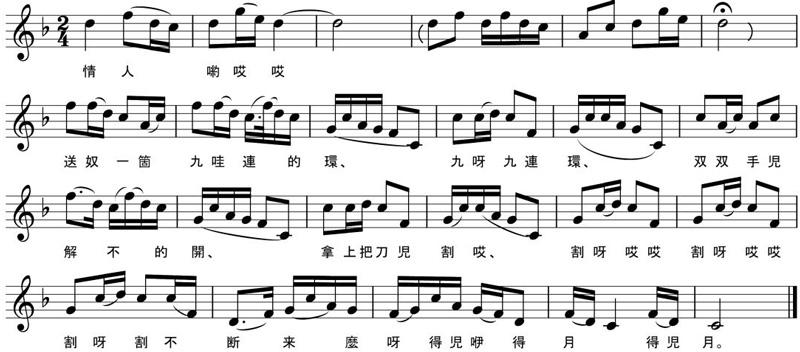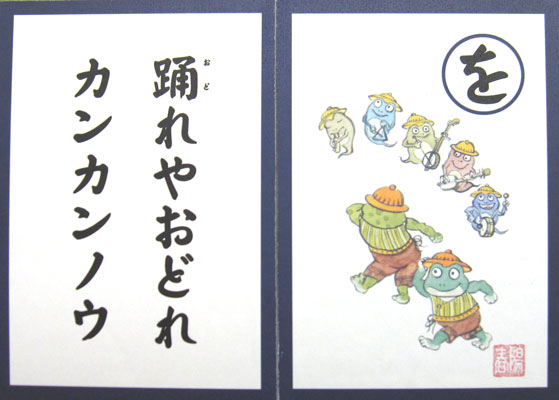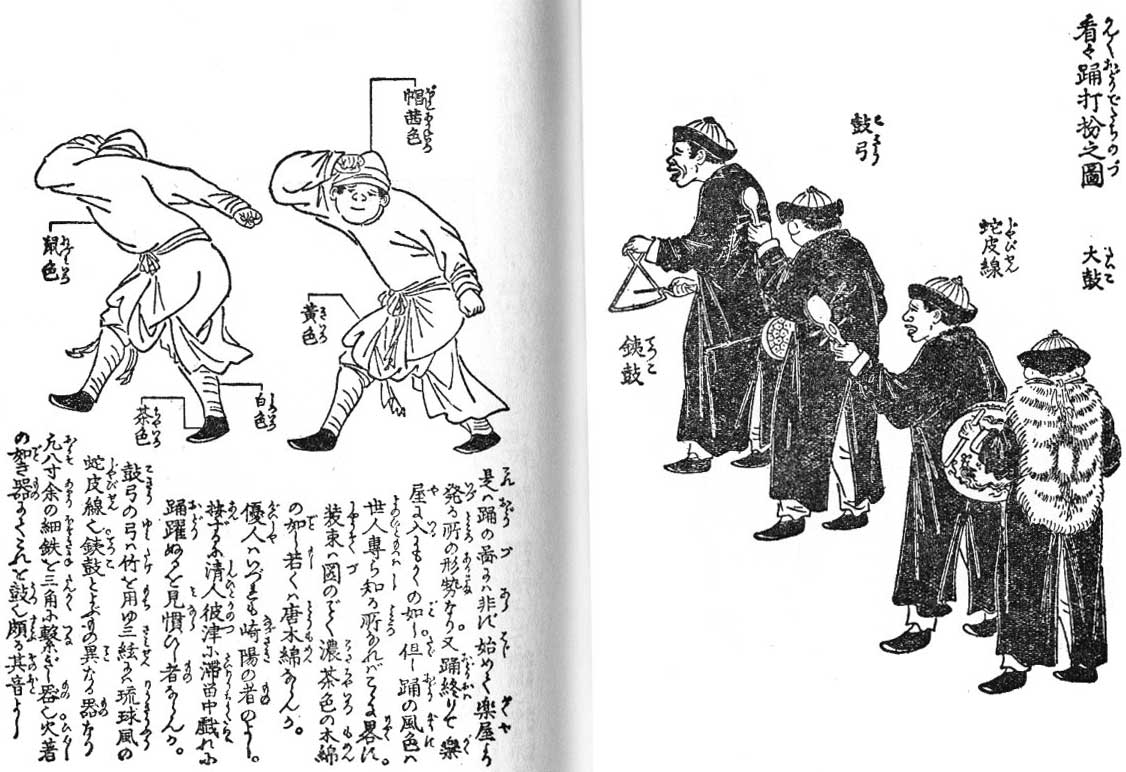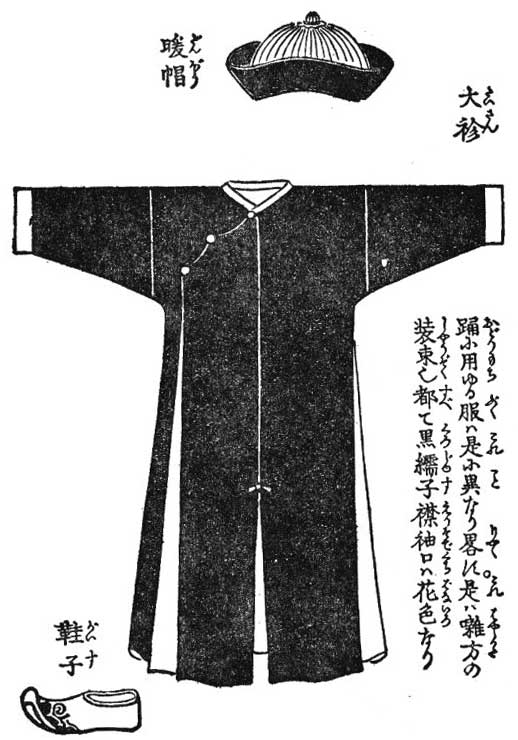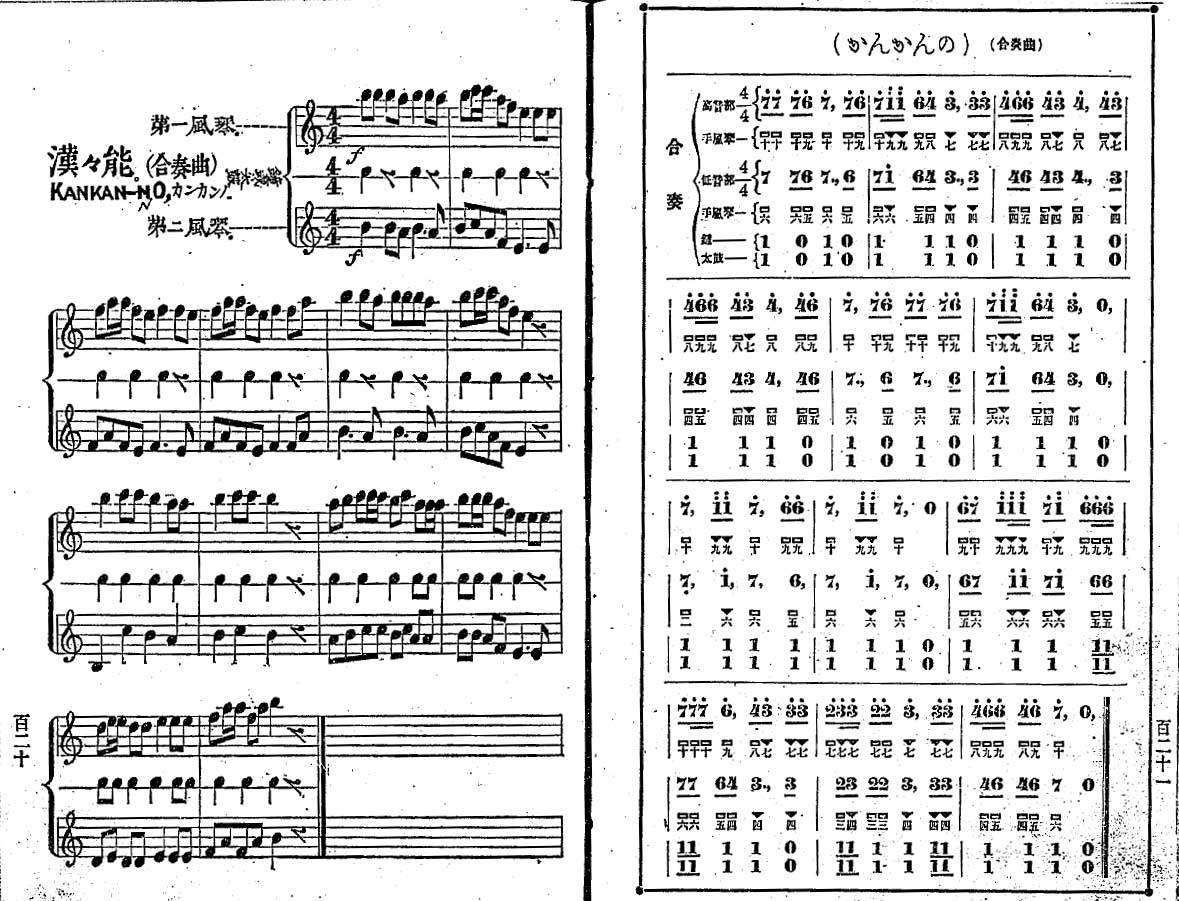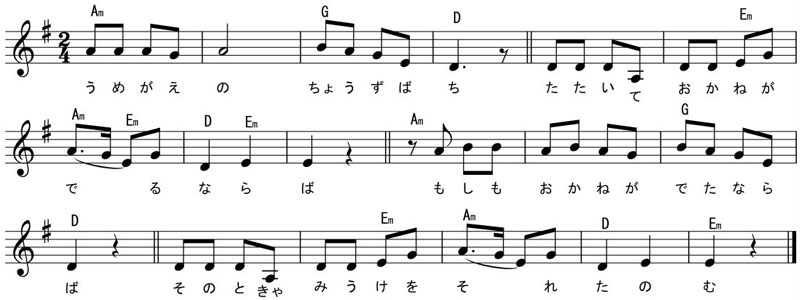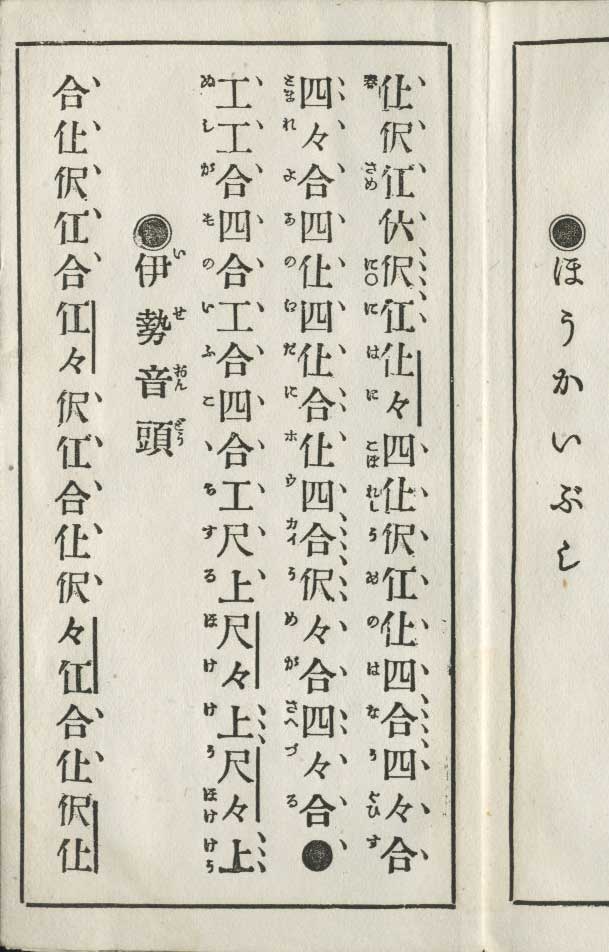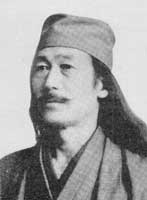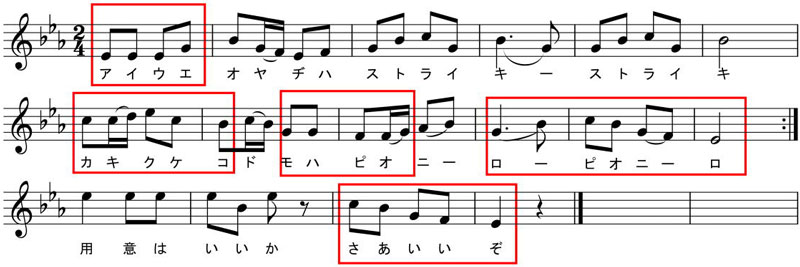工尺譜
上上工尺。ドドミレ
工四上尺工上四合々。ミラ,ドレミドラ,ソ,ー
上'上'合四。ド'ド'ソラ
四上'四上'四上'合々。ラド'ラド'ラド'ソー
四上'四上'合々。ラド'ラド'ソー
工々尺工六五六工尺上尺上。ミミレミソラソミレドレド
(最後の一行はリフレイン)
リズムや絶対音高を補い、ネット上の世界標準である「ABC記譜法」でメロディーを示すと、右のようになる。
参考サイト:ABC言語 − テキストで「楽譜」を表現するための言語
|
左の工尺譜を「ABC譜」に直したもの
X: 1
T:kyuurenkan(1)
M:2/4
L:1/4
K:D
D D/F/ | E2 | F B,/D/ | E/F/ D/B,/ | A,3/2 z/ |
d d/A/ | B2 | B/d/ B/d/ | B d | A3/2 z/ | B/d/ B/d/ |
A3/2 z/|: z/ F F/| E/F/ A | B/A/ F/E/ | D3/2 E/ |D2 :|
 [聴く(MIDI)] [聴く(MIDI)]
|
伴奏を弾くときは適宜、装飾音等を追加する。
X: 1
T:kyuurenkan(2)
M:2/4
L:1/8
K:D
D>E FA | E-E/F/ E/F/ E/D/ | F F/D/ B,D | E E/F/ D/E/ D/B,/ | A,>F A/F/ A/B/|
d>d dA | B B/d/ F/E/ F/A/ | B d B d | B/B/ A/B/ d/e/ d/B/ | A A,/A,/ AA | BA Bd |
A A, A A/A/ |: z F2 D| EF A d/d/ | BA FE| D>D D E |D3 z :|
 [聴く(MIDI)] [聴く(MIDI)] |
 【MP3で歌を聴く】(1.32MB ダウンロード形式)
【MP3で歌を聴く】(1.32MB ダウンロード形式) 清楽の「九連環」 [説明]
清楽の「九連環」 [説明] 北京・百本張抄本「九連環」 [説明]
北京・百本張抄本「九連環」 [説明] 福建省・建陽県の「九連環」 [説明]
福建省・建陽県の「九連環」 [説明] 浙江省・金華市の「九連環」 [説明]
浙江省・金華市の「九連環」 [説明] 江蘇省・無錫の「九連環」 [説明]
江蘇省・無錫の「九連環」 [説明] 安徽省の「九連環」 [説明]
安徽省の「九連環」 [説明] 貴州省の「九連環」 [説明]
貴州省の「九連環」 [説明] 陝西省の「九連環」 [説明]
陝西省の「九連環」 [説明] 日本・明治期の「かんかんのう」 [説明]
日本・明治期の「かんかんのう」 [説明] 群馬県上野村の「かんかん踊り」 [説明]
群馬県上野村の「かんかん踊り」 [説明] 日本・大正期の"九連環" [説明]
日本・大正期の"九連環" [説明] かんかんのう [説明]
かんかんのう [説明] 梅ヶ枝の手水鉢 [説明]
梅ヶ枝の手水鉢 [説明] 法界節 [説明]
法界節 [説明] 新法界節 [説明]
新法界節 [説明] サノサ節 [説明]
サノサ節 [説明] むらさき節 [説明]
むらさき節 [説明] アイウエオの歌 [説明]
アイウエオの歌 [説明]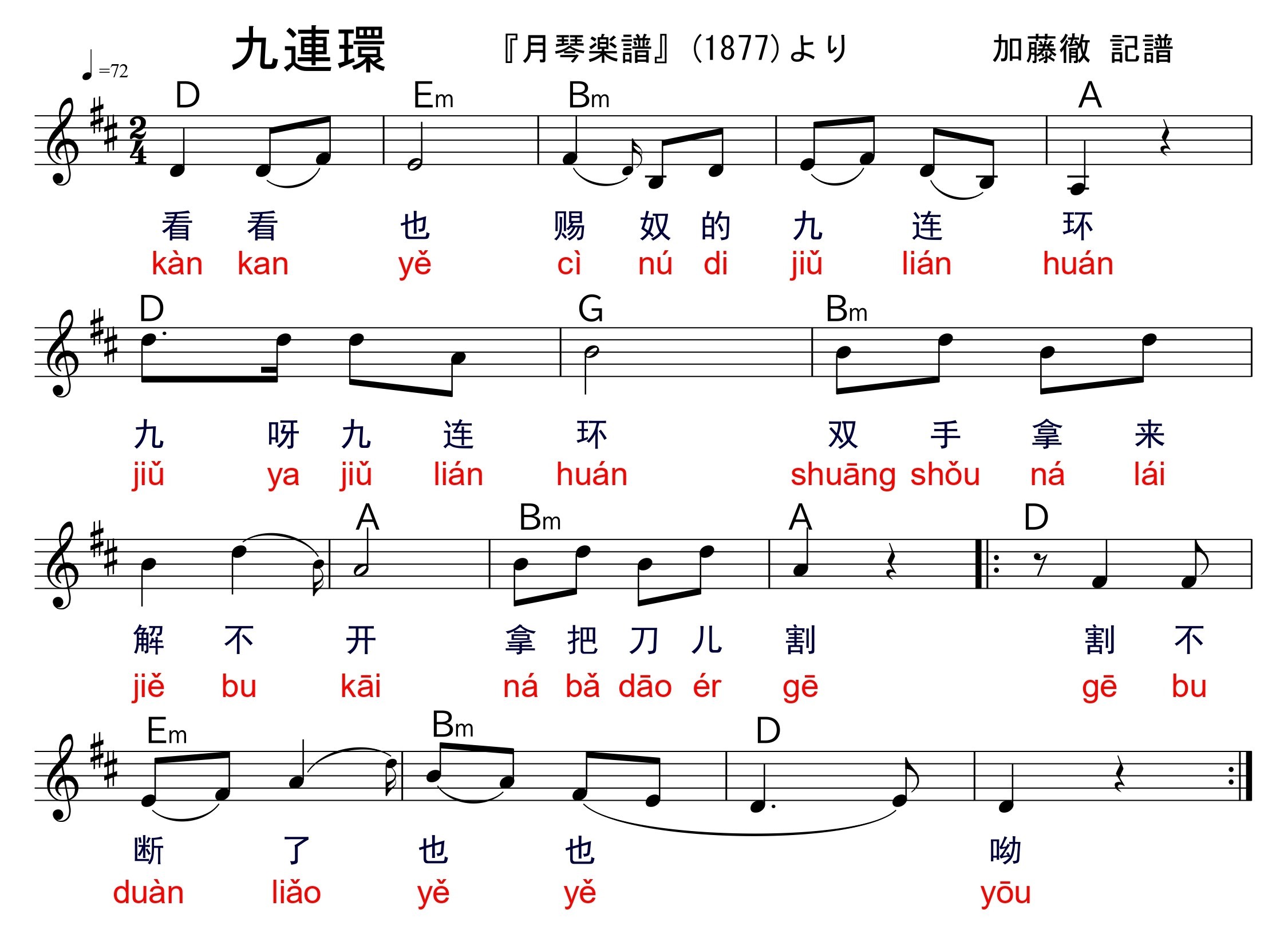
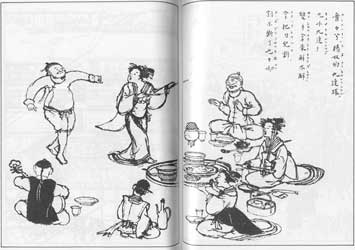

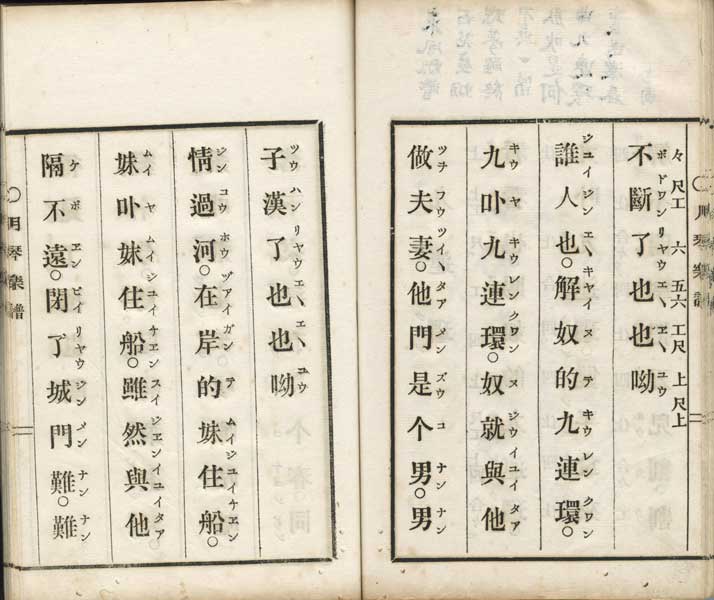
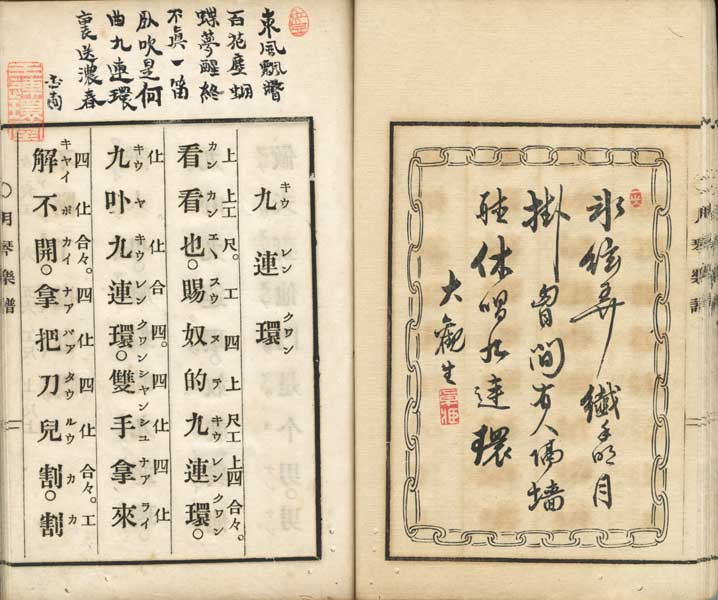
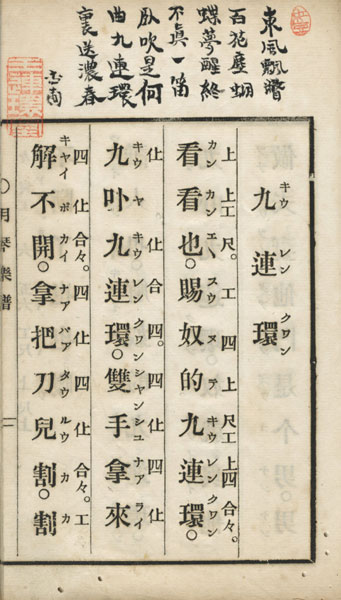

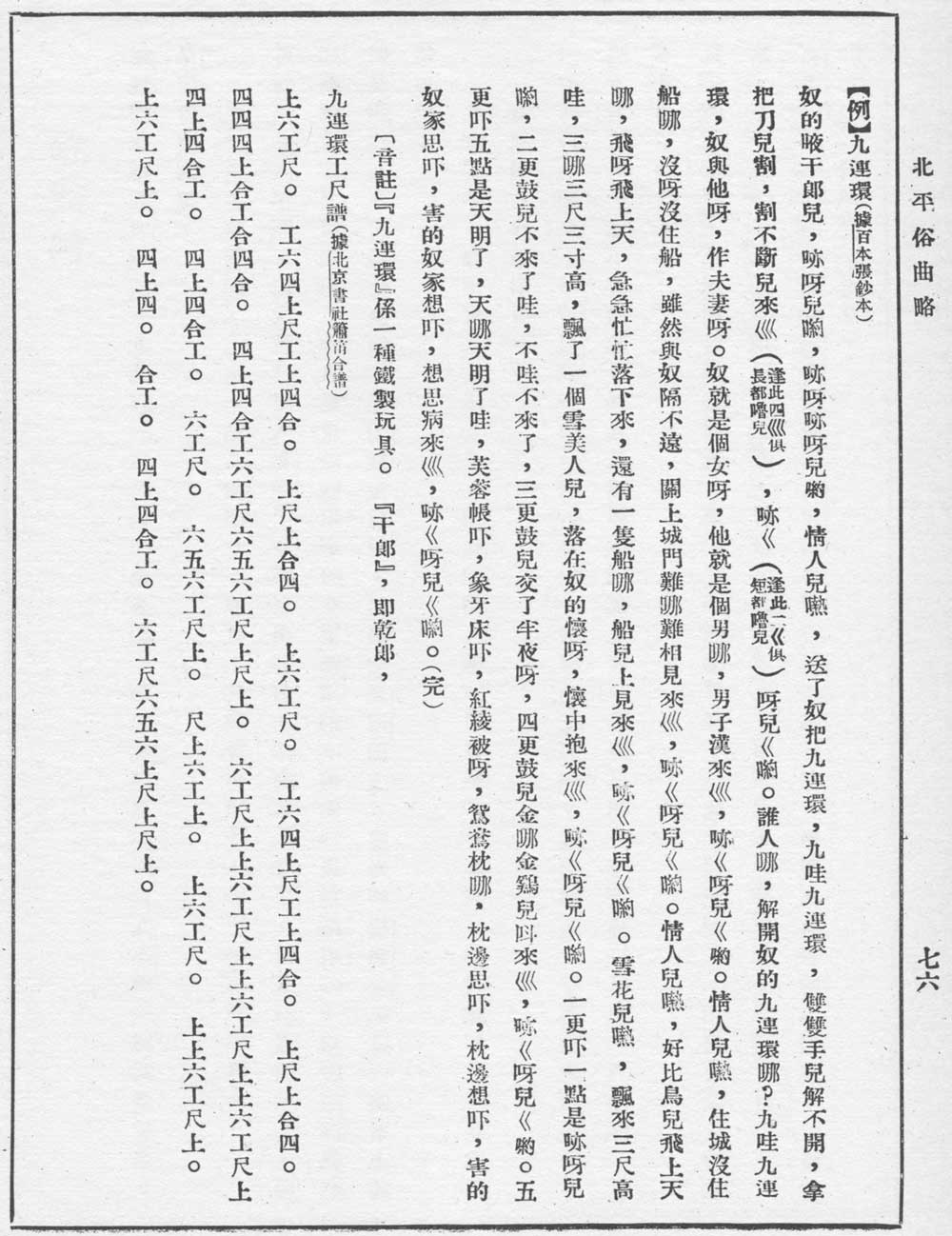 上記の楽譜のもとである工尺譜と歌詞は、李家瑞著『北平俗曲略』(民国22年=1933年1月初版)の「福建調」の項にも載っている。
上記の楽譜のもとである工尺譜と歌詞は、李家瑞著『北平俗曲略』(民国22年=1933年1月初版)の「福建調」の項にも載っている。