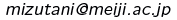全面改訂中(June 2020)
このページでは、不確かな記載または不適切な記載が含まれています。 ご迷惑をおかけいたします。LaTeX文書
LaTeXに関する書籍
 [改訂第6版] LaTeX2ε美文書作成入門
[改訂第6版] LaTeX2ε美文書作成入門- 日本語で書かれたLaTeX解説の決定版だ。 付録DVD-ROMには世界標準となったTeXシステムの配布形態である TeX Live 2013と関連ツールを簡単にインストールできるインストーラーが収録(Windows,Mac用)されているので自分のパソコンに確実にTeX環境を整えることができる。
 LaTeX2e辞典 用法・用例逆引きリファレンス(2009年2月)
LaTeX2e辞典 用法・用例逆引きリファレンス(2009年2月)- ある程度、LaTeXに親しんでくると、高度な内容を盛り込んだリファレンスが欲しくなる。 もっと美しく、もっと思うままに文書を作成したいという気持ちが湧いてくるからだ。 手元において必要に応じて参考にできる必携書(筆者もお世話になってます (^^; )。
 The LaTeX Companion (2nd Edition)(2013年)
The LaTeX Companion (2nd Edition)(2013年)- これが決定版。出た〜!、第二版。1100ページ越えちゃいました。 PDF/Kindle(Mobi)/EPUB版の電子書籍で(^^)
- 1994年の第一版は「The LATEXコンパニオン」アスキー (1998)の邦訳がある。 LateXを詳しく知るために現在でも十分に有用だ。
 MyTeXpert
MyTeXpert- 『好き好きLaTeX2e』シリーズの「入門編」。入門と称しているが相当詳しい。 『ポケットブック編』もリファレンスとして使える。
ごく簡単なLaTeXマニュアル
 LaTeX入門(PDFファイル)
LaTeX入門(PDFファイル) 走れメロスTeX版[ZIP圧縮, UTF8+改行CR]
走れメロスTeX版[ZIP圧縮, UTF8+改行CR]
- azlogo.eps.zip(青空文庫のロゴ:圧縮したEPSファイル)
- TeXファイルを編集しながら、TeX文書の体裁変更をしり、PDFファイルを作成しよう
解消されました。 実習室のWindowsのw32texによるTeXシステムでEPSファイルが貼り込めない現象は解決されました。 どんどんLaTeXを使いましょう(^^)
LaTeXドリル without Tears
ドリルを通じてLaTeX文書作成の基本を学ぼう。 使いやすい環境でより美しい文書を作成するには、まず自分のTeX環境を整えることが決定的に重要である(自らの表現手段を自前で持つことは常に大切である)。
LaTeX環境構築と利用の要点
是非、自分のパソコンにLaTeX環境をインストールしよう。 文書作成の大きな世界を手中に収めるのである。 以下に、注意すべき点をまとめておく。 特に、実習室のTeX環境を利用するには、TEXMFHOMEの利用の理解が欠かせない。
 WindowsへのTeXのインストール
WindowsへのTeXのインストール MacOSへのTeXのインストール
MacOSへのTeXのインストール TEXMFHOMEの利用
TEXMFHOMEの利用 バックスラッシュ記号の入力(「\」か「¥」)
バックスラッシュ記号の入力(「\」か「¥」)- TeXファイルの制御コマンドでは、バックスラッシュを多用します。 MacOSでは表示の仕方を選べます。
 LaTeXの特殊記号・特殊記法
LaTeXの特殊記号・特殊記法 画像ファイルの取り扱い
画像ファイルの取り扱い
LaTeXの数学表現
LaTeXの縦書き
 Beamer Slideの例[ZIP UTF8+改行CR], 画像付き
Beamer Slideの例[ZIP UTF8+改行CR], 画像付き 明治大学ロゴ入りBeamerテーマ[ZIP UTF8+改行CR], 画像付き
明治大学ロゴ入りBeamerテーマ[ZIP UTF8+改行CR], 画像付き- 展開してTEXMFHOMEに置いて下さい。
- Meiji Beamerテーマを使った例
 明治大学ロゴ入りBeamerPosterテーマ[ZIP UTF8+改行CR], 画像付き
明治大学ロゴ入りBeamerPosterテーマ[ZIP UTF8+改行CR], 画像付き- 展開してTEXMFHOMEに置いて下さい。
- MeijiBeamerPosterテーマを使った例
BeamerのMeijiスライド
プレゼンテーション用のスライドはPowerPintやKeynoteで作成するだけが能ではない。 LaTeX + Beamerパッケージで生成したPDFファイルをAdobe Readerを使って美しいプレゼンテーション用スライドを作成することが可能である。
LaTeXを学ぶということ
文書とは何かの「文書情報」の箇所を以下に再録しておこう。 LaTeXによる文書作成を知ることは、そこで要件とされる文書の要件を全て満たすように文書が作成できるということに他ならない。 以下はLaTeX学習の道標でもあるわけだ(修得するごとにチェックマークをつけよう)。
明解でわかりやすい文書にするためには、文書全体の構造を明示するように文章構成上の工夫をすることが必要である。 必要に応じて、文章(またはそのグループに)必要な属性を与えて、それらを印刷物として読みやすいように視覚的表現工夫を備えねばならない。
文書を特徴づけている要素を文書要素といい、文書にとって必要な要件や要素にはたとえば次のようなものがある。
- 文書のヘッダ
- 文書の表題(title)
- 著者・編者名(author)
- 文書を作成した日付(date)
- 文書のコメント(comment:意図・目的,変更の履歴などの記載。非表示にすることも多い)。
- 文書目次(table of contents)
- 図・表のリスト(figure/table list))
- 文書の本文(body)
- 要約(abstract)
- 文書をブロックとして構造化
- 章(chapter)、節(section)、小節(subsection)、段落(paragraph)など
- 対応した見出し(head line)をつける
- 図(figure)や表(table)
- リスト、様々な様式に応じた箇条書き
- 数式(mathematical formula)、化学式(chmical fomula)、楽譜(score)などの特殊表現(出版に際して、美しく整形するための自動化技術がもっとも遅れていた。多くは活字職人の技量に頼っていた)
- 相互参照(mutual reference)
- 章・節,図表番号と登場ページ(またはURL)
- 参考文献の参照名
- 文書の末尾(end)
- 参考文献(reference)
- 著者・編者名
- 文献の表題(論文題目・書名)
- 雑誌名・出版社名
- 巻・号,ページ(またはURL)
- 発行の年月日
- 付録(appendix)
- 索引(index)
- 用語集