 北京 東ユーラシアの主都の歴史と魅力
北京 東ユーラシアの主都の歴史と魅力
| 三千年前、中国の辺境の小都市だった北京は、千年前の遼の時代から東ユーラシアの主都となりました。 元の時代の北京の繁栄はマルコ・ポーロを驚嘆させました。 以来、一部の例外的時期を除き、北京は中国の首都であり続けています。 欧州の都市を見慣れた洋画家の梅原龍三郎も、北京の美しさに魅了され、作品を残しました。 北京の魅力とそのダイナミックな歴史を、豊富な映像資料を使いながら、わかりやすく解説します。(講師・記) |
本棚の整理がなかなか進まない。昔、学生時代に愛読した本を、ついつい読んでしまう。鐘ケ江信光(1912年- 2012年)著『中国語のすすめ』講談社現代新書もその一つ。ことばの勉強は「暗記、根気、年期」の3つの「き」が大事、というくだりには、いまも納得。 pic.twitter.com/mW9WL0toko
— 加藤徹(KATO Toru) (@katotoru1963) March 23, 2021
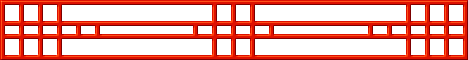
朝日カルチャーセンター 新宿 @asakaruko 「北京 東ユーラシアの主都の歴史と魅力」3月20日(土)13時30分から。ネット配信(有料)併用。民族と権力が興亡を繰り返す「世界史上最強の事故物件都市」(芥川龍之介や横光利一の北京観を超訳)の蠱惑的吸引力をやさしく解説。https://t.co/TZTxWdWOcD
— 加藤徹(KATO Toru) (@katotoru1963) March 19, 2021
北京と東京、同一縮尺による比較
|
世界の大都市圏人口ランキング、2020。世界第1位は日本の首都圏の約3800万。・・・こんなに集中して、大丈夫かな??? ちなみに中国の首都圏は世界第12位。韓国の首都圏は世界第8位。欧米のいわゆる先進国の首都圏の人口はどこも意外と少ないのは、示唆的。https://t.co/6Re4UyvYfg pic.twitter.com/ep6JRtSNtY
— 加藤徹(KATO Toru) (@katotoru1963) March 19, 2021
|
芥川龍之介(1892−1927)「北京日記抄」より。「青空文庫」より引用。 今日も亦中野江漢君につれられ、午頃より雍和宮(ようわきゅう) 一見に出かける。喇嘛寺(らまでら)などに興味も何もなけれど、否、寧ろ喇嘛寺などは大嫌いなれど、 北京名物の一つと言えば、紀行を書かされる必要上、義理にも一見せざる可らず。(このあと、詐欺めいた挿話がある。中略) 天壇。地壇。先農壇。皆大いなる大理石の壇に雑草の萋々(せいせい)と茂れるのみ。 天壇の外の広場に出ずるに、忽(たちま)ち一発の銃声あり。何ぞと問えば、死刑なりと言う。 紫禁城。こは夢魔のみ。夜天よりも厖大なる夢魔のみ。 |
|
横光利一(1898-1947)「北京と巴里(覚書)」より。「青空文庫」引用 (前略)北京は消費の街だという。なるほどこの街では生産というものをかつてしたことのない人物が、 代々かかってどれほど人間が消費を出来るものかと、あらゆる智慧を絞って工夫に工夫をこらせた有様が歴然と現れている。 (中略)北京へ行くものは悪徳と戦うつもりで行かない限り、身につけた現世の健康なものはすべて無くなってしまうかもしれぬ。 ここには精神のある美よりも詐術の美を美とする精神がある。 もし疲労と孤独のために難なくこれに襲われたら、恐らく北京ほど美しく見える都会はないだろう。 死体に色づけ客間に置き放したまま嫣然と笑わせたようなこの都会の女性的な壮麗さは、 たしかにどこの国にも類例はあるまい。 (中略)数世代も続いた都を他民族に征服され、またそれが崩れると次の民族が交代するという肉体の死滅して来た累積層 の中には、残るものはこのように頓狂なものばかりかと思って私は茫然とした。かつて有ったに相違ない良いものは、 殆ど演劇だけを残して死んでしまっていて、尨大な駄作ばかりが本尊となりすまし、樹の海がひとり祭壇をめぐっている。 ここで一番人心に感動を与えているものは、今は小唄のような哀れな歌調をもった節廻しだけである。しかし、大衆というものは駄作ほど喜ぶ。駄作が傑作となって永久に残るというこの地の特種な機構は、何かこの北京に限り他国とは比較にならぬ犯罪の深さを物語ってやまぬものがある。 北京に遊ぶ知識人はよく前から、ここは全くパリに似ているというのを私は聞いた。あるフランス人は北京はパリ以上だとも言ったという。(以下略) |