お知らせ
配布資料
授業で使用したレジュメ、資料などはこのサイトからダウンロードできます。「配布資料」の資料名をクリックして下さい。「このリンクは無効」などと表示されて、うまくダウンロードできない場合は、表示アドレスを再度読み込んでみて下さい。なお、ネット上での公開のため一部を削除、修正している場合があります。
自治労寄付講座のFacebookページ
自治労寄付講座のFacebookページを開設しました。講義の進展状況や写真・関係情報を掲載する予定です。 ここをクリック
ここをクリック
自治労寄付講座「地方自治体の仕事と労働組合」(2024年度・特別編)
2009年度から開講してきた同講座は、コロナ禍による労働環境や学生の就労意識の変化に対応して、新しい自治労講座をつくることに取り組みます。
今年度はその手がかりとして、ゼミナールにおいて開講し、学生と講師(自治労組合員)との積極的な意見交換をめざします。
また、もう一つの寄付講座「労働講座企画委員会寄付講座」での開講をとおして、民間企業志望の学生にも自治体の仕事への関心を喚起するよう努めます。
5月16日 久保隆光(商学部専任講師)ゼミナール
私のキャリア~公務員編
福元貴瑛(自治労本部地方公務員災害補償基金企画課兼メンタルヘルス対策サポート推進室)
民間企業から公務員に転職した経歴をもつ講師が、民間企業との比較で公務員の仕事のやりがいと魅力について語る。特に、地域経済に関するやりがいについて、市民と一緒に街を創り上げ、市民の暮らしを支え、街のプロフェッショナルになれる、さまざまな価値観や考え方に触れることのできる点について紹介した。講師と学生との双方向のやりとりを交えた活気ある講義となった。
5月22日 早川佐知子(経営学部准教授)ゼミナール
}地方財政の課題と取り組み
竹中慶吉(自治労赤平市職員労働組合)
2006年に財政破綻をして再建に取り組んでいる北海道夕張市と赤平市を具体的事例に、財政悪化の要因と財政が果たす機能について考える。財政破綻の防止策として、自治体の一部の責任者にだけ任せるのではなく、住民参加による経営チェックや、現場に適応しない法律・条例に対する労働組合による改正への働きかけの必要性について言及した。
参加した学生は、事前に民間企業における経営の失敗についても学習し、自治体の財政破綻との比較の視点からも考えることになった。
7月5日 石川公彦(沖縄大学法経学部教授)ゼミナール
知っておきたい公務員制度と労働組合の役割
仲本政之(沖縄県関係職員連合労働組合)
公務員の仕事について、国家公務員と地方公務員との違い、地方公務員における市区町村と都道府県との仕事の違いの説明があり、そのうえで沖縄県における県職員の職種についてご説明いただいた。
また、沖縄県の採用試験と入庁後のスケジュールなどについてお話しいただくとともに、公務員が組織している労働組合について、その役割と意義などをご説明いただいた。特に自治労の活動について、具体的な取り組みを紹介いただき、公共サービスを守ることと自治労の取り組みの関係性などについてご説明いただいた。(石川)

7月12日 石川公彦(沖縄大学法経学部教授)ゼミナール
自治体が進める市民と協働のまちづくり
我如古 誉幸(宜野湾市役所)
宜野湾市における公務員の仕事について、どのような職種があるのか、組織図をもとにご説明いただくとともに、我如古さんがどのようなお仕事をされてきたのか、具体的な内容とやりがいについてお話しいただいた。
また、宜野湾市の第4次総合計画や市民協働推進基本指針などに拠りながら、「市民と行政が共同するまち」についてご説明いただき、協働型の地域社会の意義とその取り組みの中で公務員が担う役割などの話がなされた。宜野湾市の取り組みとして、まちづくりに関する各種事業の紹介と組合活動についての説明がなされた。(石川)

7月19日 石川公彦(沖縄大学法経学部教授)ゼミナール
子どもの貧困・児童虐待を地域からなくす取組み
森田修平(児童福祉司/自治労沖縄県本部社会福祉評議会議長)
児童福祉分野を担う公務員(①児童福祉司、②児童心理司、③自動指導員、④児童自立支援専門員など)にはどのような職種があるのか、それぞれの仕事の内容などを説明いただいた。また、自治労の組織体系の中で、(児童福祉部門を含む)社会福祉評議会の位置の説明がなされた。
そのうえで、沖縄県の児童虐待の現状について、統計データとともにリアルな事実報告があり、児童虐待を無くしていくための地域での取り組みについて、森田さんご自身と一般社団法人OCFSの活動を中心に紹介していただいた。(石川)
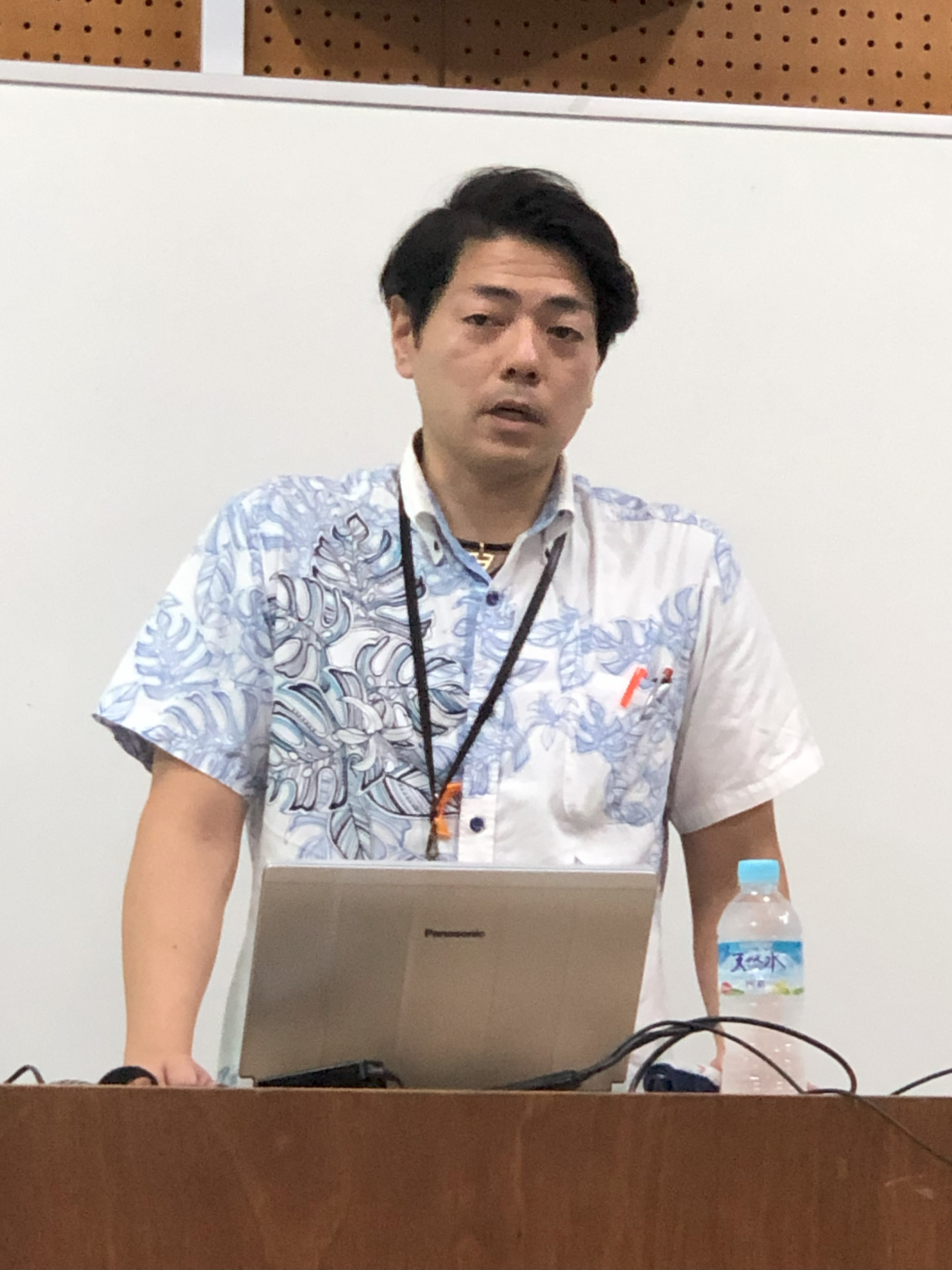
11月14日 早川佐知子(経営学部准教授)社会人大学院ゼミナール
女性消防士の活躍と定着
藤木亜純(函館市北消防署)
2024年11月14日(木)の大学院の授業にて、全国消防職員協議会の藤木亜純さんをお招きし、特別講義を行いました。テーマは「女性消防士の活躍と定着」です。
藤木さんは全国でも3.5%しかいない女性消防士の一人として活躍中です。今回は、職場において圧倒的に少数派になる性別の労働者をいかに採用・定着させるかという課題についての講演をしていただきました。
女性消防士は採用数こそ増えつつあるものの、離職率も高いとのことです。その背景にある人事労務管理上の課題や、組織文化の問題、労働組合が法的に認められていないという問題など、多岐にわたって解説してくださいました。
この授業は社会人を対象としています。後半のディスカッションでは、それぞれの職業経験から多くの質問や意見が寄せられ、時間が足りないほど盛り上がりました。女性が圧倒的に少ない職場、男性が圧倒的に少ない職場、双方に共通する課題があるでしょう。逆に、どちらかにだけ起こる課題もあると思います。今後、当センターではさまざまな事例を検討してゆく予定です。(早川)
2024年度 労働講座企画委員会寄付講座
「職場のリアルから働き方を考える」
12月12日 健康で文化的な最低限度の生活〜生活保護行政の現場から
吉弘 恵莉子(熊本市西区役所保健福祉部保護課/熊本市役所職員組合)
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する―憲法第25条は、中学生や高校生の間でも最も有名な法規定のひとつである。憲法で定められた生存権を保障するための「生活保護」制度は、様々な社会保障給付を含め、その利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用してもなお、生活に困窮する方を対象としているため、社会保障の最後のセーフティネットといわれている。しかし、昨今、不正受給の問題等から、「生活保護」という言葉が独り歩きし、ときには全くの「悪」であるかのように取り扱われることがある。まだまだ多くの課題が残された生活保護制度の現状と実態について、一現場職員の視点を交え伝えたい。
12月19日 消防職員の活動と地方自治体の責任
長谷川 亜純(函館市北消防署)
消防職員は地方自治体の職員として市民の安心・安全を守るため、24時間勤務で働いている。火災・救急・救助の現場活動はもちろん、近年大規模・複雑多様化している地震、風水害等の自然災害にも対応している。訓練も危険と隣合わせの仕事であり、装備や設備が十分でなければ、職員の安全さえも危うくなる。また、チームワークで業務にあたることから、職場の雰囲気づくりも大切であり、職員が団結し、現場の声を行政に反映させる必要があるが、日本の消防職員には労働組合権がすべて認められていない。その現状を打開するために設立された全国消防職員協議会の役割と、消防職の特性から労働組合の必要性を考察する。また、女性消防職員がまだまだ少ない消防職場の中で、男女が共に働くことの難しさや意義、消防職を通じて感じた命の大切さを伝える。
参考サイト
全国消防職員協議会
1月9日 原発事故と復興支援
愛場 学(大熊町役場/大熊町職員労働組合)
東日本大震災、福島原発事故によって世界的にも経験のない課題、矛盾が、次々と明らかになっている。特に、安全神話のもと、原子力災害への対応は無策・無防備に等しく、住民、自治体そして職員も翻弄されている。国の意思決定が自治体を住民から乖離させ、民主主義さえも否定されかねない一方、原発立地住民にとっては、未だ脱原発を唱えることが難しい側面もある。このような中で、自治体機能の回復、住民の生活再建に取り組んでいる自治体の現状を通じ、民主主義、行政、自治体とは何か考える。
参考ビデオ
『被災自治体のしごと:南相馬市2016 』(2016年、13分)
制作:明治大学労働教育メディア研究センター
 HOME
HOME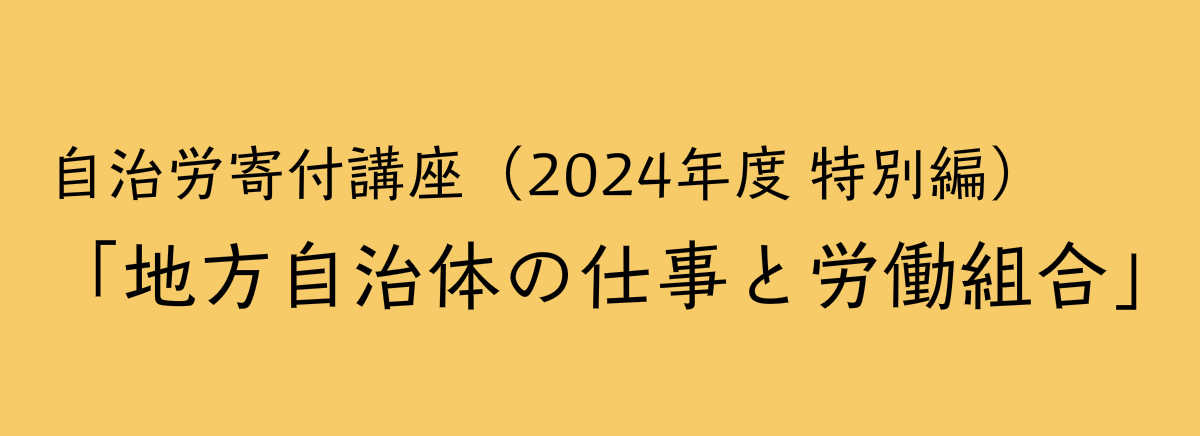
 明治大学労働教育メディア研究センター
明治大学労働教育メディア研究センター 自治労(全日本自治団体労働組合)のサイト
自治労(全日本自治団体労働組合)のサイト