 東アジア芸術論A オンライン授業 第5回
東アジア芸術論A オンライン授業 第5回
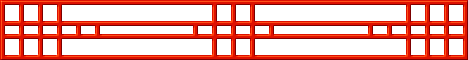
 時間芸術 Time Arts / Temporal Art
時間芸術 Time Arts / Temporal Art
 刹那生滅(せつなしょうめつ)
刹那生滅(せつなしょうめつ)
|
序 わたくしといふ現象は 仮定された有機交流電燈の ひとつの青い照明です (あらゆる透明な幽霊の複合体) 風景やみんなといつしよに せはしくせはしく明滅しながら いかにもたしかにともりつづける 因果交流電燈の ひとつの青い照明です (ひかりはたもち その電燈は失はれ) これらは二十二箇月の 過去とかんずる方角から 紙と鉱質インクをつらね (すべてわたくしと明滅し みんなが同時に感ずるもの) ここまでたもちつゞけられた かげとひかりのひとくさりづつ そのとほりの心象スケツチです これらについて人や銀河や修羅や海胆は 宇宙塵をたべ または空気や塩水を呼吸しながら それぞれ新鮮な本体論もかんがへませうが それらも畢竟こゝろのひとつの風物です たゞたしかに記録されたこれらのけしきは 記録されたそのとほりのこのけしきで それが虚無ならば虚無自身がこのとほりで ある程度まではみんなに共通いたします (すべてがわたくしの中のみんなであるやうに みんなのおのおののなかのすべてですから) 【以下、省略】 |
 ピンクスの酒 Binks no Sake
ピンクスの酒 Binks no Sake