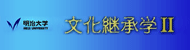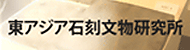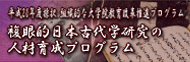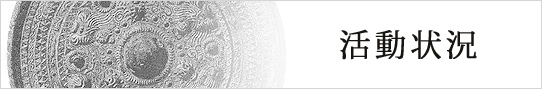〒101-8301
東京都千代田区神田駿河台1-1
03-3296-4143
| 2014年4月25日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:神野志隆光(日本文学・教員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持統天皇即位の劃期性
The Epoch-Making Succession to the Throne of Emperor Jito(持統天皇) by KOHNOSHI Takamitsu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:坂口彩夏(日本史学・院生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『藤氏家伝』による称制の一考察 ―「皇后臨朝」と殯を視角として― A study of Shosei(Ruling without official accession to the Imperial Throne) by the “Thoshi Kaden”(Biographies of the Fujiwara clan). by SAKAGUCHI Ayaka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年5月9日(金) | 【文化継承学Ⅰ・Ⅱ合同開催】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:石川日出志(考古学・教員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉原荘介と日本考古学界の組織化 :1940年代後半~1960年代前半 SUGIHARA Sosuke : an Organizer of Japanese Archaeology for two decades after WWⅡ. by ISHIKAWA Hideshi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:野田学(英文学・教員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 演劇性という思考:ウィリアム・ハズリットのキーン評と開かれた自己
Theatricality as a way of thinking: Open self in William Hazlitt’s reviews on Edmund Kean by NODA Manabu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年5月23日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:湯淺 幸代(日本文学・教員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『源氏物語』玉鬘の筑紫流離について
by YUASA Yukiyo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:石川 日出志(考古学・教員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「漢委奴國王」金印の複眼的研究
Interdisciplinary study of the gold seal“Kan no Wa no Nakoku no O” by ISHIKAWA Hideshi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年6月6日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:神鷹 徳治(日本文学・教員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那波道圓刊本白氏文集の底本について
On the Sources of NAHA Doen’s Edition of the HAKUSHI-BUNSHU(白氏文集) by KAMITAKA Tokuharu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:金木 利憲(日本文学・院生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『太平記』所引の『白氏文集』の本文系統
The Genealogy of the Text of Hakushi-bunshu(白氏文集) cited in Taiheiki(太平記) by KANEGI Toshinori |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 |
このページの先頭へ
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年6月20日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:黒田 彰(日本文学・佛教大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祇園精舎の鐘の声攷 ―祇園図経覚書― by KURODA Akira |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 其頗梨鐘、形如腰鼓。鼻有一金毘侖、乗金師子、手執白払。病僧気将大漸。是金毘侖、 口 説无常苦空无我(版本に拠る)とされる現行本文の、「金毘侖」なる表記には疑義があり、それは、「金昆侖」であろうことを論じたものであった。 さて、ここでなお二つの問題が、新たに生じる。祇園図経は、腰鼓のような形をした無常堂の頗梨鐘の鼻(取っ手)には、金師子に乗って、白払(払子)を持った、金昆侖がいると言うが、その昆侖とは、一体何なのであろうか。これが第一の問題である。さらに、祇園図経は、鼻に崑崙、師子を備えた、無常堂の頗梨鐘が、腰鼓の形をしていると言う(また、無常院の銀鐘は、須弥山の形をしているとも言っている)。すると、道宣は、腰鼓(須弥山)に似た鐘をイメージしている訳だが、その鐘は一体どのようなものなのであろうか。それが第二の問題である。 まず昆侖(崑崙)が、東南アジアの黒人を指すことは、既に戦前、駒井義明、桑田六郎、松田寿男などによる、纏まった考察もなされているが、第二次世界大戦後、特に中国における歴史、考古、美術分野の目覚ましい研究の進展があって、今日かなり具体的に、その内容を把握することが出来る。次いで、祇園精舎の鐘に関しては、残念ながら、そのイメージを追究する試みは、未だ管見に入らないが、昆侖の問題を考えてゆくと、興味深いことに、昆侖と地域的な分布の重なる、銅鼓という楽器が視野に入って来る。そこで、この度の私の発表においては、上記の二つの問題を考えてみようと思う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:牧野 淳司(日本文学・教員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平家物語と表白
Tales of the Heike and hyobyaku (a representative ritual text corresponding to the declaration of intent) by MAKINO Atsushi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 |
このページの先頭へ
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年7月4日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:土井翔平(考古学・院生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祇東日本における弥生・古墳時代移行期における墓制の変遷
Temporal Change in Mortuary Practices during the Transition from the Yayoi to Kofun Periods in Eastern Japan by DOI Shohei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:佐々木 憲一(考古学・教員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古墳から寺院へ
Transformation of Elite Symbolism from Keyhole-shaped Burial Mounds to Buddhist Temples in Seventh-Century Japan by SASAKI Ken'ichi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 |
このページの先頭へ
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年7月18日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:五十嵐基善(日本史学・院生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律令制下における甲の生産・運用について
About the Production and Use of the Armor under the Ritsuryō Code Rule by IGARASHI Motoyoshi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:吉村武彦(日本史学・教員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本古代における兵士徴発と戸籍制度
Census Registration System and Commandeering Soldiers in Ancient Japan by YOSHIMURA Takehiko |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 |
このページの先頭へ
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年10月3日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:井上和人(考古学・教員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平城京形制の成立
The Realization of Heijokyo Planning system by INOUE Kazuto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:十川陽一(日本史学・研究推進員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮都造営における天皇の意思伝達
The Emperor’s Orders in the Construction of Ancient Capitals by SOGAWA Yoichi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 |
このページの先頭へ
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年10月17日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:加藤友康(日本史学・教員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平安貴族の異国認識
Conscious mind about foreign countries of noblesse in Heian Period by KATO Tomoyasu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:朴知恵(日本文学・院生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『平家物語』に於ける朝鮮半島の認識 ―「医師問答」章段をきっかけに― by PARK Jihey |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 |
このページの先頭へ
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年11月14日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:須永忍(日本史学・院生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本古代における上毛野氏について
The Study of Kamitsukenushi(Kamitsukenu Clan) in Ancient Japan by SUNAGA Shinobu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:小野真嗣(日本史学・院生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂東における桓武平氏の勢力拡大と在地豪族
The Expansion of Kanmu-Heishi and the Powerful Local Clan in Bando by ONO Shinji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 |
このページの先頭へ
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年11月28日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:十川陽一(日本史学・研究推進員) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地方における官職と位階についての一考察 ―散位・勲位を通じて― A Preliminary Study on the relations between government posts and court ranks in provinces by SOGAWA Yoichi |
|||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 発表者:鈴木裕之(日本史学・院生) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 衛府下級官人の活動と職掌の継続 ―近衛府の夜行の分析を手がかりに― The study about Activity of the lower officer people in the Imperial Guards and Duties by SUZUKI Hiroyuki |
|||||||||||||||||||||||||||||
【報告要旨】 |
このページの先頭へ
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年12月5日(金) | 【文化継承学Ⅰ・Ⅱ合同開催】 | ||||||||||||||
| 発表者:石川 日出志(考古学・教員) | |||||||||||||||
| 建築学の日本考古学研究法確立への貢献 ―19世紀末~20世紀前半― by ISHIKAWA Hideshi |
|||||||||||||||
【報告要旨】 | |||||||||||||||
| 発表者:佐藤清隆(西洋史・教員) | |||||||||||||||
| 戦後イギリスにおけるシク・コミュニティの分裂とカースト制の役割 ―多民族都市レスターのシク教徒の「語り」から― by SATO Kiyotaka |
|||||||||||||||
【報告要旨】 |
このページの先頭へ
|||||||||||||||
| 2015年1月9日(金) | |
| 発表者:遠藤慶太(皇學館大学) | |
| 奈良時代の仏典書写と将来経
by ENDO Keita |
|
【報告要旨】 | |
| 発表者:沈慶昊(高麗大学校) | |
| 高句麗・百濟・新羅の公宴に関する窺見
by SIM Kyun-Ho |
|
【報告要旨】 |
このページの先頭へ
|