|
|
工学文書を作る上で,数式はなくてはならないものである.数式は物理的,力学的な関係等を厳密に示すものであるので,表記上も統一性のあるしっかりした書き方をしなければならない.細かな指定については,各学会等の規定を遵守するべきであるが,ここではごく一般的と思われることがらについて講義を行う.
数式は読みやすくするために位置合わをすることが重要であり,見た目にも美しくなければならない.一般的には以下の3種類の位置合わせ方法があり,必要に応じて適したものを選べば良い.
式には本文からの引用をするために式番号を付けるのが常識である.数式番号は通常,その行の右端に右寄せで付ける.
|
|
本文中で,式を引用する場合は,式番号を用いて「式1では...」等と用いる.英文中では,"Eq.1 shows ..."等とする.
ここではMicrosoft社の数式入力ソフトを用いることにする.このソフトウェアはMathTypeというソフトウェアのサブセットで,Wordの中から直接用いることができる.
数式を入力するには,まず,Wordで数式を入力したい場所にカーソルを置いた上で,メニューの「挿入」から「オブジェクト」を選んで「オブジェクト挿入」のウィンドウを出す.その中のリストの中から「Microsoft 数式 3.0」を選ぶ.すると,以下のような入力用のツールボックスが現れる.
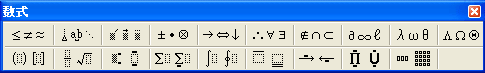
このツールボックスを駆使して数式を入力していく.以下の例を入力して練習してみよ.
=<+などはキーボードから直接打てば良い.上付,下付の指定はパレットより選ぶ.
![]()
![]()
分数や上付、下付などは数式パレットの中から適したものを選ぶ.
![]()
積分記号などは数式パレットの中から適したものを選ぶ.
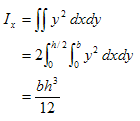
行列を表す文字は太字(ボールド)にする.これは数式エディタの中のプルダウンメニュー「スタイル」の中から「行列-ベクトル(X)」を選ぶことで設定できる.

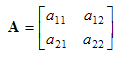
文献の引用をするには通常,文書の最後に「文献」または「参考文献」などの章を設けて,そこに参照した文献のリストを付ける.それぞれの文献には普通通し番号を付けるが,まれに著者と年号を用いて参照することもある.
引用文献が書籍である場合は,通常以下のようにする.
[リスト番号] 著者,書籍名,出版元,出版年
引用する文献が,学会や雑誌の論文である場合は以下のようにする.
[リスト番号] 著者1,著者2,「論文名」,雑誌名,巻,号,ページ,出版年月
著者数が多数の場合は最初の1,2名を書いて以下は省略する.
[リスト番号] 著者1,著者2,他,「論文名」,雑誌名,号,ページ,出版年月
論文名は""(ダブルクォート)で囲み,プロシーディングスは「Proc. of ...」,ジャーナルは「J. of ...」などと省略形を用いることが多い.ページは,「pp.最初のページ-最後のページ」とする.
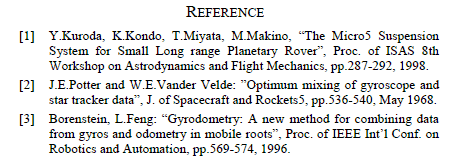
文書の最後にリストアップした文献を本文中で引用するには,以下のようにする.
...はPotter等によって示されている[2].
与えられた数式を含んだワード文書を作成せよ.(ピストンクランクの式と説明文も含む).すべての式には式番号を連番で付け,かつ簡単な式の説明文(本文)を付けること.順番は問わない.
同じワード文書中に,参考文献の章を設け,インデントをつけて綺麗にフォーマットしてみよ.さらに、この参考文献を参照して論じた本文をつけてみよ。参考にする文献は各人が持っている教科書等で良い(例:材料力学や流れ学等の教科書)。
作成したワード文書をメールに添付して提出せよ.なお,文書のフォーマットは前回指定した学会フォーマットに則ること.今回は英語のタイトル,著者名(自分の名前)を付けてみよ.ただしアブストラクトは記入しなくても良い.
添付するワード文書のファイル名は,
課題03-年組番号.doc
とせよ.(03-年組番号の部分はすべて半角で,番号は2桁)
提出期限は来週月曜午後5時までとする.
ワードによる論文作成のノウハウをさらに詳しく知りたい人は,ここを見ると良い.