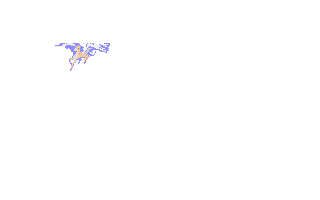HOME > 文章一覧 > このページ


『韓非子』が描く人間心理の面白さ
漢文古典の楽しみ
加藤 徹 Kato Toru [広島大学助教授]
掲載紙:『ふれあい』No.77(財団法人 納税協会連合会 納税月報臨時増刊 平成17年4月)


*二千数百年読み継がれる漢文古典
こんな笑話がある。
今から二千年後の未来。考古学者が、過去の人類の遺跡を発掘し、二十一世紀の記憶媒体の調査をした。最初に見つかったのは、フロッピーディスクやDVDなどパソコンの記憶媒体だった。二千年の歳月がたつうちに、それらは風化してボロボロの炭素の破片となり、書き込まれたデータは復元不可能になっていた。
次に見つかったのは、紙の遺物だった。紙は経年変化によって酸化し、ところどころ千切れていたが、書いてある内容はなんとか判読することができた。
最後に見つかった記憶媒体は、保存状態が完璧で、まるで昨日書かれたように文字を読むことができた。それは、二十一世紀の博物館の遺跡から発掘された、太古の時代の石板だった。・・・・・・
このジョークは、アメリカで開催された記憶媒体に関する学会のスピーチで披露されたものだというが、含蓄に富んでいる。新しいものほど、寿命が短い。昔のものは、しっかりと作ってあるので、寿命が長い。
漢文の古典もそうである。『論語』『孫子』『韓非子』など、二千数百年も前に書かれた古典は、書かれてから一度も絶版になることがなく、いまも読み継がれている。その息の長さは、驚くべきものがある。おそらく、今後の二千数百年もずっと読み継がれてゆくことであろう。
*漢文の魅力は「永遠の新鮮さ」
これは拙著『漢文力』(中央公論社刊)でも紹介した挿話だが、イギリスの戦略理論家リデル・ハートは、『孫子』を評して、この本は現代でも世界最高の軍事哲学書であり、eternal freshnessをもっている、と絶賛し た。『孫子』に限らず、漢文古典の最大の魅力はこの「永遠の新鮮さ」にあると思う。
例えば、「株を守る」とか「矛盾」という故事成語の出典として知られる『韓非子』もそうである。
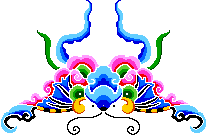 紀元前三世紀に書かれた『韓非子』の著者・韓非は、悲劇の人だった。彼は生まれながらにして重度の吃音に悩み、「口で喋るのがダメなら文章で雄弁に語ろう」と努力して名文家になった。韓非は「人間の本性は悪である」という視点に立ち、帝王たる者が天下を統治するための秘訣を書物にまとめあげた。
紀元前三世紀に書かれた『韓非子』の著者・韓非は、悲劇の人だった。彼は生まれながらにして重度の吃音に悩み、「口で喋るのがダメなら文章で雄弁に語ろう」と努力して名文家になった。韓非は「人間の本性は悪である」という視点に立ち、帝王たる者が天下を統治するための秘訣を書物にまとめあげた。
その書物は、韓非の祖国・韓ではさっぱり評価されなかった。皮肉なことに、彼の才能を評価したのは、韓の敵国であった秦の若き王、秦王政(のちの始皇帝)だった。秦王政は韓非の著作を読み「ああ、余はもしこの人と一緒に語りあうことができたら、死んでもいい」と嘆息し、奇計をもって韓非を自国に呼び寄せた。だが、秦王政の大臣は韓非の才能に嫉妬し、韓非が自分より重用されることを恐れた。大臣は讒言して韓非を入獄させたあと、ひそかに韓非に毒薬を送り、自殺を強要した。のちに秦王政が後悔し、韓非を許そうとしたとき、彼はすでに死んでいた。
秦王政は『韓非子』を熟読し、覇者となり、中国最初の皇帝・始皇帝になった。
その後も『韓非子』は帝王学のバイブルとして読み継がれた。例えば、三国志の英雄・諸葛孔明も、『韓非子』を筆写して劉備の子・劉禅に献上した。現代では、企業の管理職にも愛読されているようである。
*『韓非子』が描く人間心理の機微
◎紙幣に人物像が描かれるのはなぜ?
『韓非子』には、人間心理の落とし穴をズバリ指摘するような話が多い。例えば、次の寓話なども、二十一世紀の私たちが読んでも「なるほど」と思う。
──斉の王が、お抱えの画工に訊いた。「絵に描くのがいちばん難しいのは何か」「犬や馬でございます」「いちばん易しいのは何か」「お化けです。犬とか馬は、日常であたりまえに見慣れています。だからかえってリアルに描くのが難しいのです。ところが、お化けを見たことのある人は、めったにいません。リアルに描くのは簡単です」(『韓非子』外儲説左上)
今日のハリウッド映画の特撮でも、CG(コンピュータ・グラフィックス)でいちばん描きやすいのは恐竜で、最も難しいのは人間だという。ニセモノは、卑近なものほど作りにくい。偽造防止のため日本の紙幣に日本人の顔が描いてある理由も同じである。
一九八五年のこと。欧州の某国で、業者が安物のワインに自動車用の不凍液を混ぜ、高価な「貴腐ワイン」と偽って売っていたことが発覚し、ワインの輸入国である日本でも大騒ぎになった。これも、庶民がめったに口にできぬ高級ワインだからこその悪事だった。
◎今も昔も税務署は厳しい
また『韓非子』には納税に関する寓話もある。
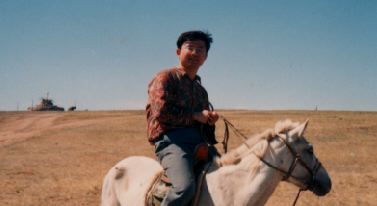 ──児説という名の論理学者がいた。彼は「白馬は馬にあらず」という有名な詭弁を展開した。その論理は見事で、同時代の学者たちは誰も反論できなかった。その彼も、白馬にまたがって関所を通るときは、係官から馬の通行税をしっかりと取られるのだった。(『韓非子』外儲説左上)
──児説という名の論理学者がいた。彼は「白馬は馬にあらず」という有名な詭弁を展開した。その論理は見事で、同時代の学者たちは誰も反論できなかった。その彼も、白馬にまたがって関所を通るときは、係官から馬の通行税をしっかりと取られるのだった。(『韓非子』外儲説左上)
たしか「ビートたけしのTVタックル」だったと思うが、論客としても有名な某国際政治学者が「税務署で署員を説得しようと頑張ったが、負けてしまいました。『朝まで生テレビ』のようにはいきませんね」と苦笑していた。今も昔も、税金はシビアである。学者の理屈なぞ通用しない。私も学者のはしくれなので、よくわかる。
◎他人の行いを美化することの危険性
また、次のようなコワイ話も載っている。
──昔、宋の都の下町に住むある男が、親の喪に服した。粗末な服を着て、最低限の飲食しかせず、すっかり体をこわした。これを訊いた殿様は「あっぱれな孝行者だ」と感心し、彼を役所の長に抜擢した。翌年、親の喪に服して衰弱死した者が、十人を越えた。(『韓非子』内儲説上)
これを読むと、私は、昭和六十一年(一九八六)の事件を思い出す。十八歳の女性アイドル歌手が、白昼、ビルの屋上から飛び降り自殺した。テレビのワイドショーは連日、悲しい音楽とともに、泣きながら現場に花束を供えるファンたちの映像を流した。その結果、多くの少年少女が「あんなふうに悲しんでもらえるなら、自分も」と思い、後追い自殺をとげた。統計によると、その年、飛び降り自殺した十代少女の数は、前年比三倍以上の一六二人に達した。
◎優しい上司の部下は過労死の危険が大きい?
次の話は、連日の「サービス残業」でヘトヘトのサラリーマンが読むとゾッとするかもしれない。
──史上、孫子と並び称される兵法家である呉起が、魏の将軍となり中山国を攻めた。ある兵卒が、腫れものができて苦しんだ。将軍である呉起は、その無名の一兵卒のために、ひざまづいて腫れものの膿を吸い取ってやった。それを伝え聞いた兵卒の母親は、悲しげに泣いた。ある人が「息子さんは、将軍様にあんなに大事にしてもらっている。どうして悲しむの?」と訊くと、母親は答えた。「あの子の父親も兵隊でしたが、昔、同じように呉起将軍に膿を吸ってもらい、その恩義に感激し、戦場でも逃げずに戦死しました。今度は、あの子も死んでしまうことでしょう」(『韓非子』外儲説左上)
現代でも、酷薄な上司がいる職場では「過労死」は起きない、と言われる。むしろ、人間関係が円満でアットホームな職場ほど、自分だけ「休暇をください」と切り出しにくいため、過労死してしまう危険が高いらしい。
◎上に立つ人は時に厳しい評価をするが、見るべきところを見ているものだ
このように『韓非子』は、人間心理の隙間を指摘するコワイ話を多く載せるが、中には次のようなホッとする話もある。
──昔、孟孫氏の殿様が猟に出て、子鹿を捕まえた。家来の秦西巴に命じて、獲物を車に載せて屋敷に帰った。母鹿が車のあとを追ってきて、悲しげに鳴いた。秦西巴はこっそり子鹿を逃がし、母鹿に返してやった。
屋敷に着くと、殿様は「子鹿はどこだ?」と訊いた。秦西巴は「あわれなので逃がしました」と正直に答えた。殿様は「軟弱者め」と怒り、秦西巴を屋敷から追い出した。
それから三ヶ月後。殿様は秦西巴を呼び戻し、わが子の養育係に取り立てた。侍従は不思議に思い「なぜわざわざ一度クビにした者を呼び戻し、若君様のお守り役に抜擢なされたのですか」と訊いた。殿様は「あの男は、鹿にさえ優しい。きっと、わしの子にも優しくしてくれるだろう」と答えた。(『韓非子』説林上)
上司はちゃんと見ている。だから自然体で働くのが、結局は一番いい。窓際族になることを恐れて無理に自分をつくろう必要なんか、ないんだよ。と、現代のサラリーマンを励ますような寓話である。
去年から今年にかけては「日露戦争百周年」とかで、テレビや雑誌で乃木希典大将の写真をよく見かける。この乃木大将にも、これと似たエピソードがある。
明治四十一年(一九〇八)、アメリカで開催される世界美人コンテストの日本代表を選ぶため、日本最初の素人女性を対象とする美人コンテストが行われた。明治の頃だから水着審査などはなく、彫刻家の高村光雲を含む審査員たちは、和服姿の白黒写真を見て審査した。その結果、小倉市長の十六歳の令嬢で、学習院中等科三年生の末弘ヒロ子が、最初のミス日本に選ばれた。
ヒロ子が普通の学校の生徒なら、何の問題もなかった。だが、彼女は華族の学校である学習院の生徒であり、しかも院長(校長)はあの乃木大将だった。乃木は「けしからん」と激怒し、ヒロ子を退学処分にした。そもそもコンテストには、ヒロ子の義兄が当人に内緒で写真を送ったもので、彼女自身は応募したことも知らなかった。しかし、ヒロ子は退学処分を受け入れた。
その後、乃木は意外な行動をとった。彼みずからが媒酌人となって、ヒロ子を、陸軍元帥で侯爵の野津道貫の跡取り息子と結婚させたのである。ヒロ子は侯爵夫人になったわけで、当時としては最高の玉の輿であった。
乃木の真意はわからない。もしかすると「美しすぎるヒロ子は、学習院の生徒としてはふさわしくないが、妻としては最高である」と考え、彼なりのけじめをつけたのかもしれない。
* * *
下の画像をクリックしてみてください。
 
|
『韓非子』を他の人が読めば、もっと別の「思い当たるふし」を連想することであろう。各人がそれぞれ勝手な読み方ができるのも、古典ならではの懐の深さである。
『韓非子』に限らず、『論語』も『孟子』も『老子』も『荘子』も、漢文の古典を読むと、人間の本質をズバリ指摘され、思わずハッとする面白さがある。しかも、例えば中学生のときに読んだ『論語』を中年になって読み返すと必ず新しい発見がある、というような、自分自身を発見する楽しみもある。
漢文の古典が、二千数百年ものあいだ一度も絶版にならずに読み継がれてきた理由は、たぶん、こんなところにもあるのだろう。
[加藤徹 略歴]=省略
(2005年2月)


HOME > 文章一覧 > このページ








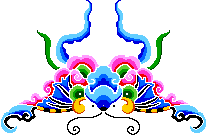 紀元前三世紀に書かれた『韓非子』の著者・韓非は、悲劇の人だった。彼は生まれながらにして重度の吃音に悩み、「口で喋るのがダメなら文章で雄弁に語ろう」と努力して名文家になった。韓非は「人間の本性は悪である」という視点に立ち、帝王たる者が天下を統治するための秘訣を書物にまとめあげた。
紀元前三世紀に書かれた『韓非子』の著者・韓非は、悲劇の人だった。彼は生まれながらにして重度の吃音に悩み、「口で喋るのがダメなら文章で雄弁に語ろう」と努力して名文家になった。韓非は「人間の本性は悪である」という視点に立ち、帝王たる者が天下を統治するための秘訣を書物にまとめあげた。