拙著『京劇』について
2002年2月11日(月) 最新の更新 : 2021年2月21日
このページの目次
- 基本データ 書名、出版社、ISBN番号、価格、体裁、内容
- 「著者から読者へ」 中公叢書の背表紙の定版です
- 漢詩 [拙著の書後に題す]
- 2002年サントリー学芸賞受賞(芸術・文学部門)
[参考]2002年サントリー学芸賞のページ(受賞者一覧、選評、等)
- 新聞等に載った書評・紹介(日付の新しい順に掲載)
- 第24回サントリー学芸賞・選評「その面白さに思わず引き込まれると言っても過言ではない」(by 大笹吉雄先生)全文はこちらをクリック
- 『シアターアーツ』17(晩成書房、2002年8月20日)p.127-p.128 書評「加藤徹『京劇』の記述方法」(by 瀬戸宏先生)
- アルク月刊『中国語ジャーナル』2002年5月号「今月のイ・チ・オ・シ !」掲載 「評者は350余ページに及ぶ本書を半日で一気に読み通してしまった」「京劇や芝居に縁のない読者もこの本の面白さには必ず引き込まれ、飽きることがないだろう」
- 内山書店「中国語」4月号 「野心的労作」
- 日本中国文化交流協会「日中文化交流」No.665(3月1日)掲載「痛快とも言える京劇通史になっている」
- 毎日新聞 2月10日(日)掲載「楽屋裏から何が見えてきたか」
- 朝日新聞 2月10日(日)掲載「革命にも影響したその魔力とは」
- 共同通信社 2月8日(金)配信「中国近現代の象徴・京劇に生きた人々のドラマ
」
- 日本経済新聞 2月3日(日)掲載「政治の動き視野に歴史活写」
- 時事通信社 2月?日配信「楽しく知る中国近現代」
- ちょっと意外(?)な反応
- 正誤表 文字の間違い等。
- 拙著『京劇』所蔵大学図書館一覧(NACSIS Webcat 検索結果)
補足 読売新聞 2021年2月21日(日)
|
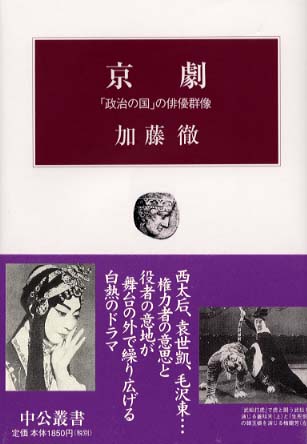 『京劇 「政治の国」の俳優群像』
『京劇 「政治の国」の俳優群像』
(きょうげき 「せいじのくに」のはいゆうぐんぞう)
加藤 徹 [著]・中公叢書(そうしょ)
出版社:中央公論新社
発行:2001-12-20 発売:2002-1-9
体裁:358p 19cm(B6)
ISBN:4120032248 価格:本体1,850円
内容:
はじめに
第1章 京劇形成までの道のり―清初から乾隆帝まで
第2章 清朝の衰退、京劇の発展―十九世紀初頭から清末まで
第3章 近代化への苦しみと京劇―辛亥革命から民国初年まで
第4章 京劇の黄金時代―慢性的内戦と平和
第5章 戦火と京劇―満洲事変から国共内戦まで
第6章 国をあげての京劇改革―建国前後から文革前夜まで
第7章 革命模範京劇の時代―文化大革命期
第8章 グローバル時代の京劇―市場経済の荒波の中で
あとがき
考文献一覧・索引
読売新聞 2021年2月21日(日曜)第9面文化欄より
[始まりの1冊]『京劇 「政治の国」の俳優群像』 2002年 加藤徹さん
京劇通して中国史に光
京劇は中国の伝統演劇だ。英語でペキンオペラと言う。日本でいえば歌舞伎にあたる。英文学者が「私の専門はシェイクスピア劇です」と言うと尊敬される。が、中国文学研究者が「専門は京劇です」と言うと、中国人に「えっ?」と驚かれることがある。
18世紀の末に北京で生まれた京劇は、芸術というより娯楽だった。歌舞音曲や立ち回りなど名人芸の集大成だった。庶民だけでなく、咸豊(かんぽう)帝や西太后、毛沢東ら歴代の権力者も京劇に熱中した。政治家の周恩来は、学生時代は美しい女形として名を馳(は)せ、首相となったあとも、女形の名優・梅蘭芳(メイランファン)の京劇団を日本に送りこむなど京劇をしたたかに活用した。毛沢東も京劇の愛好家で、京劇を愛唱しただけでなく、「文化大革命」の発動にも京劇を利用した。
日本人との縁も深い。京劇史上初の海外公演は1919年、梅蘭芳の一座による来日公演だ。当時の中国のインテリは、京劇を中国の後進性の象徴として恥じた。芥川龍之介は、中国人が気づかぬ京劇脚本の斬新な文学性を発見し、中国文芸界のリーダーである胡適に京劇改革をアドバイスした。葛飾北斎の浮世絵の真価を発見したのがゴッホやマネだったのと似ている。日本人だからこそできる京劇研究もあるはずだと、今思うと冷や汗ものの気負いで書いたのが、本書である。
執筆のきっかけは突然だった。ある日、中央公論新社の編集者・宇和川準一氏から「本を書きませんか」と連絡をいただいた。以前「嘉藤徹」というペンネームで書いた歴史小説『倭の風』(PHP研究所、1996年刊)を読み、興味をもってくださったのだ。相談の末、中公叢書(そうしょ)で京劇史を書くことにした。実名では最初の一冊である。
当時、住んでいた寓居(ぐうきょ)は狭く、押し入れがデスク代わりだった。「賞を狙いましょう」という編集者の言葉を励みに「京劇から激動の近現代史を読み解いてやる」と意気込みだけは壮大だった。京劇界のパトロンたる歴代の権力者の意思と、芸人の意地。辛亥革命、日中戦争、文革などの激動に翻弄(ほんろう)された人生の数々。
学術書なので、大胆な仮説や理論的な考察も述べた。古代ギリシャ以来、演説術と結びついた演劇を育んだ西洋文明と、京劇を生んだ中国文明の違い。中国のメタ伝統(伝統をどう扱うかという伝統)と、日本のそれとの比較。言論統制が厳しかった近世の中国で、京劇は満州人に支配されていた漢民族の民衆の不満の「ガス抜き」効果もあったこと。その他、文革中の迫害死も含め、中国の研究者が書きづらそうなことも、あえて書いた。
誤算もあった。見返しの著者近影を決めるとき、冗談のつもりで、北京の結婚写真館で撮影した写真も候補に混ぜた。私の妻は中国人である。中国では結婚前にコスプレじみた記念写真を撮る。編集者は、国籍不明の演歌歌手のような扮装(ふんそう)をした私の写真を見て爆笑し「これでいきましょう」と即決してしまった。
筆力の未熟さや肖像写真のキッチュさにもかかわらず、京劇そのものの面白さのおかげで、本書は意外な好評を得た。学術書なのに文革のくだりで泣いた、という読者もいた。サントリー学芸賞までいただいた。
始まりの一冊は、恥ずかしく、なつかしく、またいとおしくもある。
かとう・とおる 1963年、東京都生まれ。明治大教授。専門は京劇をはじめ中国の演劇・文学・音楽など。著書に『日中戦後外交秘史』(共著)、『西太后』『貝と羊の中国人』『本当は危ない「論語」』など多数。
[近況]
新型コロナの流行後、中国へ出張して京劇を見たり、来日公演を見たりする機会がなくなったのは残念です。1月末、NHK出版から出した『漢文で知る中国』の中でも、梅蘭芳の京劇にメロメロになった与謝野晶子の挿話をはじめ、京劇についてもいろいろ書きました。
|
※同紙面の「よみうり堂から」より引用。引用開始。
◆優れた本が生まれるきっかけは、「壮大なむちゃぶり」であることが多いようです。きょうの「始まりの1冊」も、中国文化学者の加藤徹さんが「冷や汗ものの気負い」で書き上げたもの。編集者が投げてくるむちゃな球を、見事に打ち返してみせる物書きの気迫。本作りは真剣勝負です。(良)
引用終了
「著者から読者へ」
中公叢書の裏表紙の定版です。拙著の背表紙に書いた文章です。
中国演劇の俳優は、肉体を極限まで酷使する超人的な表現能力を要求された。彼らは強靭な意志力を持ち、舞台上だけでなく舞台外でも、熱い人間ドラマを繰り広げた。西太后、袁世凱、毛沢東など時の最高権力者と結びついたり、芥川龍之介やチャップリンなど外国の文化人と交流した。また、抗日戦争や文化大革命の嵐のなかでも自己のプライドを貫いた。本書は京劇俳優たちの人生を取り上げ、中国史の知られざる一面に光を当てると同時に、日本の近代の歩みについても見つめ直そうとする自戒の書である。
書評・紹介
おかげさまで、新聞等の読書欄・書評欄に取り上げていただきました。(この項、随時更新します)
[参考リンク : BookWeb仮想書棚・新聞掲載書評(紀伊国屋書店のHPの一部)]
「毎日新聞」2002年2月10日(日)第10面に掲載された書評↓
「京劇はもとより、中国を知るためにも役立つ一冊である」
注 : (ふりがな)は原文どおり。赤字指定は加藤。
張 競 [評]
京劇 「政治の国」の俳優群像 加藤徹著(中公叢書・1850円)
楽屋裏から何が見えてきたか
本物の京劇通でなければ書けない本だ。とにかく、そのマニアックぶりは半端ではない。北京の劇場に通い詰め、好きな演目の録音を数百回も聞く。あらゆる演劇資料を収集し、みずから京劇の舞台に上る。もはや「研究」の領域をはるかに超え、文字通りの京劇オタクである。
マニアなら内輪の感性でしか語れない。しかし、本書では京劇ファンとして体験したおもしろさが素人にもわかるように伝えられている。むろん、そのおもしろさとはたんに演劇的な側面ではない。京劇を通して、中国人自身も気づかない長所と弱点が見えてきたから興味が尽きない。
歌舞伎とは違い、中国では市場経済が実施されるまで、京劇は政治生活のなかで特別な位置を占めていた。一九四九年から文化大革命が終了した一九七六年まで、ほとんどの政治活動は京劇と何らかのかかわりを持っていた。どの演目を上演し、歌詞やセリフの一字一句をどうするかも政争のカードになる。じじつ、文化大革命が京劇『海瑞罷官(かいずいひかん)』批判からはじまった。新作の芝居は国家の指導者からお墨付きをもらわなければ、一般公開もできない。
そのことはしばしば政治体制の弊害だと見られがちだが、必ずしもそうではない。京劇に対する権力の介入は近代以前にさかのぼる。皇帝が脚本を改編させ、楽器を指定し、あるいはみずから作詞することはけっして珍しいことではなかった。現代政治と京劇の腐れ縁は由来が古い。
康煕(こうき)帝、乾隆帝をはじめ歴代の清朝皇帝たちはみな京劇好きである。というより、彼らこそこの演劇芸術の生みの親といっても過言ではない。もしその後ろ盾がなかったら、中国南部の一地方芸能がここまで大きく発展することもなかったであろう。
近代に入ってからも、袁世凱をはじめ歴代の支配者たちは京劇に並々ならぬ関心を示した。識字率が低かった当時、京劇は政治宣伝の格好の道具である。権力を固めるためにも利用しない手はない。
京劇の変遷をたどりながら、俳優の人物伝を紹介するのは気の利いた工夫だ。二本の軸を交差させることで、過去の再現に臨場感がもたらされた。しかも名優ばかりに目を向けるのではない。歴史に忘れられた人たちにも光が当てられた。大文字の歴史から抜け落ちた部分が無名人の生々しいディテールによって取り戻された。
数々のエピソードによって、政治風土のきびしさがクローズアップされた。京劇は権力の中心にあまりにも近かったために、脚本家や俳優は権力者の逆鱗に触れたり、権力争いの巻き添えを食らったりすることは珍しくない。雍正(ようせい)帝に余計な質問をしたから、打ち殺された俳優もいれば、西太后を怒らせたために命を落とした伴奏者もいた。現代でも京劇の脚本を書いただけで、凄絶な迫害を受けた人がいる。『海瑞罷官』の作者呉晗は本人のみならず、家族も刑務所に入れられた。二十二歳の長女は獄死し、生き残れたのは未成年の息子一人だけである。涙なしでは読めない悲劇だ。
民衆の娯楽にしては、京劇はあまりにも多くのものを背負わされすぎた。異民族支配、軍閥混戦、列強の蹂躙(じゅうりん)、内部の権力争い。時代の荒波に翻弄されつづけてきた京劇は苦難の近代史の縮図でもあった。激越な節回し、派手な立ち回りの裏に展開されたもう一つの波瀾万丈のドラマは、本書によって明かされた。京劇はもとより、中国を知るためにも役立つ一冊である。
この書評の全文は、以下のサイトにも掲載されています。
[毎日新聞・今週の本棚(2/10号)に掲載された拙著の書評]
|
「朝日新聞」2002年2月10日(日)第22面に掲載された書評↓
「京劇は、その誕生のいきさつからして政治がらみだったのだ」
[評者] 津野海太郎(編集者・和光大教授)
革命にも影響したその魔力とは
六〇年代の中国で文化大革命のきっかけになったのは『海瑞罷官(かいずいひかん)』という新作京劇だった。そして当の「文革」の旗印とされたのも江青夫人肝いりの八つの革命模範京劇。ふしぎだ。日本の演劇、たとえば歌舞伎にそんな政治的魔力があるだろうか。
いや、そんなのすこしもふしぎじゃないよ、と著者はいう。満州族出身の清朝の皇帝たちは、漢民族統治のために、さまざまな地方劇を利用した。ひとつには異民族の心性を知る情報源として。ひとつには大衆の人気あつめのための官能的なアメ玉として。こうして十八世紀末、そのころ北京でもっとも人気のあった安徽省の地方劇をもとに京劇が生まれてくる。すなわち京劇は、その誕生のいきさつからして政治がらみだったのだ。
こうした傾向は辛亥革命以後の近代中国にもひきつがれた。革命に荷担(かたん)して銃殺された王鐘声(おうしょうせい)以下、はでな化粧の下に本音をかくしたり、かくしそこなったりした俳優たちのエピソードがつぎつぎに紹介される。女形の梅蘭芳(メイランファン)がヒゲをのばして日本軍占領下の舞台に立つのをこばんだ「蓄鬚明志(ちくしゅめいし)」の話もでてくる。
中国共産党とはあんがい相性がよかったようだ。マニア級の戯迷(シーミー)(京劇ファン)だった毛沢東や周恩来の庇護(ひご)のもとで、劇団や教育のシステムが整備され、女形が廃され、演目の改訂がおこなわれた。この国政レベルでの改革運動によって、それまでの民間の「小伝統」だった京劇が、はじめて国を代表する「大伝統」につくりかえられる。ところが、文化大革命の熱狂のあと、京劇人気はしだいにおとろえ、いまやナショナリズムの文化的象徴としての求心力は、ほぼ完全に失われてしまったのだとか。
著者はインターネットに「京劇城」というサイトをひらいている(http://home.hiroshima-u.ac.jp/cato/KGJ.html)。「京劇の世紀は終わった」というわりには、たいへん熱っぽい。二十年来の戯迷の意地なのだろう。
評者・津野海太郎(編集者・和光大教授)
(中公叢書・358ページ・1850円)
*
かとう・とおる 63年生まれ。広島大助教授。「嘉藤徹」名で『倭の風』など小説執筆も。
この書評の全文は「BOOKアサヒコム」のホームページの「朝日の紙面から」のコーナーに掲載されておりますので、そちらをご覧下さい。以下のURLをクリックすると飛べます。↓
http://book.asahi.com/review/index.php?info=d&no=1138
|
「共同通信社」2002年2月8日(金)配信記事↓
「巨視的な視野から深く鋭く京劇をつかみ、近現代史とそこに生きた人々を新たな視角から描き出している」
注 :赤字指定は加藤。
[掲載紙]- 2月10日(日)「北日本新聞」(9面)「歴史追い真の姿に肉薄」
「山陰 中央新報」(8面)「舞台の外のドラマ描く」
「北國新聞」(27面)「照射された中国の近現代」
- 2月17日(日)「中国新聞」(20面)「舞台の外の人物・実態追う」
「河北新報」(東北地方)「近現代中国の姿を照射」
ほか・・・(以下、調査中)
中国近現代の象徴・京劇に生きた人々のドラマ
『京劇 「政治の国」の俳優群像』加藤徹著 中央公論新社
波多野 真矢(立教大講師)
中国と日本は国交回復から今年で30年の時を経た。中国に関する情報も関心も増加の一方だが、この30年の間に両国民がお互いをどれほど知り得たと言えようか。京劇についても、訪日公演も頻繁に行われ、近年入門書や脚本梗概も出版されるなど、一通りの紹介はされてきた。しかし、京劇は近現代中国において単なる演劇を越えたある種「象徴的」な存在であったから、京劇の諸要素や約束事を知り舞台を見る、つまり「舞台の上のドラマ」だけでは、京劇の真の姿に肉迫することはできない。
この著作は、京劇入門的解説はあえてせず、京劇成立以前の清初から現代に到るまでの京劇の流れを、紀伝体風に人物・事例を紹介し論述したノンフィクションである。また幕間戯として、各章の間に本文に関連した「女形と女優」「創造的破壊に寛容だった京劇の「流派」」等の解説や私見が配され、京劇の楽器のコンセプトなど、著者の独創に富んだ分析も随所に盛り込まれている。これまでにない、日本の一般の読者が手軽に読め、京劇の流れを追い京劇の実態を知ることのできる画期的な著作であろう。また、京劇を主題としつつ、ネガとポジのように逆に京劇を通して近現代の中国の姿、日中関係の有り様が照射されており、巨視的な視野から深く鋭く京劇をつかみ、近現代史とそこに生きた人々を新たな視角から描き出している。並大抵ではない著者の京劇に傾ける情熱の結晶した労作である。
取り上げられた人物は、皇帝、権力者、役者、作曲家、歴史家、観客、外国人など多岐にわたり、それぞれに実に興味のつきぬドラマを繰り広げるが、中でも上海の役者・蓋叫天、女優・劉喜奎、「海瑞罷官」の作者で文革で無念の死を遂げる歴史家・呉晗などの生き様は、胸を打つ。京劇の舞台そのものではない「台下戯」(舞台の外のドラマ)を描きながら、むしろ「生きた京劇」がここに刻まれている。
|
「日本経済新聞」2002年2月3日(日)第22面に掲載された書評↓
「この伝統芸能の光と影をダイナミックに描き出している」
注 : 赤字指定は加藤です。
京劇 加藤 徹著
政治の動き視野に歴史活写
本書はいわゆる京劇入門書ではない。京劇俳優の人生と京劇の歴史を照らし合わせ、この伝統芸能の光と影をダイナミックに描き出している。
京劇は清朝(しんちょう)の乾隆帝時代、北京に進出した安徽省(あんきしょう)の四劇団を中心に形成された。その後、咸豊帝(かんぽうてい)や西太后も京劇を宮廷内で上演させ、俳優に厳しく注文をつけた。京劇は発生時から権力に近く、識字率が低い当時の中国では、演劇は政治宣伝の道具だった。
しかし、日中戦争時、名女形(おんながた)の梅蘭芳(メイランファン)は、愛国心からヒゲを生やし抗日の姿勢を示した。同じ女形、程硯秋(ていけんしゅう)は日本側主催のチャリティー公演出演を拒否、これ以上京劇を続けられないと北京郊外の農村に引きこもった。気骨のある俳優もいたのだ。
中国共産党も京劇を宣伝手段として重視した。文化大革命も歴史京劇「海瑞罷官(かいずいひかん)」の批判から始まった。文革期は伝統京劇は舞台から消え、「紅灯記(こうとうき)」など新しく作られた革命模範劇がもっぱら上演された。自己批判を迫られ、不遇のうちに亡くなったベテラン俳優も多い。
毛沢東は晩年、古典京劇を見たいとの思いを募(つの)らせた。また当局も「伝統演劇の俳優は年取っており、今、記録しておかないと伝統演目は消滅してしまう」との危機感から、上演禁止となった演目も含め極秘裏に映画撮影を進めたという。広島大学助教授の著者は、若いころ京劇の舞台に立ったり歌詞を自作したりした京劇通で、この演劇の波乱の歴史を、挿話(そうわ)をちりばめながら活写している。(中央公論新社・一、八五〇円) |
「時事通信社」配信の書評(評者: 金文京先生)↓
「経済発展著しい最近の中国に対しては、一部で脅威論もささやかれ始めているが、このような時機にこそ、漢詩や漢文だけでなく、本書が述べるような今の中国の生きた文化を理解する必要があろう」
注 : 赤字指定は加藤です。
[掲載紙] 神奈川新聞 京都新聞 ほか
京劇 加藤徹著
楽しく知る中国近現代
歌舞伎ブーム、オペラブームといわれる昨今であるが、音楽、歌と結び付いた演劇として、もう一つ忘れることのできないのは中国の京劇であろう。中国武術に通じる激しい立ち回りで、見る者を魅了する京劇は、近年日本で上演される機会も増え、ファンも多い。その京劇について、これまでも概説書やガイドブックが幾つか出版されているが、本書の特徴は、京劇を通して中国の近現代史が概観できる点にある。
京劇が生まれたのは異民族である満州人が中国を支配した清朝、その最盛期はアヘン戦争以後の苦難の歴史と重なる。そして辛亥革命による中華民国成立、日中戦争、社会主義中国の誕生から文化大革命を経て今日の開放経済の時代に至るまで、京劇は常に民衆の娯楽として愛好され、またその時々の権力者とも密接な関係を持ちながら、政治と時代の変化にほんろうされる波乱の道を歩んできた。そこからは通常の歴史書では読み取れない中国近現代の意外な、そして複雑な姿が浮かび上がってくる。無論、京劇自体の説明にも十分なスペースが割かれていて、入門書としても役立つ。
著者は中国文学の研究者で、北京大学留学時代に京劇の俳優としての修行を実地で積んだ異色の経歴を持ち、かつ最近では歴史小説をも物するという才人。本書にも、芥川龍之介の京劇観や名優、梅蘭芳(メイランファン)が日本公演の時に広島の被爆者のためにチャリティー公演を行った話、さらに市川猿之助のスーパー歌舞伎と京劇のかかわりなど、随所に興味深いエピソードがちりばめられていて、学術的でありなが、肩の凝らない、面白い読み物になっている。
経済発展著しい最近の中国に対しては、一部で脅威論もささやかれ始めているが、このような時機にこそ、漢詩や漢文だけでなく、本書が述べるような今の中国の生きた文化を理解する必要があろう。日本人がよく知っているようで実はよく知らない中国という隣人と、より深く付き合うためにも、それは重要である。(京都大学教授・金 文京) (中央公論新社・一八五〇円) |
ちょっと意外な(?)反応
今まで筆者のもとに届いた感想の中から、いくつか要約してご紹介します。
- 「著者近影を見て、思わず、アッ、という声をあげてしまいました」(同様の感想多数)
- 「すばらしい本を出してくださり、ありがとうございました」(拙著発売直後にご丁寧な手紙をくださった、ある在日の京劇プロ俳優)
- 「特に名を秘す、としたところを、今度こっそり教えてください」(あるマスコミ関係者)
- 「まるでその場で見てたみたいな書き方ですねえ(笑)」(ある理科系の教授)
- 「いつのまに書いたの?」(ある同僚)
- 「自分が長い年月をかけて書きたいと思っていた本を、先に書かれてしまった、という思いです」(ある高名な先生)
- 「通勤電車のなかで読んでいたのですが、蓋叫天(がいきょうてん)の最期のところを読んで、涙がこぼれそうになり、『マズイ、ここで泣いたら周囲の人に変に思われる』と思い、途中下車しました」(ある心優しき女性)
『京劇』正誤表
拙著のミスを見つけました。お詫びのうえ、以下のように訂正いたします。(この項、随時更新いたします)
- 122頁3行 (誤)パルムード賞 → (正)パルムドール賞
- 162頁9行(誤)Cehney → (正)Cheney
- 202頁 図表 京劇旧本・京劇新本・江蘇省淮劇の歌詞
(誤)開封→ (正)開封府
- 226頁12行 (誤)一九九五年十二月号 → (正)一九五五年十二月号
- 301頁上・後から3行、および345頁下・後から5行(誤)『芸海浮沈・・・ → (正)『芸海沈浮・・・
- [索引] 353頁左・16行(誤)『新・瑚蝶夢』 → (正)『新・蝴蝶夢』
- [索引] 354頁左・2行(誤)『謝雁記』 → (正)『射雁記』
上記のほかにもミスがあることと存じます。もし、お気づきの点をメールで私までお知らせくださるか(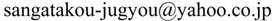 )、弊サイトの「京劇掲示板(http://6622.teacup.com/cato/bbs)」にお書き込みくだされば、幸甚に存じます。
)、弊サイトの「京劇掲示板(http://6622.teacup.com/cato/bbs)」にお書き込みくだされば、幸甚に存じます。
[拙著の紹介に戻る]
[京劇城へ行く]
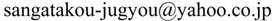 )、弊サイトの「京劇掲示板(http://6622.teacup.com/cato/bbs)」にお書き込みくだされば、幸甚に存じます。
)、弊サイトの「京劇掲示板(http://6622.teacup.com/cato/bbs)」にお書き込みくだされば、幸甚に存じます。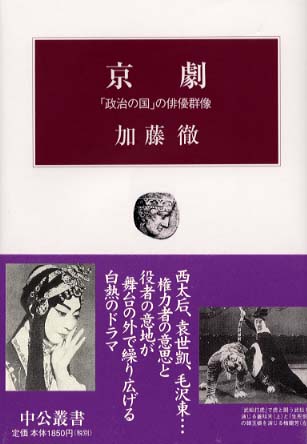 『京劇 「政治の国」の俳優群像』
『京劇 「政治の国」の俳優群像』