����ʂ����n��i�É������E���j�������ւ̊w���Q��
�l�b�g���[�N�ɂ��m�o�n�^�V���N�^���N�̎���
���@���@�@���@��
������w���Ȋw�Z���^�[
takane@isc.meiji.ac.jp
�� �� �� ��
�@�{�́A�ߑa�����i�s����É������E���̒n�抈�����̋�̍�ɂ��Ċw���ɃC���^�[�l�b�g�����p���l�Ă����A���̃v���[���e�[�V�������ۑ�Ƃ��čs�Ȃ�������E�����ɂ��Ă̕ł���B���{�����͖{�N�A�O���J�u�̎��Ƃł���B���̍ہA�ȉ��̂��Ƃɗ��ӂ����B
�@���́A��w�̐l���E�Љ�Ȋw�ɂ�������S�ʂɋ��ʂ�����@�_�̒B���ɁA�w���ɑ��铮�@�t���̕��@�B��O�́A�������Ƃ̓���(1)�A��w�̋���E�����Ɗw�O�Ƃ̒�g�ɂ��V������w�̂�����̖͍��ł���B���Ɋe���ɂ��ďq�ׂĂ䂫�����Ǝv���B
�P�@���C�w���̏�
�@�҂�������w�ŒS�����Ă������b�_�T�͗��H�w���������S�w�����ʂ̉Ȗڂł���B���C��̈ʒu�t���͊e�w���ɂ��قȂ�B���C�N���͈�E��N���ł���A�҂̏ꍇ�A�Ηj�����_�w���̊w��68���A���j�ꎞ���E�����@�w�E���w�E���o�E���w�E�o�c�̊e�w��39���̌v108���ł���B
�@����ɂ���ɉ����Ęa����w�o�ϊw���ŒS�����Ă���u���u�s���̃V�X�e���Ɖ^�p�v�̎�u�Җ�50�����O��������Q�������B�a���̊w���͍s���w�ɂ��Ĉ��̒m����L����̂ŁA��s���������̊�b�_�ɂ��Ă͎��ƗpWeb�̉{���ɂ��A�]�O�̓W�J�𗝉������A�O���̖��ɊȒP�ȉۑ���s�Ȃ킹���B�����āA�Ċ��x�ɂɂ�荂�x�ȉۑ��^���A������{�i�I�ȎQ����\�肵�Ă���B
�@�Ȃ��A�����̊w���̐��т͉��L�̒ʂ�ł���
|
�_�@�� |
�l�@�� |
|
90�_�ȏ� |
21 |
|
80�_�ȏ� |
29 |
|
70�_�ȏ� |
36 |
|
60�_�ȏ� |
3 |
|
�s �� �i |
19 |
|
���@�@�v |
108�� |
�O��13�`15��̎��Ǝ����Ŋe�\�t�g�̑�����擾���A���ӎ��������ĉۑ�쐬�Ɏ��g�ނ̂́u��b�v�_�Ƃ��Ă͖��炩�ɓ��e�I�ɍ��x�ł���B�������A����A
�����w�Z�܂ł̏�炪�[�����邱�Ƃ��ӂ݂�ƁA��{���e���V�[�͎擾�ς݂ƂȂ����w���ɑ��鋳���z�肷�邱�Ƃ��K�v�ł��낤�B
�Q�@���̑g�D��
�@��w�ɂ�������̊�{���O�Ƃ́A���Ȃ��Ƃ��R���s���[�^���g�������ł͂Ȃ��A�R���s���[�^�[�����������邱���łȂ���Ȃ�Ȃ��B�܂�A���Z�p�̍��x�����̂��̂́A�{���̖ړI�ł͂Ȃ��B
�@�T�^�I�ȕ��Q�͖ړI�ӎ�������Ȃ��܂܂ɍs�Ȃ��錾��E�v���O���~���O����ł���B���݁A����ɂ��Ă͗l�X�ȋ����@���l�Ă���Ă��邪�A���n�Ɍ����Ă݂�ƁA������A���́u���O���ꉻ�v�ƂȂ錙�������顂����ŁA���n�̏����X�L���̍��x���ł͂Ȃ��u���̑g�D���v�Ƃ����ϓ_����l�������K�v������B
|
���̑g�D�� |
||
|
�i�@�K |
�e�[�} |
������e |
|
���x���T |
�����W |
��� |
|
���x���U |
��� |
�G�N�Z���E���[�h�� |
|
���x���V |
��M |
���ϗ��A�g�o�쐬 |
|
���x���W |
���������锭�M �i���Љ�ւ̎Q���j |
�v���[���Ƒ��ݕ]�� |
|
���x���X |
���Љ�ւ̎Q�� |
�w�O�Ƃ̐ړ_�̍\�z |
�@�u���̑g�D���v�Ƃ͏��̗��O���u���l�`������ӎv����Ɏ����i�Ƃ��ď��̃e�N�m���W�[���������邱�Ɓv�ƈʒu�t���A���̉ߒ������̎��W�A���́A���M�A���������锭�M�A���Љ�ւ̎Q��̔��W�i�K�Ƃ��Ē�`�������̂ł���B
�R�@����E�����E�w�O�̎O�Ғ�g
�@����E�����̒�g�ɂ��ẮA��ʂɁg�w���Ƃ̑Θb�������ւ̎h���ɂȂ�h�Ƃ����B���Ŋ��o�I�Ȃ��Ƃ�������ɂ������A����E�����ɋ�̐�����A�g���\�z���悤�Ƃ���X���͗]�茩���Ȃ�����(�}�T�Q)�B�܂��A�w���ӎ������Ƃ������^�C�v�̌����ł��A�������ʂ̎��Ƃւ̃t�B�[�h�o�b�N�A����ɂ��̌��ʂɑ���w���ɂ��c�_�Ƃ������o�����I�Ȏ��݂͏��Ȃ��B������̓W�J���u�`�ɔ��f�����邱�Ƃ́A���O��ɂ��Ȃ��Ǝ��Ɖ^�c�͍���ł���B
�@�܂��A���̎�́̕A�����A�w���A���P�[�g�̌��ʂ���Ă��邾���Ƃ������ᔻ���������A�w�p�I�ɂ͉ߏ��ɕ]�������X��������B����͊w�������̗ނ����l�Ȏ�̊Ԃł̘A�g�Ɍ����A����u��O���X�v�̈�ۂ��@���Ȃ�����ł���B���̏]���^�́u�����ꂽ�v����̍ő�̖��́A�w���̃��������オ��Ȃ��_�ɂ���B
�k�}�T�@�]���^�̕����ꂽ����

�@����ɑ��A�J���ꂽ����͎��Љ�ւ̎Q��̎��������Ƃ̒��ɍ\�z����B�l�b�g���[�N�̐��E�̏����o�[�`�����E���A���e�B(���z������)�́A���̍\�z�̕~����Ⴍ�����ƌ����額����A�}�U�ɑz�肵���e���(�w���A����A�����ҁA�����ΏہA�w�O�g�D)�́A��������l�b�g���[�N�ŗe�Ղɑ��ݒʐM���\�ł���A�������K����������p�ӂ���A�\���͒������g�傷��ƌ�����
�k���x���X�̋���l
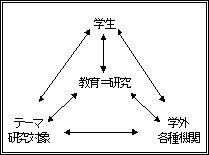
�@���̂��߂ɂ́A���������A�������������������S�Ď���悭�������Ȃ�������Ȃ��Ƃ������z����E�p����K�v������B��ʂɕ��n�����ɂ͑勳���ł̍u�`�������@�̃C���[�W�Ƃ��ċ����蒅���Ă���B�������A�����ȍu�`�m�[�g�����O�ɏ�������Ƃ������z�ł́A�p���Ċw���̈ӗ~���킢�ł��܂�����������B
�@���̎��Љ�ւ̎Q����@�Ƃ��āA�҂��Œ���Ɏ��O�ɗp�ӂ����̂́A�É������E���̊W�ҁA���тɒn�抈�������ɊW����w�O�̒c�̂Ƃ��Đ헪�o�c������(2)�A���̓�Ƃ̊W�̍\�z�A���тɁA����E�����ւ̋��͗v���ł���B
�@���͗v���ɍۂ��P�ɋ���ւ̋��͂ł���A������ɖw�ǃ��`�x�[�V�����͂Ȃ��B�|�C���g�͍���E�ߑa�̒n��Љ�A�n��O�̎�҂��猩�����A�ǂ̂悤�Ɍ�����̂��Ƃ����_�ɂ���B
�@���̑��ɂ��A�w���E��҂̎��_�Ƀj�[�Y������̂����o�����Ƃ��ł���͂��ł���A���̂悤�ȗ̈�ɏ��̐V���ȉ\�������邾�낤�B
�S�@�w���ւ̓��@�t���@�u���E���Ăǂ�ȂƂ��H�v
�@�w���̖w�ǂ����E���̂��Ƃ�m��Ȃ��A�Ƃ����͍̂D�s���ł���B�ŏ��̉ۑ�̓C���^�[�l�b�g��ɂ����鐅�E�Ɋւ�������W(URL�R���N�V����)�ł���B���̒�o�ۑ���������܂Ƃ߂āA���E�����N�W���쐬���A���̌��J�Ɠ����Ɂu���E�ɂ��čl����y�[�W�v���쐬�����B����ɂ͂��̌�̏d�v�Ȏd�|���ƂȂ�f����݂��A����ɐ��E���W�ҁA�헪�o�c������A�҂̊ԂŃ��[�����O���X�g��ݒ肵���B�Q�l�Ɍf���ł̂����̌��������L�Ɏ����Ă����B
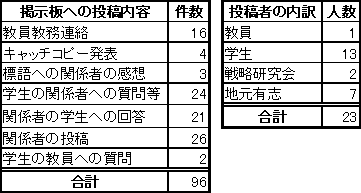
�@���̉ۑ�́A���̍����ɂ��Ăł���B�����������A���l�Ȋw���̗��C������Ȃ��u�҂ɒn�������Ɋւ��鋤�ʔF�������߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����Łu�����͎w���v�A�u����䗦�v�̗p��̈Ӗ����l�b�g�T�[�t�Œ��ׂ����ۑ�Œ�o�Ƃ������@���Ƃ����B�҂͍��w�X�^�C���̍s���w�̍u���������Ă��邪�A���炩�ɍu�`�X�^�C���ŋ���������A�l�b�g�Ŏ�̓I�ɒ��ׂ����������w���̗����͐[�������B�ܘ_�A��������ɂ�闝��������̂ōu�`�Ńt�H���[���邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@�����̐[�x�̎菕���Ƃ��āA�����̂g�o(3)�ɓ��{�̖�3200�̒n�������̂ɂ���100���ڂɊւ��鐔�l�f�[�^(�G�N�Z���E�t�@�C��)��p�ӂ��A������_�E�����[�h�ł���悤�ɂ��Ă������B�������āA��O�̉ۑ�Ƃ��āA���E�̍����̓����𑼂̎s�����Ɣ�r���Ē�`�����邱�Ƃɂ����B���̍ہA�G�N�Z���̕��ёւ��A�I�[�g�t�B�����ɂ��Ď��O�ɋ������Ă������Ƃ��K�v�ł���B
�@�����ɏ]���ƁA���@�t���Ƃ��u��̓I�Ȓ�`�ւ̎��g�݁v�̂��Ƃł���(4)����Ȃ̗~������̓I�ɐ����ł��邱�ƁA�܂�͎��ȋK��ł���B
�@�ۑ�ɑ��铮�@�t���̎d�グ�Ƃ��āA���E���́u�L���b�`�R�s�[�v���l�������A���̕W��Ɨ��R(��`)���ۑ�Ƃ��ė^�����B�܂�A�w���e���ɂ���̓I�Ȑ��E�̒�`�ł���B
�@���̕W����f���Ɍ��J��(�w�����͏o���Ȃ�)�A�헪�o�c������A���E�W�҂Ɋ��z�������Ă��炤���ƂŁA�ŏI�ۑ�쐬�ւ̃��`�x�[�V�����Ƃ����B���̌f���͊w���ɂƂ��đ��l�̔��z��m��@��ł�����A���`�x�[�V�����̌���ɂ��v����B
�@�L���b�`�͑傫���l�̃J�e�S���[�ɕ����邱�Ƃ��o�����B��͂�A�ő����u���R�ҁv�ł���A���R�A�A�X���L�[���[�h�Ƃ���B���ʂ��u�ӂ邳�Ɠ`���ҁv�ł���A�u���₵�v�A�u�₳�����v���L�[���[�h�Ƃ��A�����炩�ɓs��l�����R�Ɋ��҂���C���[�W��z�肵�Ă���B��O�́A�u�����E����ҁv�ł���A�O��҂Ƃ͔��ɔے�I�]���ł���A�u�����̊낤�����v�A�u����i�݁@���̐�ǂ�����v�Ȃǂ��Ȃ茵�������̂ł������B��l�͑��̉���̃J�e�S���[�ɂ�����Ȃ��u���ҁv�ł��額��̂̎R�x���Z�J�Òn�A�R�x���Z�Œ����������A�Ƃ�������̐������Ă�����ꂽ�B
�T�@���E���̌���Ə��K�͎����̂̒n�抈�����@
�@�����ŐÉ������E���̊ȒP�ȏЉ���s���Ă����B�����͐É����Ŗk�[�̒��쌧��M�Z���Ƃ̌����Ɉʒu����B��������̃A�N�Z�X�͂��Ȃ舫���A�V�����ŕl���܂�2���ԁA���B�S���ɏ�芷���������܂�40���A��������Ԃ�2���Ԏ�ł���B�������A���R�͖L���ł���A�n���̒ʂ萅�����Ɍb�܂�A2000m���̎R�X�Ɉ͂܂ꂽ�����̕W������1000m�ȏ�ɒB����B�����ɐ�������J���V�J�͐��v��2000���O��Ƃ���Ă���B
�@�l����1955�N��10,947�l���s�[�N�ɁA2000�N�x�ɂ�3723�l�ƂȂ�A�ߔN�A�N��100�l�̃y�[�X�Ō������Ă���B2000�N�̍���җ��i65�ˈȏ�j35.2���A�\�N��ɂ�50���ɔ���B�ߑa���E���q���E����̐i�s���������A�l�����x��13.72�l�ł���B
�@�Γ�39.4���~�̂����n���ł�3.4���~�A�n����t�ł�19.7���~���߂�B����S�䗦15.9���A����35.3���~�ɏ��B���Ă͗ыƂ���Y�Ƃ������������ȊO�ނɉ�����A�ыƂ͌o�c����قǐԎ����o�錻��ł���B���̂��ߗыƕs�U����Ԕ����x��A�����E���R����������Ƃ����A�S���̎R�ԕ��ߑa�n��ɋ��ʂ�����ɒ��ʂ��Ă���B
�@���{�̖�3200���鎩���̖̂����l���ꖜ�l�����ł���B����A�����ŏ��K�͎����̂̐�������Ƃ͌����A�����Ƃ����S������ɉ߂��Ȃ����낤�B����͒P�Ɏs�����̐����������邾���ł���A����E�ߑa�̒n��̌������Ӗ�����킯�ł͂Ȃ��B�ނ���A���̂悤�Ȓn��͍���A���悢�摝������̂ł���B
�@����E�ߑa�E������̖��ɒ��ʂ��n�抈������͍����Ă��鎩���̂͐��������݂��顖{���Ƃ̂悤�Ȏ��݂͂��̂悤�Ȏ����̂̃j�[�Y�ɋɂ߂ēK������ƌ�����B
�@���ɁA�{���͍�����Ƃ��Ă��A���̂悤�Ȏ�i���s�����ł͗l�X�ȗ��R���琧�������Ă����i5�j�B���ԃV���N�^���N���ւ̊O���ϑ����\�Z�������A����ł���B�����������Ԃ̉c���c�̂ɂƂ��āA�㏬�����͖̂��͂���c�Ƃ̑Ώۂł͂Ȃ��B
�@���ɁA���̂悤�Ȓn��̖w�ǂ���҂̐l�����o�ɒ��ʂ��Ă���A��������Ⴂ����̐����E�����Ƃ�����ł���B�܂��A���ڂȒn��Љ�ł͈ӌ��\��������ł���B�]���āA�O������̊w���̈ӌ��́A�ɂ߂Ďh���I�ł���B���ӔC�ł��邩�炱�������闦���Ȉӌ��́A�M�d�ł��炠��B�����炭�A���K�͎����̖̂w�ǂ͎�҂̊O���]�������o���͊F�����낤�B
�@��O�ɁA�w���ɂƂ��Ď��������̐����u�K�v�Ƃ���Ă���v�Ƃ��������́A�m���Ɉӗ~����������ʂ����B
�U�@�v���[���e�[�V�����̎��ہ@
�@�O���ŏI�ۑ�͐��E���̒n�抈�����ɂ��Ẵv���[���e�[�V�����ł���A������Ȃ��đO�������Ƃ����B�X���C�h�́u�^�C�g���A���O�v�A�u�e�[�}�̒�`�A���R�v�A�u��̓I�ȕ��@��`���@�v�A�u�����ƒZ���v�A�u����v��5�X���C�h�̍\�����Œ�v���Ƃ����B
�@���ɍ̓_���@�̓��F�ł��邪�A���\���Ɋw���ɂ��̓_�\��z�z���A���̊w���̔��\�������ł͂Ȃ��A�̓_����Ƃ����`�ŕ]���ɎQ�悳�����B�]���̒���_�͓��e�̎��A�����̗ʁA�v���[���̉��o���ʁi�X���C�h�̎��A�b�@�j�̎O�_���e5�i�K�]������B�̓_�̔z���͊w�����݊Ԃ̕]���k30%�l�{�W�҂̕]���k30%�l�{�����̕]���k40%�l�̔z���Ƃ����B�W�҂̕]���ɂ��ẮA�헪�o�c�������Ζؐ������i�i�@���m�j�\��ɏ����č̓_�����Ă����������B
�@���̂悤�ȍ̓_���������O�����m�O�ꂳ���Ă������Ƃ́A�ۑ�쐬�ɑ���ӗ~���h��������_�ŋɂ߂ďd�v�ł���B
�@��Ă��ꂽ���e�́A�m���x����������@�A�����̊ό������̉��P�A�O���[���c�[���Y���A�R�����w�E�t���[�X�N�[���E�ыƊw�Z�E���R�������̎��R���̋��玖�Ƃւ̗��p�A����Ȋό�����i�f��ہA�|�p��ԉ��o�A���b�̗��j�A�����̓��Y�i�̉��P�A���̃L�����N�^�[�ݒ�A�R�x���Z�E�j�����̑��J�Ó��X���푽�l�ł������B
�V�@�m�F���ꂽ���ʂƍ���̓W�J�@
�@�l�b�g�T�[�t�͎��ȑI���ɂ�����ɉ߂��Ȃ��B���̂��߃C���^�[�l�b�g�́u�����v�ȏ��ɑ��A�{�����Ă��鐢�E�̕��͈ӊO�Ƌ������̂ł���B����ɑ��A���E�̒n�抈�����Ƃ����ɂ߂č���ȉۑ�Ɏ��g�ނ��ƂŁA���Ȃ̑I�����L����������A�C���^�[�l�b�g���v�l�̓���ƂȂ蓾�邱�Ƃ�̓������邱�Ƃ��ł����B���{�̊e�n�Œn�抈�����Ƃ�������Ȗ��Ɏ��g��ł��鑽���̎�������邱�ƂŁA������������߂��ɖ������Ɏ��g�ނƂ����p��(���̒��ɂ͂������F�X�Ȃ��Ƃ��v�����Ȃ�Ƃ����P�Ɏ��g�����Ƃ��Ă��鎖��m��Ƃ�������)���w�_�͑傫�Ȏ��n�ł���B�s�s��Ԃ�����������Ԃł͂Ȃ��̂ł���B
�@�ŒZ�̑�s�s�l�����炳����3���Ԃ����鐅�E�́A�n�抈�������l����ΏۂƂ��Ĕ��ɍ���ȃP�[�X�ł���B�ȒP�ɖK����ł��Ȃ��B���̂��Ƃ��l�b�g���[�N���������Ǝ��H�̈Ӌ`�𑝂����ƌ�����B�w���̑������ۑ�Ɏ��g�ނ����ɁA�I�����C���ʼn��u�̒n�Ɓu�Ȃ���v���Ƃ̑�햡���������B�܂��A���ЂƂd�v�ȓ_�Ƃ��āA�u���n�ɍs�������Ȃ��Łv�_���邱�Ƃ̋��U�������������Ƃł���B
�@�s��l���u�c�Ɂv�ɋ��߂�u���₵�v�Ɓu���R�v�̃C���[�W���A�����ɓƑP�I�ŁA�n�悪����������ɖڂ������Ȃ���O���薼�ȗ~�����Ƃ������ƂɋC�Â��A���̏�ŁA����ɉ�����̓I�Ȃ��Ƃ����Ƃ����������o�ɁA���߂ĐӔC�����|����̂ł���B�w�O�Ƃ̐ړ_������ɐ݂���Ӌ`�͂��̈�_�ɐs����Ǝv���B
�@�����A�p���[�|�C���g�̃t�@�C���𐅌E���W�҂ɑ���A��������Ă����������z�����炢�A����ɂ������̎��ƓW�J�ւȂ��悤�ƍl���Ă����B�Ƃ��낪�A���E���Ńp���[�|�C���g�����邱�Ƃ��ł�������[���ɂ͂Ȃ����Ƃ����������B�����ŁA����͑O���̊w���ɑ��A�v���[���̓��e�����Ƃ�HP���쐬�����A����𐅌E�W�҂ɉ{�����Ă����������ƍl���Ă���B
�@���ЂƂ̌��ʂ́A���E�n��̐l�X�ɂƂ��Ăł���B�O���̎�҂��Ƃ炦���n��̉\���A���_�����ꂽ�̂ł���B���̒��œs�s�Z���ɂƂ��č��Y�Ɖf�鎩�R�����A�n��Z���ɂƂ��ĉ��l������̂Ƃ��ĔF������Ă��Ȃ��Ƃ����F���̊i�������������B����͌���ȍ~�̋���E�����E�n��̒�g�ɂ��W�J�Ŗ��߂Ă䂫�����ƍl���Ă���B
8�@�m�o�n�^�V���N�^���N��ڎw�����@
�@���ڂ��ׂ��́A���̎����̂ł̎{�����̏Љ�i���̍ہA���E�ł̎��{�̉\���̌������܂߂�悤�Ɏw���j���A���������_�ł���B�C�O�̎�����܂܂�A�����ɒ��W�҂����@���������邱�ƂɂȂ鎖��(�y����̉���s�b�L�I���R����)���������B�܂�A�w���̒�Ă̑����͈��̍������̂ł���B
�@����Ă݂ĉ����������R�̂��Ƃł͂��邪�A�S�l�̊w�����������Ă�����ʂ͈�l�̌����҂�y���ɗ����Ƃ��������ł���B���������̒~�ς����̈�ł́A��\�I�Ȑ�s������}���邱�ƂŁA���Y�̈�̑S�ʓ�����c���ł���B�������A�����݁A�i�s���̎����ł���A�������A�����A�w�ǂ̎����́E�����@�ւ�Web�ɂ���M�����Ă���ł́A�K�v�ȏ��̎��W�E�����̘J�͂��A�K�ȓ��@�t���̉��Ɋw���ɕ��U���������邱�Ƃ��A����E�����̒�g�Ƃ��ċɂ߂ėL�Ӌ`�ł���B
�@�w���͔��\�̎Q�l�����Ƃ��ăz�[���y�[�W�Ō��J����Ă����e�풲���A�@���E�ȗ߁E�K�����A�V���̐蔲���A���̎����̂ł̎��{���A�����E�Ȓ����ł̎��Ǝx����̎������o���Ă���A��100���̒�o�ʂ͑����ȃ{�����[���ƂȂ�B���ɂ͒S�������E�₢���킹�d�b�A����܂Ŗ��L���Ă���A���̂悤�Ȃ��Ƃ́u���U�����v�Ȃ����ĂȂ����Ȃ��ƌ�����B
�@�{�N���܂łɊw���������S�̈Ă������A����𐅌E�����ɒ�o����\��ł���B����ɂ�蓖�Y�n��̊������������ނƈ��Ղɍl���Ă͂��Ȃ����A�{�ōs�������̎�@�́A���̃e�[�}�ɒu�������邱�Ƃŗl�X�ȉ\�������ƌ����邾�낤�B����ƌ����̗Z���A��w�ƎЉ�̗Z���ł���A����͋��猤���@�ւƂ��Ă̑�w���n��Љ�E�n��s���ɑ��m�o�n�^�̃V���N�^���N�Ƃ��ċ@�\����\����Nj����鎎�݂ł�����B
�@�҂́A��N�x�̌����������_�@�Ƀz�[���y�[�W�ŏ�M���s�Ȃ��Ă���S���̒n���c����700���ƌ𗬂������ƂɂȂ���(6)�B�g�o��Ō��J����čs��ꂽ���̎��݂ɑ��A���ɑ��̎s��������̖₢���킹�����Ă���B���̂悤�ȋ���E�����E�n��̒�g�̎��݂��A����A�n���c���E�n���s���@�ւ̐����⍲�@�֓I�Ȉʒu�t���Ƃ��āA�������Ă��������ł���B
�@���ɂ����āA��w�Ƃ́A�l�X�Ȏ�̂Ǝ�̂��u�Ȃ���v�ł���B
���@�L
[1]�@�{�Ɍ�����悤�Ȏ��Ɠ����̑�\�I�Ȑ�s����Ƃ��āA���c���v���̊ɘa��Â��e�[�}�Ƃ������Ɠ����̎��H�������Ă����B�����͂���ɂ��đ����̕��s���Ă��邪�A�ŐV�̂��̂Ƃ��āu�w�K�x���l�b�g���[�N��p���������I�w�K�̓W�J�ƃl�b�g���[�N�̎����I�����@�\�㎖�@�w�̎��Ɨp�l�b�g���[�N����s���^���ց\�v�i�w����13�N�x������猤���W��_���W�x237�ňȉ��j�A�u�v�V���P�E�l�b�g�̍��@�\�l�b�g��ɕ��V����w�Z�́u���v����\�v�i�w��10������@�������\��\�e�W�x96�ňȉ��j�������Ă����B
[2]�@�S���K�ً͂̈Ǝ�𗬉�̈�ł������I�ɃI�t�E���C���Ō�������J���Ă���B�����o�[�͍s�����m�A�i�@���m�A���F��v�m�A�Љ�ی��J���m�A�ŗ��m���̗L���i�҂����S�ł���A�o�c�R���T���^���g���ʂ������B����̂g�o�́A
http://www5a.biglobe.ne.jp/~senryaku/home5/
[3]�@�҂̃z�[���y�[�W��URL�́A
http://www.isc.meiji.ac.jp/~takane
[4]�@�҂͂���ɂ��āA�{�N7��������w��狦��ɂ����Ĕ��\���s�����B�܂��w���ւ̓��@�t���Ƃ��Č����G���W�������p�������Ȍ[�����@�Ƃ��āu�C���^�[�l�b�g�h�c�@�v������B�u�V�������e���V�[����̒�ā@�\�����G���W���𗘗p�������Ȍ[���̎��݁\�v�i�w��10������@�������\��\�e�W�x12�ňȉ��j�B
[5]�@���K�͎����̂ł́A�X�̍s�����͖��ڂȒn��Љ�̋�Ԃ���A����̖͍��́A�u�v�f�v��������ꂩ�˂Ȃ��Ƃ̔z�����玩�ȋK���������B�܂��A���{�̒n���������̃������͊T���ĒႢ�B���X�N������s���̌����ƂȂ��Ă��邽�ߒȂǂ͏o�ɂ����B
[6]�@�ٍe�u�C���^�[�l�b�g�Ɠ��{�����̌��݁v�i�w������w���Ȋw�Z���^�[�N��@��13���x�ňȉ��j�B