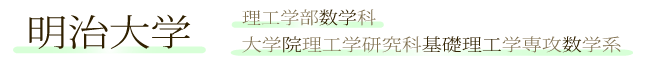
|
|
|
|
|
|
メイン>研究室紹介>砂田ゼミ>論文・著書一覧
論文・著書一覧:砂田教授
著書(単著)
- [1] 「基本群とラプラシアン」、紀伊国屋書店、1988年
- [2] 「行列と行列式」、岩波書店、1996年
- [3] 「幾何入門」、岩波書店、1996年
- [4] 「曲面の幾何」、岩波書店、1997年
- [5] 「バナッハ・タルスキーのパラドックス」、岩波書店、1997年
- [6] 「分割の幾何学 −デーンによる2つの定理をめぐって−」、日本評論社、2000年
- [7] 「数学から見た物体と運動」、岩波書店、2003年
- [8]「数学から見た古典力学」、岩波書店、2004年
- [9]「数学から見た連続体の力学と相対論」、岩波書店、2004年
- [10]「数学から見た統計力学と熱力学」、岩波書店、2004年
- [11]「数学から見た量子力学」、岩波書店、2005年
- [12]「幾何入門」、放送大学、2004年
- [13]「ダイヤモンドはなぜ美しい? --離散調和解析入門--」、シュプリンガー・フェアラーク東京、2006年
著書(共著)
- [1] 志賀浩二・砂田利一、高校生に贈る数学 III「面積と体積」、岩波書店、1996年
- [2] 砂田利一・他、かんたんなのにムズカシイ!!数学篇 (単行本)、「フェルマーの問題」、日本評論社,1996年
- [3] 砂田利一・他、現代数学の流れ1(岩波講座「現代数学への入門」)、第2章「無限を数える」、岩波書店、1996年
- [4] 砂田利一・他、現代数学の広がり1(岩波講座「現代数学の基礎」)、第3章「ゼータ関数から見た数学の世界」、岩波書店、1996年
- [5] 砂田利一・他、パラドックス(林晋編)、「バナッハ・タルスキーのパラドックス」、日本評論社、2000年
- [6] 砂田利一・他、20世紀の予想(数学セミナー編集部編)、「ヒルベルトの精神と21世紀数学」、日本評論社、2000年
- [7] 砂田利一・他、現代数学の土壌、「有限の世界から現代数学を眺める」、日本評論社2001年
- [8] 砂田利一、他、算数ができない大学生: 理系学生も学力崩壊、(岡部恒治ほか編)、「数学の衰亡 −湯の中の蛙−」、東洋経済新報社、2001年
- [9] 砂田利一・他、ゼータ研究所だより(黒川信重編)、「離散と連続」、「素数とゼータ関数」、日本評論社、2002年
- [10] 砂田利一・他、数理システム科学、「離散システム」、放送大学、2002年
- [11] Koji Shiga and Toshikazu Sunada, A Mathematical Gift, III, originally published in Japanese in 1996 by Iwanami Shoten, and translated by E. Tyler, Amer. Math. Soc., 2005.
- [12] 砂田利一・他、現代幾何学の流れ、「現代幾何学の生成」、日本評論社、2007年
- [13] 砂田利一・他、トポロジーデザイニング --新しい幾何学からはじめる物質・材料設計--、「対称性の幾何学」、株式会社エヌ・ティー・エス、2009年
解説文
- [1]「跡公式とLaplacianのspectrum」、数学33(2)、p134〜142、日本数学会、1981年
- [2]「幾何学における数論的方法について、−zetaおよびL-関数の幾何学的類似とその応用−」、数学 38(4)、p289〜301、日本数学会、1986年
- [3]「基本群とラプラシアン」、数学 39(3)、p193〜203、日本数学会、1987年
- [4] 「球面上の酔っぱらい,−ランダムウォークについて−」、数学セミナー、1月号、 37-41、1987年
- [5]「リーマン多様体のスペクトル:問題と展望」(調和解析と数論), 数理解析研究所講究録 0631、1-7、京都大学、1987年
- [6]「現代数学とユークリッド幾何」、数学セミナー、6月号、5-8、1989年
- [7]「連分数のはなし--数の遊びから,数論へ」、数セミ 29(8)、p56〜60、日本評論社、1990年
- [8]「革命的進歩の陰に空間への深い直観--幾何学」、現代数学の最前線(特集)、科学朝日 50(9)、p22〜25、朝日新聞社編、1990年,
- [9] 「フェルマーの問題」<かんたんなのにムズカシイ!!>、数学セミナー、5月号, 1991年
- [10]「素数と測地線と太鼓の音」、数理科学 374、20-24、1994年
- [11]「ゼータ関数と行列式」 (特集 行列式の進化)、数理科学 33(4)、p42〜45、サイエンス社、1995年
- [12]「楕円型偏微分方程式」 (特集 楕円もおもしろい)、数学セミナ- 34(9)、p30〜33、日本評論社、1995年
- [13]「素数とゼータ関数」、数学通信創刊号、5月、5-24, 1996年
- [14]「量子エルゴード性」、数理科学 9月号, 1997年
- [15]「バナッハ−タルスキのパラドックス −無限の彼方にあるもの−」、数学 50(1)、86-97、日本数学会、1998年
- [16]「大域解析学入門」 (特集 局所と大域)、数学セミナー 35(12)、14〜19、日本評論社、1996年
- [17]「完備性をめぐって」、数学のたのしみ、1997年第1号から6回連載
- [18]「図形の分割をめぐって」、数学セミナー、1997年4月号から15回連載
- [19]「ピタゴラスの定理と宇宙のかたち」、数学通信 4(3) (通号 15)、4〜18、日本数学会、1999年
- [20]「離散スペクトル幾何」 (フォーラム:現代数学の風景/ラプラシアンの諸相)、数学のたのしみ (通号 12)、67〜80、日本評論社、1999年
- [21]「グラフのゼータ関数」、数理科学 38(2) (通号 440)、49〜55、サイエンス社、2000年
- [22]「ヒルベルトの『精神』と21世紀の数学」 (特集 21世紀への問題)、数学セミナ- 39(11) (通号 470)、14〜18、日本評論社、2000年
- [23] ゼータ月報「離散と連続」、数学セミナー、10月号、2001年
- [24] 現代数学の土壌 「測地線」、数学のたのしみ (通号 27)、115〜129、日本評論社、2001年
- [25]「数学とは何か」(連載)、数学のたのしみ、2004(夏)から5回、日本評論社
- [26]「分割合同と面積・体積」 (特集 数や図形を分割しよう)、数学セミナー 44(2) (通号 521)、12〜16、日本評論社、2005年
- [27] 高校生のための数学セミナー、「宇宙の裏と表 --右と左の数理--」、数学のたのしみ、冬号、2006年
- [28]「私たちを取り巻く『空間』」、数理科学4、2006年
- [29] 重要な定理・概念……大学生のために 「陰関数定理と逆関数定理」、数学のたのしみ 2007(春・夏)、11〜18、日本評論社、2007年
- [30] 重要な定理・概念……大学生のために 「ジョルダン標準形」、 数学のたのしみ 2007(冬)、8〜16、 日本評論社、2007年
- [31]「不動点定理入門」 (フォーラム:現代数学のひろがり 不動点定理とは何だろう?)、数学のたのしみ 2007(冬)、18〜26、日本評論社、2007年
- [32]「結晶と幾何学 --K4 結晶を中心に--」、 数理科学4月号(N.526)、特集「現代数学はいかに使われるか(代数編)」、2007年
- [33]「『人間業』と『御神託』」 (特集 計算とは何か)、科学 77(10) (通号 902)、1044〜1046、岩波書店、2007年
- [34] 高校生のための数学セミナー、「論理と計算」、数学のたのしみ 2008(最終)、9〜20、日本評論社、2008年
- [35]「線形代数と幾何--図形で楽しむ線形代数」 (特集 線形代数の力--その歴史から多彩な応用まで)、 数理科学 46(6) (通号 540)、20〜24、サイエンス社、2008年
- [36] 「一般化と抽象化」 (抽象化・一般化--知れば知るほど深まる数学)、数学セミナー 47(6) (通号 561)、10〜13、日本評論社、2008年
- [37]「世界の形,方程式の形」、(特集「方程式に潜む対称性」−``美しさ"から探る方程式の見方−、 数理科学 2009年3月号 No.549
随筆
- [1]「マニラの熱い日々、−数学者の見たフィリピン−」、数学セミナー6月号、32-35、1986年
- [2] 数学最前線「幾何学と数論の交差点」、数学セミナー1月号、17-20、1989年
- [3] 現代数学最前線−幾何学−、科学朝日9月号、22-24、1990年
- [4]「現代数学−純粋数学を中心として−」、数理科学 346, 16-20、1992年
- [5] 砂田利一、岡部靖憲、往復書簡「純粋数学vs応用数学」、数学セミナー、1994年
- [6]「物理教育に何を望むか」、大学の物理教育 96(3)、22-23、社団法人日本物理学会、1996年
- [7]「『純粋』数学の擁護」、数学通信創刊号、5月、38-43、1996年
- [8]「太鼓の音は聞き分けられるか? −スペクトル幾何学入門−」現代思想 8、64-77、1997年
- [9] 数学百歩一飲「饒舌,晦渋,韜晦」、数学のたのしみ (通号 20)、140〜143、日本評論社、2000年
- [10] 河北新報「プリズム」欄、1999年−2000年(12回)
- [11]「数学者になる方法」、岩波「現代数学への入門講座」月報
- [12] 数学まなびはじめ「生涯一教師」、数学のたのしみ (通号 22)、8〜12、日本評論社、2000年
- [13] 数学百歩一飲「20世紀の数学はどこでおかしくなったのか」、数学のたのしみ (通号 23)、128〜131、日本評論社、2001年
- [14] 数学百歩一飲「思考停止」、数学のたのしみ (通号 26)、132〜135、日本評論社、2001年
- [15]「ようこそ、数理アルプスへ!」 (特集 理科系の基礎知識 part2)、数学セミナー、40(5) (通号 476)、40〜43、日本評論社、2001年
- [16] 数学百歩一飲「ゴキブリ原理」、数学のたのしみ (通号 29)、124〜127、日本評論社、2002年
- [17]「いつか行く路」、数学セミナー増刊号、2002年
- [18]「日付のない手紙」、こんな入試になぜできない、大学入試「数学」の虚像と実像、日本評論社、2005年
- [19]「数学者の目,小説家の目」、数学書房編集部編、2006年
- [20] 心に残る一冊「ユークリッド原論」、科学 vol.76、No. 2、岩波書店、2006年
- [21] 巻頭エッセイ、科学、4月号、岩波、2008年
- [22] 巻頭言、数学通信 7巻4号
- [23] 「ダイヤモンドに似た結晶構造がもう1つだけ存在することを数学的に発見」、科研費NEWS VOL.1、2008年
翻訳
- [1] グロモフ「このさき数十年に起こり得る数学の動向」、数学の最先端、第1巻、シュプリンガー・ジャパン、2002年
- [2] ブルギニョン「数学と社会の新しい関係」、数学の最先端、第2巻、シュプリンガー・ジャパン、2002年
- [3] アティヤ「緒言」、数学の最先端、第3巻、シュプリンガー・ジャパン、2003年
- [4] チャーン「リーマンに戻る」、数学の最先端、第4巻、シュプリンガー・ジャパン、2003年
- [5] マニン「職業および使命としての数学」、数学の最先端、第5巻、シュプリンガー・ジャパン、2004年
- [6] ルーエル「数学についての地球外生物との会話」、数学の最先端、第6巻、シュプリンガー・ジャパン、2006年
書評
- [1] 名著発掘, Emil Artin,Galois Theory, 数学のたのしみ (通号 8), 123〜125, 1998/08,日本評論社〔編〕/日本評論社
- [2] 最近の数学書から, アラン・ソーカル,ジャン・ブリクモン/著(田崎晴明,大野克嗣,堀茂樹/訳)『知の欺瞞--ポストモダン思想における科学の濫用』, 数学のたのしみ (通号 20), 132〜134, 2000/08,日本評論社〔編〕/日本評論社
- [3] Book Review in Bull. Amer. Math. Soc. ``Random walks on infinite graphs and groups" by W. Woess, 39 (2001), 281--285.
- [4] 早すぎた天才, 数学のたのしみ
- [5] わたしたちはなぜ科学にだまされるのか、数学のたのしみ
- [6] 代数学の基本定理、数学のたのしみ
編者
- [1] K. Shiohama, T. Sakai and T. Sunada (Ed.), Curvature and topology of Riemannian manifolds. Proceedings of the 17th international Taniguchi symposium held in Katata, August 26--31, 1985, Lecture Notes in Mathematics, 1201. Springer-Verlag, Berlin, 1986
- [2] T. Sunada (Ed.), Geometry and analysis on manifolds. Proceedings of the Twenty-first International Taniguchi Symposium held in Katata, August 23--29, 1987 and the conference held at Kyoto University, Kyoto, August 31--September 2, 1987, Lecture Notes in Mathematics, 1339. Springer-Verlag, Berlin, 1988
- [3] N. Kurokawa and T. Sunada (Ed.), Zeta functions in geometry. Papers from the Research Conference held at Tokyo Institute of Technology, Tokyo, August 14--18, 1990. Advanced Studies in Pure Mathematics, 21. Publ. for Math. Soc. Japan by Kinokuniya Company Ltd., Tokyo; distributed outside Japan by the American Mathematical Society, Providence, RI, 1992
- [4] T. Sunada and P. W. Sy (Ed.), Functional analysis and global analysis. Proceedings of the International Conference held at the University of the Philippines, Quezon City, October 20--26, 1996, Springer-Verlag Singapore, Singapore, 1997
- [5] M. Masaki and T. Sunada (Ed.), Taniguchi Conference on Mathematics Nara '98, Papers from the conference held in Nara, December 15--20, 1998, Advanced Studies in Pure Mathematics, Mathematical Society of Japan and Amer. Math. Soc.
- [6] T. Sunada, Y. Lo, P. W. Sy (Ed.), Proceedings of the Third Asian Mathematical Conference, Held at University of the Philippines, Diliman, October 23--27, 2000, World Scientific Publishing Company, 2002
- [7] M. Kotani, T. Shirai and T. Sunada (Ed.), Discrete geometric analysis, Proceedings of the 1st JAMS Symposium held in Sendai, December 12--20, 2002, Contemporary Mathematics, 347. American Mathematical Society,
- [8] P. Exner, J. P. Keating, P. Kuchment, T. Sunada, and A. Teplyaev (Ed.), Analysis on garphs and its applications, Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, 77 (2008)
- [9] 青本和彦、上野健爾、加藤和也、神保道夫、砂田利一、高橋陽一郎、深谷賢治、俣野博(編)、岩波講座:現代数学への入門、全10巻(20分冊)
- [10] 青本和彦、上野健爾、加藤和也、神保道夫、砂田利一、高橋陽一郎、深谷賢治、俣野博(編)、岩波講座:現代数学の基礎、全17巻 34分冊
- [11] 青本和彦、上野健爾、加藤和也、神保道夫、砂田利一、高橋陽一郎、深谷賢治、俣野博(編)、岩波講座:現代数学の展開、全12巻 23分冊
- [12] 砂田利一、黒川信重(編)、数学レクチャーノート 、培風館
- [13] 上野健爾、志賀浩二、砂田利一(編)、現代数学の展望、日本評論社、 2001年
- [14] 佐藤文隆、甘利俊一、小林俊一、砂田利一、福山秀敏(編)、岩波講座物理の世界、岩波書店、2001-、全85冊.
- [15] 熊原啓作、砂田利一(編)、数理システム科学、放送大学教育振興会、2002年
- [16] 上野健爾、志賀浩二、砂田利一(編)、現代数学の土壌:数学をささえる基本概念、日本評論社、2000年
- [17] 砂田利一(編)、数学の最先端、21世紀への挑戦、シュプリンガー・ジャパン、全6巻,2002年〜2006年
- [18] 砂田利一(編)、現代幾何学の流れ、日本評論社、2007年
その他
- [1] 上野健爾、砂田利一、小島寛之、討議 可視化への戦略--内在から宇宙へ (特集=幾何学の思考), 現代思想 34(8),48〜64,2006/7,青土社
- [2] 金子晃、砂田利一、山本昌宏、韓国の数学事情, 数学 42(3),p266〜270,1990/07,日本数学会 編/日本数学会
- [3] 砂田利一 他、21世紀に向けての数学の役割(シンポジウム) (現代数学者セミナ-(国際数学者会議(ICM90)記念)) 数セミ 30(4), p68〜72, 1991/03,日本評論社〔編〕/日本評論社
- [4] 森田茂之、砂田利一、日本数学会賞春季賞受賞者深谷賢治氏の業績, 数学 46(4),352-358,1994,日本数学会 編/日本数学会
- [5] 浪川幸彦、岡本和夫、砂田利一 他、<数学の仲間たち> 日本数学会とはどんなところ ? 数学のたのしみ (通号 4), 12〜22, 1997/12,日本評論社〔編〕/日本評論社
- [6] 深谷賢治、森田茂之、砂田,利一、21世紀の幾何学 (フォーラム:現代数学の風景/21世紀の幾何学) 数学のたのしみ (通号 7), 24〜50, 1998/06,日本評論社〔編〕/日本評論社
- [7] 上野健爾、砂田利一、ゲッチンゲンの栄光と挫折 (フォーラム:現代数学の風景/20世紀数学の渦流(1)) 数学のたのしみ (通号 18), 28〜38, 2000/04,日本評論社〔編〕/日本評論社
- [8] 高橋陽一郎、志賀浩二、砂田利一、 ロシア・東欧の数学の擡頭 (フォーラム:現代数学の風景/20世紀数学の渦流(1)) 数学のたのしみ (通号 18), 39〜52, 2000/04,日本評論社〔編〕/日本評論社
- [9] 京都大学数理解析研究所インタビュー, RIMS for the 21st Century, 森正武/斉藤恭司 聞き手:砂田利一, 数学の最先端,第2巻,シュプリンガー・ジャパン,2002年
- [10] 21世紀の数学、幾何学の未踏峰、宮岡礼子、小谷元子 編、2004年 日本評論社
- [11] チャート式 数学I+A (チャート式)、柳川 高明と共著、数研出版、2003年
- [12] 数学III―新課程 (チャート式)、数研出版、2005年
- [13] 数学III―新制、数研出版、1996年
- [14] 数学II―新課程 (チャート式)、数研出版、2004年
- [15] 数学B―新制、数研出版、1995年
- [16] 数学I―新課程 (チャート式)、数研出版、2003年
論文 (peer-reviewed)
- [1] T. Sunada, Non-linear eliptic operators on a compact manifold and an implicit function theorem, Nagoya Math.J. 57(1974), 175-200.
- [2] T. Sunada, Holomorphic mappings into a compact quotient of symmetric bounded domain, Nagoya Math.J. 64 (1976), 159-175.
- [3] T. Sunada, Closed geodesics in a locally symmetric space, Tohoku Math.J. 30 (1978), 59-68.
- [4] T. Sunada, Holomorphic equivalence problem for bounded Reinhaldt domains, Math. Ann. 235 (1978), 111-128.
- [5] T. Sunada, Spectrum of a compact flat manifold, Comment. Math. Helv. 53 (1978), 613-621.
- [6] T. Sunada, Rigidity of certain harmonic mappings, Invent. Math. 51(1979), 297-307.
- [7] T. Sunada, Trace formula for Hill's operators, Duke Math. J. 47(1980), 529-546.
- [8] T. Sunada, Geodesic chains and the spherical mean operator, Proc. "Global Differential Geometry/Global Analysis", Lect. Note in Math. 837 (1981), 229-232.
- [9] T. Sunada, Spherical means and geodesic chains in a Riemannian manifold, Trans. A.M.S. 267(1981), 483-501.
- [10] T. Sunada, Trace formula and heat equation asymptotics for a non-positively curved manifold, Amer. J. Math. 104(1982), 795-812.
- [11] J. Noguchi and T. Sunada, Finiteness of the family of rational and meromorphic mappings into algebraic varieties, Amer. J. Math. 104(1982), 887-900.
- [12] T. Sunada, Trace formula, Wiener integrals and asymptotics, Proc. Japan-France Seminer "Spectra of Riemannian Manifolds", Kaigai Publ. Tokyo 1983, 159-169.
- [13] T. Sunada, Mean-value theorems and ergodicity of certain geodesic random walks,
Compositio Math. 48(1983), 129-137.
- [14] T. Sunada, Geodesic flows and geodesic random walks, Advanced Studies in Pure Math. "Geometry of Geodesics and Related Topics", Vol.3 (1984), 47-85.
- [15] T. Adachi and T. Sunada, Energy spectrum of certain harmonic mappings, Compositio Math. 56(1985), 153-170.
- [16] T. Adachi and T. Sunada, Geometric bounds for the number of certain harmonic mappings, Proc. "Differential Geometry of Submanifolds", 1984, Springer Lect. Note in Math. 1090(1985), 24-36.
- [17] T. Sunada, Riemannian coverings and isospectral manifolds, Ann. of Math. 121 (1985), 169-186.
- [18] T. Sunada, Gel'fand's problem on unitary representations associated to discrete subgroups of PSL(2,R), Bull. A.M.S. 12(1985), 237-238.
- [19] T. Adachi and T. Sunada, Homology of closed geodesics in a negatively curved manifold, J. Diff. Geom. 26(1987), 81-99.
- [20] A. Katsuda and T. Sunada, Homology of closed geodesics in certain Riemannian manifolds, Proc. A.M.S. 96(1986), 657-660.
- [21] T. Adachi and T. Sunada, Twisted Perron-Frobenius theorem and L-functions, J. Funct. Anal. 71 (1987), 1-46.
- [22] T. Sunada, L‐functions in geometry and some applications, Proc. Taniguchi Symp. 1985, "Curvature and Topology of Riemannian Manifolds", Springer Lect. Note in Math. 1201(1986), 266-284.
- [23] T. Sunada, Number theoretic analogues in spectral geometry, Proc. The 6th Symp. "Differential Geometry and Differential Equations" , held in Shanghai, 1985, Springer Lect. Note in Math. 1255(1987), 96-108.
- [24] A. Katsuda and T. Sunada, Homology and closed geodesics in a compact Riemann surface, Amer. J. Math. 110(1987), 145-156.
- [25] T. Sunada, Unitary representations of fundamenatl groups and the spectrum of twisted Laplacians, Topology 28(1989), 125-132.
- [26] T. Sunada, Fundamental groups and Laplacians, Proc. Taniguchi Symp. "Geometry and Analysis on Manifolds", 1987, Springer Lect. Note in Math. 1339(1988), 248-277.
- [28] A. Katsuda and T. Sunada, Closed orbits in homology clasees, Publ. Math. IHES. 71 (1990), 5-32.
- [29] T. Kobayashi, K. Ono and T. Sunada, Periodic Schroedinger operators on a manifolds, Forum Math. 1(1989), 69-79.
- [30] T. Sunada, Dynamical L-functions and homology of closed orbits, Bull. A.M.S. 20(1989), 73-77.
- [31] T. Sunada, A periodic Schroedinger operator on an abel cover, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo 37 (1990), 575-583.
- [32] T. Sunada and P. W. Sy, Discrete Schroedinger operators on a graph, Nagoya Math. J. 125 (1992), 141-150.
- [33] T. Sunada, Group C^{*}-algebras and the spectrum of a periodic Schroedinger operator on a manifold, Canad. J. Math. 44(1992), 180-193.
- [34] T. Sunada and T. Nishio, Trace formulae in spectral geometry, Proc. ICM-90 Kyoto, Springer-Verlag, Tokyo, (1991), 577-585.
- [35] T. Sunada, Homology, Wiener integrals and density of states, J. Funct. Anal. 106(1992), 50-58.
- [36] J. Bruening and T. Sunada, On the spectrum of periodic elliptic operators, Nagoya Math. J. 126(1992), 159-171.
- [37] T. Adachi, T. Sunada and P. W. Sy, On the regular representation of a group applied to the spectrum of a tower, Proc. "Analyse algebrique des perturbations singulieres", (1993), 125-133.
- [38] J. Bruening and T. Sunada, On the spectrum of gauge-periodic elliptic operaors, Asterisque 210(1992).
- [39] T. Adachi and T. Sunada, Density of states in spectral geometry, Comment. Math. Helv. 68 (1993), 480-493.
- [40] T. Sunada, Magnetic flows on a riemann surface, Proceedings of KAIST Math. Workshop 8 (1993), 93--108.
- [41] T. Sunada, Euclidean versus non-Euclidean aspects in spectral geometry, Prog. Theor. Phys. Supplement 116 (1994), 235-250.
- [42] T. Sunada, A discrete analogue of periodic magnetic Schroedinger operators, Contemporary Math. 173(1994), 283-299.
- [43] T. Sunada, On the number-theoretic method in geometry: geometric analogue of zeta and L-functions and its applications, Selected papers on number theory, algebraic geometry, and differential geometry, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, vol. 160, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994, pp.1--17.
- [44] T. Sunada, Fundamental groups and {L}aplacians, Selected papers on number theory, algebraic geometry, and differential geometry, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, vol. 160, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994, pp.19--32.
- [45] T. Sunada, Quantum ergodicity, Trend in Mathematics, Birkhauser Verlag, Basel, 1997, 175 - 196.
- [46] M. Kotani, T. Shirai and T. Sunada, Asymptotic behavior of the transition probability of a random walk on an infinite graphs, J. Funct. Analy. 159 (1998), 664-689.
- [47] M. Kotani and T. Sunada, Jacobian tori associated with a finite graph and its abelian covering graphs, Advances in Apply. Math. 24(2000), 89-110.
- [48] M. Kotani and T. Sunada, Standard realizations of crystal lattices via harmonic maps, Trans. A.M.S. 353(2000), 1-20.
- [49] M. Kotani and T. Sunada, Albanese maps and an off diagonal long time asymptotic for the heat kernel, Comm. Math. Phys. 209(2000), 633-670.
- [50] M. Kotani and T. Sunada, A central limit theorem for the simple random walk on a crystal lattice, Proceedings of the Second ISAAC Congress, Vol. 1 (Fukuoka, 1999) (Dordrecht), Int. Soc. Anal. Appl. Comput., vol.~7, Kluwer Acad. Publ., 2000, pp.1--6.
- [51] M. Kotani and T. Sunada, Zeta functions of finite graphs, J. Math. Sci. Univ. Tokyo, 7(2000), 7-25.
- [52] M. Kotani and T. Sunada, The pressure and higher correlations for an Anosov diffeomorphisms, Dynam. Sys. Ergod. Th. 21(2001), 807-821.
- [53] M. Kotani and T. Suanda, Spectral geometry of crystal lattices, Contemporary. Math. 338 (2003), 271-305.
- [54] T. Sunada, Geometric aspects of large deviations for random walks on crystal lattices, Proc. of“Microlocal Analysis and Complex Fourier Analysis”, 2003.
- [55] M. Kotani and T. Sunada, Large deviation and the tangent cone at infinity of a crystal lattice, Math. Z., 254 (2006), 837-870.
- [56] M. Shubin and T. Sunada, Mathematical theory of lattice vibrations and specific heat, Pure and Appl. Math. Quaterly, 2 (2006), 745-777.
- [57] T. Sunada, Crystals that nature might miss creating, Notices of the AMS, 55(2008), 208-215.
- [58] T. Sunada, Discrete geometric analysis, Proceedings of Symposia in Pure Mathematics (ed. by P. Exner, J. P. Keating, P. Kuchment, T. Sunada, A. Teplyaev), 77 (2008), 51-86.
- [59] T. Sunada and H. Urakawa, Ray-Singer zeta functions for compact flat manifolds, Contemporary Math. A. M. S. 484(2009), 287-294.
- [60] M. Itoh, M. Kotani, H. Naito, T. Sunada, Y. Kawazoe, and T. Adschiri, New metallic carbon crystal, Phys. Rev. Lett. 102 No.5 (2009),
ゼミの内容・方法
学生の声
教員からのメッセージ
論文・著書一覧
略歴
担当授業
研究内容
代数分野
後藤研究室
蔵野研究室
中村研究室
幾何分野
砂田研究室
佐藤研究室
阿原研究室
数理解析分野
森本研究室
廣瀬研究室
二宮研究室
現象数理分野
三村研究室
桂田研究室
上山研究室
確率統計分野
岡部研究室
對馬研究室
松山研究室
数学教育分野
長岡研究室
|
|
|
© Meiji University, All rights reserved.
|
|
|