研究室紹介
三浦研究室(機能デバイス研究室)は、電気電子生命学科の中でも整った環境の研究室です。
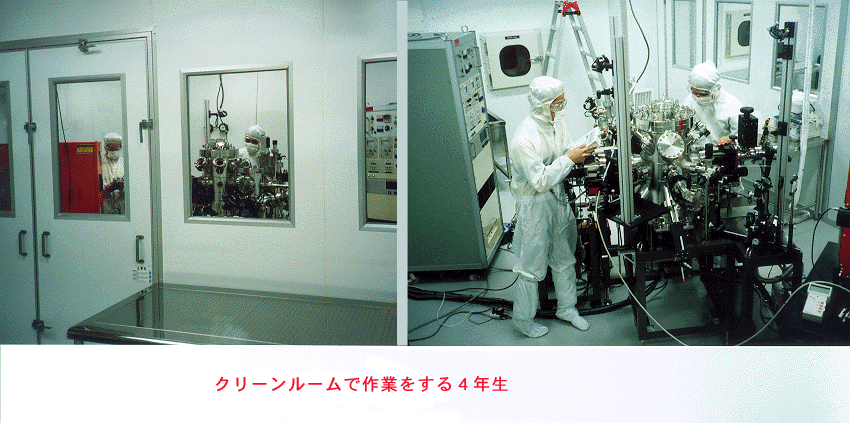
20世紀に形作られたエレクトロニクス社会は、コンピュータや通信機器の進展に伴うものでもありますが、これら機器をはじめ多くの機器が半導体デバイスをはじめとする物性・新材料の研究開発に支えられてきました。今後においてもこの傾向は変わりません。
私たちの研究室では次世代のエレクトロニクスをめざし、 新材料・新デバイスの創造と開発、新機能の探索を行っています。
21世紀になり、日進月歩で性能・特性を上げてきた旧来のエレクトロニクス技術には多くの技術的壁が現れてきています。また、電子機器産業はコモディティー化してきており、現在の日本は半導体を「産業の米」と呼べるような状態ではありません。このような状況で、エレクトロニクス産業にもイノベーションが求められます。一方で、文明生活のツケである地球温暖化は切実な問題であり、CO2削減は我々人類が取り組まざるをえない課題です。まさに、エネルギー問題は食料問題と並び、我々が今世紀中に取り組まなくてはならない最重要な課題です。私たち研究室では、超低消費電力エレクトロニクスを目指し、新たなエレクトロニクスデバイスを検討しています。学生達は、各自のテーマに情熱を持って研究に励んでいます。
- 目的:社会貢献
- 科学技術の進歩に貢献する。
20世紀における文明の発達は、科学技術の進歩の歴史です。資源を持たない日本は、「モ ノ作り」で経済大国としての地位を獲得してきました。今後も強い日本であり続けるためには、「革新的なモノ作り」を生み続けることです。そのために私達は研究します。研究と言っても、「夏休の自由研究」とは異なります。料理研究家の「研究」とも異なります。教えられてもらった作業の結果をまとめること、道具や他力に頼って確認した課題をまとめること、これらは科学技術の進歩に貢献する研究とは言えません。また、キーボードを叩いているだけ では、21世紀の科学技術の進歩はありえません。答えのない課題を解決していくことが必要です。
- 21世紀を担う優秀な科学技術者の育成
大学は国家の科学技術・知的財産を支える重要な研究機関であると同時に、教育機関です。社会で真に活躍できる優秀な人材を輩出することは、大学の責務です。「ハイテク」研究をするには、集中しきびきびと働かなくてはなりません。また、学 生は、正しい研究の進め方を体得しなくてはなりません。鍛えられた優秀な学生を社 会に送り出すことは、国家の繁栄に欠かすことのできないことと考えます。
- 基本姿勢
- 来る者は拒まず、去る者は追わず、落とすことは厭わず。
- 卒業研究は、授業料を払ってする板前修業である。
- 研究室に居る時間を拘束と考えるのなら前進はありえない。
- 研究は自分で実験し、新しいことを見出し、解析することである。
- 直面する問題点を積極的に克服しなくてはならない。
- 礼儀、思いやり、親切心、常識を持ってない人は認めない。
- プライドを持って研究しなくてはならないが、 他人の意見には耳を傾けなくてはならない。
- 指導教官は研究のマネージャであり、 コンパなどの行事・就職活動に関して意見はしても強要はしない。
- 視野を常に広げ、現状に甘んじない。
- 研究はお金でするのでなく、頭と行動力でする。
- 未熟な知識を掲げて妥協するのでなく、 真実を追求し、可能性を信じて着実に努力する。
- 連絡先
- 質問等は、 miura@isc.meiji.ac.jp または、